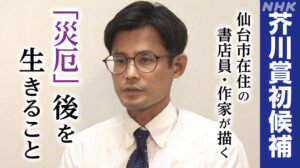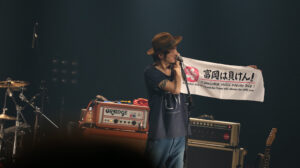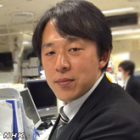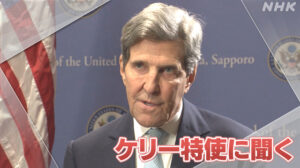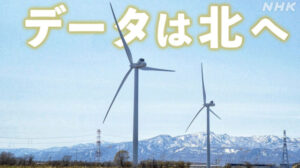科学と文化のいまがわかる
科学

復興・復旧工事 その裏で生態系への影響が
2021.10.29
東北の海の再生を考える上で避けて通れないのが、生活再建や復興のための工事が生態系に与える影響だ。
震災後、大津波に備えるため、東北の太平洋側では、堅固な防潮堤が建設された。
こうした新たに造られた防潮堤は、総延長400キロメートルに及んでいる。
震災や原発事故だけでなく、私たちが安全に暮らすための工事が、海の再生に、影響を与えていることが明らかになってきた。
回復したはずの干潟に異変
福島県いわき市を流れる鮫川。太平洋に流れ込む河口の両岸には干潟が広がっている。鮫川干潟だ。

この干潟は、希少な生き物を育むだけでなく、海の魚の産卵場所や、餌の供給源になってきた。

東北の干潟の調査を行っている、国立環境研究所の金谷弦さんが、この鮫川干潟の調査を始めたのは、震災の3年後。

津波で一度破壊された生態系は、大きく回復し、見つかった生き物は、50種類以上。
しかし、その後異変が起きた。戻っていたはずの生き物がほとんど姿を消したのだ。

(国立環境研究所 金谷弦 主幹研究員)。
「2014年まで、このホソウミニナという貝は、この鮫川の干潟に、1平方メートルに2000匹以上いました。もうざくざく、一面にホソウミニナ。それが、毎年頑張って探しているんですけど、残念ながらほとんど死んだ殻しか見つかっていない」
異変が起きたのは、河口の北側。火力発電所の前にある干潟だ。
震災後、発電所を囲むように、高さ7メートルの防潮堤が新たに建設された。

金谷さんは、この防潮堤が、干潟の環境に影響を及ぼしたと考えている。
工事が始まる前と、始まった後の干潟を比べると、海と防潮堤の間にある『水面』が、小さくなっていることがわかる。

新たな防潮堤は干潟の一部を埋め立てて設置された。
さらに工事によって、干潟に入る海水の量が減ったためだと金谷さんは考えている。

(金谷さん)
「工事が始まって、それ以降は地形が変わってしまって、海の水が入りにくくなったせいもあって、本来海にすむ生き物というのが絶滅してしまっていると」
工事の工夫が干潟を救う
工事の影響に危機感を抱いた金谷さんは、建設を進める県に対し、働きかけを始めた。
震災後、河口の南側には、新たな水門が設置されることになった。

かつての水門は、干潟より内陸側にあったが、津波が川を遡上するのを防ぐため、位置を変えることになった。
その結果、干潟を分断する場所に造られることになった。

「あそこが閉じられてしまうと、海の水が上流に行かなくなって、奥に棲んでいる干潟の生き物が死んでしまう可能性がある」
そこで金谷さんは、工事によって、干潟をつぶしたり、干潟に流れ込む海水を減らしたりしないよう、県に要望。
その結果、工事の期間中、海と干潟をつなぐ、専用のパイプが設置された。

その結果、干潟の生き物は守られることになった。

工事の後、金谷さんたちが継続的に行っている調査では、海水と淡水が混じり合う、汽水域でしか生息できない「ハマガニ」など、貴重な生物が見つかっている。

(金谷さん)
「こういう問題って、すぐ『命と自然とどっちが大事なのか』って話になりがちなんですけれど、ちょっと配慮して工夫すれば、防災もしつつ、生き物も生きていけるということはできると思うので、そういうやり方をみんなで考えていくことは、これから大事になってくるんじゃないかなと思いますね」
復旧工事の生態系影響 広範囲に
こうした工事の影響は、被災地の沿岸の広い範囲で確認されている。
金谷さんやみちのくベントス研究所の鈴木孝男さん、岩手医科大学の松政正俊教授らの研究グループは、震災後、東北沿岸の各地の干潟を調べ続けてきた。
その結果、岩手県、宮城県、福島県の3県では、34か所の調査地点のうち7割以上にあたる25か所で、防潮堤の工事など、復旧・復興工事に伴って、生き物の生息場所が減るなど何らかの影響が確認されたという。

被災地の復旧工事は、大規模な復旧作業を急いで進めるという観点から、環境影響評価が簡素化された。
このため、工事が生態系に与える影響が考慮されにくかった実情があると考えられる。
さらに、干潟の価値や役割がなかなか見えにくく、行政や住民の意識が高まらなかったことも背景にあるとの指摘もある。
干潟には、水をきれいにしたり、生き物のゆりかごになったりする機能があるだけでなく、ヒラメやカレイといった、漁業資源の繁殖の場ともなるので、大きな役割がある。
震災から10年。つぶさに被災地の海を見てきた、研究者や漁業者に話を聞くと、自然環境は、自ら再生する力を持っていることがよく分かる。
こうした力を長期的な視野に立って、どう復興や生活再建に取り入れていくのか。
震災からの復興がそれを問い直すきっかけになることを願いたい。

NEWS UP“奇跡の干潟”が消えていく

NEWS UP津波の海 回復を阻む温暖化の影

NEWS UP原発事故 汚染された海の再生はいま
ご意見・情報 をお寄せください