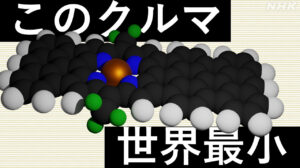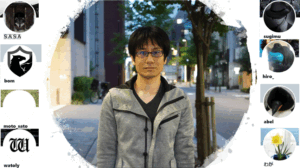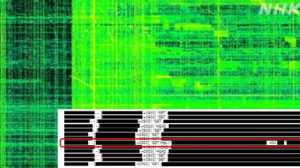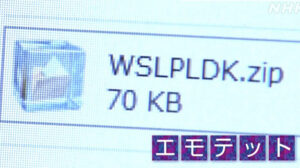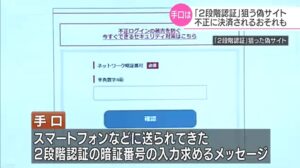科学と文化のいまがわかる
文化

二重のまち 語らない被災者 知りたい若者
2021.03.12
「ぼくの暮らしているまちの下には お父さんとお母さんが育ったまちがある」
先月公開された、東日本大震災をテーマにしたドキュメンタリー映画「二重のまち/交代地のうたを編む」の冒頭は、こんな言葉で始まる。
舞台は、津波対策のため、町全体が10メートルほどかさ上げされた岩手県陸前高田市。
制作したのは2人組の芸術家、「小森はるか+瀬尾夏美」だ。
震災の翌年、東京から陸前高田市に活動拠点を移し、被災地の変化を見続けてきた。
未曾有の大災害の記憶を未来にどうつないでいくのか。
2人がその答えの一つとして映画で示したのは、被災の当事者ではない人たちが「語り部のバトン」を受け継いでいくことだった。
語らない被災者 知りたい若者

映像作家の小森と画家で作家の瀬尾は、東京芸術大学に通っていた時に、震災を体験した。
その後、1年間にわたって岩手県陸前高田市に毎月足を運び、ボランティアを行った。
大津波で破壊された町並みとともに目の当たりにしたのは、みるみるうちに土から草が生えたり、被災した人たちが避難所から仮設住宅に移ったりするなど、物事がめまぐるしく動いていく様子だった。
表現者を志していた2人は、この体験を何らかの形で作品にしたいと考えていた。
しかし「東京だと変化がわからず、なにも表現出来ない」と感じた。

そこで、2人は、大学院の修了を待たずに移住を決意。
震災の翌年の2012年、活動拠点を陸前高田市に移すことにした。
震災から10年の間、瀬尾は言葉と絵、小森は映像で、被災地の変化を記録してきた。
陸前高田市は、町全体の土地を10メートルほどかさ上げし、将来の津波に備える決断をした。
かさ上げ工事は、この10年で少しずつ進められ、現在は、ほぼ完了、今はかつての町の上に、新しい町ができている。
2人が大事にしてきたのは、町の変化の中で起きる「何気ない風景」を丹念に記録することだった。
盛り土から生えている草が風でたなびく様子。沿岸をただ歩いている住民の姿。
かさ上げで埋もれてしまう大きな岩にお礼をするために開かれた盆踊り大会。
大きな厄災に見舞われた人たちが、矛盾を抱えながら前進する、その日々の営み。復興に向けた大きな社会の変化の中では、余白のような場所にある些細な出来事を記録しておくべきだと感じていた。
(小森はるか)
被災地の変化を見続けるうちに、自分が作品を作るのではなくて、別の人が覚えておきたいものを、私が代わりに撮っておいて、いつか知りたい誰かに返せるかもしれないという考えで、カメラを持つようになってきました
そして、2人がいま強く感じているのは、10メートルのかさ上げで、下の町が埋もれてしまったのに合わせるかのように、震災が語られなくなっていることだ。
その一方で、全国の被災地以外の場所では、震災当時子どもだった若者たちが、「何もできなかったけどいま震災について知りたい」と思っていた。
(瀬尾夏美)
震災の時に起きたことが誰かに伝わる前に語りが止まってしまうというのが、どうなのかなという思いがあった。語らなくなった被災地の人と、今なら聞きたい人たちが出会うことによって、継承の始まりが生んでいけるのではないかと思いました
聞く 語り直す

映画では、震災当時、小学生から高校生だった震災を現地で体験していない全国の4人の若者が15日間、陸前高田市でホームステイして、人々の話を聞いていく様子が描かれる。

息子を亡くした父親。元消防団の男性。化粧をしなくなった女性。
聞き取った被災の体験を、若者たちはみずからの言葉で語り直し、さらにほかの人たちに伝えることを試みる。
しかし、つらい被災体験をうまく聞き出すことすらできず、戸惑う。

(坂井遥香)
本当に、そのまま伝えたいっていうのがある。誰かの存在っていうのを傷つけずに
(古田春花)
自分の聞いた人の話を自分が伝えるのも限界がある
みずからのことばで伝え直すことの難しさに直面する若者の心の変化。
そのこと自体、記憶の継承の始まりだと、2人は言う。

(瀬尾夏美)
聞いた話を語るというのは必ず戸惑いがあるし、それを大事にしようとすればするほど自分にその資格があるんだろうか、この言葉でいいんだろうかと悩むことがあると思うんですけど、それでも語ってみるしかないというのが、本当に大事な話を聞いた時の感覚だと思います
未来への架橋

瀬尾は、今から10年後の未来の陸前高田市の物語を執筆。
映画の中では、若者がその物語を朗読する。
例えば次のような場面。
(かさ上げ後の町で生まれ育った幼い息子が、父親に手を引かれ、地下に埋もれたかつての町を訪れるシーン)

ふと、お父さんは立ち止まって
ここがお父さんの育った家だよ、と言った
このまちがあるから、上のまちがあるんだよ
そう言って、胸の前で手を合わせる
お父さんはすこし、泣いていた
未来は、過去の積み重ねの先にある。
かさ上げされた町で、過去を背負いながら暮らす陸前高田の人々の心情。
震災の体験を“聞く”ことは、その土地の歴史を知ることにほかならない。
2人は、被災した人たちと被災を経験していない人たちが繰り返しことばを交わしていくことこそが、震災の記憶をつないでいくと考えている。

(瀬尾夏美)
丁寧に聞く人も、語る人もお互いに背景があって、尊重し合いながら起きてしまった災禍を一緒に分かち合う、その先に継承がある、ということができたら良いなと思います
(小森はるか)
記録はどういうふうに、形にして、別のひとに渡していくか、その間に自分がいる。伝えたい人と知りたい人の中間地点にいて、映像でそれをとどめている、そういう認識でやっています
教訓とは?

「東日本大震災の教訓は?」「私たちは今後どうすべきなのか?」
私たちは、つい、災害から教訓を学び取ろうとする。
もちろん、それは大切だが、2人の映画では、教訓めいた逸話は登場せず、押しつけがましい戒めも説かれていない。
そこにあるのは、聞き、伝え、語り直す行為だけだ。
先祖から語り継がれてきた民話のように、未来の人たちがその物語から本当の“教訓”や“歴史”を読み解いていく。2人の作品は、そのことの大切さを静かに語りかけている気がした。