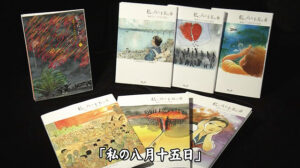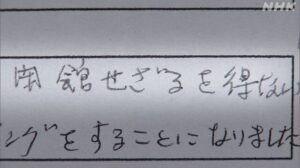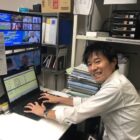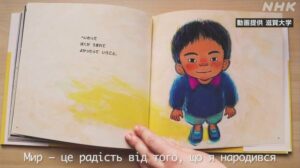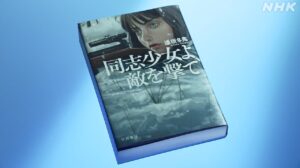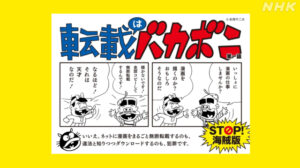科学と文化のいまがわかる
原子力

「核軍縮は長いマラソン」走り始めた大学院生
2023.05.12
5月19日に開幕するG7サミット。
被爆地・広島で開かれる会議の中で主要な議題の1つとして取り上げられることになっているテーマが、核軍縮だ。
世界が向き合うべき、このテーマについて、アメリカで学び続けている広島出身の大学院生がいる。
「核兵器は絶対になくさないといけないもの」という環境で育った彼女が、現地での生活を経て、理解できたことばがあるという。
「核軍縮は、長いマラソン」
その意味とは…
アメリカに渡ったきっかけ

アメリカ・カリフォルニア州のミドルベリー国際大学院モントレー校の2年生、倉光静都香さん。
出身地の広島では、小学校から平和教育が行われ、核兵器の恐ろしさを訴える被爆者の声を直接聞いて育った。
そんな倉光さんが核軍縮について本格的に学びたいと考えるようになったのは、高校生のときだったという。
(倉光静都香さん)
「たった1発の原爆で一瞬で多くの人が亡くなり、生き残った人も70年以上、苦しみ続けています。
そうしたことを、ずっと学んできた自分にとって、核兵器が今も1万発以上存在するということを知り、信じられない思いでした。
日本でもまた核兵器が使用される可能性がゼロではないというなかで、核軍縮・核不拡散という分野があることを知り、興味を持ちました」
世界では核軍縮がどのように議論されているのか、知りたい。
倉光さんは、高校を卒業後、アメリカの大学に入学して国際政治を学ぶ。
そして、大学院へと進学し、核不拡散を専攻した。
アメリカでの学びがもたらした変化

私が倉光さんを初めて取材したのは、2年前のこと。
アメリカでコンサルタントとして働く広島出身の竹内道さんが製作した1本の映画がきっかけだった。
女性は、被爆2世という自身のルーツと向き合い、カナダ在住の広島の被爆者・サーロー節子さんの半生を描いた。
倉光さんは、映画の日本公開にあたってのPR役を買って出たのだ。
そのときのインタビューでは、次のように語っていた。
(倉光静都香さん)
「故郷の広島で、過去に何が起こったかということは知らないといけないし、話さないといけないと思っています。
どのようにすれば、被爆地『ヒロシマ』に興味がなかった人に、自分ごととして見てもらえるか、琴線に触れさせることができるか。
映画は、そうしたことを深く考える機会になりました。
被爆者の高齢化は進み、その体験を語れる人は年々、少なくなっています。
被爆体験がない私ですが、なんとか“被爆者の拡声器”としての役割を果たしていきたい」
学びによる“変化”
核兵器の廃絶を実現するためには、若者による発信が必要だと、力強く語っていた倉光さん。
それから2年がたつ。
アメリカでの学びを経て、改めて聞いてみると、倉光さんの考え方にも少し変化があったようだ。

(倉光静都香さん)
「自分の考えが少し変わったかなと思う点は、軍縮がどれだけ難しいのかを理解したことだと思っています。
NPT(=核拡散防止条約)など、軍縮を議論する場に足を運んで、どのように交渉が行われるかを実際に自分の目で見ることができました。
そこでは政府や市民など、いろいろな人が何十年にもわたって核軍縮に取り組んでいることを実感したんです。
それでもなかなか前に進まない核軍縮の難しさ。
そのことを出発点として考えなければと思いました」
ようやく分かった「長いマラソン」の意味
倉光さんにとって、忘れられないことばがある。
「高校生の時にCTBTO(=包括的核実験禁止条約機関)の事務局長を務めていた、ラッシーナ・ゼルボ博士が広島に来たときに話を聞く機会がありました。
ゼルボさんは、そのとき『核軍縮は長いマラソンだ』っておっしゃっていました。
でも、私は当時、『長いマラソン』の意味が全く分からなかったんです。
“核兵器の廃絶”という目標は、普遍的で多くの人が掲げています。
しかし、そこにたどりつくためには、困難で複雑なプロセスをくぐり抜けなければなりません。
私は、今になって、そのことばの意味をようやく理解することができたんだと思います」
それでも変わらない思い

核軍縮の道のりの険しさを実感した倉光さん。
それでも、「核兵器をなくさないといけない」という思い自体は揺らいでいない。
「日本を離れてから、アメリカや、ほかの国にも核実験の被害者がいることを知りました。
被爆者一人ひとり事情は違います。
ただ、多くの被爆者が訴えたのは、『核兵器が二度と使われないように、核兵器の廃絶という目標を追求し続けなければいけない』ということでした。
被爆者から受け継いだこの価値観は、私の中でも変わることがないと思っています」
世界で高まる核使用の危機感

ウクライナへの軍事侵攻を続けるロシアは核戦力を誇示し、北朝鮮は、核・ミサイル開発を続けている。
今、核兵器が実際に使われる危険性は、一段と高まっている。
倉光さんは、こうした状況のなかだからこそ、対話による解決の重要性を訴えている。
(倉光静都香さん)
「国際社会は今後も多極化して緊張や分断が続くと思います。
しかし、こうした状況だからこそ、国家間の対話を続けることが大切だと思います。
難しいことだとは理解していますが、核兵器廃絶を働きかけることが、この対話の中心にあるべきだと考えています。
核リスクを減らすために、できるかぎりの手段を各国に模索してほしい。
すぐには核軍縮にはつながらなくても、対話を続けることが、重要なステップだと考えています」
広島でG7サミットが開催される意義

19日には、G7広島サミットが始まる。
核軍縮も、重要なテーマの1つとして取り上げられる予定だ。
生まれ育った広島で行われる今回の会議に、倉光さんは何を期待しているのだろうか。
(倉光静都香さん)
「G7の首脳が広島を訪問したからといって、一夜にして核軍縮につながるような効果が出るとは期待していません。
広島という土地を、各国首脳がこのタイミングで訪れるということは象徴的なことだと思います。
しかし、広島訪問を通して、現在、核兵器が使われた際の被害に関して、より鮮明に考えられるようになることが重要なのではないでしょうか。
78年前と現在の違いを想像して、核兵器がもたらす影響が全く違うということを感じてほしい。
平和記念資料館を訪れ、被爆者とことばを交わし、核軍縮に向けた目標や過去の合意、そして核保有国であることの責任を改めて確認してほしい。
サミットという場で、核軍縮をどのように前進させるかということを議論することが、対話の促進やリスク軽減への方法を見いだす道筋につながることを期待しています。
また、G7サミットと並行して、広島を中心に市民による平和と持続可能な未来を推進するためのさまざまなイベントが開催されると聞いています。
このような市民からの期待を、各国のリーダーたちが感じてくれることを願っています」
倉光さんは、5月に大学院を卒業する予定。
広島に帰るのではなく、そのままアメリカで核軍縮に関する研究や仕事に携わりたいと考えている。
「居心地がいい広島からではなく、その外から広島のメッセージを発信したい」。
「長いマラソン」の厳しさを理解したうえで、これからも走り続ける覚悟を決めた倉光さんのことばに、核なき世界に向かう希望の道筋が見えるような思いがした。


NEWS UP「逆境でも届けたい」 サーローさん描いた映画と2人の女性
ご意見・情報 をお寄せください