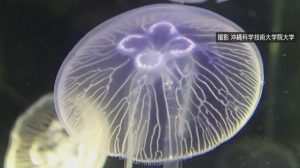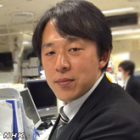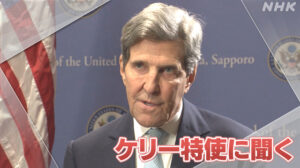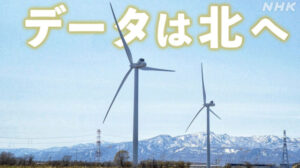科学と文化のいまがわかる
科学

フグ調理資格の統一基準づくりへ 厚労省が検討開始
2019.04.26
高級魚として知られるフグは、温暖化のために生息域が北上し、これまであまり食べられなかった地域でも、食材として扱われるようになっています。しかし、毒を取り除いて調理する資格が地域によって大きくばらついているため、厚生労働省は26日、検討会を設置し、全国統一の基準づくりに向けて議論を始めました。
(科学文化部記者 黒瀬総一郎)
フグは、かつて九州や中国地方での漁獲が多く、主に西日本を中心に消費されてきましたが、温暖化や海流の変化によって生息域が北上し、これまであまり食べられず、調理できる人が少ない地域でも食材として扱われるようになりました。
フグの体内には、テトロドトキシンと呼ばれる猛毒があるため、専門の資格を持った人以外調理できませんが、資格を得るための要件は、都道府県などの自治体が定めていて、地域によって厳しさが大きくばらついています。

このため、厚生労働省は専門の検討会を設置し、26日からフグの毒を取り除いて調理するための全国統一の基準づくりについて議論を始めました。
検討会ではフグの毒の専門家や、各地のフグ調理者の団体から現状を聞き取り、どのような基準がふさわしいか、議論を進めることになっています。
検討会の座長を務める国立医薬品食品衛生研究所の朝倉宏さんは「現状をしっかり把握して、フグの処理技術の全国的な平準化を図っていきたい」と話していました。
自治体によって異なる現在のフグの調理資格をめぐっては、調理人が別の地域で仕事できないとか、ほかの国への輸出がしにくいなどといった問題も指摘されています。
調理資格は都道府県によってさまざま
フグを調理したり、さばいたりするのに必要な資格の要件は都道府県によって大きく異なります。
厚生労働省の調査によりますと、全国の21の都府県は学科と実技、それぞれの試験を設けています。
一方、残りの26の道府県では試験に合格しないでも資格を取得することができ、このうち15の道府県は学科と実技の講習会を、1つの県については学科の講習会を受ければ、調理資格が得られます。
また試験や講習会を受けるのに必要な要件も都道府県によって差があり、調理師免許や実務経験を求める自治体がある一方、何も求めない自治体もあります。