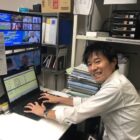科学と文化のいまがわかる
文化

「すてきなひとでした。原稿が遅いこと以外は」
2021.09.28
「ひと言で言うと、すてきなひとでした。もう、すてきだとしか言いようがないですね。思いやりがあるし。“原稿が遅いこと”以外ですと、もうほとんど何もいうことはない」
向田邦子さんの作品に「無名仮名人名簿」というエッセー集がある。
週刊文春で、この連載を担当していた元編集者、関根徹さん(73)は、今回のインタビューで、こんなふうに話した。
これはもう「ベタ褒め」だ。
ただ、“原稿が遅かったこと”以外は。
向田邦子さんとの出会い

当時、関根さんは入社7年目。
31歳のときに向田さんの「無名仮名人名簿」を担当することになった。
向田さんは49歳。テレビドラマの「時間ですよ」や「寺内貫太郎一家」、「阿修羅のごとく」などを手がけた売れっ子の脚本家で、すでに初のエッセー集「父の詫び状」も刊行されていた。
連載が始まるときの様子を関根さんに振り返ってもらおう。
「『無名仮名人名簿』というのを連載するというので、そのときから担当ということになりました。
その前から何度かデスクと一緒にごあいさつにうかがって。
絵はどなたにしましょうということで村上豊さん(※)にお願いしたいというようなご相談は前からしていて。
ただ、そのときから『私遅いんですよ』とおっしゃっていました。いわゆる連載ものの締め切りっていうのは、当時は木曜日と金曜日が校了日だったので、金曜日の校了にはしたんですね、一応。“木曜日の夜に原稿を頂ければ、じゅうぶん間に合います”と。
最初は「胸毛」というエピソードの原稿だったんですが、これは早く頂きました。それで次の原稿も早めにお願いしますと。
ところが、「青い目脂」という原稿でしたけれど、それは約束よりも遅くなって。そのときのお手紙がいちばん最初に頂いたお手紙でした。
『何ともお詫びの言葉もないのですが、出来が気に入らないのでもう1日だけください』という書き出しで」
(※画家、数多くの作家の作品の挿絵なども手がける)
「書けませんでした」の手紙
原稿のやり取りは、主に向田さんが住んでいたマンションのロビーで行われていた。
関根さんが原稿を受け取るのは、早くて未明の2時ごろ。関根さんは会社から2時間おきに催促の電話をかけていたそうだ。「ごめんなさい、まだなの」という応答があるときはよいけれど、留守番電話になっていたこともあったという。
最初は焦っていたが、毎週のことなので慣れてきたという関根さん。「ちょっと早いんだけれど、2時ごろには受け付けに預けておきます」と伝えられ、「やれ、うれしや」と喜び勇んで訪問してみると、置いてあった封筒はとても小さかった。
入っていたのは「書けませんでした」という手紙だったという。
「でも、ロビーまで来て空振りっていうのは、そんなにはないですね。『もういらしていいわよ』っておっしゃると、大体、原稿はできていて、いつもの勝負服というか、上着とブラウスを兼ねたような、何枚も持っていらっしゃったんですね。それで原稿を抱えてロビーまで降りていらっしゃいました」
関根さん!
そのときの向田さんの姿が目に浮かぶようです。
あと、編集者って、大変な仕事なんですね…。
編集者から見た“向田邦子”

“原稿が遅い”というエピソードがおもしろくて、少し強調したような形になってしまったが、関根さんにとって、向田さんはとても魅力的なひとだったという。
「連載を始めるときに、こちらもまだ認識不足というか、向田さんを見損なっていたというか、恥ずかしいんですけどね。
週刊誌ですから『テレビ局で親しくしているタレントとか、そういう話を書いていただくとありがたいです』と申し上げたら、『うーん、なかなか書きにくいのよね』とおっしゃったんです。
でも、それから何回かに1回は、名前は出さないけれども、タレントのエピソードというのを入れてくださいました。
最初のとき以降は、こちらから何も注文はなく、タイトルも何もすべておまかせだったんですが、やっぱり心にどこか留めていてくれたんですね。週刊誌が初めてということもあったんだと思います。
どんな意見でも聞いてみようと。友人にも感想をお聞きになったりしたようですね」
20も年の離れた若手編集者の意見を取り入れようとする向田さんの謙虚な姿勢がうかがえる。
また、さりげない気遣いをするひとでもあったようだ。
「何か不満があっても愚痴をこぼすことはありませんでした。
あるいは、どなたかと関係が悪くなることがあっても悪口を言うのを聞いたことがないんです。『テレビ局ってそういうとこだからしょうがないわよね』みたいなことはありましたけれども、悪口はおっしゃらない。
それでおいしいものはときどきくれる。お酒を頂くこともあったんですけども、いい銘柄のなかなか手に入らない一升瓶をマンションのロビーまで持ってきてくれる。向田さんは『私が飲むためにたくさん取ってある。そのお酒なので1本どうぞ』って言うんですけれど、それが実はわざわざ取り寄せたやつなんですよ。
私に子どもが生まれたときも、“おもちゃ”と書いたのし袋に現金が入っていたんです。もらうほうは現金がいちばんありがたいんですけれど、それを和らげるというか、こちらに気を遣わせないためにおもちゃとかお花とか書いて。そして、『いいお花を買おうと思ったけれど、時間がなかったのでごめんなさいね。これで何か見繕ってくださる?』と渡してくれる。実際ありがたいんですよ。
そういう気配りはどこで身に着いたのか。お母様やお父様がそうだったのか、あるいは天性でそういうふうに考えることができたのか。
それからファッションセンスがよくて、どこかでお食事しましょうというときに着るスーツとか、さっそうとしていましてね。
動きも何ていうか、見ていて気持ちがいいくらいさわやかに動くっていうか、運動神経がよかった」
関根さん!
もう、ベタ褒めです。
「書けないということはなかったのではないか」

最初のエッセー集=「父の詫び状」以降、向田さんは次々と作品を生み出していく。
いわゆる“ネタ枯れ”はなかったのだろうか。
「書くことは、たくさんあったと思います。特に取材もしないように見えました。それから私たちに『何か調べて』ということもほとんどありませんでした。
覚えてるのは、『蜆』というエピソードを書くときに、シジミはどのぐらいで育つのかと聞かれたことです。なにやら60年かかると聞いたことがあったらしいんです。お昼どき、日本橋界隈の食堂や定食屋に行くと、だいたい男性がシジミのみそ汁をすすってると。肝臓にいいと聞いてるので頼むんだろうと。でも、みんなが60年たたなければ育たないシジミを食べていたら、そのうちにシジミはいなくなるんじゃないかという心配なんですが、『本当はどうなの?』と聞かれました。
それで調べて、1年に2~3ミリ大きくなるようですから5~6年で食べられるようですよと答えました。それぐらいですね。
これは小説もそうではなかったかと思うんですが、こういうテーマで書くから、時間をかけて取材するということは、もし、ずっと長く元気でいらしたらあったかもしれませんけれど、亡くなるまでに書いたエッセーや小説では、そういうものはなかったんじゃないかと。
向田さんの中に全部蓄積されていたという感じがあります。
それは子どものころからの読書の蓄積、それから好奇心ですね。とにかく何でも見る、どこへでも行く、そういうことから蓄積されたものと、ご自身の創造力。
これは天性の能力だったのではないでしょうか。
『うそつきの才能がないと脚本は書けませんよ』ということをおっしゃっていたので。こちらもうそをつかれたことはありましたけれど(笑)。
同時期に『週刊新潮』でエッセーを連載していた山口瞳さん、向田さんが尊敬していた作家の1人ですけれども、忠告なさっていたそうなんですよ。『週刊誌で連載をすれば3割当たればいいんだよ。あなたは10割を目指すから大変だよ』と。
毎回、いくつもエピソードが盛り込まれて、あとは次に回せるんじゃないかというのを、惜しげもなく入れるというところがありましたのでね」
何が読者をひきつけるのか

それでは、関根さんが考える向田作品の魅力の秘密を聞いてみよう。
1つ目はことばづかいだという。
「よい時代の日本の家庭というか、家族の味がするんですね。非常に、いいことばづかいというか、懐かしいことばづかい。
例えば、お母様のほうのおじいさんが優秀な建具職人だったらしいんですけれど、これが他人の“請判”を押してから落ちぶれてしまった。“請判”という書き方をするんですよ。今ですと、保証人になったということですよね。それから“障子の開けたて”。開け閉めじゃなくて“開けたて”。1食分の食事じゃなくて“ひとかたけ”、あるいは“ひとかたき”。そういうことばを使うので、とても懐かしい感じがしました。
それから物の名前でも、今、七味っていえば“七味唐辛子”ですが、向田さんは“七色唐辛子”。そういうドラマ(「七色とんがらし」)もお作りになりましたけれど、これ、私も子どものころ、“七色”だったんですよ。
ご自分が使ってた、あるいはお父様、お母様がお使いになってたことばを使うというところがありました。
それから家族どうしの会話とか、生活の描写とかが非常に細かくて、しかもこちらの共感を呼ぶような。気取ったものもないし、きちんとした庶民の生活が感じられる。これはひょっとしたらお母様がネタ元というか、お母様もかなりエッセーには貢献なさってるかなという気はします」
2つ目は、文章からにじみ出てくる温かさだという。
「テレビドラマでは不倫とか、いろいろな家族の確執を書いていますが、ご自分の家ではほとんどなかったと。
かなり厳しいお父さんですけれど、昔のお父さんは明治生まれですから普通ですし。何でもきちんとしなければ気が済まないという人で、しかも苦学をした人ですから、そこはちょっと家族に厳しいけれども、それを奥さんであるお母さんも全部受け入れていらっしゃる。
昔はお客様っていうのは出し抜けに来るんですね。部下を何人連れてきてもちゃんと接待する。向田さんもお手伝いする。そういうところでのお客さんとのやり取りも向田さんの中に蓄積されて、人生経験というほどオーバーな話ではないかもしれませんけれども、人間ってこういうところがあるのか、こういうものなのかと。
ですからエッセーに変な人は出てくるんですけど、悪い人は出てこない。『金覚寺』に出てくる青年なんていうのは本当に変な人なんですけれども、でも可愛げがあるとかですね。
それと、押しつけないんですよ。向田さん自身の生き方はしっかりあるんです。好みもきちんとしていて、こういうのは嫌。たとえばカバーっていうのは嫌だ。本も表紙まで取っちゃうぐらいの人でしたけれど、こちらがカバーのある本を読んでたりしても、『嫌ね』とか、そんなことは絶対おっしゃらない」
向田邦子さんと病気
向田さんの病気についても聞いてみた。
向田さんは40代半ばで、乳がんの手術をしている。
仕事が軌道に乗り、「まさにこれから」というときだったはずだ。
「これはもう本当にご自分でも死ぬんじゃないかと思われたのではないでしょうか。
手術をして、5年大丈夫だったら成功で、これで再発の心配はないということで。
その間、やはりいろいろ思い悩むということはあったんじゃないかと思うんです。
ただ、こちらには全く気づかせなかったですね。澤地久枝さんや親しい人、あるいはご家族、弟さんの保雄さんとか、妹の和子さんはお分かりになっていらしたと。
でも、お母様には黙っていたんですね。ただ、『父の詫び状』が本になって出るとばれてしまうので、本になる前にお母様に白状したと。これも白状ということばを使って、告白ということばは使わないんですが、そうしたら『そんなことだろうと思った』と、お母様のほうの役者が一枚上で」
そして関根さんは、こんなエピソードも明かしてくれた。

「夜中のボウリングというのがあるんですよ。私の貴重な経験で。
『遅くまで待ってるときには何なさってるの?』って向田さんに聞かれて、『実は深夜、ボウリングに行ったりしてるんです』って答えました。
当時は何人かつきあってくれる編集部員がいまして、みんな向田エッセーのファンだからだと思うんですが、私がエッセーを受け取るまでの時間を潰すのに協力してやろうと。
そうしたら向田さんは『じゃあ、私もボウリングやってたから、やりましょうか。大会をしましょう。カップを出してもいいわよ』と。
さすがにカップは辞退しましたけれど、一緒にボウリングをしたんです。
向田さんはかつてマイボウルを持っていたので、200ぐらいのスコアはよく出していたというんですね。確かに投球する格好は板についているんですよ。ほれぼれするぐらいプロボウラーみたいに手が伸びて足が伸びて。
だけど、肝心のボウルはなかなか思ったところにいかなくて、ブービー賞かなんかでした。
そのときは何も気がつかなかったんですけれど、あとで考えたら、乳がんの手術をしたので、ボウリングはどうだろうかということを自分で試そうという気があったんじゃないかと。
向田さんは安心したと思うんです。スコアは悪くても全然何でもない。それで打ち上げをしてお酒を飲んでいたら『あんなもんじゃない』って言うんです。自信がついてきたのか、『もう1回やりましょう』って。明け方までやっているボウリング場に行って、これもまぁブービー賞ではなかったけれど、やはりそれほどよくはなかった。
それで『お疲れになったでしょう』と声をかけると、『私、これから真鶴(神奈川県)へ行くよ』って言うんで仰天しましてね。『えっ、何ですか?』って言ったら『中川一政画伯のところに“あ・うん”の表紙をお願いに行くの』って。『これからですか?』って聞くと、『大丈夫、シャワー浴びればシャキッとするから』って答えて、東京駅から出かけていったんです。
そのとき、“あ・うん”を担当してた私の大先輩の編集者に、あとでさんざん叱られました。『お前がボウリングなんかに連れていくから、こっちはどのくらいハラハラして待ったか分からない。列車のベルが鳴るかどうかってときに駆け込んできた。でも中川先生のところへうかがって元気にお話をしてくれた』と。
ですから中川先生は、まさか向田さんが徹夜でボウリングをして、その足で訪問したとはお思いにならなかったと思うんですけどね(笑)」
関根さんは、自分の大失敗についても話してくれた。

「私は大誤植をしたことがあるんですよ。
それは『メロン』というエピソードで、『メロンというものはなかなか1人でいっぱい食べるということができない、今も貴重だ』という話なんですが、『病気で入院したが、そのとき“死”とメロンが病室にあふれた』って書いてあるように見えたんです。
向田さんは、忙しいときでも必ずゲラはご覧になったんですが、そういうときに限って外国へいらっしゃったのかな。そのときだけ、ゲラをご覧になれなかった。
それで、記事になったら『あれ違うのよ、あなた。死とメロンじゃないの、花とメロンなのよ』って。
向田さんの書く“花”の草冠は、ちょっとカーブした線1本なんですよ。それで“花”と書いてあったのが、“死”と見えちゃったんです。
こちらは乳がんで入院したということを分かっていますから、それですぐ死というのが頭に浮かんだんです。
向田さんは達筆なんですけれども、急いで書くんですね。私が担当したエッセーの場合は、書くまでが時間がかかる。その間にいろいろ頭の中でテーマや構成ができて、ようやく何時間かたって、いざ書き出すと速い。ですから字もサッと書いて、難しい漢字はひらがなにして丸がしてあって、あとで漢字にしてねっていうことなんです。
それを私が清書して、印刷所へ渡して。それでつい“死”と書いてしまった。もちろん単行本では直しましたけれど」
こんなエピソードもありました
関根さんが語ってくれたのは、どれもこれも興味深いエピソード。
もう少し、教えてもらおう。
「名前を伏せて、こういうニックネームのタレントさんがいらっしゃると原稿に書いてあったときに、それはどなたですか、と聞いたことはありましたね。
1つだけ例を挙げると…これは悪いことではないので、許されるかと思うんですけれども、『地球の裏側』という俳優さんがいらっしゃると。向田さんに『地球の裏側って、どういうことですか』と聞くと、『その役を掘り下げて掘り下げて、地球の裏側に到達するぐらい掘り下げて研究する人よ』って。
文章では名前は挙げられていなかったんですけれども、『言いませんから教えてください』って聞いたら、加藤剛さんだと」
加藤剛さんはテレビドラマの「大岡越前」で名奉行・大岡忠相を30年近くにわたって演じ続けた名優で、映画「砂の器」などの作品でも知られる。
向田さんは加藤さんのことを、こんなふうに見ていたんだと、思わずため息がもれた。
加藤さんもすでに他界したが、「地球の裏側」と向田さんに呼ばれていたことを知ったら、なんと思うだろうか。
少し、てれたりしただろうか。
少し、うれしかっただろうか。
最後はやはり、締め切りについて
最後は、向田さんが海外旅行に出かけたときのエピソードを紹介していただこう。
向田さんは南米にも出かけたし、アフリカも訪問している。
そんなときは必ずお土産を買ってきてくれたというが…。
実は、こんなこともあったらしい。
「忙しいなかで絵はがきをくださったんですけれど、モロッコに行かれたことがあったんです。
そして、はがきの最後のほうには、『ここでは誰も時間を言いません。締め切りなどもないのでしょう。HAHAHAHA』って。
お前は締め切り、締め切りってうるさいやつだけれども、こちらには締め切りもないのです。HAHAHAHAって。
ハハハだけ、ローマ字で書いてあるんですけれど(笑)」
おちゃめでかわいらしく、そして思いやりのあるひと。
そのひとは、40年前に、突然いなくなってしまった。
しかし、その作品は今も残っている。
そして、かつての編集者は、そのひとのことをいつまでも心に刻んでいる。

NEWS UP“刃物を渡るように文章を” ~親友・向田邦子~

NEWS UPその瞬間に心に刺さる~小川糸の“向田邦子”~

NEWS UP今もスタートラインに 姉・向田邦子の贈り物
ご意見・情報 をお寄せください