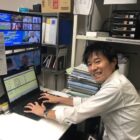科学と文化のいまがわかる
文化

今もスタートラインに 姉・向田邦子の贈り物
2021.09.30
「作家生活は短かったので、40年続くなんて夢のまた夢というか。願望として、向田邦子って名前を忘れられないようにして没後40年を迎えられたらいいなとは思っていました」
脚本家・作家の向田邦子さんが航空機事故で亡くなって、ちょうど40年。
私たちは、妹の和子さんに話を聞くことができた。
和子さんは、向田家4人きょうだいの末っ子。
会社勤めや喫茶店経営のあと、20年にわたって小料理屋「ままや」を営んだ。
いちばん上の姉・邦子さんから受け取ったものは、まだ返せていないという。
願わくは、姉のことが、この先も5年、10年と伝わっていってほしい。
和子さんは、そう言ってほほえんだ。
向田家ってどんな家庭だったの?

和子さんから見た向田家の構成は、以下のとおりだ。
保険会社に勤めていた父親・敏雄さん。それを支えた母親・せいさん。いちばん上の姉が邦子さん、兄の保雄さん、2番目の姉の迪子さん、そして末っ子の和子さん。
和子さんによれば、ごく普通のサラリーマン家庭。
ただ、和子さんは口うるさい父親のことがあまり好きではなかったという。
「父親であり、人間でありっていう視点で見たら」
邦子さんは、初のエッセー集「父の詫び状」の中で次のように記している。
父親が家にお客を連れて帰る。
そして向田さんが玄関先に脱いであった靴をそろえる場面だ。
「父は音痴で、『箱根の山は天下の険』がいつの間にかお経になっているという人である。うちの中で鼻唄をうたうなど、半年に一度あるかなしのことだ。こっちもついつられてたずねた。
『お父さん。お客さまは何人ですか』
いきなり『馬鹿』とどなられた
『お前は何のために靴を揃えているんだ。片足のお客さまがいると思っているのか』」(「父の詫び状」~“父の詫び状”より)
うん。確かに口うるさそうな父親だ(ごめんなさい)。
和子さんは、こんなふうに話す。
「お父さんちょっとヤダと。相手にしてくれないのは分かるんですけれど、でもなんか、“なんだこのお父さん”って思っていて、それで姉は私より叱られているわけですからね。
姉と一緒にいたときに、『お姉ちゃんこのうちに生まれてどう思う』って聞いたんですよ。私は不満ばかりだから、『そうだね、お父さんうるさいもんね』と言うかと思って期待して待っていたんです。
そうしたら『このうちに生まれて本当に幸せだと思う』って言われて。私は本当に崩れ落ちそうになって。びっくりっていうか、え、何だろうって思って。忘れられないんですけどね。
姉はそのときに、『このうちの環境は、いろんなものを考えたりするときに、非常にいい位置にいると思うから、私は本当にこの環境に生まれたことは宝物よ』って。『あなた、お父さんをこれから父親であり、人間でありっていう視点で見たら、違うんじゃない?』って」
「私、そんなこと言った?」
和子さんに影響を与えた邦子さんのエピソードをもう1つ。
「私、小学6年生の5月に仙台から東京に来たんですね。小学校と自宅がわりと近かったんです。
雨がザーザー降りになったんで急いでうちに帰って、番傘を何本か担いで教室に戻ったんです。そして『先生どうぞ』って差し出すと、『こんな傘なんかさせない』って、ものすごく叱られたんです。すごいショックでね。
私はいいことをしたと思うのに、なんでこんなに叱られるんだと思ってしょげていたら、姉が7時か8時に帰ってきて『きょう、なんかあった?』って聞かれたんです。
番傘を持って行って、私はいいことをしたと思っているのにって話すと、『和子、あなたがやったことは、とてもいいことなんだよ。でも先生も人間だよ。おもしろくないことがあって、あなたにあたったのかもしれないわよ。心というものには、子どもだから、大人だから、女だからで優劣関係があるわけではなくて、いいものはいいし、合うものは合うっていうことがあるんだよ』って言われたんです」
生きていれば、理不尽だと感じることがあるかもしれない。
でも、許してあげることも大切だ。
邦子さんは、そうしたことを伝えたかったのだろう。
和子さんは、邦子さんから教わったことを、今も折に触れて思い出すという。
「姉には言ったことはないけどね、姉に言っても『私、そんなこと言った?』って、いつも返してくるんですよ。だから一度も言ったことないんですけど、そのことは思い出していますね」
和子さんのことばがエッセーの題材に

ちょっとした和子さんの返事が、邦子さんのエッセーに生かされたこともあった。
「突然、姉は私に質問をしてくるんですよ。『戦争でいちばん記憶に残ってることは何?』って聞かれて。『ええ?』って。でも即答しないとすごく不機嫌になっちゃうんですよ。だから何でもいいから答えるっていう習慣ができているんで、そのときに私は『おばあちゃんの背中』って言ったんです。
それは3月10日(1945年)に空襲が本当にすごくて、それまでと全く異質だったんですよ。もう空は真っ赤だしね。
火の粉が飛んできたと思うんですけれど、父が『保雄(兄)は和子を連れて逃げろ』って言って、ちょうど門の外に出たときに、リアカーに乗っているおばあさんの背中が見えて、ものすごく悲しそうな背中だったんです。で、そこに息子らしい若い人がいて、そのお母さんを置いて逃げちゃったというのを私、見ちゃったんです。
その背中が忘れられなくて。だから、ふと『おばあちゃん背中』って言ったら、姉が本当に驚いて、『和子ちゃんはそれ見てたの?』って言ったから、『うん。寂しそうで悲しそうで、もう何とも言えない』みたいなことを言ったら、姉がそのおばあちゃんはどういう着物を着てて、こうだ、ああだということを全部説明してくれたんですね」
このエピソードは、のちに「ごはん」として、「父の詫び状」に収録された。
その中には一度は避難した保雄さんと和子さんが、逃げる際に持って行った救急袋の乾パンを全部食べたと記されている。和子さんは「おなかいっぱい乾パンを食べられて嬉しかった」と話したという。
和子さんの話は、ほんのりとしたユーモアで味つけされていた。
和子さんが登場するエッセー=「字のない葉書」
では、和子さんが最も好きなエッセーとは何だろう?
それは、「字のない葉書」だという。元は「眠る盃」に収録された作品。
和子さんは、去年3月に出版された「向田邦子ベスト・エッセイ」にも、このエピソードを選んだ。
「字のない葉書」は、次のようなストーリーだ。
東京大空襲のあと、幼かった和子さんは学童疎開をすることになった。
しかし、まだ字を書けなかったため、父親はおびただしい枚数の葉書に自分の名前を書いたうえで、元気な日は○(マル)を書いて毎日、ポストに投かんするよう和子さんに伝える。
最初は大きな○が書かれた葉書が届くが、○はだんだん小さくなり、×になり、ついには届かなくなる。
和子さんがようやく家に帰ってきたとき、父はその肩を抱いて声を上げて泣いたという。
邦子さんは、そのときの様子を温かく描写した。
「なぜ姉が、このことを知ってるのかなって。私が話していないことまで知っているのがすごく不思議でね。
姉が亡くなったあと、もう1人の姉の迪子に『お姉ちゃんは何で私が梅干しの種をポトンと落としたって、私、誰にも言ってないのに、知ってるはずないと思うのに、何で書いてあったんだろう』と聞いたんですよ。
そうしたら迪子が『私が言ったの。お姉ちゃんに質問されたのよ。あなた、いちばん戦争で記憶に残ることは何?って。それで、和子に偶然出会ってね、和子がつまらなそうにしてて、大事に大事になめていた梅干しの種をポトンと落としたっていうようなことを話した』って言うの。
それで『字のない葉書』というエッセーが成立したんですね。姉が亡くなってみて初めてそれがつながったという。
だから、どれを1つ選ぶかっていったら、やっぱりこの作品です。自分のことを細かく書いてあること。そして、戦争の中で父親が何を思って私を疎開させたのかというようなことについて、すべて記憶を戻してくれる作品でもあると思うしね」
「やり遂げる人です」

さらに、さらに。
邦子さんのことを話す和子さんの勢いは止まらない。
「1つ言っていいかな。思い出したことね。夏休み前に成績が出るじゃないですか。通信簿には先生から『こうしなさい』って書かれていて、それに対して返事を書く欄があったんです。普通は父か母が書くんですけれど、父が急に大きな仕事が入っちゃって、母が一緒に出張するので提出日に間に合わなくて。母は『私、ちゃんと書けないから邦子に書いてもらって』って。それで、姉が書いてくれたことばを私一生忘れないと思いました。
めちゃくちゃ感動したの。『やや積極性に欠けますが、やらせれば最後まで責任をもってやり遂げる人です』って書いてあった。
私は自分を評価していなかったから、そんなふうにお姉ちゃんが見てくれているっていうことがうれしかったの。そのあと、すっからかんと忘れてしまっていた。
でも思い出した。
それはね、姉が私に店を頼んだときです。『ええ?なんで。私しか頼む人いないの?』って戸惑っていたときに思い出したの。『やや積極性に欠けるが、やらせれば責任を持って最後までやり通す』って。
それで「よっしゃ、やってやろうじゃないか」と思いました。
今、『お姉ちゃん、私はやり遂げたって言えるかな?』って聞きたい。
そうやって笑いたいと思う」
邦子さんに励まされた和子さんは、1978年、東京・赤坂に食べ物とお酒の店、「ままや」を開いた。「ままや」は、邦子さんが亡くなったあとも親しまれ、20年後に閉店した。
「やったって言える?」
和子さんの問いかけに、邦子さんはきっと笑顔で応えるだろう。
姉からの贈り物
邦子さんが和子さんに贈った“最後のことば”があるという。
それは、邦子さんが直木賞をもらったあとのこと。
邦子さんは、この受賞を「スタートライン」だと位置づけていた。
「『自分も直木賞の受賞で新たなスタートラインに立った。これから一生懸命やる。最初は60点でも、努力していけば最後は90点を取れるようになるし、95点も取れるよ。だから、あなたも、いくつになってもスタートラインに立てます』って。
これが私にくれた最後のことばです。
やればできるんだっていうことを伝えたかったんだと、私はそう受け止めています。
だから私は、今でもまだスタートラインに立とうと思ってます。ずうずうしいですね(笑)」
和子さんはみずからの著書、「向田邦子の恋文」に次のように記している。
「姉から大きな影響と心に残る思いをたくさんもらった。普通、時の経過とともに薄れ、ほんのひとにぎりになってしまうものだが、姉邦子は違う。姉からもらったものは私の核となり、私の生きる基準となっている」
向田邦子さんが亡くなって40年がたった。
1人の人間が生まれ、成長し、40歳になったということだ。
その間、向田さんの作品は残り続けてきた。
そこには、きっと私たちの心をつかんで離さない、何かがある。
邦子さんは、「え?、私、そんなこと書いた?」って笑うだろうか。

NEWS UP“刃物を渡るように文章を” ~親友・向田邦子~

NEWS UP「すてきなひとでした。原稿が遅いこと以外は」

NEWS UPその瞬間に心に刺さる~小川糸の“向田邦子”~
ご意見・情報 をお寄せください