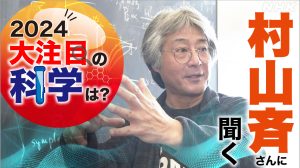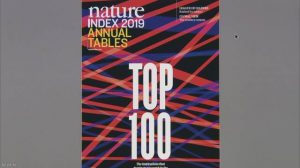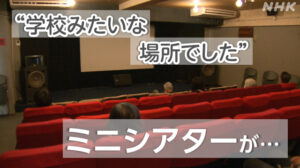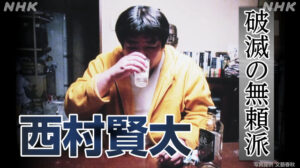科学と文化のいまがわかる
科学

揺れる科学者 軍事的研究にどう向き合う
2017.02.13
「軍事目的のための科学研究を行わない」。
日本の科学者たちが、先の大戦に協力した反省から、戦後維持してきた声明です。
ところが今、この声明をめぐり、日本の科学者たちが揺れています。状況に変化があったのは、戦後70年のおととし。安全保障環境が厳しさを増す中、防衛省が民間の技術を防衛装備品の開発につなげたいとして、大学などの研究機関に資金を提供する制度を始めたのです。
昨年度およそ3億円だった予算は、今年度およそ6億円になり、新年度の政府予算案ではおよそ110億円と大幅な増額の方針が示されています。
さらに、アメリカ軍も、ここ数年日本の大学に資金提供を進めていることが明らかになりました。
こうした状況の中、日本の科学者は安全保障技術など軍事的な研究と、どう向き合えばよいのか。今、議論が山場を迎えています。
“科学者の国会”で白熱する議論
“科学者の国会”とも呼ばれる日本の科学者の代表機関「日本学術会議」が、今月4日、東京・六本木にある日本学術会議の講堂で公開討論会を開きました。テーマは、「軍事的な技術の研究に科学者はどう向き合うべきか」。会場は事前の申し込みで満席。国内の大学や研究機関などから、文系・理系を問わず、さまざまな専門分野の研究者、300人余りが参加しました。
学術会議として、軍事研究を認めないという厳格な姿勢を示しておくべきだと思う」。「自衛も含めて、そういう研究をやらない場合、じゃあ日本は誰がその研究をするのか」。
日本の科学者としてのあるべき姿勢や、安全保障技術の研究に関わることの是非について活発に意見が交わされ、参加者全員による討論では、予定した1時間半を過ぎても、発言を求める挙手が絶えませんでした。
戦後、科学者が掲げてきた声明
今こうした議論が起きている背景には、日本の科学者が、戦後掲げてきた2つの声明があります。

「日本学術会議」は、先の大戦で科学者が戦争に動員され、兵器の開発などに協力した反省から、終戦の5年後の昭和25年、「戦争を目的とする科学の研究には、今後絶対に従わないというわれわれの固い決意を表明する」とする声明を出しました。
しかし昭和42年、日本物理学会が前の年に開いた半導体研究に関する国際会議に、アメリカ軍が資金提供を行っていたことが明らかになります。

事態を重く見た日本学術会議は、「決意を新たにしなければならない情勢に直面している」として、「軍事目的のための科学研究を行わない」とする声明を改めて出しました。
防衛省が大学などに資金提供
状況に変化があったのは、戦後70年のおととし。防衛省が、民間の技術を防衛装備品の開発につなげたいとして、大学などの研究機関に資金を提供する「安全保障技術研究推進制度」を新たに始めたのです。

この制度の背景には、安全保障環境が厳しさを増す中での政府の方針があります。政府は、4年前の平成25年に閣議決定した「国家安全保障戦略」と「防衛計画の大綱」の中で、防衛力を支える基盤を強化するため、大学などとの連携を強めて民生技術の積極的な活用に努める方針を掲げました。
防衛省の「安全保障技術研究推進制度」には、導入された昨年度と2年目の今年度に、大学や研究機関などから合わせて153件の応募があり、19件が採択されました。
このうち大学からは81件の応募があり、艦船のスピードを上げる研究や防毒マスクに使える繊維の研究など9件が採択されています。
この制度の予算、導入された昨年度はおよそ3億円でしたが、2年目の今年度はおよそ6億円になり、新年度の政府予算案ではおよそ110億円と、大幅な増額の方針が示されています。
アメリカ軍も日本の大学に資金提供
またアメリカ軍も、ここ数年、日本の大学に資金提供を進めていることが明らかになりました。
アメリカ空軍は、NHKの取材に対し、2010年度から2015年度までの6年間に、日本の大学や研究機関の研究、のべ128件に合わせておよそ7億5000万円の研究資金の提供を行ったことを明らかにしました。このほか、同じ6年間に、日本の研究者がアメリカの研究者と交流するための渡航費用や、日本で開かれる国際会議への支援金として、のべ129件合わせておよそ5000万円を提供したとしています。

検討委が中間取りまとめ
国立大学への国からの交付金が削減される中、防衛省やアメリカ軍からの研究資金にどう向き合えばよいのか。
「日本学術会議」は、去年5月「近年、軍事と学術とが各方面で接近を見せている」として、安全保障技術など軍事的な研究と大学などとの関わり方について議論するため、「安全保障と学術に関する検討委員会」を設置。検討委員会は、先月議論の中間取りまとめを発表しました。
この中では、先の大戦に科学者が協力したことへの反省について触れたうえで、「学術研究が、政府によって制約されたり動員されたりしがちであるという歴史的な経験をふまえ、学術研究の自主性・自律性を担保する必要がある」としています。

そのうえで、防衛省による大学などへの研究資金の提供制度については、「将来の装備開発につなげるという明確な目的に沿って公募・審査が行われ、防衛装備庁の職員が研究中の進捗管理を行うなど、政府による研究への介入の度合いが大きい」と指摘しています。
また、「科学者の研究成果は、時に科学者の意図を離れて軍事目的に転用され、場合によっては攻撃的な目的のためにも使用されうる」と指摘したうえで、「大学などの研究機関は、軍事的安全保障研究と見なされる可能性のある研究については、その適切性について、技術的・倫理的に審査する制度を設けることが望まれる」としています。
科学者の議論大詰めへ
こうした中間取りまとめを踏まえた上で行われた、今月4日の公開討論会。参加者全員によるこの日の議論では、「軍事目的の研究を行わないとしてきたこれまでの立場を修正したり撤回したりすれば、世界の科学者から日本に対して不信感を抱かれることになる」、「大学で、防衛省の制度に応募すれば、未来の科学者である学生も巻き込むことになる」などとして、軍事的な研究は行わないというこれまでの姿勢を改めて明確に示すべきだという意見が相次ぎました。

一方で、「学術会議の最終目的は、社会の負託に応えることで、自衛を含めた防衛に関する研究を一切行わない場合、いったい誰がその研究をやるのか」などとして、安全保障を目的とした研究に関わることは認められるべきだという意見も出されました。検討委員会の委員長を務める、法政大学の杉田敦教授は、公開討論会のあとの取材に対し、「参加者からは『軍事研究を行わない』とする日本学術会議のこれまでの声明を堅持すべきだという意見が多かった」という認識を示しました。
そのうえで、「今回の学術と軍事をめぐる議論は、先の大戦の反省の上に立つ日本学術会議という組織の存在理由にも関わる問題だ。きょうの討論会での意見を踏まえ、国の政策にそのまま対応するのではなく、政府から独立した立場として、日本の学術の在り方を長期的な視点で考えていきたい」と述べました。
4月に新たな見解示せるか
「日本学術会議」の検討委員会は、公開討論会の意見も踏まえ、来月までに、委員会としての最終報告をまとめることにしています。「日本学術会議」では、検討委員会の最終報告をもとに、4月に開く総会で何らかの見解を示すことを目指しています。防衛省の制度にどう向き合えばよいのか、国内の大学の間では、制度への応募を認めるところと、制度には協力すべきでないと大学独自の方針を示すところが出てきています。
その一方で、「日本学術会議の議論の結果を待って大学としての対応を検討する」としているところも少なくありません。日本の科学者として、どのような姿勢を掲げ、国の政策に向き合っていくのか。議論は重要な局面を迎えています。