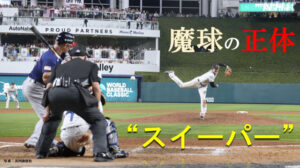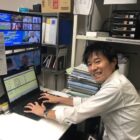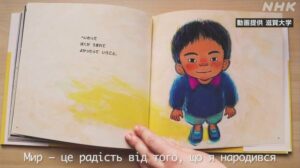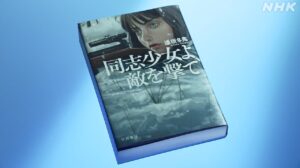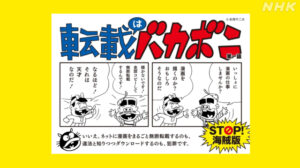科学と文化のいまがわかる
医療
サイカル研究室
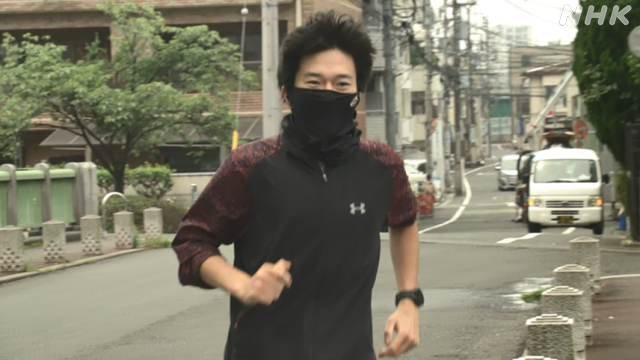
ランニングがやめられない!
2022.06.25
5300キロ。
これは私がこの1年間にランニングで走った距離です。
調べてみると、日本列島のおよそ1.5倍でした。
趣味としておよそ10年にわたって続けているランニング。
年々走る距離が増え、毎日走らならいと気が済まないようになっていました。
「これはちょっと異常なのではないか?」
そう思って調べてみたところ、あることばに行き着きました。
「ランニング依存」。
走ることを愛してやまないランナーのみなさん、心当たりはありませんか?
朝のルーティーン

午前4時40分。
私は毎朝この時間に目覚めます。
起きてまず水を飲み、準備運動で体を無理やり目覚めさせ、血糖値を上げるためにチョコレートを2粒食べる。
そして、眠い目をこすりながら5時すぎに外に出て、自分で決めたおよそ15キロのコースを走る。
これが私のモーニングルーティーンです。
この習慣は、雨が降ろうが、強い風が吹こうが、眠り足りなくてもどんなに疲れていても、欠かすことができません。
走りたくないな、という日も正直あります。
それでもなぜ続けているのかというと、走ることができない日は「調子が出ない」「気分が上がらない」という違和感、そして自分を甘やかしてしまったという劣等感を抱えて1日を過ごすことになるからです。
しかし最近になってこのルーティーンに不安を感じるようになってきました。
「こんな生活を続けていて大丈夫なのか?ちょっと異常なんじゃないか?」
そう思うきっかけになったのは、最近感じるようになった体の異変です。
これまでは毎日走っていても平気だったのに、数か月前から足の疲れが抜けにくくなり、タイムも落ち込み、走っていても「楽しい」と感じることが少なくなってしまったのです。
そして何より深刻だと感じたのは、休みが必要だと頭では理解しているのに、休んだり走る量を減らしたりする決断が自分ではどうしてもできなかったことです。
走り始めたきっかけはダイエット

そもそも私が走るようになったのは高校2年生の時です。
当時の私は自他ともに認める肥満体型で、容姿をからかう同級生を見返してやろうと一念発起し、ランニングを始めたのです。
体育の授業のマラソンで、200人いた同級生のうち下から10~20番目が定位置だった私は、走り始めた当初、毎日2キロ走るのがやっと、というありさまでした。
それでも諦めずに1か月ほど続けると余裕を持って走れるようになり、次第に走れる距離だけでなくタイムも伸び、1年が経過した頃には学年で上位20番目に入るほどにまでになりました。
こうして私は、走ることの楽しさに目覚めたのです。
大学に入ると、さらに自分を追い込もうと、トライアスロンチームに所属し、走ることに4年間、本格的に取り組みました。
練習の一環としてフルマラソンにも挑戦し、卒業する頃には3時間台前半のタイムを出せるようになり、1か月に3度フルマラソンを走る、なんてこともできるまでになっていました。
社会人になってからは趣味として休みの日に10キロほどゆっくり走る程度になり、ランニング熱は収まったかのように見えました。

しかし7年前、久しぶりに出場したマラソン大会で、ほとんど練習できていない状態ながら3時間半を切るタイムでゴールできたことで、「頑張って練習すれば『サブ3』(3時間以内にゴールすること)を達成できるかもしれない」という気持ちが芽生え、マラソン熱が再燃したのです。
それ以降、仕事の影響を受けにくい早朝の時間を使って、たとえ食事や睡眠の時間を削ってでも走る生活が続いているのです。
ひょっとして、「ランニング依存」?
その結果、冒頭で述べたような体の異変と不安を感じるようになってしまった私は、よい解決策はないかと調べ始めました。
調べてすぐに目にしたのが「ランニング依存」ということばです。

果たして自分が該当するのかどうかを確認しようと、アスリートのメンタルヘルスサポートに携わっている慶應義塾大学スポーツ医学研究センターの山口達也医師のもとを訪れました。
(筆者)
「ランニング依存はどういう状態のことを指すのでしょうか」
(山口達也医師)
「過度なランニングによって日常生活に影響を及ぼしているかどうかが重要な基準になります。ただし人によって運動量が違うので、明確な診断基準はないんです」

そこで手渡されたのは、依存の度合いを測るチェックシートです。
6つの質問に対し、「とてもそう思わない」の1点から「とてもそう思う」の5点まで、5段階の評価で回答し、その点数をポイント化して、依存の度合いを数値化します。
「依存症の傾向が見られる」基準となるラインは30点中24点。
回答の結果、私は28点。依存症の傾向が強く見られるという結果でした。
依存症とは、日々の生活や健康、大切な人間関係や仕事などに影響をきたしているにも関わらず、特定の物質や行動をやめたくてもやめられない状態を指します。
お酒や薬物、ギャンブルなど依存の対象はさまざまですが、ランニングは、続けることが悪いことではなく、むしろ「良いこと」「偉いこと」として捉えられ、依存症の対象とくくってしまうことに違和感を覚える人もいるかもしれません。
そこで、ほかのランナーたちの声を聞いてみることにしました。

皇居での練習を毎週行っているランニングクラブにお邪魔し、月間走行距離が300キロを超えるメンバーに話を聞くことができました。
(ランニング歴2年 渡邊拓馬さん)
「自分にとっては歯磨きのような感覚で、『走らない日を2日続けない』という自分のルールがあります。その分、ケガをした時にちょっと痛くても我慢して走ってしまうことはありますね」
(ランニング歴6年 船山洋祐さん)
「どうしても走る距離を求めてしまっています。予定があるのに少し時間あるからと思って無理に走って、予定ギリギリになったりとか、走りすぎて帰るのが遅くなって妻に怒られたりしたこともありました」

走ることに熱中するあまり、生活や仕事、健康に影響が出てしまったという失敗談を明かしてくれた二人。周りにも同様の経験をしたことがあるというランナーはたくさんいると教えてくれました。
私だけでなくほかのランナーも、走りすぎによる不安や悩みを抱えているようです。
私は、ランニング依存について、本格的に取材を進めることにしました。
そもそも「ランニング依存」って?

「ランニング依存」を詳しく知るために話を聞いたのが、スポーツ心理学が専門で、脳科学のアプローチから研究を進めている、早稲田大学スポーツ科学学術院の正木宏明教授です。
正木教授によると、「ランニング依存」と呼ばれる症状には、決まった定義はないとのことですが、海外の論文では「規則正しいランニング生活における心理学的・生理学的本質をもつアディクション(嗜癖・依存)で、ランニングをしない場合には24時間から36時間後に離脱症状(不安感、罪悪感,いらいら感など)が生じることから特徴づけられる」と説明されています。
ギャンブルや買い物など、特定の行動に依存する症例はほかにもありますが、ランニングを含む運動依存に特有の特徴があると正木教授は指摘します。
(正木教授)
「お酒や薬物などと違うのは、『やりたい』というよりも『やらなければ』という強迫的な側面です。そして運動が過剰に行われることによって、人間関係や仕事に支障をきたすほどのネガティブな結果を生み出し、さらに健康管理を度外視して行うことがあるため、受傷や体調不良に繋がってしまう恐れもあります」
「ランニング依存」にあたる人がどれくらい存在するかについて正確なデータはありませんが、ランニングを含めた「運動依存」に該当する人は「運動習慣のある人のうちおよそ3%」とする研究報告が、複数あるといいます。
1000万人あまりとされている日本の現在のランニング人口で考えると、推計で30万人が「ランニング依存」に該当する可能性があると考えられるのです。

そして、ランニング依存を引き起こす背景には2つの要因が考えられるといいます。
1つは運動によって多幸感が生み出されるカテコールアミン(ドーパミン、ノルアドレナリン、アドレナリンといった神経伝達物質の総称)が増えたり、βエンドルフィンが分泌されたりすることで、依存へとつながっていく可能性があること。
もう一つは、運動ができないとネガティブな気持ちになって離脱症状が起きてしまうため、その気持ちを抑えるために運動をやめることができなくなることです。
運動をやめると24時間~36時間後に離脱症状と言われる不安感、イライラ感、気が休まらないことなどが生ずることもあると言います。

日常的に運動をしている人が突然運動をやめるとどうなるのかを調べるため、今回、トライアスロンのトレーニングを毎日2時間程度行っている大学生に協力してもらい、脳波を使った実験を行いました。
最初に脳波を測定したあと、3日間運動を中止し、『運動を毎日続けている状態の脳波』と『運動を3日間やめたあとの状態の脳波』を比較したのです。

すると、不安に思っていたり、イライラしたりする時に現れるという「エラー関連陰性電位」といわれる波形が運動をやめたあとに大きくなっていました。
(正木教授)
「強度の高い運動習慣がある人は、運動を停止することで一過性にネガティブな感情や心理的な反応があることが見て取れます」
(実験に協力してくれた大学生・岩本和磨さん)
「1日目は平気だったのですが、2日目以降は運動したくてウズウズしていました。やっぱり運動がある上で自分が生活できているんだなと改めて思いました」
正木教授は、特に強迫傾向が強く、完璧主義の強い性格の持ち主は運動を止めることができない状態に陥りやすいと考えられているといいます。
ただ、ランニング依存のメカニズムが、強迫傾向などの性格によるものか、ドーパミンといった神経伝達物質の作用によるものか、それとも両者の相互作用に基づくものなのか、はっきりとは解明されていません。
この症状に関する研究は世界的にまだ調査や研究が十分に進んでいないのです。
(正木教授)
「ランニング依存は分かっていないことがまだまだたくさんあり、明確な判断基準もありません。走るのがやめられない症状の人を集めて実験や研究を行うのがとても難しく、データが集まりにくいんです。明確な対策があるわけではありませんが、予防法としては、実行可能な範囲でのランニング計画を立てて、その計画を超えてしまっていないかをモニタリングし、家族やランニング仲間との協働で計画を無理なく実行していくことが重要だと思います」
解決の糸口を求めて

症状を改善させるためには、何をすればいいのか…。
私のランニング依存度を確認してくれた山口医師に助言を得ることにしました。
そこでまず求められたのは、1週間分のタイムスケジュールを記入することです。
記入しながら、「こんな朝早くにほぼ毎日走っていることを知られたら、恥ずかしいな…」と思わずにはいられませんでした。
記入し終えたシートを受け取った山口医師は、驚いた様子もなく、穏やかな表情で「早朝に走ることが習慣化しているんですね」と言った上で、
①1日に走る量を少なくする日を作り、全体的な量を減らすこと、
②ほとんど毎日続けていた、ランニング以外のトレーニング(筋トレや体幹強化など)の時間を削ること、
以上2つの改善策を提示してくれました。
「走る日を削れ!」と言われることを覚悟していた私は思わず聞き返してしましいました。
(筆者)
「それだけでいいんですか?」
(山口医師)
「いきなりゼロにするのは無理だと思いますし、実現できないと思います。現在の運動量が10だとしたら、まずは9を目指し、それができたら8、7と減らしていき、自分にとって適切な運動量を探っていくことが重要です」
「これくらいならできる、助かった!」
このときの私はそう軽く考えていました。
なかなか計画通りには…

山口医師の助言に従い、自分のランニングスケジュールを見直しました。
これまでは1日およそ15キロの距離を7日間走り続けて1日休む、というスパンだったのを5日間に短縮し、そのうち1日は走る距離を10キロ程度に抑えるという計画を立てました。
結論から言うと、この計画は失敗に終わりました。
まず走る距離を抑える日を決めるにあたり、「調子が良くない日に距離を減らせばいいかな」と軽く考えていました。
ある日、走り始めてから調子が上がらないことを自覚した私は「よし、きょうは距離を短くしよう!」と心に決めます。
が、そのあとすぐに「もう走り始めているのだから、途中で切り上げるのは妥協ではないか?」という考えがよぎり、結局その思いを払拭できず、いつも通りの距離を走ってしまったのです。
この反省から、翌日はあらかじめいつもより短いコースを走ることにしましたが、その分、上り坂を多く走るなど強度を高めることになり、いつもとさほど変わらない疲労感をため込んでしまいました。
またランニングのスパンについても、休養日を5日おきと決めていたにもかかわらず、「翌朝は雨の予報だから、きょうは休養日の予定だったけど走っておくか」とか「仕事が夜遅くまで長引きそうな日の翌日まで休養日をとっておこう」など理由づけをして、結局いつも通り7日や8日連続して走ってしまったのです。
0から1を生み出すのが難しいのと同じように、10から9に減らすのも簡単ではないと痛感しました。
失敗の中で得た学び

2週間後、再び山口先生のもとを訪れました。
(筆者)
「努力をしたんですが、なかなか走る距離を減らせなくて、すいません…」
(山口医師)
「いえいえ。できなかったらできなかったで全然OKで、できなかった時にどういう風に改善できるかとか、できなかったことの原因を一緒に考えるっていうことを繰り返していくことが大切なんですよ」
優しいことばに励まされ、この2週間にできたこと、できなかったことを正直に報告しました。
その中で、改善策の②として提案された「ランニング以外のトレーニングの時間を削ること」については、トレーニングをやらない日を作ることができていることに、山口医師は着目し、私に優しく語りかけました。
(山口医師)
「できたこともこの2週間であったと思うんです。今回のように筋力トレーニングとかは上手に調整できているんだってことに自信を持って下さい」
(筆者)
「トレーニング量を減らせたように、走る量も減らしていけるかもしれないということですか?」
(山口医師)
「減らす経験をしたという自信を、いざランニングの調整の時にも生かすことができるようになればいい。できることをクリアしながら、時間をかけて行動変容につなげることが大切です」
必ずしも計画通りにいかなかったこの2週間。
しかし、自覚していなかった意識や行動の変化を山口医師は気付かせてくれました。
ランニングをこれからも楽しむためには
1度習慣化してしまうと簡単には変えられないことを身を持って学んだ私は、反省の意味も込めて、「ランニング依存」に陥らないために必要なことを最後に聞いてみました。

(山口医師)
「自分のライフスタイルを定期的に見つめ直すことが大事です。自分のランニング習慣について家族以外の第三者にアドバイスをもらったり、どんなコメントをされるか想像したりするだけでもいい。走ることは楽しいことだということを忘れずに、適度にバランスをとって走り続けてもらえればと思います」
取材を続けて1か月。
自分が「ランニング依存」であることを自覚し、「完治」を目指しましたが、やはり一朝一夕では難しく、今もこの「症状」と向き合っています。
しかし、走り続けることで抱えていた漠然とした不安は消え、自分にあったランニングスタイルをいつか実現させるという決意に変わりました。
私の願いはただ1つ。
「これからも走り続けたい!」
2022年6月26日 おはよう日本「サイカル研究室」で放送

NEWS UPゴールドラッシュおきるか 深海に眠る金鉱脈

NEWS UPソメイヨシノ その起源を探る旅
ご意見・情報 をお寄せください