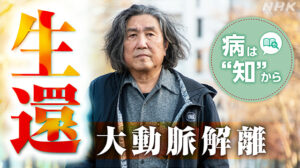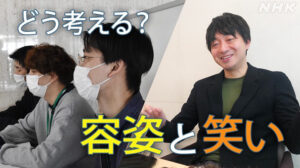科学と文化のいまがわかる
文化

“容姿”と”笑い” どう考えますか?
2023.03.27
これまで「お約束」ともされてきた笑いに対して、論争が起きたり、SNSで炎上したりするケースが相次いでいます。
その典型例が容姿に関するネタで、厳しい目が注がれています。
一方で、お笑いの世界からは、戸惑いや悩みも聞かれます。
容姿と笑いについて、どう考えますか。
“笑いの学校”の現場は今
吉本興業が運営するお笑いの専門学校「NSC吉本総合芸能学院」。
お笑いの道を目指す人たちが、現役で活躍するお笑い芸人や放送作家から、芸の手ほどきを受けています。

取材に訪れると、「ネタ見せ」の授業が行われていました。磨き続けてきた芸を披露する時間です。
漫才コンビやピン芸人、トリオなど様々なグループが参加しましたが、多少の下ネタや過激なネタはあっても、「容姿ネタ」と思えるような内容はありませんでした。
NSCでは、最近、容姿に関するネタを発表する生徒は減ってきているそうです。
日本有数の「笑いの学校」に通う生徒たちに聞いてみると・・・。
「自虐ネタで、最終的に自分が傷つくかたちならいいと思う」
「“いじられキャラ”というポジションになるのが難しくなりそう」
容姿そのものではなくても、「ネタ中に女性を“女”と呼んだだけで客席が引いてしまい、“女性”に言い直した」というエピソードを披露してくれる生徒もいました。
どの生徒たちも真剣で、ネタ選びから言葉づかいまで、批判や炎上の可能性があるなか 試行錯誤している様子がうかがえました。
容姿ネタへの厳しい視線
かつてテレビのバラエティー番組などで「お約束」のひとつでもあった容姿ネタ。
お笑い芸人どうしが顔の特徴や体型をいじったり、自虐ネタにしたり。
吉本興業が発行する雑誌で、「よしもとブサイクランキング」がお笑い芸人の人気の指標のひとつになったこともあります。
しかし、容姿に関連した笑いに対する社会の意識には変化がみられます。
たとえば、東京オリンピック・パラリンピックの開会式をめぐって、過去に女性タレントを動物に見立てて容姿を侮辱するような演出案が提案されていたことが発覚したケースなど、容姿をめぐって「炎上」する例が相次いでいます。
また、女性お笑いトリオ「3時のヒロイン」の福田麻貴さんが、容姿に関するネタをやめることをツイッター上で宣言したことも話題となりました。
将棋界のエンターテイナーは
こうした笑いを続けるか、迷いを感じているという人もいます。「将棋界のエンターテイナー」と呼ばれるプロ棋士の佐藤紳哉さんです。

インターネットでの将棋解説中などに突如カツラを外すパフォーマンスが人気を集めています。
佐藤棋士が、このパフォーマンスを始めたのは10年あまり前のことでした。
佐藤さん
「20代半ばから髪が薄くなり始めて、どうしたものかと思い、そこで考えつきました。最初はびっくりされたんですけど、けっこう良い武器だなと思いました」
今では楽しみにしているファンも多く、自分をきっかけに将棋を好きになる人が増えてほしいという佐藤さんですが、今後も続けていくか迷いもあるといいます。
佐藤さん
「直接自分自身には言われないのですが、特に最近、容姿を笑いにしてはいけないという流れが強まっていると感じています。オリンピックの件が話題になったときには、世の中の人がこういう反応をするのなら、すごく慎重にならないといけないとか、早いうちに手を引いていかないといけないのかと思いました。嫌な思いをする人がいるかもしれないし、共演する人や番組を制作する人にバッシングとか批判が行ってしまうのも申し訳ないと思いました」
一方で、単にやめれば済むのだろうかという思いも抱えています。

「僕自身はやりたくてやっているし、いじってほしいのに、それもやめてよっていわれたら、逆に『ずっと隠していなさい』と言われているような、何か醜いものとして扱われているような気がしてしまいます。容姿も性格もすべてひっくるめてその人で、ひとつの個性だと思います。もちろん本人が嫌がっていたらやらないということはとても大事で、薄毛に限らず本人が触れて欲しくないことをやるのは違うと思います」
“付け鼻”はダメですか?
「容姿」に関する世間の敏感さを知り、悩んだお笑い芸人もいます。若手トリオ、「青いデルタ」です。

準々決勝まで進出した2021年のキング・オブ・コントでのことです。
留学生が日本の家庭にホームステイしているという設定で、留学生の役は、金髪と付け鼻で演じました。
順調に勝ち進むなか、「私は気にならないけど、付け鼻を気にする人もいるのではないか」と心配するファンの声をツイッターで見つけたといいます。
青いデルタ
「ネタを作っているときは、問題になるとは全く思っていませんでした。子どもの頃に見ていたお笑い芸人の方たちを真似したつもりでしたが、確かにステレオタイプな表現だなと気づかされました」
そこで、NSCの講師など、何人かに意見を聞いてみました。
「決勝がテレビで放送されるということは考慮した方がいいかも」
「良いんちゃう?」
「心配だったらやめておいた方がいいかも」
賛成と反対が半々くらいという結果も踏まえ、設定の伝わりやすさ、ネタの面白さ、人を傷つける可能性があるかなどを、3人で話し合ったといいます。

「設定が留学生というだけで、外国人を笑いものにするネタではありません。その後、テレビのオーディションでもこのネタを披露したことがありますが、特に何か言われることはなかったので、賛否が分かれる微妙なラインだったのかなと思います」
「僕たちがテレビを見始めたときはすでにコンプライアンスを守ろうという雰囲気がありましたし、学校でも“悪口を言ってはいけない”と教え込まれてきた世代なので、同期を見ていても容姿ネタをやる人は少ないと感じています。もし、やる場合は、冒頭に相方同士で信頼関係が成り立っているという前提を示した上でネタに入るとか、悪意がないことを分かってもらうとか、工夫が必要だと考えています」
専門家は
この問題、どう考えればよいのでしょうか。
薄毛の男性について調査した『ハゲを生きる』の著者で、ルッキズムやジェンダーに詳しい昭和大学の須長史生准教授がポイントとして挙げたのは、他人に与える影響です。
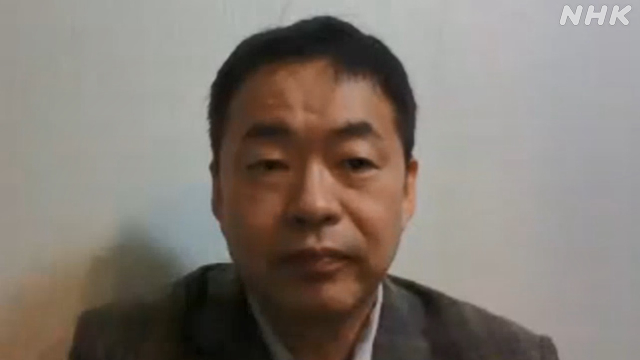
「『本人がネタにしたいのなら良い』ということがよく言われますが、その感覚だけでは不十分だと思います。外見を笑いにすることは、外見差別、つまり外見に対する定型化されたイメージによる攻撃につながるおそれがあります。特定のイメージを生きながらえさせ、社会に波及させてしまうことに問題があり、自分が良くてもその発言によってほかの人が苦しめられる可能性があることを考える必要があると思います」
一方、極端な反応も見られるとして、状況ごとに丁寧に判断する姿勢が重要だと指摘します。
須長准教授
「人はどうしてもわかりやすいルールを求めがちなので、『外見を話題にしたりジョークにしたりするのは一切やめましょう』となることがありますが、すべて封じてしまうのは『言葉狩り』であり文化的な貧困にもなってしまいます。異なる成育環境や価値観の人々が集まっている社会の中で考えるべきは、『妥当なラインがどこなのか』ということです。表現する側は発言が自分の意図とは異なって受け止められてしまう可能性や波及効果を自覚した上で、相手や状況を見て常に理性的に表現し、笑いにして許されるライン、許されないラインの間の妥当な線がどこなのか探っていく必要があると思います」
変わるか、笑いの現場?
笑いの世界が直面する変化。
NSCで10年以上講師を務め、これまで数々のお笑い芸人を送り出してきた放送作家の桝本壮志さんに聞くと、やはり現場では難しさを感じているということでした。
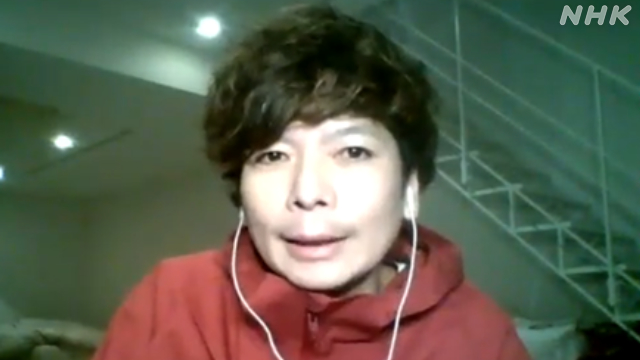
「今まで7000人くらいのお笑いの卵と接してきましたが、いじめられた経験があったり、家が貧乏だったりと、悩みやコンプレックスを抱えてきた子も少なくない。容姿の特徴もその1つです。そのキャラクターをあけすけにして自分のポジションを築いてきた子には、ある日“お笑いに向いているのかも”と思う瞬間があったと思うんです。そういう人たちの笑いを奪ってしまって良いのか、という思いはあります」
最近は、炎上への不安から「このネタはやっていいと思いますか」と質問に来る若手も多いといいます。そこで心がけているのは、コンプライアンスを守る大切さを前向きに伝えることです。
桝本さん
「僕の授業では、なんでもいいから面白いネタを持ってきてほしいと言っています。最初は、自分がどこまで(ネタの)飛距離を出せるかを知ってもらわないといけない。そこから先を修正していくのが、テクニックなんです。いまはお笑い芸人が世界中のファンを獲得し、活躍できる時代です。“このネタはダメだ”とか“芸人人生が終わるぞ”とかではなく、可能性の方を話してあげる。その上で、コンプライアンスは自分の身を守る鎧にもなるし、世界に打って出る武器にもなるんだよと伝えています」
そして、今後、重要になるのは、笑いに携わる人たちが、表現についての感度を高めていくことだと話しました。
桝本さん
「お笑いというのは相手を苦しめたり泣かせたりしようとしているのではなく、笑わせようとしているものです。音楽にもクラシックがあればロックやパンクもある。すべて品行方正なわけではなく、社会の端っこにいる人間の叫びもありますよね。お笑いが文化として本当に成熟していくなら、リテラシーも求められていく時代だと思う。そういう風に楽しんでいかないと、エンタメが育ちません。ひとつの芸術や表現方法として容姿があり、差別や偏見とは違う。そういった仕分けが、これから始まるんだと思います」
容姿と笑い 届ける側も 受け取る側も
「笑ってほしいと思って言ったことで傷つけた」、「つい笑ってしまったが、あとから『笑って良かったのかな』と考えた」。今回の取材では、こうした声に多く接しました。
どんなネタを笑いにするのか、何を面白いと感じるかは、時代や文化、その場の状況によっても変わるものではないでしょうか。
笑いを届けようとする人たちが試行錯誤を重ね、受け取る私たちも少し立ち止まって考えてみる、そんな姿勢が大切ではないかと感じました。