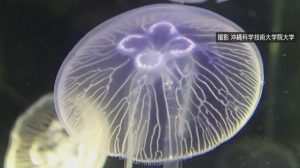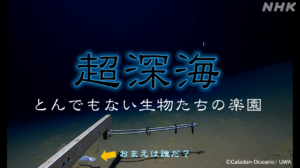科学と文化のいまがわかる
科学

畑にヒグマが出て困るぅ。だったら作物を変えてみたら? 北海道 上川町の畑で対策を見てきました。
2022.02.17
長年、北海道の酪農家を悩ませてきた飼料用のトウモロコシ被害。ヒグマの被害に遭わない方法に挑戦したのは酪農家と農業研究機関。栽培する飼料作物を変えてみたら成果が!
大雪山山麓の上川町で取材
ヒグマによる飼料作物のデントコーン(トウモロコシ)の被害が深刻な北海道の上川町で、北海道ではまだ馴染みが少ない新しい飼料作物を利用して、ヒグマ対策を行う試みを取材しました。
訪ねたのは大雪山の北にある上川町。
標高300メートルから600メートルの高原の冷涼な気候が牛の成育に適しているということで昭和49年から乳牛の生産が始まり、その後肉牛も生産されるようになりました。

現在では2つの農業法人と、2軒の個人経営の酪農家が牛を育てていて、町内では乳牛と肉牛あわせておよそ2000頭が育てられています。
経営を安定させようと自らの手で飼料用のデントコーンを生産してきましたが、長年ヒグマに食べられ、大きな被害に悩まされてきました。

畑のクマ
これまでヒグマは夏でも奥深い山の中にいると思っていた私の認識は大間違いでした。
奥山だけで生活する一部のヒグマをのぞくと、植物性の食べ物が固くなり栄養価が落ちる夏の終わり頃、多くのヒグマは人が育てた作物を食べるために畑に集まるのです。

専門家によるとヒグマは食べ物への順応力が高く、これまでにトウモロコシ、麦、米、カボチャ、ニンジン、ビート、牧草、スイカ、リンゴなど様々な農作物の味を覚えてきたといいます。
この様子を自分の目で確かめるところから取材を始めました。
8月下旬、上川地方北部の畑で白昼堂々とビートを食べるクマに出会いました。
夕陽が射し込む美しい風景の中、目の前に広がる畑には親子と思われるクマがいて食べたり、無邪気にじゃれあったりしていました。

デントコーン畑に暗視カメラを設置しました。
すると3日間で3頭の子連れと2頭の子連れの親子や単独で行動する3個体。あわせて10頭が映りました。

いったい何頭のヒグマが目の前の広大な畑に通って来ているのか?ただただ驚きました。
これまでに本州や北海道で野生のクマを撮影してきた私にとって、ヒグマが畑に当たり前のようにいる風景を目の当たりにして、どう解釈して良いか困ってしまいました。現れるヒグマの多さにも衝撃を受けました。
でもそれは私の思い込みから来る混乱であり、これがいまの彼らの姿なのでしょう。

デントコーン作付け奨励
国と北海道は飼料作物の自給率を高めようと、牧草に比べて栄養価が高いデントコーンの作付けを奨励しました。
その結果、今日に至るまで栽培面積は増え続け、令和2年度の道の統計によれば全道の作付け面積は57400ヘクタール。現在でも、毎年1000ヘクタールずつ増え続けています。
栽培面積の拡大はそれまでデントコーンを作っていなかった地域のヒグマにもデントコーンの味を覚えさせる結果を招き、ヒグマによる農作物の被害拡大の増加につながったと考えられます。
研究者は「デントコーンをたくさん食べたヒグマは、そのまま冬眠に入ることができるくらいの栄養を蓄えることができるのでは」と指摘します。
上川の酪農家 熊倉信幸さん
取材で訪ねた熊倉信幸さんは上川町内の農業法人で乳牛370頭を育てている酪農家です。
酪農家にとって牛のエサを自給自足することは経営の安定につながるため、これまで積極的に牧草とデントコーンを作ってきました。
しかしヒグマによる被害が年々増え続け、6年前には収穫前のデントコーンのおよそ7割が食べられてしまったことがありました。

「対策として48ヘクタールある畑の広範囲に電線を張り巡らせたが、漏電を防ぐために電線に接触する草木を刈り払うなど、広範囲を維持管理せねばならず大きな負担になっていた。また畑に出入りするヒグマと予期せぬ鉢合わせをしてしまう危険もあった(酪農家 熊倉信幸さん)」
冷涼な上川町でソルガム栽培
転機が訪れたのは4年前。上川町のヒグマ被害を気にかけていた、道立の上川農業改良普及センターの職員が、熊倉さんに話を持ちかけました。デントコーンに代わる飼料として、イネ科の「ソルガム」という植物を栽培してみないかと言うのです。

ソルガムはどのような植物?
ソルガムは温暖なアフリカ原産。気温が高くて乾燥している地域でも育つためアフリカからインド、中国に広がり日本にも入ってきました。
日本にいつ入ってきたのか正確には分かっていませんが、ソルガムは日本では「もろこし」、「たかきび」、「ほうきぐさ」などと呼ばれ、アワやヒエなどと同じ雑穀のひとつとされています。
「もろこし」も日本では古くから食用として栽培されてきました。日本では主に山間部の畑などで作られることが多く、気候が厳しい環境でも一定の収穫があるのが特徴です。

ソルガムにはデントコーンのような実がつかないので栄養価は劣りますが、穂を出す時期の前後になると茎の糖度が高まり、発酵させて保存性を高めた飼料にするのに適しています。
シンプルにいえば牧草と同じような栄養価で、収量が格段に多い飼料作物だといえます。
ソルガムの育種は戦後、温暖な広島県福山市にある農林水産省中国農業試験場で始まりました。
その後、熊本県にある九州沖縄農業研究センターや長野県畜産試験場などで試験栽培や品種改良が行われてきましたが、これまで北海道の気候に適したものはありませんでした。
こうした中、北海道にも拠点をもつ群馬県の種苗会社がドイツの冷涼な地域で栽培された品種を9年前に輸入し、群馬県と北海道の圃場で栽培試験を行ったところ、順調に育つことが確認されました。
この新しいソルガムは、栽培期間中の平均気温が、従来の15度よりも3度低い、12度で育つのが大きな特徴です。
上川農業改良普及センターはこの品種を含めた3種類のソルガムの栽培試験を上川町で行い、生育状況が良い1種類を選びました。
翌年には熊倉さんの牧場20ヘクタールで本格的に栽培したところ順調に育つとともに、クマが寄ってこないことも確認されました。
熊倉さんは、今では48ヘクタールのデントコーン畑のうち33ヘクタールをソルガムに切り替えて順調に収穫をあげています。

ソルガムは3.6メートルから4メートルほどの高さに成長し、今年の収穫は当初の予想より2割ほど多くなりました。
収穫したソルガムは9月下旬から12月上旬までサイロで発酵させます。厳冬期には、牛の体力を維持するために栄養価が高いデントコーンも与えますが、冬のはじめと春から秋にかけては同じく発酵させた牧草と配合飼料を混ぜたソルガムを与えます。
「たくさん食べてくれているので良かったと思います。嗜好性が良いのか、食いつきが良いので牛の健康状態もこれで良い方に保てるかなという感じですね。うちの牛たちはソルガムの味を覚えていると思うので毎年楽しみにしてくれているんじゃないかなと思います(酪農家 熊倉信幸さん)」

クマがソルガムの味を覚える日が来る!?
北海道立総合研究機構で長年ヒグマ対策を行ってきた、間野勉さんに聞きました。果たしてソルガムは、ヒグマ対策に有効なのでしょうか?
「ソルガムは穀物です。これまで麦や米、蕎麦を食べてきたヒグマには、いずれソルガムの味を覚えられてしまう可能性はあるでしょう。上川町でソルガムの栽培が成功して今のところヒグマがソルガムに寄りつかない状況だからといって安心はしないで欲しい。ヒグマは好奇心旺盛なので試しに食べてみる個体が出て来るかもしれない。美味しいと思ったら親から子へ、ほかのクマにも広がっていく」
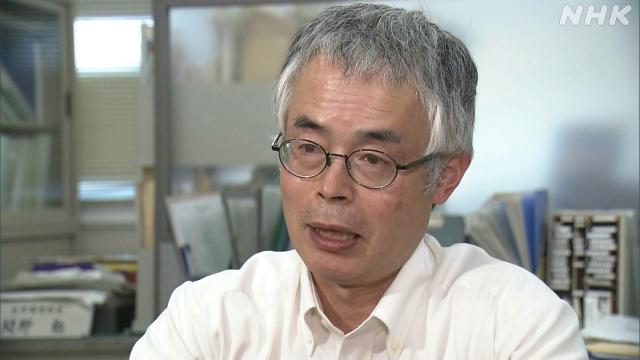
そのうえで「10年から15年間様子を見てそれでもヒグマがソルガムを食べなければ、ようやく安心できるかもしれない。今後も地元でソルガム畑へのヒグマの態度を観察し、ヒグマが食べ始めた兆候があれば、そのヒグマを特定して素早く排除することが大切だ」と話していました。
また間野さんは「新しい作物をヒグマの生息地に導入するときは、栽培の技術や普及を研究する行政機関や地域の農家、獣害対策を支える猟友会の人たちなど皆で考えて欲しい。そのための仕組み作りが実効的な対策に結びつく」と話します。
ヒグマが味を覚えてしまったら・・・ 品種改良はさらに続く
ソルガムは国や県の研究機関や大学、種苗メーカーなどで品種改良が進められています。
その中でも長野県畜産試験場は標高760メートルの塩尻市にあり、寒冷地におけるソルガムの育成試験や品種改良を昭和59年から進めてきました。
これまでに飼料用だけでなく食用やバイオマス燃料に利用するソルガムの開発にも取り組んできました。
今後はニーズに合わせて幅広い種類のソルガムをつくることを目指しています。

長野県畜産試験場では最近、病気に強く牛の消化を高める遺伝子を取り込んだソルガム「東山交37号」を民間の種苗会社と共同で育成しました。
消化率を高めたことで、栄養を多く摂取できるようになりました。
さらに牛が好んで食べる傾向が見られ、東山交37号と従来のソルガムの品種を牛の鼻先に並べて食べる量を比較する実験では、牛は好んで東山交37号を食べました。

また長野県畜産試験場では極晩生品種のソルガムの育成も行っています。
この品種は丈が3メートルにもなり十分な収量が確保できるうえ、動物たちのエサとなる穂を出す前に収穫期を迎えます。
クマやイノシシ、野鳥による被害をおさえるために試験を行ってきました。
獣害対策にもなり牛が好んで食べるソルガムが、涼しい北海道でも育つように改良されれば、ヒグマがソルガムを食べ始めた時の対策の次の一手になるかもしれません。