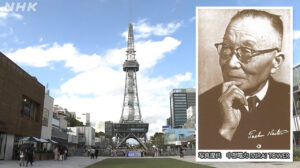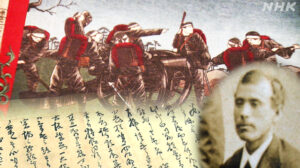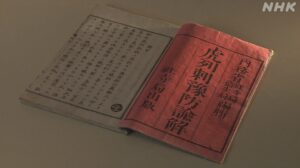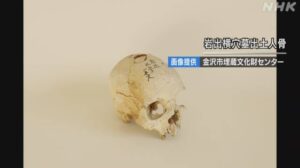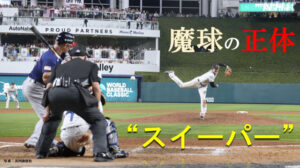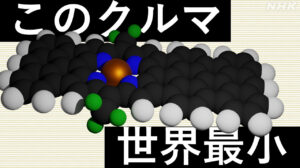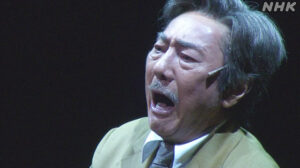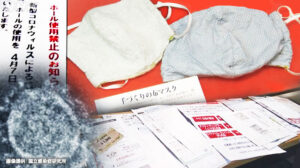科学と文化のいまがわかる
文化

YS11 陸路で引っ越し 一大プロジェクトに密着
2020.04.17
ことし3月、「YS11型機」の機体がトレーラーに載せられて、深夜の東京都心を駆け抜けた。羽田空港の格納庫から茨城県内の民間施設に保管場所が変わったことによる、陸路での「引っ越し」だ。この機体は、日本の科学技術史を語るうえで欠かすことのできない、YS11の「量産1号機」。陸路で搬送するには翼やエンジンを取り外す必要があるが、移転先での公開に向けて、再び組み立てることを前提にした慎重な作業が求められた。巨大な機体を解体したうえで搬送するという前代未聞のプロジェクトに密着して見えたのは、貴重な飛行機を何としても残したいという、関係者の熱い思いだった。
日本航空史上 非常に重要な機体
YS11は昭和30年代に開発が進められ、昭和40年から平成18年まで日本の定期路線を運航していた戦後初の国産旅客機。昭和39年の東京オリンピックでは聖火を運んだことでも知られ、試作機を含めて182機が生産された。

このうち量産1号機は昭和40年に当時の運輸省航空局に引き渡され、空港の無線の状況などをチェックする飛行検査機として、平成10年に引退するまで2万時間を超えるフライトを行ってきた。
引退後は国立科学博物館が引き取り、羽田空港にある格納庫を借り受けて保管。平成19年には、日本機械学会が設けた第1回目の「機械遺産」に、東海道新幹線の「0系」などとともに選ばれている。

国立科学博物館 産業技術史資料情報センターの鈴木一義センター長は、終戦で航空機の製造が禁止されたあと、日本の航空産業がどのように発展していったのかを知るうえで、非常に重要な機体だと指摘する。
日本の戦後復興が終わって、各地に空港ができて、これから航空の時代だということになった時に、飛行場をチェックする際に使われたのが量産1号機。日本の航空史上でも非常に重要な機体です。当時の設計された方、現場の方たち、いろんな苦労が注がれるわけですから、その結晶として非常に価値があると思いますね。
貴重な機体がスクラップの危機に
鈴木さんは、この機体のメンテナンスをおよそ20年にわたって続け、実際に飛ばすことはなかったものの、エンジンの掛かる状態で維持管理を続けてきた。しかし、一転、スクラップの危機に陥る。保管している格納庫での管理が難しくなり、立ち退かなくてはならなくなったのだ。
鈴木さんが移転先探しに奔走した結果、茨城県筑西市にある民間施設「ザ・ヒロサワ・シティ」に移して一般に展示・公開することになった。機体を一度解体して搬送し、再び元通りに組み直すプロジェクトが立ち上がった。
ベテラン整備士が集結
去年の9月30日。鈴木さんと、解体作業を行うメンバーが「解体はじめ」に臨んだ。
リボンを付けた工具で1本のネジをみんなで少しずつ回して抜き、現場での作業がスタートした。

解体作業を行うのは、かつて航空会社で働いていた、およそ20人の元整備士たち。全員が70歳前後の大ベテランだ。
その1人、佐藤正弘さん(73)は、およそ50年前にYS11の整備に携わった経験があり、チームの頼れるリーダーだ。佐藤さんは、量産1号機を残していきたいという思いとともに、これまでたった1人で保管を続けてきた鈴木さんの熱意に胸を打たれていた。

この飛行機を直接解体するなんていうのはまずない。YSをいじっていた人間としては感動しますよね。
解体は大変な作業だが、なんとしてもやり遂げようと思うのは、やはり鈴木さんの思いがあるからです。あの人にはかなわない。ものすごい熱意を持って、機体を残していこうという気持ちがみんなを動かしている。
解体は取り外しやすいところから
10月に入ると、次々に機体からパーツが取り外されていった。まず取りかかったのは、プロペラ、エンジン、タイヤだ。

機体は再び組み立てられるように、慎重にパーツを取り外す必要がある。当時の整備マニュアルなどを参考に、どこを取り外すことができるのか確認したうえで作業を進めていった。
当初は、半年間かけて解体する予定だったが、鈴木さんのメンテナンスが功を奏して、ネジやボルトにさびが無く、作業は前倒しで進んでいった。

11月には機体の後ろ側に足場を組み、尾翼の取り外しにかかっていた。垂直尾翼は、高さ5メートルほど。クレーンでつり上げて、慎重に地上に降ろしていった。
外れないパーツをどうするか
作業がスムーズに進んでいくなかで、どうしてもうまく進まない部分があった。主翼の解体が、思うように進まないのだ。

主翼は幅が広く、胴体から取り外すだけでは運ぶことができない。
このため後ろ半分を取り外すことにしたのだが、タイヤなどの消耗品と違い、外れないように永久結合されているため、どの場所を切り離せばパーツが外れるのかわからない。佐藤さんたちは再び組み立てる際に影響が出ないよう、検討を重ねながら慎重に切り離す部分を決めていった。
永久結合なので、ここを外しなさいという手順が全くないんですよね。普通外さないですから。いろいろ組み合わさっているので、ここだけ外れれば全部外れるということではないんですよね。どこで分けるのか。元に戻るように考えながら、解体の方法をとっていく。(佐藤正弘さん)

検討を重ね、およそ1か月かけて主翼の後ろ部分を取り外すことに成功。ことし1月には主翼がすべて取り外され、解体作業は無事に終了した。
解体して初めてわかったこと
リーダーの佐藤さんは、解体する中で、ある違和感に気がついた。主翼に、設計図にはない部品やつぎはぎが見つかったのだ。佐藤さんは、部品を取り付ける位置を間違えたり、取り付けた部品を改良したりと、試行錯誤しながら量産1号機が造られていったと推測し、当時の人たちの苦労や熱意を感じたと話す。

翼の左右の造りが違う。右のほうの翼は、今の設計図に描いてあるものなんですけども、左側は部品が付け足しのようになっている。必要のないところに、いろいろ穴が空いていたりとか、そういうのを直したりとかもありますし。それはいかにも、造る人の苦労なんじゃないかなと。造った人が見れば、『あぁ、ここはこうだったな』とわかるかもしれませんね。(佐藤正弘さん)
「娘を嫁に出す気分」

3月27日。格納庫には、胴体と左右の主翼をそれぞれ載せる大型トレーラーが3台到着した。積み込みは夕方までに完了し、午後4時半、ついに格納庫を出発。その姿を見守っていた鈴木さんに今の気持ちを聞こうと話しかけたところ、「今は何か話したら泣いてしまうかもしれない。大切に育ててきた娘を、嫁に出す気分だ」と声を震わせた。解体を行った佐藤さんは、少し離れたところから、じっと機体を見つめていた。

28日午前0時。胴体を載せた大型トレーラーが羽田空港を出発し、品川駅前、上野駅前、千住大橋と、深夜の東京都内を走って行った。

沿道には、ふだんは見ることができない「飛行機が道路を走る姿」を写真に収めようと人が集まっていた。全長26メートルという巨大な胴体が道路を通過する様子は非現実的で、SF映画のワンシーンを見ているようだった。

そして午前5時ごろ、およそ100キロ離れた茨城県筑西市の施設に到着。その日のうちに保管場所に降ろされ、損傷などがないことが確認された。
実物があるからこそ伝わる
引っ越しを終えたYS11の量産1号機は、年内には組み立てを終えて、展示・公開される予定だ。
なぜ、ここまでして機体を残さなければならないのか。そこには、実物が残っているからこそ、人々がたどってきた過去や科学技術の進歩の過程を伝えることができるという、鈴木さんの強い思いがあった。

近代、現代のものは、江戸時代の美術品などと違い、残すために造られているわけではない。その機能が終わったらスクラップされてしまうものです。日本がものづくり大国、科学技術立国であるというのであれば、そういうものを残して、それを伝えていくことで、初めて次の人たちにバトンタッチして、思いをつなげることができる。
飛行機も含めて、本来ならスクラップにされるものをどう残していくのか。こういった試みを通してこれからも『大いなる実験』が続けられていくんだと思います。
私が量産1号機の移転の話を聞いたのは、今から2年前の平成30年5月だった。その後、この機体をなんとか残そうと、鈴木さんが移転先探しに奔走している姿を見てきた。熱意や思いのある人がいて初めて文化財が残っていく現状を、目の当たりにした。文化財の保存・管理という、地道だがとても大切な仕事を行っている人がいるということを少しでも知ってもらうために、これからも取材を続けていきたい。