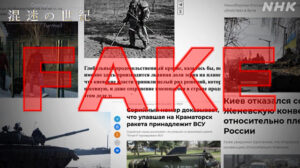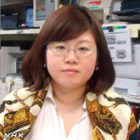科学と文化のいまがわかる
文化

高校教師が挑む 2人の巨匠背負った舞台
2018.10.19
8年前に亡くなった劇作家で小説家の井上ひさしが、タイトルと構想だけを残していた作品「母と暮せば」が、この秋、初めて舞台化された。戦争について多くの作品を書き残していた井上が「書かなければ死ねない」とまで言っていた、長崎で被爆した母と息子の物語。その遺志を継いで、3年前に山田洋次監督が映画化した作品でもある。
この2人の巨匠の思いが詰まった作品の舞台化に挑んだのは、青森の高校で美術を教える1人の教師だった。
その名は「畑澤聖悟」

ことし7月に東京 新宿で行われた製作発表。壇上に現れた1人の劇作家の言葉やたたずまいに、私はとてもひかれた。
「8月6日や9日、15日が何の日か知らない生徒がいる。そこに私は悲しさを感じる」
まっすぐなまなざしに、確かな志が感じられた。

畑澤聖悟さん(54)。青森市内の県立高校で美術を教える現役の教師だ。22年前から演劇部の顧問を務め、戦争や原爆、いじめなどを独自の視点で描いてきた。
演劇部は全国大会の常連で、これまでに3度「最優秀賞」を受賞。高校演劇でその名を知らない人はいない劇作家だ。

畑澤さんが「母と暮せば」の脚本を書いてほしいと依頼を受けたのは、ことし1月。当時のことを「喜んで引き受けたあと、だいぶ後悔した」と振り返る。
井上ひさしには「父と暮せば」という広島で被爆した父娘を描いた屈指の名作があり、今回の作品が、この「2人芝居の教科書のような作品」(畑澤さん)と比較されることは避けられない。
しかも、「母と暮せば」は山田洋次監督の手によって映画化もされている。改めてこの映画を見直した畑澤さんは、その完成度の高さに圧倒されたという。
「何度見ても新しい発見があって、1回目と10回目の印象が全然違う。ものすごく高い壁だと思った」
原爆や差別への怒りを表現
畑澤さんは、現地調査などを踏まえて脚本を執筆。原爆で亡くなった医学生の息子 浩二が、幽霊となって助産師の母親のもとに現れるという映画の設定を踏襲したうえで、新たな2人芝居にしていった。

作品づくりの根底にあるのは原爆への強い怒りだ。自分が死んだことを「運命さ」と嘆く息子に、母親は怒りをあらわにする。
<違う。断じて違う。こげん馬鹿なこつは運命なんかじゃなか!>

畑澤さんは「原爆という、あんな恐ろしいものを人の頭の上に落とされたことに対する怒りをきちんと持つべきだ。どの高さで爆発させればいちばん効果が得られるかという研究をしていることに、きちんと怒らないとだめだと思う」と語る。

井上ひさしも、そんな憤りを表現し続けてきた。今回の舞台のチラシに引用されている井上の言葉がある。
「核兵器というものは、どこまでも人間をつけ回し、なんどもなんども人間を騙し討ちにして、人間の生きる勇気と誇りを台なしにする悪魔の贈物であって、こんなものを兵器だの爆弾だのと『やさし気に』呼んではいけない。たとえ、どんな理由があろうと、こんなものをつくったり、保持したり、人間の上に落としたりするやつは、この世の大ばかやろうである」
さらにもう1つ、畑澤さんがどうしても入れたかったことがある。
被爆者に対する差別への怒りだ。
助産師をしていた母親が妊婦に食べ物を届けた際、相手の家族から断られたことを振り返る場面。諦めたように話す母親に、息子は強く訴える。
<無知が招いた偏見たい!>

こうしたやり取りは、今の社会にも通じると畑澤さんは指摘する。
「ピカの子は結婚できないとか、職場で差別されたりしたのは、神奈川で福島の小学生がいじめられるのと一緒だ。要は何も変わっていない」

山田監督も感服
9月中旬、舞台の稽古場に山田監督が訪れた。

監督は出来上がった脚本を読み、劇団の担当者に電話で4回も感想を伝えたという。
稽古を見たあとに改めて感想を聞くと、「はっきり言って映画よりいいところがたくさんあると思う」と率直な思いを語ってくれた。

山田監督がいちばんの見せ場と指摘したのが、息子が被爆するシーンだ。映画では、大学の授業中にせん光が走り、窓ガラスが爆風で吹き飛ぶ様子を衝撃的に描いた。山田監督がこだわり抜いた描写だ。
演劇ではどう表現したか。畑澤さんは、被爆した瞬間の体が燃える様子を、息子自身に語らせた。
脚本のト書きには「浩二の体に熱さが蘇る」と書いてある。
<足首が燃えて、膝が燃えて、もう何も見えん。ただ熱か>
<腿が燃えて、腰が燃えて、もう何も聞こえん。でも熱か>
<熱か熱か熱か熱か…>
30回以上も「熱か」と叫び、もがき、苦しみながら、「もう一度だけ母さんに会いたか」と願う。
一人の生きていた人間が死んでいくさまを、徹底して表現した。被爆体験を1人の人間に落とし込む。このことが見る人の想像力をかき立てると信じたからだ。

被災地で感じた「絶望的な喪失感」
70年以上前に起きたことを、どう自分のこととして感じてもらうか。
戦争体験がない世代の書き手として大切にしたのが、東日本大震災の被災地で考えてきたことだ。畑澤さんは震災の半年後から、被災地で高校生と演劇を上演してきた。
被災者と交流する中で感じたのは、今なお残る「絶望的な喪失感」だったという。あの時、こうしておけばー。大切な人を失った悲しみは、やがて後悔となって、生き残った人の心をいつまでもかき乱す。
「1万8000人が亡くなると普通に弔うこともできない。普通に死ねないことが、こんなにも悲しいことなのかと思った。大震災の悲しみはそこなのだと感じた。それはあらゆる自然災害やテロでも同じことだと思う」
<なして、うちはあんたば止めんかったとやろう?…空襲警報が鳴っとったのに>
<なして、うちはあんたば止めんかったとやろう?…あんなに胸騒ぎのしとったとに>
舞台で、母親が8月9日に息子を大学に送り出したことへの後悔を繰り返し叫ぶシーンは見る者の心を打つ。戦争や大震災を経験していない人でも、この喪失感は共有できるー。畑澤さんの意図はそこにある。

ラストシーンに込めた思い
そしてラストシーン。畑澤さんは強いメッセージをせりふに込めた。生きる苦しみから解放されたいと訴える母親に対し、息子はそれでも「生きろ」と諭すのだ。
「生きることに絶望しながらも、どこかで生きたいと願っている。生き残っていい人間ではないと思いながらも、どこかで生きたいと願う。そういう人の願いが、幽霊となって出てくるのだと思う」
生きることを肯定して、終わりたい。苦しみを抱えながらも今を生きる人たちへの、温かく力強いメッセージだった。

過去の悲劇を未来に伝える
戦争やその痛みを伝えるために演劇でできることを考え抜いた日々。畑澤さんは、そこで得た一つの答えがあるという。
「悲劇を今に伝えるだけでなく、未来に伝え続けるのだという強い覚悟をもつこと」
時に「時代の子」とも評される舞台演劇。時代の空気を反映させるため、畑澤さんも作品には賞味期限があると考えていたという。しかし、井上ひさしの作品のように古びないものもある。
「数十年の時間に耐えられるものを作る努力をこれからも続けていきたい」

舞台は10月21日まで東京で上演されたあと、12月にかけて全国を巡回する。畑澤さんの作品はそのあとも語り継がれるものになるはずだ。