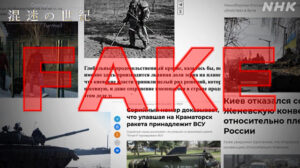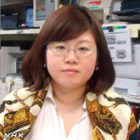科学と文化のいまがわかる
文化

“沖縄”を伝え続ける 演出家・栗山民也
2021.12.27
栗山民也さん。
今、最も忙しい演出家の1人だ。
その栗山さんが手がけた舞台が来年早々、幕を開ける。
本土復帰50年となる“沖縄”がテーマ。
「頭の中にはずっと沖縄がある」と語った栗山さん。
それはなぜなのか。
そして、どんな舞台を観客に届けようとしているのだろうか。
演出家・栗山民也

栗山さんは東京都出身で68歳。
1980年に「ゴドーを待ちながら」で演出家としてデビューし、その後、数々の舞台を手がけてきた。
芸術選奨文部科学大臣賞や紫綬褒章、それに菊田一夫演劇賞などを受けた演劇界の重鎮でもある。
私が、最初に栗山さんを取材したのは3年前。
井上ひさしがタイトルと構想だけを残した「母と暮せば」の舞台だった。
俳優やスタッフにかけることばからは、演劇にかける情熱が伝わってきた。
なぜ“沖縄”を伝えるのか
戦争の惨禍や平和の尊さを描いてきた栗山さんが今回挑むのは“沖縄”。
沖縄は来年、本土復帰50年となる。
「きっかけはある」のだ。
とはいえ、“なぜ今、沖縄なのか”。
改めて聞いてみると、栗山さんは「直球だね」と苦笑した。
(栗山さん)
沖縄との出会いは25年くらい前。
沖縄在住のプロデューサーから電話があり、彼女の熱がすごくて、初めて沖縄を題材にした作品を演出しました。
沖縄で飲み屋に行けば、初めて会ったのに数年来の知り合いのように話しかけてくる。
あっという間に手をつないで、輪になっていくような感覚があるんです。
一方で、空港から車を走らせると、左側にはずっと米軍基地がある。
これはいったい、どういう状況なのだろうと。
すごく明るく陽気で温かい感触と、全く変わらない米軍基地の存在。
この25年でよい方向に行ったのかと言われると、何も変わっていない。
頭の中にはずっと沖縄があるんです。
ある意味でこだわりがあるんでしょうね。
政治ではなく、家族を描く

新作舞台「hana-1970、コザが燃えた日」は、沖縄の本土復帰の2年前、基地近くの「Aサインバー(アメリカ軍公認の飲食店)」で起きる、ある家族の物語を描く。
その狙いは何だろう?
(栗山さん)
50年の節目で舞台を作ろうとすると、必ず“メッセージ”になってしまう。
しかし演劇は、メッセージを声高に言うことが大切なのではなく、そこに生きている、あるいは生きてきた人間たちの空気感を観客に伝え、同時に体験していくものなんだと、僕はずっと思ってきました。
実はシェイクスピアも、ギリシャ悲劇でも、全部、家族を描く「家族劇」なんですよ。
ただ、背景にある社会の動きや歴史の重みのようなものが、必ず家族に何か影響を及ぼしている。
そこまで描かないと、作品の深さや広さが伝わらないと思っています。
なるほど…
家族の姿、そして、そこに押し寄せる運命のようなもの。
そうしたことを描くということなのだろうか。
栗山さんは続けた。

(栗山さん)
今回の作品も基本的には“家族のかたち”を描くんですが、やはり沖縄ですからね…
俳優たちにもよく言うんですが、僕が泊まるコザのホテルの食堂には、朝食のとき、いろんな人が集まって、いろんなことをしゃべっているんです。
僕のテーブルの隣では、地元の女性たちが普通にオスプレイの話をしている。
つまり日常の中で政治が語られているわけです。
日常生活の中に、くさびのように、基地問題に代表されるようなことが刺さっている。
だから家庭劇を作るとき、1つのことばの裏側には、必ず沖縄の空気が流れているべきだと。
そうでないとウソになると思うんです。
沖縄の人たちの生活のすぐ隣には、アメリカ軍の人がいて、基地がある。
そうした存在を切り離すことは不可能。
栗山さんは、そうした空気感のようなものを、舞台で表現しようとしているのかもしれない。
「コザ騒動」とは
栗山さんが舞台の背景に据えるのは、1970年12月の「コザ騒動」だ。
太平洋戦争でのアメリカ軍の攻撃と多数の死傷者、その後の占拠。
占領下の沖縄では罪を犯したアメリカ兵を裁くことも、ままならなかった。
そうした歴史が積み重なるなかで「コザ騒動」は起きた。
コザ市(現在の沖縄市)で、アメリカ兵が住民をはねたことをきっかけに、人々の怒りが爆発した。
アメリカ軍の憲兵の威嚇発砲をきっかけに、米軍関係者の車に次々と火が放たれた。
「コザ暴動」、「コザ事件」などとも呼ばれる。
(栗山さん)
「コザ暴動」とは、果たして暴動だったのかなと。
沖縄の大学の先生のことばに「これは市民革命であった」と、あるんですよ。
僕はそれが正しいと思う。
つまり市民たちの煮えくりかえるようなメッセージが、ああいう形になったんだという気がするんです。
沖縄で、家族で、何を描くかというときに、敢えてこの時代を描こうと思った。
やはり、あの騒動は沖縄の人たちが自分について見つめ直したときだったのではないかなと僕は思いますね。
でも、そうした政治的メッセージだけではなくて、僕が沖縄で肌と肌で感じた熱さもあって、それは何だろうと。
向こうからどんどんぶつかってくる。
それはむしろ愛情ですよ。
僕はそれを沖縄でつぶさに感じているので、当然、劇の中に入れなくてはならないと思っています。
いろんな要素があり、ぶつかり合いながら、すごく健康に人々が生きていることも伝えないといけない。
その矛盾ですね。
僕の体の3分の1くらいは沖縄ですよ。
演劇はエンターテインメントか?
話は栗山さんの演劇観に及んだ。
栗山さんは「ちょっと長くなるけどいいかな」と、少し笑った。
(栗山さん)
僕はね、演劇はエンターテインメントだとは思わないんです。
そういうものがあってもいいと思うけれど、実は死者たちがよみがえるのが演劇なんです。
え!?
それはどういうこと?
詳しく聞きたい!

(栗山さん)
人間の記憶は、時代の記憶になる。
そのなかで忘れられていった人々、つまり切り捨てられた人たちに目線を送らなくてはいけない。
フランスの演劇学校で授業を聴講したときに、「演劇は歴史の記憶装置である」と言った先生がいました。
そのことばは僕の中に刻まれています。
つまり演劇の作品とは、「まだ生きたい」と思いながら死んでいった人間たちに、今を生きる劇作家がことばを与えるものだという気がするんですよね。
現代の作家が昔の人に与えたことばを、現代の肉体をもった俳優が、現代の観客と共有する。
これが僕は演劇だと思うんです。
そんなことを思いながら、ずっと稽古を続けています。
「コザ騒動」とはいったい何だったのか、いつも考えています。
そこにいた人間たちの声は、どんな声で、どんな温度で、どんな匂いだったのか。
それを必死で探すのが今の稽古です。
稽古の間に、俳優たちと“声”を見つけようよと。
僕たちは実は歴史の旅をしていくっていうか。
それが僕たちの演劇の時間だなと。
栗山さんのまなざしの先には…
栗山さんは、芝居の合間、俳優たちに本土復帰前後の沖縄での出来事や、自分が学んだ人々の思いを熱量たっぷりに伝える。
栗山さんのまなざしは、今の社会にも向けられている。
(栗山さん)
沖縄でお酒を飲んでいると、30分後には、お祝いの踊りの「カチャーシー」が始まって、誰からともなく歌う。なんだろう、この空間はと。
東京で仕事をして生活していると、人間どうしのぶつかり合いがなくなってしまったと感じる。
けんかも恋もしない。
自分が傷つくことがイヤで、ただインターネットと向き合って、毎日を送るようになってしまっている。
今、新型コロナの影響で、「演劇」とは対極の状況にあります。
劇場は密になるし、それが本当に芝居になったときには全員が1つになり、家族になる。
その状況になったときに、僕はこの仕事をやっていてよかったなと思う。
劇場の使命は、僕はそういうことだと思う。
いろんな形でぶつかり合って、そこから何かを見つける。
それが、沖縄には存在しているんですね。
そんなことをぜひ感じてもらいたい。

「hana-1970、コザが燃えた日」は来年1月9日、東京芸術劇場プレイハウスで幕を開ける。
主演は俳優の松山ケンイチさん。余貴美子さんや岡山天音さんも出演する。
この1か月、私は取材を続けている。
改めて、その稽古の様子を、そして舞台に込められた思いを、伝えたいと思う。

NEWS UP“沖縄”と向き合う 俳優・松山ケンイチの挑戦

NEWS UP高校教師が挑む 2人の巨匠背負った舞台
ご意見・情報 をお寄せください