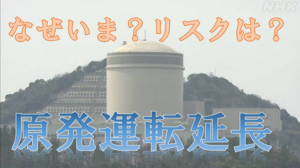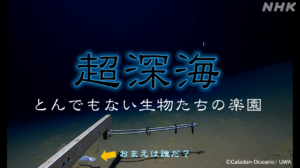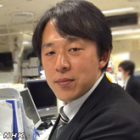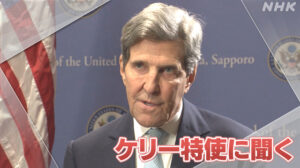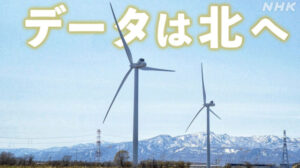科学と文化のいまがわかる
科学

過度な放流は逆に魚を減らす!? 最新の研究にどう向き合うか
2023.08.31
「魚の稚魚を放流しすぎると、逆に魚が減ってしまう」
ことし2月、驚きの研究が明らかになった。
北海道をはじめ全国では、魚の資源を増やそうと、100年以上にわたって放流が行われてきた。ところが発表された研究は、過度な数の稚魚を川に放流すると、生態系に悪影響を及ぼして、川に生息するすべての魚を減らしてしまうと指摘していた。
魚を増やすため、放流に長く頼ってきた私たち。最新の科学は何を突きつけているのか。取材した。
(札幌放送局記者 黒瀬総一郎)
過度な放流は逆に魚を減らす
世界的な科学雑誌、「アメリカ科学アカデミー紀要」で研究を発表したのは、北海道立総合研究機構や、アメリカ東部にあるノースカロライナ大学などの国際共同研究チームだ。

資源を増やすために行われている人工授精で産まれた魚の放流が、川の生態系にどのような影響を与えているのかを見極めようと、北海道で長年、放流が行われてきたサクラマスに注目した。

2019年までの21年間に北海道内の31の河川で調査したサクラマスの放流の規模や川にいる魚の生息数のデータを利用して、放流後、川に生息する放流したサクラマスを含むすべての種類の魚の数がどのように変化していくのかを統計学などを用いて解析した。

その結果、放流が大規模に行われている河川ほど、すべての種類の魚の数が減る傾向があり、さらに大規模な放流を繰り返せば繰り返すほど、魚の中には、とうたされて、いなくなってしまう種類も出てくるとする解析結果が出たという。

北海道立総合研究機構 卜部浩一 研究主幹
「私たちにとっても非常にショッキングな解析結果で、間違っていないか、シミュレーションを含めて何度も検証した」
しかし、そのシミュレーションでも、同じ結果が繰り返されたという。すなわち過度な放流は、在来の魚を追い出してしまうという思わぬ効果があり、さらに増やすために放流したはずの魚の繁殖にもつながらないというのだ。
北海道立総合研究機構 卜部浩一 研究主幹
「川の生態系の許容量を超えた大規模な放流を行うと、エサや住みかの奪い合いになり、生態系のバランスが崩れてすべての種類の魚の減少につながってしまう可能性があることを理論と実証の双方で証明したのは、世界で初めてだ」
この研究は、SNS上でも大きな反響を呼んだ。
「ショッキングだ」
「放流の新たな常識になるのではないか」
長年、放流について取材を続けてきた私にとっても、衝撃の研究だった。
確かに、関係者のあいだでは、放流の効果について疑問を呈する声はあった。
しかし、過ぎた放流は効果がないだけでなく、川にいるすべての魚を減らしてしまうほど生態系に影響があるという帰結は、想像を超えていた。
そして研究は「環境収容力」、すなわち、「ある川が養うことのできる生き物の総量」というキーワードを挙げた。
北海道立総合研究機構 卜部浩一 研究主幹
「自然界における放流は魚の種類によっては必ずしもプラスに働かないことがわかった。自然の持つ『環境収容力』、いわゆる器の大きさを超えない範囲での放流が今後は大前提になると思う」
川にはその川なりの許容量がある。だから魚はそれに見合った数しか生息できない。人の都合だけでは魚は増やせない。これまで想定されていなかった現実を最新の科学が示していた。
「ふ化放流」でサケの生態が変化!?
サクラマスの最新研究は、「環境収容力」の重要性を明らかにした。一方、サケの研究でも、新たな知見が次々と明らかになっている。
このうち、国の水産研究・教育機構の長谷川功 主任研究員たちの研究チームは、日本に生息するサケ=シロザケの卵=イクラについて、年々小さくなっているとする研究結果をまとめた。

国などが1994年から2010年までに集めた、サケおよそ3万匹分のイクラのデータを分析すると、17年間で1粒の平均の重さが最大でおよそ6%軽くなっていたことが分かったのだ。粒が徐々に小さくなったことが原因とみられるという。一方、サケ1匹あたりの産卵数は増えていた。
1匹から採れるイクラの量はほとんど変わっていないというが、研究チームではサケの生態に何らかの変化が起きているのではないかと分析する。

水産教育・研究機構 長谷川功 主任研究員
「卵はサケにとっては次世代を残すために一番重要なもので看過することはできない」
なぜイクラが小さくなっているのか。研究チームは、気候変動などの影響に加えて、放流も原因になっているのではないかと指摘する。
サケのふ化放流は明治時代から続けられてきた。稚魚を「ふ化場」でおよそ半年間、エサを与えて人工的に育て、1グラムほどに成長すると川に放流する。サケはその後、海に下って、北太平洋を回遊、3年から5年ほどで再び生まれた川に戻ってくる。その際、沿岸に仕掛けた定置網で漁獲される。

長谷川さんは「ふ化場」の環境がイクラの小型化に関係しているのではないかと考えているのだ。
水産教育・研究機構 長谷川功 主任研究員
「ふ化場の中だとエサも十分に与えられるし、外敵もいないということで、小さく産まれても大丈夫。卵がどんどん変わってきたのだと考えている。何らかの負の側面があるかもしれないため、さらなる研究が必要だ」

ふ化放流がサケの生態に影響を及ぼしている可能性を指摘する研究は、実は国内外で相次いでいる。
日本では、ふ化放流のサケが野生のサケに比べて遊泳力が低いとする研究があるほか、アメリカやカナダでは、ふ化放流の魚はと野生の魚と比べて、発現している遺伝子が一部異なっているとする研究も発表されている。
こうした研究結果を国も深刻に受け止めている。水産庁が設けた検討会は、「サケ資源が急激に減少している要因として、ふ化放流による遺伝的な影響による可能性も否定できない」と指摘して、検証を求めているのだ。
人は魚にどう関わっていけば良いのか
最新の科学が新事実を次々と明らかにするなか、放流の現場でも新たな取り組みが始まっている。
キーワードは、「自然産卵」。
放流だけに頼るのではなく、自然産卵も促すことで、資源を増やそうというのだ。
北海道日高地方。ここでは8のふ化場で「ウライ」と呼ばれる、ふ化放流に欠かせないはずの設備を撤去するという試みが行われている。

サケのふ化放流では、産卵のために生まれた川に戻ってくる性質を利用して、「ウライ」で川の下流をふさぎ、すべてのサケを捕獲する。その上でふ化場まで運び、人工授精を行ってきた。
ところが。


ふ化場で「ウライ」を取り除いて、サケが自力で川をのぼれるようにしたところ、大量のサケがふ化場の池に自力で戻ってきたほか、川で自然に産卵するサケが増えたという。
ふ化場を運営する団体では、自然産卵を増やすことが資源全体の増加につながる可能性があるのではと考えていて、今後も継続して効果を見極めることにしている。

日高管内さけ・ます増殖事業協会 清水勝 専務理事
「ふ化放流しかだめだという状態ではなくて、自然の環境も形成しながら共にやっていったらいいと思っている」
日高地方のような取り組みの効果を裏づける研究もある。
水産研究・教育機構の佐橋玄記研究員たちの研究チームは、ふ化放流のサケと野生のサケが交配したときに、稚魚から成長して大人になって戻ってくる「回帰率」にどのように影響するのか、道内の6つの川を対象に調べた。

その結果、人工授精に用いるサケの親に野生のサケが含まれていて、その割合が2割から4割に増えると、稚魚の「回帰率」が高くなり、試算では1.9倍にまで増えることが分かったという。
ふ化放流と自然産卵のどちらかを選ぶのではなく、両立させることが、資源増加につながるというのだ。
水産研究・教育機構 佐橋玄記 研究員
「ふ化放流と野生、両方を可能にすることで資源の回復につながる可能性がある。だからこそ、自然産卵を促す方策が必要だ」
そして佐橋研究員は、両立は無理なくできるはずだと話す。

実は「ウライ」で回帰してきたサケをたくさん捕獲しても、ふ化場が育てられる稚魚の数には限界がある。捕らえても人工授精に用いることのできないサケを、自然産卵できるようにする。日高地方の試みは、全国のふ化場で行える取り組みではないかと指摘する。
一方、「環境収容力」の向上を目指した取り組みも始まっている。
ことし3月、北海道開発局は、北海道の十勝川水系で、水害への備えを強化しながら、サケなど魚の資源回復にもつながる新たな治水対策についての検討を始めた。

北海道の川も気候変動で洪水リスクが高まっている。そのリスクを下げるために、川を掘って水が流れる面積を増やす「河道掘削」という工事が検討されているが、川の「環境収容力」が高まるように工事を行えないか、議論することにしている。

例えば、「ワンド」と呼ばれる池のような地形を川に沿って作り出せば、大雨が降ったときに、一時的に水をためることができる。そこは魚のすみかにもなりえる。

検討会の委員長 北海道大学大学院 中村太士 教授
「漁業者など地域の方々の理解を得ることが重要で、取り組みの効果について科学的に評価、検証しながら進めていきたい」
さらに、北海道の川にあるダムや「えん堤」と呼ばれるせきを改良すれば、サケが自然産卵ができる場所が飛躍的に増えるのではないかと指摘する研究成果もある。

北海道大学などの研究チームは、サケが北海道で自然に産卵できる場所はどのくらいあるのか分析した。すると、産卵が可能な領域のうち、49.6%が利用できない状況にあるとみられることが分かった。ダムや「えん堤」に阻まれて、サケがそれより上流に行けないからだ。

研究チームによると、ダムやえん堤を改修すれば、上流での産卵が増えると指摘する。そしてすでに改修が行われ、効果が確認されている川もあるという。

北海道大学大学院 山田太平さん
「いまあるダムやえん堤のかたちを改造するなどして、サケがのぼりやすいようにする必要があるのではないか」
最新の研究が明らかにする、放流に関わる新事実。そして、北海道で始まった新たな取り組み。
取材を通して実感するのは、自然環境の複雑さだ。研究の対象となっていたサクラマスとサケは、川で暮らす期間が違う。このため一方の研究結果を、もう一方に安易に当てはめてはならない。どのくらい放流すると過度なのか、その具体的な数を見極めるには、魚ごとのさらなる研究が必要だ。

最新の科学を踏まえて放流を行うことの重要性。それは人が魚、そして自然にどう関わっていくのか、模索することでもあると、専門家は指摘する。

北海道立総合研究機構 卜部浩一 研究主幹
「生態系は非常に複雑な結びつきで成り立っていて、人間がすべて理解することは難しい。自然界の営みを乱さない、本来、生物の持っている関係性をより健全に再生していく。これが今後、資源を保全する基本的な考え方になっていくと思う」

NEWS UP漁獲激減のサケ 繁殖に新事実
ご意見・情報 をお寄せください