
「女王陛下の健康状態を、医師団は懸念している」
バッキンガム宮殿の発表を見た瞬間、血の気がさーっと引くのが分かった。
まさか。
2日前、元気そうな顔の写真を見たばかりだったのに…。
「イギリスの顔」として70年間、君臨したエリザベス女王。
その死去を受けた対応について、イギリス政府は『オペレーション・ロンドンブリッジ(=ロンドン橋作戦)』というコードネームを付け、長年準備を進めてきた。
その作戦の舞台裏は、テレビでは伝えきれなかった場面の連続だった。
(ロンドン支局長 大庭雄樹)
油断していた昼前に
9月8日。
イギリスでは2日前にトラス新首相が就任し、ロンドン支局も約3週間にわたった取材に一区切りがついたところだった。
1か月前に赴任したばかりの私にとって重圧を感じていた仕事をどうにか終え、この日は午前中、自宅近くの中学校にいた。
イギリスでは9月に新年度が始まったが、わが家の子どもたちはまだ学校が決まらず、「ウエイティングリスト」入り。どこも定員オーバーで、順番待ちを余儀なくされていた。
そうした中、やっと空きがあると声が掛かり、学校との面談を終えたタイミングで「女王の健康状態悪化」を知らせるメールが入ってきた。
一段落、と油断していた気持ちが完全に打ち砕かれた。
スコットランド行きの便がない
ただ、予兆はあった。
エリザベス女王は2日前、静養先の北部スコットランド・バルモラル城でトラス氏を首相に任命していた。

女王にとって15回目となった首相の任命だが、バッキンガム宮殿以外で行うのは初めてだったのだ。
政権発足に向け多忙のはずの次期首相を、首都ロンドンから約650キロ離れた静養先に呼ぶのは、女王の体調がすぐれない証拠にほかならなかった。
体調不良は一時的なもので、しばらくすれば良くなるのではないか。そんな希望も抱きながら、支局に上がって情報を集めたが、公共放送BBCは深刻な調子で女王のニュースばかり伝えている。
そして、女王も治療のため病院に向かうのではなく、逆に長男のチャールズ皇太子夫妻や孫のウィリアム王子(いずれも当時)など家族が続々とバルモラル城に向かっているという。
これは本当にまずいかもしれない。
支局の記者やカメラマンなどに、バルモラル城に向かってもらうことにした。しかし、そう決めたときにはスコットランド行きの飛行機は、ヨーロッパ経由便を含めて残っておらず、片道7時間かかる列車を手配した。
最後の国歌
そして約3時間後、8日の午後6時半(日本時間の9日午前2時半)。支局のイギリス人スタッフが、声を上げた。
「Here it comes(来た)!」。
バッキンガム宮殿からの発表だった。

「女王は本日午後、バルモラル城で安らかに息を引き取った」
その瞬間、BBCの画面には王冠をかぶった生前の女王の肖像画、それに女王の治世では最後となる、国歌「ゴッド・セーブ・ザ・クイーン」が流れた。

「最期の地」の意味
エリザベス女王が死去したバルモラル城は、女王が毎年夏の約2か月間滞在した避暑地だ。
亡き夫・フィリップ殿下をはじめ、家族との思い出が詰まった城、そして緑あふれるハイランド地方の静けさを、女王は愛していたと言われる。

エリザベス女王は「最期の地」に、あえてスコットランドを選んだのではないかという見方も出ている。
300年余り前に事実上、イングランドに吸収される形で併合されたスコットランドでは、イギリスからの独立を目指す動きもあり、連合王国の行く末を女王は案じていたという。
今回、特に地元では、女王がスコットランドで亡くなったことで、王室との結びつきや愛着を再認識したという声が聞かれた。
ひつぎに拍手と歓声?
今回、取材にあたった記者やカメラマンが一様に戸惑ったのは、女王のひつぎを沿道などで出迎えた人たちの反応だ。
日本なら、ほとんどの人がこうべを垂れたり、手を合わせたりして厳粛に見送ると思う。
ところがイギリスの人たちはひつぎに拍手を送ったり「声」を上げたりしていた。

この「声」のトーンは、歓声に近いものだ。
ことばにするなら「お疲れさまでした、ありがとう!」という感じだが、これを日本向けのニュースで「歓声で出迎えた」と表現するべきかどうか。
「敬愛を込めた拍手などで迎えた」という風にことばを補えば、日本の視聴者にも誤解を与えずに伝えられるだろうか。
いろいろと思い悩み、異なる文化や風習について伝えることの難しさを、あらためて感じさせられた。
新国王も楽じゃない
バッキンガム宮殿に向かってまっすぐ延びる道路「ザ・マル」を横断しようとしていたときのこと。
突然「敬愛を込めた拍手や声」が聞こえたかと思うと、黒塗りの車がゆっくりと進んでくるのが見えた。
どうやら、即位の宣誓を終えたばかりのチャールズ新国王のようだ。
わざわざ沿道に近いところを、窓を半分開けて進み、人々に笑顔で手を振っている。

チャールズ新国王はその前日にも宮殿前で車から降り、女王を追悼しようと訪れた市民と握手やことばを積極的に交わしていた。
中には、手の甲やほおに口づけをする女性までいた。
「開かれた王室」を実践した母・エリザベス女王の方針を継承していると言われるチャールズ新国王だが、警備やコロナ対策などの観点からは大丈夫なのか、心配になったのも事実だ。
「5人目の君主」
女王が死去したあと、バッキンガム宮殿前に手向けられた花があまりに多くなったので、王室は隣の公園「グリーン・パーク」に特別な区画を設け、そちらに手向けてほしいと呼びかけるようになった。
公園を訪れると、芝生の上にバラやひまわりなどの花束がずらりと並び、木の周りにも幹を何重にも取り囲むように花が手向けられていた。

車いすで来ていた、90歳の女性に話を聞いた。

「6歳年上の女王は、姉のような存在でした。
一緒に育ってきたように感じているし、これまでしてくれたことすべてに『ありがとう』と言いたいです。
私にとってエリザベス女王は、ジョージ5世、エドワード8世、ジョージ6世に続い て4人目の君主でした。
チャールズ新国王で5人目。
新国王も、国民に愛されたお母さん(エリザベス女王)のようになってくれると思います」
弔問の列の先頭は…
エリザベス女王のひつぎはロンドンのウェストミンスターホールに安置され、9月14日から国葬当日の19日朝まで、一般の人たちが弔問に訪れた。
その列の長さは一時16キロ、並ぶ時間は最長で24時間にも及んだ。
弔問が始まる前日の昼、テムズ川の岸には早くもテントを立てて並ぶ弔問者の姿が。
インド洋の島国スリランカ出身で、ロンドン在住の56歳の女性だった。

最初の弔問者
「恩返しのようなものです。
イギリス王室がスリランカの独立を認め、コモンウエルス(=イギリス連邦)の加盟国のためにしてくれたことに感謝したい。
家族全員、イギリス王室を尊敬しています」
25万人が振り返った
弔問の期間中、私も取材でウェストミンスターホールに入った。
ひつぎの横で数秒立ち止まり、頭を下げる人。
手を合わせる人。
十字を切る人。
涙を流す人。
それぞれの方法で別れを告げると、歩いて去って行く。
それでもホールの出口の前でほぼ全員が再び立ち止まり、ひつぎの方を振り返っていた姿が印象的だった。
25万人以上と推計されている弔問者たちはみな、エリザベス女王の記憶をいつまでも忘れないよう、脳裏に焼き付けようとしているかのようだった。
鳴らなかったビッグベン
「肩すかし」もあった。
国葬前夜の18日夜。
イギリス全土で午後8時から1分間の黙とうがささげられることになり、私たちはロンドン市内など各地で取材に当たった。
市内では時計台「ビッグベン」の鐘の音が黙とうの合図だということで、ビッグベンの映像・音声も狙いながらの取材だ。
しかし、午後8時になっても、ビッグベンの音は聞こえない。

テムズ川岸に並ぶ弔問者などは、何となく「そろそろ時間かな」という雰囲気で思い思いに黙とうを始め、終えていった。
事前の報道では、ビッグベンに消音装置が付けられると伝えられていたので、ひょっとして音量をかなり抑えたのかなと思っていたが、議会の担当者は翌日「技術的問題で鳴らなかった」と明かした。
それでもビッグベンは国葬当日には重厚な鐘の音を鳴らし、「本番」にはきっちりと合わせてきた。
「彼女は別だ」
どこの国もそうだと思うが、イギリスでも君主制に賛成の人ばかりではない。
特に若い人に話を聞くと、記録的なインフレ率で自分たちの生活が厳しい中、王室は生まれたときから特権を与えられているとして、批判も耳にする。

国葬当日、式典の6時間前から周辺の道路が封鎖されるという情報があり、午前4時にタクシーでウェストミンスター寺院に向かった。
その途中、私と同じ40代の運転手と女王の話になった。
運転手「俺は王室なんかには興味はないが、彼女は別だ」
記者 「どうして?」
運転手「70年間も国民のために働き続けた。なかなかあんな風に生きられるもんじゃない」
記者 「きょうの国葬はテレビで見る?」
運転手「パブで1杯引っかけながら見ると思う。どうせ道路の封鎖で、商売あがったりだからな」
生涯守り続けた誓い
エリザベス女王は、生まれたときは女王になるはずではなかった。
父親が次男だったためだ。
しかし、叔父のエドワード8世が離婚歴のあるアメリカ人女性と結婚するため王位を退いたことで、父親がジョージ6世として即位。
その後、21歳の誕生日に行った演説では「私の人生が長くても短くても、生涯を国民にささげることを誓います」と、その覚悟は固まっていた。

それから70年間。
果たして女王自身が、そんなに長い年月をささげることになると思っていたかどうかは分からない。
それでも、国民に常に優しく寄り添い、ときに力強く励ますなど、21歳のときの誓いを生涯貫いたその生き方は、世界中の多くの人の心を動かした。
私たちが今回目の当たりにしたのは、間違いなく、歴史の1ページが閉じる瞬間だったのだと思う。












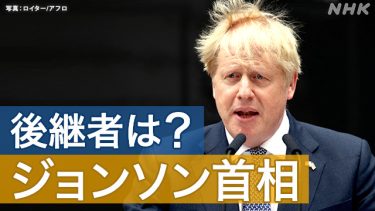



 国際ニュース
国際ニュース
