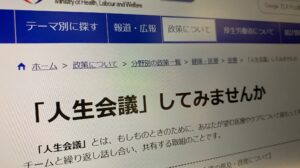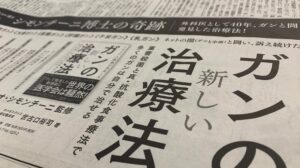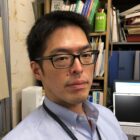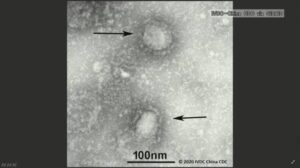科学と文化のいまがわかる
原子力
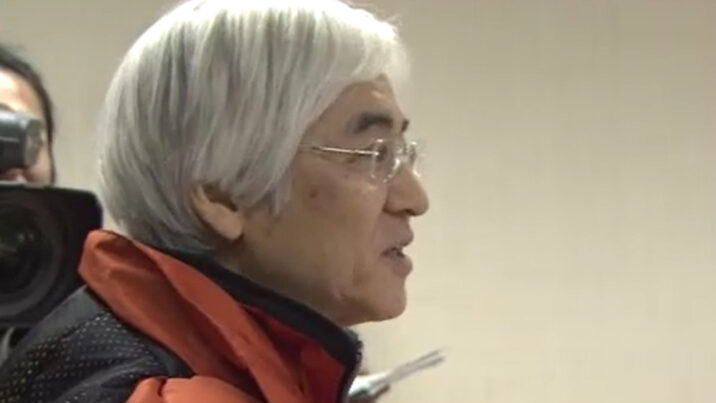
“問題ない”が通じない 危機で問われた科学者
2021.03.25
10年前の3月11日、福島第一原発にほど近い、いわき市で取材していた私は、想定していなかった事態に驚き、何を信じたらよいのか分からなくなりました。
「がんになるのではないか」「ここにいて安全なのか」。当時、大きな不安を感じていた地元の人たちに向けて、被ばく医療や放射線の影響に詳しい科学者たちがリスクについて説明してきました。
しかし、原発を推し進めてきた科学への信頼が揺らぐ中、不安が和らぐことはほとんどありませんでした。
いま私は、コロナ禍で医療担当記者として、感染症の専門家を取材し、どう伝えるか、悩みながら原稿を書いています。
原発事故から10年、当時、危機に際して、福島に乗り込んだ科学者たちは何を感じていたのか、話を聞いてみると、返ってきたのは反省の言葉でした。
“全然信用されていないな”

10年前の原発事故では、原発から放射性物質が大量に放出され、多くの住民が避難しました。
事故の後、放射線の影響に詳しい広島や長崎などの専門家が、住民の不安に応えてほしいと、福島県から招かれるなどして、現地に入りました。
そのうちの1人、京都大学や広島大学で、放射線の身体への影響を研究してきた丹羽太貫さん。
原発事故後、ほかの専門家とともに福島に入り、住民に当時の放射線量でどのような影響が出ると考えられるか、研究成果をもとに説明してきました。
事故の翌年(2012年)から3年間は、福島県立医科大学の特命教授になり、放射線のリスクや健康影響について地元の人たちに説明する役割を担いました。丹羽さんが当時のことをどう感じているか、聞きました。
Q:福島に入って、どういう印象だったかを教えてください。
丹羽さん:当時、私は放射線関連のさまざまな規制や規則について議論し、国に答申する放射線審議会という組織の会長でした。事故直後から、被ばくの影響を考えて食品に含まれる放射性物質の基準など、いろいろなことを議論していたのですが、やはり実際に現地に行かなければいけないだろうと思い、6月くらいにいわき市で開かれた200人規模の講演会に参加しました。
「線量の低いいわき市では、健康へのリスクは問題ありません」などと説明したのですが、明らかに反応が薄い、冷たい。これは全然信用されていないなと思いました。
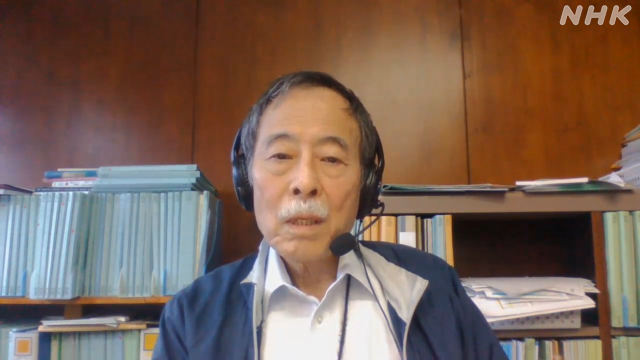
当時、いわき市にいた私は、丹羽さんの話を聞く住民と同じ立場でした。いわき市は線量は飯舘村や福島市などに比べると低かったのですが、放射線の影響を恐れて、一時、数万人の市民が市外へ逃れたともいわれています。
当時、「科学的には安全だ」という専門家の話をよく耳にしていましたが、自分が持たされていたポケット線量計の数値が少しずつ上がっていくのを見ていると、本当に安全なのかと不安が募りました。
Q:反応が冷たかったのは、なぜだったんでしょう?
丹羽さん:当時、すぐには理由はわからなかったのですが、現場の状況も知らずにこれは科学的に正しいですよ、とだけ言っていたんです。
地元の人たちがどんな状況で、どんなことに不安を抱いているか把握できていないから、線量が低いから安心だ、と言ってしまう。
私は科学的な事実を伝えれば安心するだろうと思って言ったんですが、まったく安心につながらなかった。これは本当に驚きました。
暮らしを襲った原発事故

丹羽さん:いわき市の講演会からしばらくして、飯舘村で一番線量が高かった長泥地区の区長さんのご自宅にうかがえることになりました。
区長さんのお話を伺うと、避難して、飼っていた動物だとかもいないわけですよ。すると区長さんがこのトラクター、2000万円くらいしたんだけど、まだローンがあるんだっていう話をしていたんですよね。
こうした生活がある中で、原発事故と放射線の不安に見舞われたんだなと、ようやくこれは大変なことだとわかったんです。
私たちが説明していることが、暮らしの中でどういう意味を持つのか、地元の人に寄り添うということを考えながら説明しないと意味がないと思い知らされました。
“モノローグ”ではなく“ダイアローグ”を
Q:その後、説明や行動は変わりましたか?
丹羽さん:私がやっていたのは、一方的に説明するいわば「モノローグ」。でも、必要だったのは「ダイアローグ」、住民の方々との対話だったんです。
その後、福島県立医科大学の特命教授を任されて福島にいた3年間は人の話を聞くということに徹しました。
福島が教えてくれたのは、科学者はデータを出すだけではなく、人の言うことを聞きなさい、現場の中で考えなさいということだったのだと感じます。

丹羽さんは、福島の地元住民たちや、チェルノブイリ原発事故の後、住民との信頼構築に取り組んだ世界各地の放射線の専門家などとともに、事態にどう対応し、どう復興していくか考える対話集会を開催。いまも交流を続けている。
“家族ががんになるかの問題なんです”

対話の姿勢が欠けていた、と振り返る科学者がほかにもいました。
放射線とがんの関係を研究する被ばく医療の専門家、広島大学の神谷研二さんです。事故直後、3月中に、福島県から「放射線健康リスク管理アドバイザー」に任命され、県内を中心に130回以上、被ばくの影響について講演して回りました。いま、福島県立医科大学の副学長も兼任し、放射線被ばくの影響を調べる「県民健康調査」の責任者も務めています。

Q:かなり早い段階で福島県に入り、放射線のリスクを説明しました。実際にその当時、どんな説明をしましたか?
神谷さん:放射線の影響については、広島だとか長崎のデータを基に、放射線の健康リスクを説明していました。
たとえば、100ミリシーベルトを超えて初めて、がんのリスクが0.5%上がると言ったように。
こういう科学的事実があります、ということを伝えようとしていたのですが、それが伝わらなかったように思います。
100ミリシーベルトを超えると、がんで死亡するリスクが0.5%上がる、という説明も当時、よく耳にしました。しかし、この説明を聞くたびに逆に安心なのか心配なのかわからなくなった、という声を多く聞きました。
※ 年間100ミリシーベルト、としていましたが、国際放射線防護委員会(ICRP)は期間を明示せず、100ミリシーベルトでがんで死亡するリスクが約0.5%上がるとしています。修正しました。
Q:説明したことがなぜ伝わらなかったのか。原因は何だと思いますか?
神谷さん:放射線の発がんリスクというのは確率的な影響で現れる訳なんですけれど、私も含めて専門家というのはできるだけ正確にお伝えしようとしたんです。
そうなると、確率の話になるわけですが、住民の側からすると理解が難しい。一般に危険か危険でないか、日常的には「あるかないか」で考えるわけですから、確率的に考えるということが今までの習慣の中にないんですよね。
住民の方にとっては、いくら確率的なリスクが低いという話をされても、当事者はがんになるかならないかの問題として受け取ります。
私たちの説明の仕方が、十分相手の気持ちに添ってなかったということではなかったかと思います。
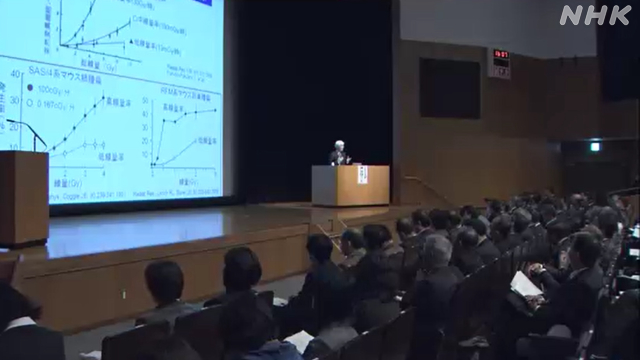
Q:そういったことに思いがいたったのは、いつごろなんでしょうか?

神谷さん:いつ頃からとは言いにくいんですが、一番印象に残っている言葉は、確率的ながんのリスクの話をしたときです。
ある住民から「それは先生にとっては確率的な問題かもしれませんけど、わたしにとっては家族ががんになるかならないかの話なんです」と言われました。これには言葉を失いました。
住民の方にとっては、本当に白か黒の問題として原発事故が立ちはだかっているんだと思いました。
対話から始まる信頼関係
Q:そうした反省が、後にどのような形で生かされたんでしょうか?
神谷さん:ずっと多くの人を対象にした講演会をやってきたんですけど、徐々に質問の内容も変わり、対話的な話し合いになりました。徐々にそうなっていったという感じです。
その経験からいうと、情報を正確に伝えようと考えたら、対話は不可欠の方法だと思いました。
相手の話をよく聞いて相手の気持ちを理解して聞くというのが非常に重要で、そういう中でお互いに理解していくという過程がないと信頼関係を築けないと思うんです。

Q:一方的に話すという方法は正しくなくて、相手の話を聞くところから始まるということを学んだということですか?
神谷さん:福島ではいろんなことを学んできましたけど、リスクに関する知見を私たちが話すことではなくて、相手の話を聞くことが第一歩。
そこからだんだんと話をしていくということを学んだように思います。
そして一番重要なポイントは、一方的に他者を説得するのではなくて、情報を共有して考えていくというプロセスが重要なのではないかと思うようになりました。

御用学者と呼ばれて

一方、当初、強い反発を受けながらも、福島の復興に関わり続けることで、信頼を得ようとしてきた人もいます。長崎大学で放射線の体への影響を研究している高村昇さん。
チェルノブイリでの健康被害を研究してきた経験を買われ、大学から福島県に派遣されました。福島県の「放射線健康リスク管理アドバイザー」に任命され、各地で被ばくの影響について説明して回りました。
高村さんは当初、「放射線の影響は大きなリスクにはならず、過度に心配する必要はない」という説明を繰り返しました。
現地で放射線の影響を心配する身からすると、かなり楽観的に写っていました。

Q:高村さんが説明に入ったとき、まず福島に対してどういう印象を受けましたか?
高村さん:とにかく一言で言うと、会場がすごく殺気立っていました。
話している最中もときどきヤジのようなものが飛んだり、普通の講演会とは全く違う雰囲気だなと感じました。
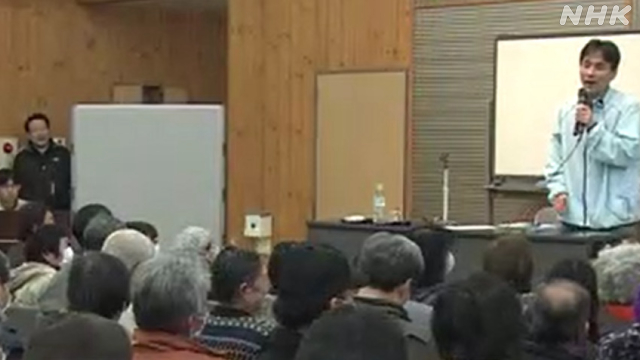
講演を続けていくと、「御用学者じゃないのか」と言われることもありました。
要するに国から利用されているんじゃないかっていうようなことを言われる方はいて、不安が大きかったんだろうなとは思いました。
Q:私も事故当時、福島にいたのですが、安全側に立った話をされると本当かなと思ってしまうっていうところはありました。かえって不安を掻き立てられました。
高村さん:パニックに陥ったような人がいる場合は、なかなか多くの情報は伝わらないので、危機管理の観点からなるべくわかりやすく説明をすることを心がけていました。
30分とか40分は説明をするんですけど、おそらく説明は十分ではなかったんだと思います。
ですので、特に最初の頃は、質問が1時間半、長いときは2時間ぐらい、ずっと出ることもあったんですけれども、最後まで聞いて答えるようしました。
質問をずっと受けていくと、会場の雰囲気は少し変わってくるのがなんとなくわかるんですよ。
復興支援を続ける
2016年、福島県立医科大学と長崎大学が被ばく医療の専門人材を育てる大学院の講座を設置し、高村さんは中心的な役割を担っています。
これまでにおよそ80人が卒業し、保健師や看護師として原発が立地する自治体や病院に勤務。
高村さんは、大学院生やスタッフなどとともに毎月数回のペースで福島を訪れ、一時ほぼ全住民が避難した川内村や大熊町などの帰還の支援を行うなど、被災地の復興に関わり続けています。


Q:なぜ、今も福島の復興を支援し続けている?
高村さん:私は原爆を落とされた長崎生まれで、さらにチェルノブイリの支援をライフワークとしていたというのもあるのですが、特に事故初期のころ、避難されてきた住民の方から、自分たちは戻れるのか、戻れないのかという質問をぶつけられたんです。そのときに私は戻れます、そのためのお手伝いをしますと申し上げました。
申し上げてきた以上は、やっぱりやらなきゃいけないという責任を感じて、今も福島の復興に協力しています。
Q:どんな支援をしているんですか?
高村さん:大学のサテライトオフィスを大熊町や川内村などに作って、住民の帰還などの地域の復興に協力しています。
同じものを食べて、同じところに住んで、生活をともにすることで、生活ができるんだという説得力も生まれて、本当に戻っていいのだろうかという住民の不安にある程度、応えられたのではないかと思っています。

リスコミの専門家は
原発事故当時、専門家が行ったコミュニケーションで明らかになった課題について、リスクコミュニケーションの専門家、早稲田大学の田中幹人准教授に話を聞きました。
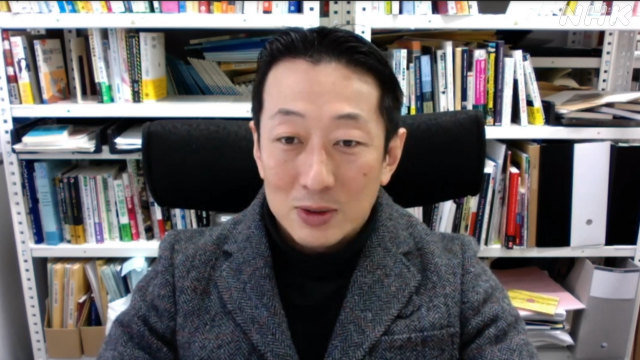
福島の失敗は、混乱する現地の人たちが、科学的な知識が足りないから混乱するのだろう、というある種の決め付けのもとに知識を注ぎ込んだ点です。
一方的な情報を与えると失敗するということは古くから指摘されていて、残念ながら福島でも類似のことが起こりました。
本来は、専門家と現地を知る地元の人たちがお互いの知識を組み合わせて、解決策を考えていかなきゃいけない。
専門家が自分たちの持っているピースで問題が解けると思ってしまったのが間違いでした。

田中さんは、当時明らかになった課題も踏まえて、いま、「コロナ専門家有志の会」のメンバーとして発信しています。

コロナについてはまだまだわからないこともありますし、今まで通用した施策が通用しなかったり、ここは対策を緩めても大丈夫、でもここはもうちょっと厳しくしないとまずいというところも出てくる。
それによって生活の糧が奪われる人がいるんだったら、どうやって補償しようかとか、様々な施策をしていくための納得感を得るために、対話、コミュニケーションは重要になってくると考えています。
危機に際し、科学者に求められるもの
危機に際して、不安を抱く私たちが頼りにするのは、科学者の専門的な知識や経験のはずですが、原発事故後は必ずしもうまく生かされませんでした。
新型コロナで不安が続くいま、当時、福島に入った3人の科学者に、科学者に求められるものは何か、いまの考えを聞いてみました。
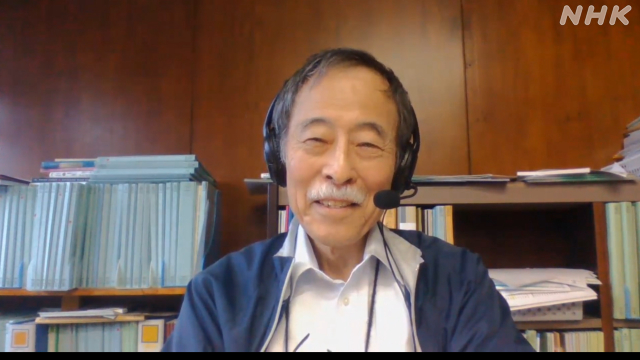
視野を広くして、人の言うことをちゃんと聞くこと。それから経験ですよね。
私もこんなことを言うようになったのは福島に行ってからです。
それまで、本当に長く放射線の研究をやっていたのに、放射線が一般の方にもたらす問題っていうことをまったく顧りみなかった。
福島の人に放射線っていうのを教えてもらったんです。

科学技術はますます高度化して進歩するはずで、より社会の中に深く組み込まれ、社会への影響力は強くなると思います。
これからの科学者は社会に対して責任を持ったメッセージを出さないといけないと思いますし、社会に対して自分の研究、科学がどのような影響を持つか、どのような貢献ができるかということにもっと真摯に向き合っていかないといけないと思います。

科学と技術、社会がどういう風に調和していくのかということが問われているように思います。
ですから、これからの研究者、科学者はやはり社会とどう関わっていくのかということを意識していかないといけないのではないかと思います。
取材後記
福島を経験した3人の科学者が、当時の反省を踏まえ、社会との関わりなど、社会を意識することが大事だと言っていたのが印象的でした。
科学者の立場から科学的な事実を分かったこととして話すのでなく、どう受け止められるか、相手のことを考え、対話しながら共有する。
コロナ禍のいま、社会の中における科学のあり方を考える上で、重要なメッセージだと感じました。