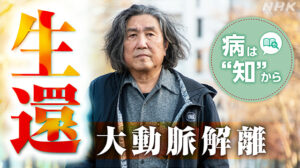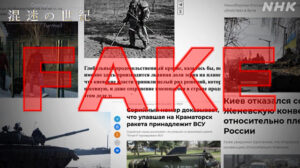科学と文化のいまがわかる
文化

ケンドリック・ラマーは語る
2018.09.10
ケンドリック・ラマ-。1人のアメリカ人ラッパーの言葉が、いま、世界を動かし、社会から疎外された人々を1つにつなげている。暴力や差別がなくならない混とんとした現代に生きる苦悩を表現してきた彼の歌詞は、世界中の若者の共感を集め、最新アルバムは、優れたジャーナリズムに贈られるアメリカのピュリツァー賞の音楽部門を受賞した。その彼が、ピュリツァー賞受賞後としては海外メディアで初めて、NHKの独占インタビューに応じた。ケンドリック・ラマ-が語る社会を変える“音楽の力”、そして日本へのメッセージとは。
若き“社会派ラッパー”の素顔は
ことしの「フジロックフェスティバル」に出演するため、5年ぶりに来日したケンドリック・ラマ-。
「取材に応じる」と返事が来たのは、インタビューした日の前日。どんな人物かと緊張して待っていた私たちの前に現れたのは、もの静かで知的な雰囲気の青年だった。

ピュリツァー賞の受賞作となった最新作「DAMN.」は、分断が進むアメリカの現実をリアルに描いた痛烈なメッセージが強く印象に残った。彼は、今回の受賞をどう受け止めているのだろうか。
---受賞おめでとうございます。「DAMN.」のどのような部分が評価されたと思いますか?
思うに、「DAMN.」にはみんなが共感しやすい対話のやり取りが含まれていたのだと思います。僕は、人として生きていれば経験することや音楽やレコードを聴くことによってわき起こる感情を純粋に表現しようと思ってアルバムを作りました。その共通の対話が、ピュリツァー賞の人たちも含め、みんなに共感できるものとして受け止められたのだと思います。

---このアルバムの中で最も伝えたかったテーマは?
「DAMN.」を通して伝えたかったメッセージは、基本的には自己表現についてです。感情を表に出すことを恐れてはいけない。特にアルバムの中の「PRIDE.」や「HUMBLE.」といった曲はアルバムに込めた僕の感情を体現しているものであり、自分自身の“品格”を表したものでもあります。
---そのテーマを最も端的に表現した曲を1つ挙げると?
最も気に入っているのは「PRIDE.」です。楽器(ビート)の使い方や歌詞が気に入っています。「PRIDE.」という言葉や、どんな状況でも誇り高くいることは誰でも共感できるもの。この曲で語られているストーリーは、(自分が)最も共感できるものなんです。
---「PRIDE.」の中で特にそういった意味を込めた歌詞はどこですか?。
どれかな…。「In a perfect world/I would be perfect,world」(完璧な世界でなら、僕だって「完璧」になれるさ、世界よ)。これが「PRIDE.」の中でも気に入っている歌詞です。僕らは、自分たちでは手に負えないような環境で育ってきた。このサイクルから抜け出せれば、ありのままの自分に、そしてなりたい自分になれる。だからこの歌詞が好きなんです。
---そうしたメッセージは広く観客に届いていると感じますか?
間違いなく、観客はメッセージを理解してくれています。僕は毎晩、この曲を何千人もの観客の前で歌うんですが、その時、「携帯電話のライトを照らしてくれ」と伝えるんです。そうすると、みんな(携帯のカメラを)揺らしながら一言一句を一緒に歌ってくれる。確実に絆を感じますね。
ヒップホップが切り開いた新たなジャーナリズム
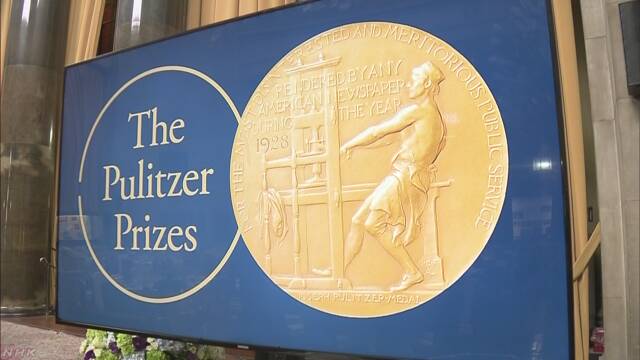
ピュリツァー賞の音楽部門は、実に75年の歴史があるが、過去の受賞作はいずれもクラシックやジャズなどから選ばれてきた。ヒップホップ・ミュージック初の快挙となった今回の授賞理由について、ピュリツァー賞の事務局は、「複雑なアメリカ社会に生きる難しさが見事に表現されている」と評価している。
---以前から、ジャーナリズムやピュリツァー賞に関心はありましたか?
ジャーナリズムには、以前から強い興味がありました。詩や長編小説、短編、エッセー、なんであれ書くことは好きでした。高校生の時に、少しだけピュリツァー賞を意識したことはありましたが、こんな形でこのようなすばらしい賞をもらうとは夢にも思っていませんでした。僕も、皆さんと同じように、衝撃を受けています。ただ、受賞できたのは、これまでにたくさんの努力をし、献身的に頑張り、学んできたからだと言えます。
---ヒップホップ・ミュージックがピュリツァー賞を受賞したということをどう感じていますか?
気分はいいですよ。僕のヒップホップ・コミュニティーにおいても、多くの扉を開いた出来事だと思います。信じるにせよ信じないにせよ、いまだにヒップホップを理解していない人々が少なからずいますから。ほんの少し(の人々)ですが、今回の出来事はそうした人たちにも、僕たちがここにいる理由を知ってもらう新たなきっかけになったと思います。ヒップホップはまだ新しい文化ですが、多くの表現の自由や、常に進化する詩的表現、そして教育の機会にあふれています。ピュリツァー賞がこうした事実に気がついてくれたということは、また一つ、大きな扉が開いたということだと思っています。
---ヒップホップの表現がジャーナリズムとして認められたということは、ヒップホップの歴史のなかでも非常に画期的なことです。それについてはどう感じていますか?
僕がヒップホップを聴き始めた頃、ビッグ・ダディ・ケインやKRS・ワン、パブリック・エネミー、スヌープ・ドッグ、イージー・Eなどを大きな音で流していました。僕が「本物のヒップホップとは何か?」と理解する前から、彼らに影響を受けていたんです。家の中で(彼らの音楽が)流れていて、リリック(歌詞)の裏側から、いかに過去の烙印(らくいん)を背負っているか、いったい何人の人が立ち向かってきたかを、僕らはニュースを見ながら、感じとってきた。今や、その相手から賞を受けるまでになった。これはとても大きな変化だと思います。僕たちが最初から伝えようとしてきたことは、自分たちのコミュニティーに根ざした表現の自由、そして、そこで何が起こっているかということです。今は、こうしたコミュニティーだけにとどまらず、世界中に(そのことを)広く伝えることができていると思います。

---ピュリツァー賞を受賞したことは、あなたにとって、そして社会にとって、どのような意味を持つと思いますか?
僕がやっていることは単なる歌詞や曲をつくっているだけでなく、もっと深く人々とつながることだという確信につながりました。僕が発表してきた作品や、音楽に対して学んできたことは、僕自身のためだけじゃない。これらは、逃げ場のない街に育った子どものためのものだったんです。なので、(アーティストとしての)成功を確かなものにしたこと、そして限界に挑み続ければ何であれ、また次のつながりが生まれるだろうということを確信しました。一人のアーティストとしての立場、そして世界的な視点からも、より多くの人々を一つにまとめることができたと思います。コンサートで、「DAMN.」に収録された曲を歌う時、(舞台の上から)非常にさまざまな宗教や肌の色、人種の人たちが見えるんです。これが、究極のゴールだと思っています。なぜなら、ライブの2時間のステージにおいて、そこに存在するのは争いではなく、「愛と幸福」だけなのですから。
ヒップホップの持つ力とは

銃撃事件が絶えないカリフォルニア州・コンプトン地区。この「全米で最も危険」と言われる場所で、ケンドリック・ラマーは生まれ育った。子どもの頃から親しんでいたラップに社会的なメッセージを込めるようになったのは、友人が銃撃されるなど、差別と暴力の過酷な現状を訴えたいとの思いからだったという。
---今回の受賞は、アメリカにいるいろんな立場の人を勇気付けていますね。
まさにそう思います。僕自身だけではなく、自分のコミュニティーの人たちにとってもとても勇気付けられるものだと思います。それに、勇気づけられたのはアメリカ国内だけだとは思いません。ほら、あなたたちもコンプトン出身の少年が作ったアルバムについて質問してくれているじゃないですか。この部屋にいる皆さんが、インスピレーションを受けた。そして、僕たちはお互いのエネルギーを感じて、感情に触れ合っているんです。それは、僕自身へのインスピレーションだけではなく、自分の持つ言葉や想像力、そしてジャーナリズムに宿るパワーに気がついていなかったすべての人々のインスピレーションによるものだと思うんです。

なぜなら、僕自身も(そのパワーに)気がついていなかったから。もしも11年生(※日本では高校2年生)の時に僕がピュリツァー賞を受賞すると言われても、それがうそか本当か分からなかったと思います。
---ヒップホップとは、あなたにとって何を実現するためのツール?
僕にとってのヒップホップは、「表現の自由」そのものです。人には、他人に対してなかなか言い出せないことが、音楽の力を借りてやっとふさわしい言葉が口から出て来ることがあります。それは説明できないことなんです。スネアの音や、ドラムの音、そしていくつかの乱暴な言葉といった創造性を通じてコミュニケーションを図ることは、感情に根ざしたものであり、(ヒップホップは)僕にそうした感情を表現するチャンスをくれたんです。それらをあなたたちが有り難がるかどうかは別ですが、僕にとっては、それは吐き出さなきゃいけない感情だったし、それこそが、ヒップホップがすべてのコミュニティーに対して成し遂げてきたことだと思います。
---そういった思いは初期の頃から抱えていた?
今と同じ考えは持っていませんでした。ただ楽しくやっているだけでしたね。それが当時の目標でしたから。9歳から13歳の頃は、とにかくラップを書くのが楽しくて、それに対して情熱を傾けていました。その後、だんだん成長していくうちに、自分の声を楽器としてどう扱うべきか、そして、人々を本当に結びつけるためには何を伝えるべきなのかを考えるようになりました。でもその前に、まずは自分のスキルをレベルアップすること、それが頭の中のすべてでしたね。
---楽しみから自己表現へ、今のスタイルになったのはどのようにして?
だんだんと進化していったんです。一度、僕はあらゆるスキルを用いながらたくさんの歌詞を書いた時点で、これで「ラップのやり方」を網羅したと感じたんです。そこで僕は、ただの優れたラッパーとしてだけではなく、もっと大きな存在として知名度を上げたいと思うようになりました。自分の音楽に対して、もっと多くの人々につながってほしいと思うようになったのです。なので、20代前半の頃までには、シフト・チェンジをしなければなりませんでした。コンプトンや、自分の家の裏庭だけではなく、日本やイギリス、アフリカなど、世界中の人々とつながるにはどうすればいいんだろう。そこで、ラジオ(でかかるヒット曲)を意識した曲だけではなく、自分が心地よく、そして重要だと感じるような曲を作り始めたんです。そして、旅に出ていろんな人たちとコミュニケーションを取るようにしたら、これまでとは違う創造性とともに、新しいアイデアが湧いてきたんです。それが始まりでしたね。
共感と対話で広がる世界
3年前に発表した代表曲の「オールライト」。やり場のない思いをつづりながら、それでも「大丈夫さ」と語りかけるこの曲は、思わぬ広がりを見せた。全米に広がった差別撤廃運動のデモで、人々が歌いはじめたのだ。しかも、この動きはアメリカを超えて世界に広がった。専門家は、「ケンドリック・ラマーは若者と世界をつなぐシンボルになっている」と指摘する。

---アメリカ以外の活動で、どんな影響を受けましたか?
かなり大きな影響を受けています。僕がファースト・アルバム『Good Kid,M.A.A.D. City』をリリースした時…いや、セカンド・アルバムかな。ちょっと議論を呼びそうだけど…(※1)。あのアルバムをリリースした時、あの作品はあくまで自分のコミュニティーに向けて作ったものだったんです。コンプトンやワッツ、カーデナ、イングルウッドにホーソーン…(※2)。どこでもいいですが、ロサンゼルスに住んでいる人に向けて作りました。なので、自分のコミュニティー以外に住んでいる人に理解されるとは思っていなかったんです。一度、ロンドンに行った時のことですが、キッズたちが自分の曲を一語一語歌ってくれたんです。そのキッズたちを見て「どうやって(僕の曲を)理解してるの?」と尋ねました。だって僕は、実際に(地元で)起こったストーリーや、自分たちが使っているスラングや言葉を使っているにもかかわらず、彼らは1行ずつ(歌詞を)歌ってるんですから。そしたら1人の子が「僕たちは共感してるんだ。だって、これは君だけの歌詞じゃない。これは、暗い場所から抜け出して新しい人生を始めようとする物語だから」と言ってくれたんです。その男の子は、劣悪な家庭環境に育ち、そこから抜け出そうとしながらも、いつもそこに戻ってしまい、その環境に染まろうとしていたらしいんです。でも、僕が自分のコミュニティー(の環境)を抜け出したのと同じように、彼は僕のアルバムのおかげで、その家庭環境から抜け出すことができたそうなんです。それで、理解することができました。おかげで、新たな創造性と、自宅の裏庭(地元)だけでなく世界中のみんなと通じる新たな方法を得ることができたんです。
(※1:『Good Kid,M.A.A.D. City』はメジャー・レーベルからのファースト・アルバムであり、インディーズ時代から数えると2枚目のアルバムになる)
(※2:いずれもカリフォルニア州の都市)
---そうした経験から、歌詞の内容などは変わっていきましたか?
いえ、変わっていません。僕は、実際にレコーディングする数日から数か月も前から、座りながら何を歌うべきなのかを考えるんです。僕がやるのは、ひたすら楽曲制作です。もしも一曲、ないしは一行の歌詞がうまく浮かんでこなければ、それは言葉のむだ、そして良質なビートのむだになります。まずは、制作に尽きる。僕は音楽制作とともに生きていますから。一人の「感情に訴えかける」だけなら、壮大な言葉を使う必要も、長い曲である必要もなく、30秒あれば十分かもしれない。でも、その30秒の間に、その人と「つながる」ことができるでしょうか?
創造性の源は「自然な感情」
危険な街の子どもから、いまや“社会派ラッパー”を代表する1人にまで上り詰めたケンドリック・ラマー。しかし、その歌詞は決して扇動的ではなく、ありのままの自分の姿を文学的な表現で伝えている。その豊かな才能は、インタビュー中の語り口からも感じられた。

---尊敬する先駆者は誰ですか?
挙げ始めればきりがないですが、ジェイ・ZにDr.ドレー、スヌープ・ドッグにE-40。彼らの創造性だけではなく、(アーティストとしての)寿命の長さをお手本にしたいと思っています。彼らは常に「何が起きているか?」ということを理解していますし、常に自分のやり方で活動し続けています。そして、いつも新しいアイデアに対してオープンです。こうした先駆者たちを、僕は近くから、そして遠くから見つめて来ました。彼らがこの業界の中で30年以上のキャリアを続けていることも、僕が見習いたいと思う点です。それは、音楽業界のみならず、創造性全般において言えること。彼らにはいつも刺激されます。
---あなたの音楽、ヒップホップに必要な要素とは何ですか?
先ほどの答えに戻るようですが、僕にとっては、楽曲制作ということでしょうか。(制作に込める)感情はあくまで自然な感情です。人々に会い、何が、そしてどの歌詞が彼らの心を動かしたのかを理解した今、僕にとって楽曲制作は、(計算された)科学なんかではありません。そこには感情と音楽しかありません。もし人々が感じるなら、そこに心を動かす要素があるということです。一つの歌詞に何行の節を使うべきだとか、フック(サビ)はどれくらいの長さであるべきとか、アウトロ(曲の終わり)はどれくらいの長さであるべきといった問題ではありません。そうではなく、私とつながる何かが重要なのだと思います。
日本の若者へ伝えたい“音楽の力”
5年ぶりに立った日本のステージ。どしゃ降りだったにもかかわらず、大観衆が会場を埋め尽くし、彼の音楽に酔いしれていた。若者たちにみずから考え行動するよう訴えるケンドリック・ラマーのメッセージは、確かに日本の若者にも届いている。
---率直に日本の印象はいかがですか?
たくさんの文化がある。日本には豊かな文化があると思います。だから僕は、早くこの(インタビューの)場を出たいですね(笑)。いま受けているこのインタビューも好きですが、ストリートに出て(文化を)体験したいし、人々のストーリーや歴史、彼らが生活しているフッド(地元)のことを知りたい。
---日本でもラップで自己表現する若者が徐々に増えています。彼らに伝えたいことは?
僕たちがアメリカやヒップホップ・コミュニティーで培ってきたインスピレーションを受け取ってほしい。そして、それを自分のものへと昇華させていってください。ヒップホップは常に進化しています。僕のストーリーが、普通の小さな男の子のストーリーになったように、それが日本の若い男の子や女の子のストーリーになる。僕の野心やインスピレーションを受け取って、そこから自分のストーリーを作り上げていってほしい。別に、ケンドリック・ラマーやアメリカのほかのラッパーのように聞こえなくてもいいんです。自分のものを作り上げる。そして、一度それが実現できたら、きっとたくさんの扉が開くはずです。あなたのコミュニティーや日本だけが誇りに思うのではなく、きっと世界の人々すら、(あなたを)もっと尊敬するようになるはずです。
---日本にもヒップホップやラップが広がってほしいですか。
本当にそのとおりですね。ヒップホップはすべてのエリアに拡がっていくべきです。可能であれば、火星にも。これは止められないことですし、音楽の力を見せつけているんです。だから、ヒップホップが永遠に息づいていくことを願っています。間違いなく、日本でも永遠に根付いていくでしょう。
(インタビュー翻訳/渡辺志保(音楽ライター)・翻訳協力 Abe Spiegel)