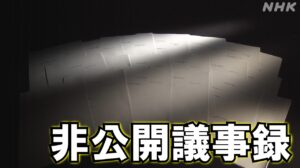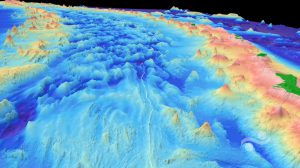科学と文化のいまがわかる
原子力

「赤提灯をともし続ける」福島・浪江町 ある消防団員の思い
2021.06.04
明かりの乏しい浪江駅近くの通りに赤提灯をともす1軒の居酒屋がある。避難指示は解除されたとは言え町民はまだほとんどが戻っていない中、通ってくるのは役場の職員か復興事業に携わる東京の大手建設会社の社員や作業員が多い。
店を切り盛りするのは33歳の大清水一輝さん。「採算がとれるはずがない」町内で再開すると決めたとき、周囲は多くが無謀だと反対した。それでも決意は揺るがなかった背景には、消防団員として直面した原発事故の経験と、そこで新たにしたふるさと再生への思いがあった。
原発で賑わった町に生まれて
居酒屋「こんどこそ」が開店したのは大清水さんが生まれた昭和62年。当時、浪江町には多くの飲食店が立ち並び、一時は人口あたりの店の数が“東北一”などと言われたこともあった。大清水さんが幼心に覚えているのは、20人ほどの客が店の外で席が空くのを待っている姿だ。客の半分ほどは東京電力など原発関係だったという。通りには大勢が行き交い、町は活力に満ちていた。

「親が忙しかったから、外で過ごせるようにサッカークラブに入れられたりしていました。家の前の道を歩いて帰ってくると、近所の人たちが声をかけてくる。しかられることも多かったけど、俺はこの町に育てられたんです」
壁のような津波 強いられた避難
2011年3月11日、その町を東日本大震災と原発事故が襲った。当時、大清水さんは両親が経営する店を手伝う傍ら、消防団員を務めていた。
「その日は、務めていた南相馬市の測量会社の仕事で河川の調査を行っていたのですが、とてつもない揺れを感じて会社に戻りました。すぐに浪江町の自宅へと車を走らせたのですが、幹線道路の国道6号線は渋滞していたため、少し海側の道を通ると黒い壁のような津波が押し寄せてくるのが見えました。なんとか帰り着くと、すぐに近所のお年寄りの安否を確認するため声をかけて回った。店にあった飲み物は支援物資として配りました。その時は原発なんて頭になくて、避難を指示する防災無線を聞いたのは翌朝のことでした」
浪江町の中心部から国道114号線を福島市方面に向かう途中、山あいに見えてくる集落がある。浪江町の津島地区。3月12日午後、避難指示は20km圏内に拡大。避難を迫られた浪江町の住民たちは、町からの指示もあり、多くが福島第一原発から30km近く離れたこの地区へと向かった。普段1500人ほどが暮らすこの地区に、1万人を超える人たちが詰めかけた。

「自分は避難する人たちの誘導にあたっていました。津島地区の交差点付近に消防団の車を止めて、渋滞の中なんとかたどり着いた人たちを、町の施設や学校などに急遽設置された避難所に振り分けていった。途中、両親にも会ったのですが、ゆっくり話をしている時間もない。『きっと大丈夫』と信じて自分は誘導を続け、家族は避難所へと送り出しました。両親の行き先と無事が確認できたのは数日後のことでした」
不安と緊迫の避難所で
避難所の雰囲気は殺伐としていた。大清水さんが担当したのは津島地区にある高校で、1000人以上の人たちが着の身着のままで身を寄せていた。
「水は使えず食料もほとんどない。テレビ以外の情報はなにもなかったんです。運営にあたるのは町の職員も含めて4~5人で、自分は一番若かったこともあって、夜も眠らずに校舎の昇降口に座り続けて、避難者からの相談や、後から避難してくる人たちの受け入れに対応していました。何でそんなことが出来たのかと聞かれますが、若かったし大好きな町のためにという思いしかなったですね」
「これはあんまり話したことがなかったんだけど」と言いながら、大清水さんが語り出したのは、強く記憶に残っている避難所であったある出来事だった。
「実は避難所で一度だけ本気で怒ったことがあったんです。あるとき、全身を防護服姿でマスクをした警察官が避難所を訪ねてきたんですが、その姿を見るなり頭に血が上ってしまって『そんな格好を住民たちが目にしたらどう感じると思っているんだ』と大声で怒鳴りつけてしまいました。当時原発の情報もほとんどない中、避難所の雰囲気はすごく悪くて、何を考えているんだと思いましたね。すぐさま校舎の外に連れ出し、要件は自分を通じて伝えてほしいと求めましたが、今考えれば、その警察官も上司に指示されてのことだったろうと思います。ただ、住民たちがどれだけの不安の中にいるかと考えると、声を荒げずにはいられなかった」
3月15日。浪江町は津島地区を離れ、二本松市へと避難することを決めた。のちに分かることだが、この日、津島地区を含む原発の北西方面には高い濃度の放射性物質が降り注ぎ、汚染が広がっていた。避難者を送り出し、大清水さんが、二本松市についたのは夜のことだった。
「着替えもなかったので、5日間期続けた防火服と法被姿のままだったのですが、16日に放射性物質のスクリーニング検査を受けるため二本松市内の会場を訪れると、自分の前の並んでいた男性の放射線量が高いと言っていた。その人は上着を脱いだりしたんですがやはり高い。それで、どこに放射性物質が付いているのかとなったのですが、本人にも心当たりがないというので、なんだろうと思っていたら気がついたんです。測定器は、後ろに並んでいた俺の放射線量を拾っていたんですよね。案の定、測ってみるとすごく高くって、ただちに服を脱ぐように指示されて、3月の凍える寒さの中、冷たい水を浴びて頭や体を洗いました」
2日ほど二本松市に避難したあと、いわき市にある姉の家に身を寄せた。いわきにたどり着いたとき、それまでの緊張が一気に解けたように涙があふれ出してきた。その日は用意されていたおにぎりと味噌汁を食べながら眠ってしまった。
“必ず戻る” 再開への歩み
避難先の二本松市で「こんどこそ」が再開したのは原発事故から半年余りたった10月のことだった。浪江町の人たちから頼まれたこともあり、母親が二本松駅前の店舗を借りて店を開いたのだ。大清水さん自身は、勤め先の測量会社の仕事が、復興工事のために大忙しになった。
「避難指示や津波の被害で自宅に帰れない人も多い中、会社が用意した一軒家でほかの社員と共同生活し、8畳間に5人くらいで寝たこともありました。自分はどちらかと言えば人と接触するのもされるのも苦手なんですよね。人柄の良い人たちばかりだったが、震災がなければ絶対しないような経験でしたよ。その頃はほとんど記憶もないほどの忙しさでした」
1年ほどして大きな現場の仕事が一段落したことから、会社を辞め店を手伝うようになった。すべての仕入れルートが失われ、すべてが一からのスタートだったが、当時から浪江町で再開することは心に決めていた。

「避難指示がいつ解除されるかも分からなかったが、補助金や賠償金に頼ることにもいい気持ちはしなかった。自分たちの生活は自分たちでしなければいけないし、いつまでも震災や東京電力のせいにはしたくなかったんです。町の保育士だった妻には結婚する前に『絶対に町に戻るから』と決意を伝えて、理解してもらいました。指示解除から1年半後の2018年の9月に、元の場所で店を再開しました。そのころ子どもも生まれたんですが、再開できたのは家族の理解があったからだし、本当に妻には感謝しています」
長い道のりの途中に
それから2年余り。町内で暮らす人は1500人あまりと震災前の10分の1にも満たない。売り上げもまだ震災前の5分の1程度で新型コロナウイルスの感染拡大以降はさらに厳しい状況が続いている。だが、大清水さんの顔に悲壮の色はない。

「お金儲けをしたければこんなところではやらないし、町に人の流れを生み出すためには店が開いていることが大事だと思ってやっています。ただ、避難先で生活基盤も出来ている人もいるし、いまだに放射能が怖いという人もいるのが現実で、個人的には町民に戻って来いとは思っていないし、新たな人が来て、新たな生活スタイルが作れれば良いと思っています。どこにでもある町でなく、どこにもない町を作っていきたい。それが自分を育ててくれた町に対してできる、せめてものことだと思っています」
大清水さんにとって10年は節目ではない。マスコミが向ける「10年たってどうですか」という質問にも特段の感慨はなく「生活は少しずつよくなっているが、先の長い道のりの途中にいることに変わりはない」と答えている。けれど、10年だからという理由で町の現状が伝えてもらえるなら、それでもよいとも言う。
「町のことを知ってもらえるなら、発信してもらえるならありがたい」
その言葉に、ふるさと浪江町の再生をあきらめないという思いがにじんでいた。