火山噴火 その時どうする?対策は?

突然の噴火が発生した時。噴火発生を知らせる「噴火速報」や、噴火が予想されるとして「噴火警報」が発表された時。「噴石」「火砕流」「火山灰」「土石流」「溶岩流」から、どうすれば身の安全が守れるのか。知っておきたいポイントです。
噴火関連ニュースや解説で放送された内容をまとめた記事です
目次
噴石
火口の近くにいる場合、まず怖いのが噴石です。大小さまざまありますが、高速で落下してくる噴石が直撃すれば、命が危険にさらされます。

✅近くにシェルターがあれば、直ちに避難を
✅山小屋は噴石貫通のおそれがあるも、外にいるよりは安全度は上がる
✅避難場所がない時は大きな岩や斜面などの陰に避難を
✅ヘルメットをかぶって身を小さく
✅ヘルメットがない場合は、リュックなどで頭を守る
火砕流
高温で高速の火砕流に巻き込まれると命の保証はありません。火口周辺に近づかないことが最も重要です。

✅流れ下る様子が見えたら、立ち止まらずに反対方向へ
✅谷筋からも離れたほうが安全度は上がる
✅直撃を免れなくなった場合、コンクリートで出来た頑丈な建物などの中に入り、口をタオルでふさぐなど少しでも助かる可能性のある対応を
火山灰
量によって異なりますが、人体や交通、ライフライン、建物への影響が心配されます。

<人体>
火山灰を吸い込むと、ぜんそく患者など肺に疾患がある人は症状が悪化するおそれがあります。健康な人でも長時間火山灰にさらされると目や鼻に異常を感じ、深い呼吸をすると
のどや気管支などに影響が出るおそれがあります。
✅室内で過ごす
✅外出の場合はマスクやゴーグルなどを着用
<車>
車が出せる速度は1ミリ以上の灰が積もった場合は30キロ程度、10センチ以上で通行できなくなるとされています。火山灰が降っている際には視界も悪くなります。タイヤがスリップして交通事故の危険性も高まります。
✅不要不急の運転は避ける
✅運転の場合は速度を落とし慎重なハンドル操作を
<ライフライン>
2ミリ以上の灰が積もると、浄水場が利用できなくなったり、下水道が詰まってしまったりするおそれもあります。3ミリ以上積もると、送電設備がショートして停電するおそれもあります。
✅水や食料を備蓄
✅懐中電灯やラジオなどを準備
<建物>
7センチから8センチの灰が積もると、体育館のような屋根の大きな建物で損傷したり倒壊したりするおそれがあります。また、少量の灰でも雨が降ると重くなり雨どいなどがこわれることもあります。
✅大量の場合はコンクリートで出来た建物などに避難
✅少量で降灰が止まった場合、雨どいや排水溝などの掃除を
土石流
大量の火山灰や噴石が雨水や川の水に押し流され、土石流が発生することがあります。冬の間は山から離れていても、火口周辺の雪が一気にとけて「融雪型火山泥流」が発生し、ふもとの街に甚大な被害が出るおそれがあります。

✅川や谷筋から離れた場所への早めの避難を
✅川や谷筋の様子を見に行かない
溶岩流
火山から流れ出る溶岩は、比較的速度が遅いため、逃げる時間はあります。ただ、溶岩は1000度にも達する高温で、近づくと大変危険です。家屋や植物も破壊し、燃やしてしまいます。

✅溶岩流が迫っているときは近づかない
✅表面は固まって見えても内部は高温 噴火活動が終わった後も近づかない
いざという時の備えを!
それぞれの火山でどのような災害が発生するのか、具体的な危険性は、地元の自治体などが公表しているハザードマップで知ることが出来ます。
火山の近くで住んでいる人だけでなく、観光や登山の目的で火山に近づく人も、必ず目を通し、いざというときの心構えをしておくことが大切です。
あわせて読みたい
-

全国111活火山はどこに 噴火の種類や警報、警戒レベルとは?
日本の111活火山の場所を地図で。マグマ噴火・水蒸気噴火・マグマ水蒸気噴火といった噴火の種類と溶岩や火砕流、噴石など被害の様相は。噴火速報や噴火警報、警戒レベルとは?火山に近づく際、特徴やリスクを知り備えておくことが大切。
-

富士山大噴火 降灰シミュレーション 首都圏に深刻な影響も
富士山が噴火した場合、火山灰は首都圏にも飛来するおそれがあります。江戸時代の宝永噴火をもとにした降灰シミュレーションの詳細です。
-

東京で噴火再び!? その時、どうする…
噴火すると、影響は火山周辺だけでなく、都市にも及んできます。避難の方法、...
-
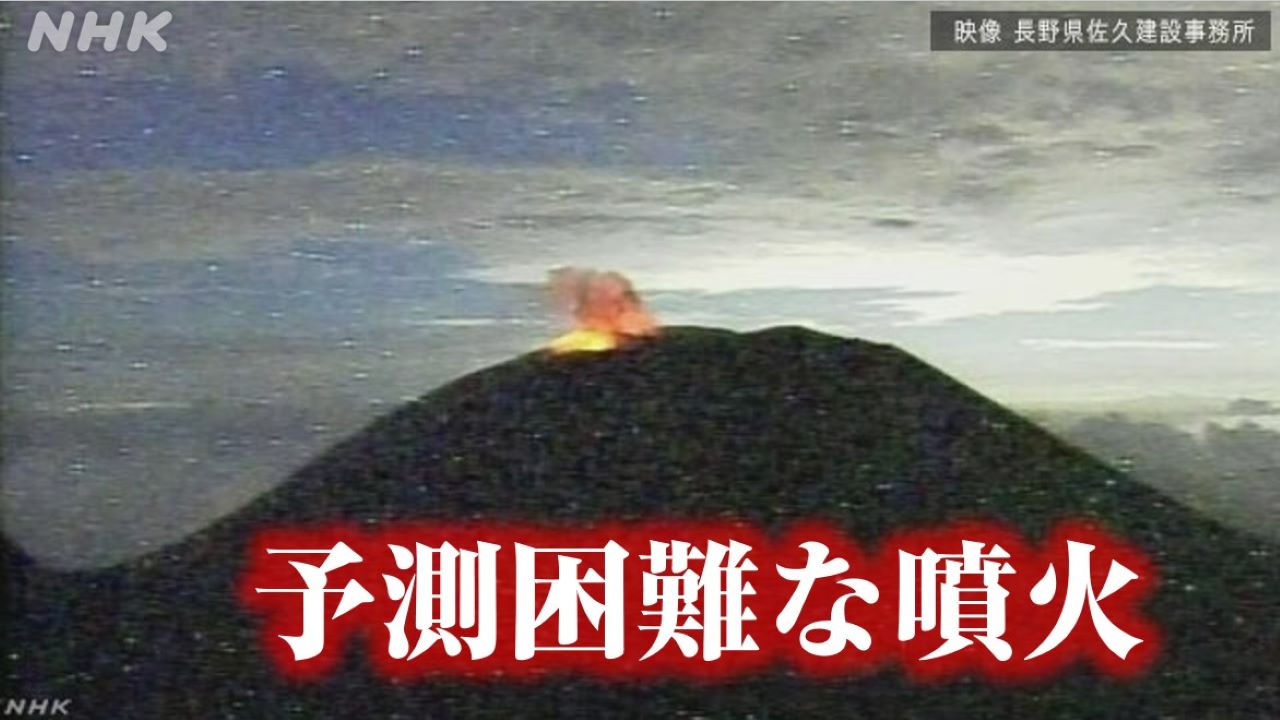
警戒レベル1で噴火も…予測困難な噴火 火山情報のジレンマ
全国に111ある活火山。御嶽山や浅間山など噴火警戒レベルが最も低い「レベル1」でも噴火することはある。予測が難しい中「どうやったら命を守ることができるのか」を考える。
-
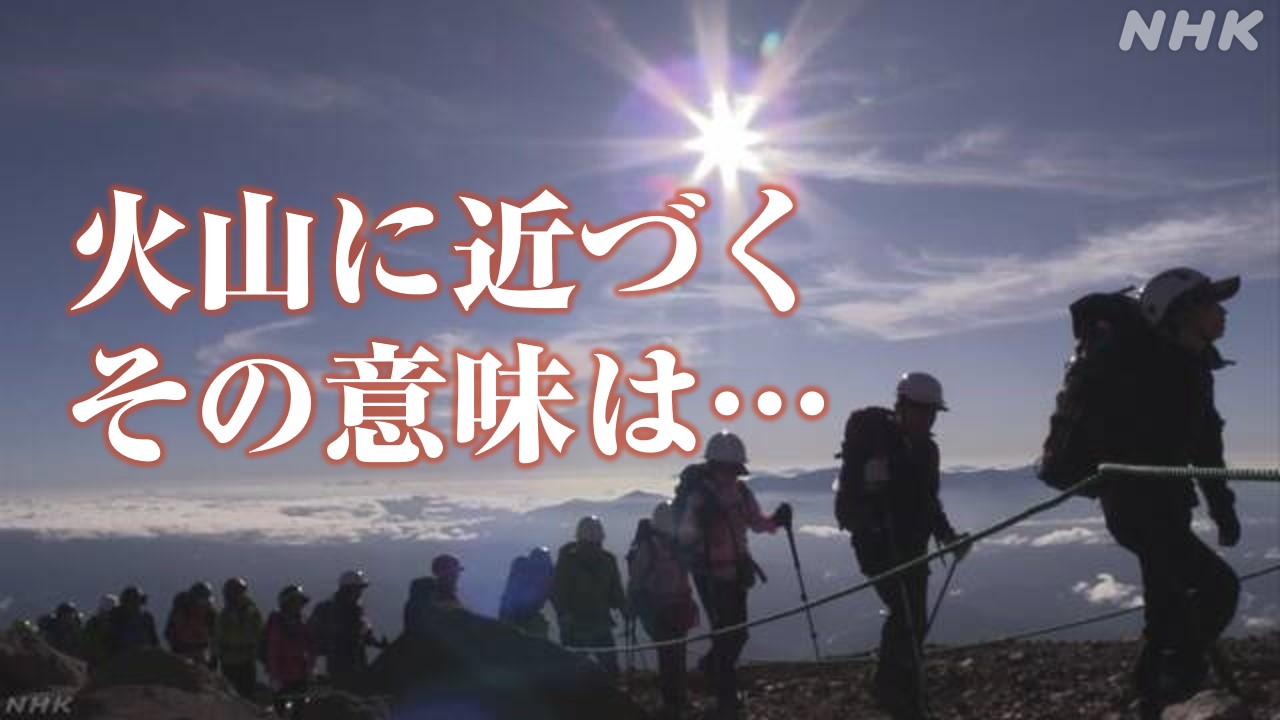
火山に登るなら そこに絶対の安全は無い…御嶽山噴火災害
御嶽山の山頂。雲海が広がる最高の景色、澄み切った気持ちのよい空気。でも、もしまたあの日のように突然噴火が起きたら…。当時を知る登山者に同行し、課題や教訓、身を守るすべを探った。
-

“危険と分かって近づいたのか” 雲仙普賢岳 火砕流災害の教訓
43人が犠牲になった雲仙普賢岳の大規模な火砕流災害。なぜ被害は起きたのか。マスコミ・報道関係者は。見えてきたのは、いまも突きつけられている課題でした。
-

発見!富士山噴火で消えた村 300年の時を超えた教訓
江戸時代に発生した富士山の宝永噴火による火山灰や噴石などで埋没した村を発掘する調査に単独で密着。そこには300年の時を超えた教訓が。
