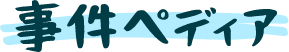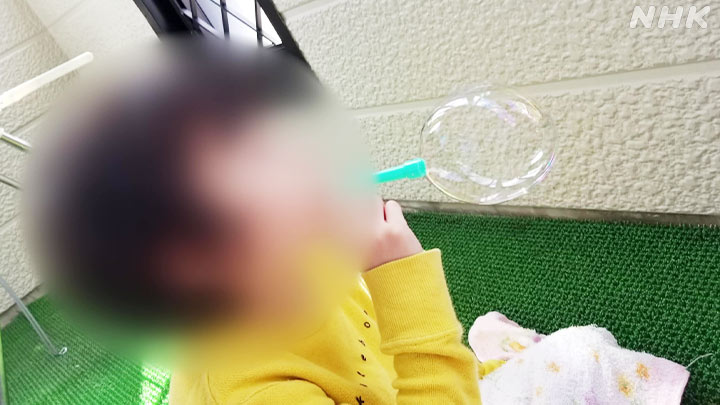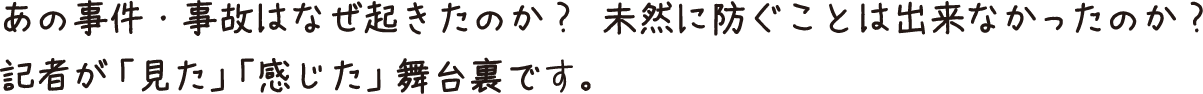母親は息子を後ろから支えるようにして階段を上りはじめたが、前に進まない。
息子は体を動かしたくないのか、膝を曲げようとしない。一段あがるだけでもかなりの体力と時間が必要だと感じた。
「筋肉が硬直してしまって…」
ようやくトイレにたどり着いたが、息子はズボンの着脱ができない。母親が介助すると「ギャー」と部屋中に響く声を出し、頭を前後左右に激しく振った。
トイレの壁に容赦なく頭をぶつけ、母親は息子の頭を守るようにして抱きかかえた。しかし、息子はやめるそぶりをみせず、母の腕のなかで激しく頭を振り続けた。
ふいに息子の顔がぶつかって母親が大きくのけぞった。
私はどうして良いのかわからず、立ち尽くすことしかできなかった。
「まだ小さいから私でもなんとか対応できますけど、大きくなったら私の力ではどうにもならないかも」
息子をしっかりと抱きかかえた母親は、息を切らしながらそう言った。
この息子の状態は「強度行動障害」と呼ばれ、国によると自閉スペクトラム症の障害児などの二次障害として現れるという。周囲の環境や人の関わり方で誘発され、大声や頭突き、かみつきなど他害や自傷行為を頻繁に繰り返すとされる。
母親によるとトイレに連れていき40分押さえつけてもおしっこが出ず、1日のうちにトータルで3時間から4時間トイレにいることもあるという。食事も飲み込む行為を嫌うので3時間を費やす。