
「家賃は無料で入居できます。ただし、毎月少なくとも10時間、高齢者に付き添うこと」
社会人になったばかりで、お金に余裕はありません。そんな中、ふと目にした「家賃無料」という宣伝文句にひかれ、男性は高齢者施設に住み込むことを決めました。
かつては「爆買い」の印象が強かった中国の人たち。今、節約志向が強まっていて、若者の中には「高齢者にあやかろう」という動きも広がっています。
(上海支局長 道下航)
高齢者に付き添えば無料で入居
募集を出したのは、中国東部・浙江省杭州にある高齢者施設です。

去年(2023年)、大学を卒業した岳洪偉さん(24歳)は、さっそく、応募してみることにしました。高齢者の役に立つのならという思いもありましたが、家賃代が浮くことに大きな魅力を感じたからです。就職難のもと、苦労してプログラミングに関わる仕事に就いたものの、給与は低く、自分で部屋を借りることは簡単ではありませんでした。
岳さんが住み込みを始めた高齢者施設は1100人余りの利用者がいました。その一角の部屋を岳さんはあてがわれました。毎月少なくとも10時間、施設の高齢者に付き添うことで、部屋の家賃が無料になる仕組みです。

「部屋は比較的広く、独立のベランダやトイレ、風呂場もあるので、とても満足しています。新卒の若者にとっては、家賃の支出は非常に大きいです。その負担を減らせることは本当に助かっています」
若者たちは、面接や身体検査などで選ばれましたが、介護などの資格を持っていたり、勉強していたりするわけではないといいます。お年寄りの付き添いについても、若者たちは、高齢者の話し相手になったり、趣味を一緒に楽しんだり、スマートフォンの設定を手伝ったりと、簡単なものです。

実際、高齢者と向き合う若者たちの様子は、どこかぎこちなくも見えましたが、付き添う姿勢は懸命そのもの。若者と交流する高齢者たちも、若者たちとの時間を楽しんでいました。

人とのつきあいがあまり得意でなかったという岳さん、高齢者たちとの生活を通じて、以前よりも社交的になったといいます。また、高齢者と同じように早寝早起きをするようになり、生活の規律を保てるようにもなったということです。
取り組みを行っている高齢者施設の院長は、若者と高齢者の双方にとって良い影響が出ていると感じていて、今後も、取り組みを拡大させていたきいと言います。

「施設側は若者のために少しの経費を負担しているだけですし、若者たちも決して多くの労力を費やす必要はありません。彼らの時間や、ちょっとしたことを高齢者に提供してくれればいいのです。そうすることで、高齢者は、美しい生活の思い出を、若者は、成長の過程における素晴らしい経験を得られるので、若者と高齢者の双方にとって、非常に意義のある取り組みになっていると思います」
消費に慎重になる若者たち 失業率は約15%
中国の若者たちは、今、生活の負担を少しでも小さくしようと考えるようになっています。若者の失業率は高止まりしていて、去年(2023年)12月の16歳から24歳までの失業率は14.9%となっています。景気の先行きも不透明な状況が続く中で、若者たちの間では、消費に慎重な姿勢が広がっています。

▼「コストパフォーマンス」を意味する「性価比」、▼「ブランド品ではなく品質がそれほど変わらない安い商品を選ぶ」という意味の「平替」という中国語の単語が若者の間では定着しています。また「理性的な消費」という言葉もニュースでは使われています。

30代男性
「多くの会社が人員を整理し、貿易の状況も悲観的で、経済はどの方面も良くないです。私も消費をかなり減らしていて、以前と比べ、支出は半分といった感じです。もちろん『平替』もしています。例えば、服を買うときは、実店舗で商品を見てから、ネット通販でコストパフォーマンスが良い商品を買うようにしています」

20代女性
「今でも、好きなものにはお金をかけますし、高くても購入することはあります。しかし、以前と比べて、必ずしも必要のないものに対しては、買う回数や『買いたい』という気持ちが少なくなっています。消費は前よりも理性的になっています」
さらにSNS上では、自分の節約や貯金の状況を共有するというトレンドも見られます。

この画像は若者が投稿した動画の切り抜きです。キャッシュレス決済が普及している中国ですが、その月の消費計画などをあえて現金で可視化し、公開することで、自らを律して節約や貯金につなげようというのが狙いのようです。
「高齢者食堂」に通う若者たち
中には、高齢者向けの低額サービスを利用する若者もいます。こうした動きは「高齢者へのあやかり消費」とも呼ばれています。その現場が、上海の中心部にありました。そこは「高齢者食堂」。
朝食、昼食、夕食をそれぞれ提供する、もともとは高齢者向けに作られた食堂です。

私が訪れたのは、昼食の提供が始まる午前10時。食堂には、すでに、大勢の高齢者が詰めかけ、料理が並ぶカウンターから、好みの1品を選んでいました。
メニューの値段は、肉や魚の料理と野菜料理、それにごはんがついて、およそ400円から。料理の種類や品の数で値段は変わりますが、ボリュームのある料理を低価格で提供しています。訪れる人の中には、食べきれない料理を家に持ち帰るための「弁当箱」を持ってきている人もいました。

中国では、政府の指導のもと、高齢者の生活を支援する狙いで、こうした低価格の食堂の設置が各地で進んでいます。この食堂もそうした施設の1つです。ただ、高齢者以外の客も受け入れています。

昼前になると、客の中に、若者の姿が目立つようになりました。話を聞くと、彼らは近くで働いている若者たちでした。彼らの間では、値段の割にはボリュームがあると評判を呼んでいるといいます。

20代女性
「1週間に2、3回来ます。上海の住宅は高く、負担が大きいため、生活では、コストパフォーマンスを重視しています。その点でこの店はとてもいいです。経済的に大きな助けになりますし、私のまわりの人たちは、ここで食事をするのが好きですね」
若者が増える昼になると、店内の混雑は激しくなり、店外には行列も見られるようになりました。それでも、高齢者からは批判的な声は聞かれませんでした。

高齢の男性
「食堂は、高齢者向けの低額食堂とはいうものの、今の時代、若者にだって必要なサービスですよね。いろんな人たちに役立っていていいと思いますよ」
取材を終えて
中国の経済や地方財政が厳しくなる中、若者を取り巻く環境も、社会保障に頼る高齢者の生活も、過酷になっているという声を聞くようになりました。
そんな中、中国で減退する若者の消費意欲が「高齢者へのあやかり」を生み、さらには思わぬ形で若者と高齢者の新たな接点となっています。

30代の私も「高齢者食堂」で食事をしてみました。すると、すぐさま前に座っていた高齢の女性から「お肉をいっぱい食べているね」と笑顔で話しかけられました。いろいろな高齢者から話を聞きましたが、若者の存在を疎ましく思うような人はおらず、むしろ「若者がいることで、店がにぎやかになっていい」と話す人もいました。
中国は、65歳以上の人口が全体の14%を超える「高齢社会」に入っていて、今後、さらに高齢化が加速するとみられています。この「あやかり」が厳しさを増す時代を生き抜く支え合いにつながっていくのか、注目していきたいと思います。

3月5日BS国際報道2024、3月7日おはよう日本で放送



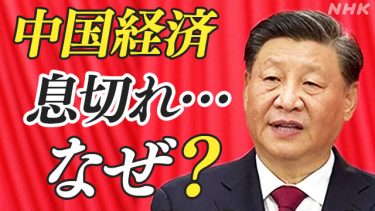








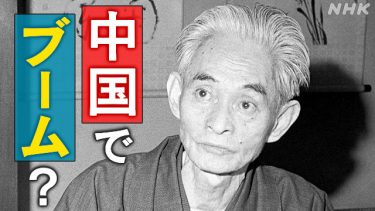

 国際ニュース
国際ニュース
