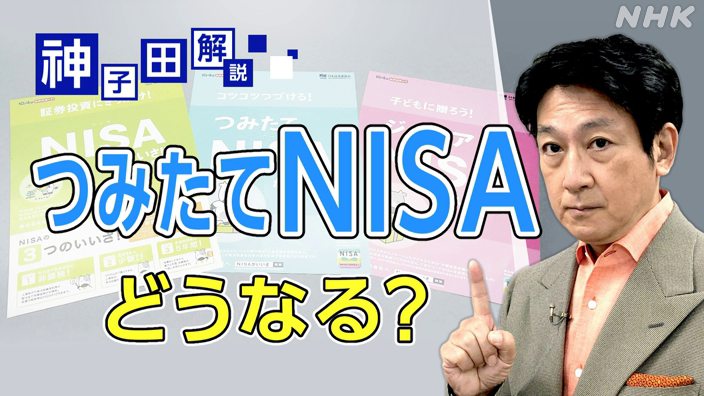資産形成の手段として関心が高まっている「NISA(ニーサ)」。耳にする機会も増えているのではないでしょうか。
11月18日から2023年度の税制改正の本格的な議論が始まり、「つみたてNISA」の年間購入額や非課税になる期間が拡充されるかどうかが注目されています。
いま知っておきたいつみたてNISAの仕組みや、今後の議論のポイントを神子田キャスターが詳しく解説します。
そもそも「NISA」とは?
「NISA」とは「個人の金融資産運用に関する税制の優遇制度」のことです。
「一般NISA」と「つみたてNISA」があり、今回の税制改正では、投資信託と呼ばれる金融商品による長期的な資産運用を対象にした「つみたてNISA」を基本に議論が行われます。

そもそも「投資信託」とはどんな金融商品なのでしょうか?これは個別の企業の株に直接投資するのではなく、預けたお金をほかの人のお金と一緒にして、複数の企業の株や債券を“束にしたもの”に投資する仕組みです。
もし投資した企業の一部が倒産しても、ほかの企業の株も買っているため、その分リスクを低く抑えられるといいます。

投資家は、この商品から発生する分配金や、値上がりして売却した時の利益を得る際に、国と地方を合わせて約20%の税金を徴収されます。
これが「つみたてNISA」では、年間の購入額40万円(上限)を最長で20年間、非課税で保有できます。税金を取られない分“お得”になるというものです。

「つみたてNISA」拡充か?議論のポイント3つ
今回の税制改正では次のポイントが議論されます。
▼2042年までとなっている「つみたてNISA」の制度を恒久化する?
▼年間40万円の投資枠を引き上げる?
▼非課税で保有できる期間を無期限にする?
こうした議論が行われる背景には、預貯金を寝かせておくだけでは収入が増えないなどとして、政府が個人の金融資産を「貯蓄」から「投資」にシフトさせることを目指していることがあります。
また若い世代が老後を見据えて資産を形成するためには20年では短いという考え方もあります。

富裕層さらに優遇との指摘も
この投資の限度額を引き上げるとなると、富裕層がさらに優遇を受けることになるのではないかという指摘も出ています。
今の制度でも1人当たり年間40万円×20年=800万円まで投資できます。夫婦2人なら1600万円まで非課税で投資できます。一方、年間40万円を投資に回すだけでもたいへんな世帯が多いと思います。
今後どのような議論が行われるか注目したいと思います。
【2022年11月18日放送】
あわせて読みたい