
神は地球を作り、7日目に「休み」を取ったー
この聖書の記述に由来する「安息日」を今でも厳格に守っているのがユダヤの人たちです。
安息日には火を使うことや働くことなどが禁じられているため、イスラエルでは公共交通機関の運行はなく、ほとんどのレストランやスーパーが休みです。
この安息日ならではの朝食が「ジャフヌン」。
いったいどんな朝食なのか、調べてみました。
(エルサレム支局長 曽我太一)
イスラエル料理?ユダヤ料理?
現在のイスラエルが建国されたのは、今から70年あまり前の1948年。
世界各地で迫害を受けていたユダヤ人の間で「自分たちの国を作ろう」という運動(=シオニズム)が19世紀以降に広がり、東ヨーロッパ、西ヨーロッパ、モロッコ、中東など各地のユダヤ人がこの地に移り住みました。

こうした背景のほか、もともとこの土地に暮らしていたのはパレスチナ人ということもあり、「イスラエル料理とはなんぞや」という質問はイスラエル人でも意見が分かれるところ。
そして、今回取り上げるジャフヌンは、ある地域からのユダヤ人伝統の料理であるため「ユダヤ料理」として紹介します。
訪れたのは?
今回、お目当てのジャフヌン。
それを食べようと訪れたのは、イスラエル最大の商業都市テルアビブの一角にたたずむ食堂です。
今や「世界一物価が高い都市」の1つともされるテルアビブですが、食堂の周囲には年季の入った建物が建ち並んでいます。壁には、落書きも。

頭に冷たいものが落ちてきたと思ったら、歩道側に張り出したエアコンの室外機からしたたる水滴のようです…。
気を取り直して食堂に入ると、まず目に留まったのが歌を歌う女性の写真。
聞くと、イスラエルの伝説的な歌手オフラ・ハザなのだそうです。

2000年に42歳の若さで亡くなりましたが、「イスラエルのマドンナ」とも呼ばれ、1989年の東京音楽祭でグランプリを受賞するなど、世界的に一世を風靡したエスノポップ歌手だということです。
1986年生まれの私は、恥ずかしながら彼女のことを知りませんでした。
イエメン系ユダヤ人?
実は、ユダヤ人の中にはイスラエルから南東に2000キロ以上離れた中東イエメンにルーツを持つ人たちが多くいます。
先ほどの「イスラエルのマドンナ」ことオフラ・ハザも、こうしたイエメン系のユダヤ人です。
正確な数字はありませんが、イスラエルには数十万人のイエメン系のユダヤ人が暮らしているとされ、各地に離散したユダヤ人の中でも、古来のユダヤ文化を色濃く受け継いできたとされています。
例えば、イエメン系の人たちが話すヘブライ語の発音は、古典のヘブライ語に近いとも言われています。
そんなイエメン系のユダヤ人の人たちが、安息日の土曜日の朝に食べるのが、今回紹介するジャフヌンです。
ジャフヌンってどんな料理?
ジャヌフンは、小麦粉の生地を薄く伸ばしてバターを塗っては折り重ねるという作業を繰り返して作ったパイ生地を焼き上げた料理。

ただ、100℃に熱したオーブンで焼き上げる時間は、なんと10時間以上。
なぜこんなにも時間をかけるのでしょうか?
それは、ユダヤ教の安息日「シャバット」と密接に関係しているのだそう。ユダヤ教では、金曜日の日没から土曜日の日没までがシャバットです。
そして教えでは、この間、電気や火を使って作業することなどは一切許されないとされているのです。
このためジャフヌン作りでは、シャバットに入ったあとに火を使った作業をしなくて済むように、金曜日の日没前に火を付けたオーブンにパイ生地を入れて、翌土曜の朝まで時間をかけて焼き上げるのだそうです。

気になる味は?
10時間以上かけて焼き上げられ、目の前に出されたジャフヌンは生地が茶色に変わり、香ばしい香りを漂わせています。

アメリカでは“映えないSNS”が流行っていると聞きますが、目の前のジャフヌンもあまり“映えている”と言えないような…
食わず嫌いもいけませんので、さっそく一緒のプレートに並べられたオリーブオイルと潰したトマトのディップソースに付けて食べてみました。

たっぷりとバターが塗り込まれたパイ生地の重厚さ、しっかり焼かれた生地が醸し出す香ばしい香り、そして独特の味わい… これはなかなかクセになりそうです。
イエメン系のユダヤ人に伝わる料理はこれだけではありません。
ジャフヌンとともに、シャバットの食卓を飾るのが「クバネ」。
こちらも、同じように一晩かけて焼き上げるのですが、バターたっぷりでヘビー級のジャヌフンと違うのは、バターは少なめ。さしずめライト級といったところでしょうか。

こちらはパン生地がふっくらしていて、ほんのりした甘みもあり、日本人が食べ慣れているパンに近いので日本でもウケそうです。
町の人は?
この日、ジャヌフンを買いに来たというテルアビブ出身の女性に声をかけてみました。
夫はイエメン系のユダヤ人で、毎週金曜日には自宅でジャフヌンを作っていて、子どもたちも大好きなんだそうです。

「私はイエメン系ではないけれど、幼い頃から土曜の朝にはジャフヌンを食べて育ちました。土曜の朝にビーチに行けば、そこには露店でジャフヌンを売っている人たちがいるのですが、毎週それを待ち遠しく思っていたのを覚えています。ジャフヌンは言ってしまえばただの生地です。私は蜂蜜が入ったちょっと甘酸っぱい感じのジャフヌンを、トマトや辛いソースにつけて食べるのが好きなんです」
実はイスラエルではシャバットの間、ユダヤ教の教えを厳格に守り一切電気も使わず車もスマートフォンも利用しないという人たちがいる一方で、車もスマートフォンも使う人たちもいます。
前者は「正統派」、後者は「世俗派」と呼ばれ、テルアビブが世俗派都市の代表格です。
話を聞かせてもらったテルアビブ出身の女性は、シャバットでも車を使う世俗派だということでした。
宗教的な日であるシャバットと深く結びついているジャフヌンですが、今や宗教に関係なくイスラエルの食文化の一部になっているようです。
イスラエルにはイエメンの文化も
イエメンにルーツを持つ人たちが多く住むイスラエルには、イエメンの文化が各地に持ち込まれています。
そのことがわかる店が、NHKエルサレム支局から徒歩5分ほどの所にあります。それはエルサレムの観光名所の1つでもある「マハネ・イェフダ市場」にある、イエメン系の人たちが経営するジュースショップ。
この店の一番の売りが、「ガット・ジュース」です。
ガット(一般的には「カート」と呼ばれています)という覚醒作用のある植物から作られたジュースです。

アルコールが禁止されているイスラム教徒が主流のイエメンで、人々が陶酔感を味わうための嗜好品としてたしなんできたものなんだそうです。
イスラエルに移り住んだイエメン系の人たちが持ち込んで、ジュースとして出しているといいます。
宗教への敬虔さの度合いや、家族の出身地など、さまざまなバックグラウンドを持つ人たちが、まさにパッチワークのように社会を作り上げているイスラエル。
それ故に、意見も主張もさまざまで、総選挙はこの3年半で5回も行われました。政治も社会も一筋縄ではいかない、そんなイスラエルを引き続き取材していきたいと思います。







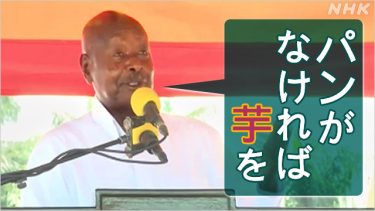
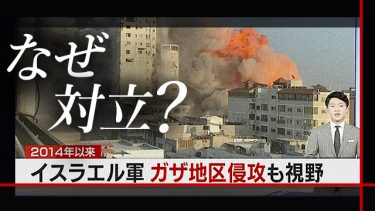

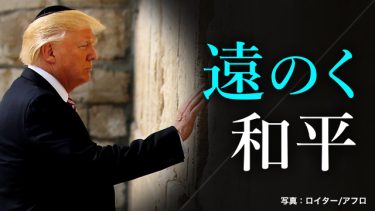


 国際ニュース
国際ニュース
