
「当たり前だったものの大切さを学ぶことになりました」
ウクライナ国内に残る男性は、取材に対してこう話したのだそうです。
今もロシアによる侵攻が続くウクライナ。現地の人たちはどんなことを思い、どういった生活を送っているのでしょうか。
現地を取材した記者に話を聞きました。
(ウクライナ現地取材班 鈴木陽平)
今回、話を聞いたのは?
5月中旬から約1か月間ウクライナの首都キーウを拠点に取材した、国際部の鈴木陽平記者です。

2011年に入局し、初任地は鹿児島局。次の横浜局では県警キャップなどを務めたあと、国際部へ異動。ウクライナ情勢などを取材しています。
(以下は、鈴木記者の話)
ウクライナにはどうやって行ったの?
向かったのは、ウクライナの首都キーウ。日本からは直線距離で約8000キロ離れていて、日本との時差はマイナス6時間です。
羽田空港から出発し、トルコのイスタンブール空港で乗り継ぎ、丸1日かけて、まずは隣国ポーランドにある南東部の都市ジェシュフに到着しました。

ジェシュフはウクライナとの国境に近くにある都市なので、次の日の朝早くジェシュフを出発して、徒歩で国境を通過してウクライナに入りました。
そこからは事前に手配した車に乗って、8時間半かけて首都キーウに到着しました。
ウクライナ国内の様子は?
ウクライナの面積は日本の約1.6倍ありますが、ロシアによる軍事侵攻以降は、旅客機が運航できない状態が続いていて、鉄道か車で移動するしかありませんでした。
車でキーウに近づくにつれて、ウクライナ軍の検問所が多く設けられていて、通過する際は1台ずつ止められ、厳しいチェックが行われていました。ロシア軍の侵攻を阻むために設置されたバリケードも多く見られました。
また、幹線道路にある道路標識は塗りつぶされていました。キーウまでのルートが分からないようにするためだということでした。
街の至る所に、銃を持ったウクライナ兵の姿があり、パスポートの提示を求められたり、スマートフォンの写真やSNSのメッセージを確認されたりすることもありました。ちなみに、兵士や検問所の撮影は禁じられていました。
首都キーウの状況は?
当初ロシア軍は首都制圧を目指して、一時キーウ近郊まで迫りましたが、ウクライナ側の抵抗により、4月上旬までに撤退しました。

それ以降、キーウには少しずつ人が戻り始めています。
営業を再開する飲食店なども増えてきていて、街にはにぎわいが戻りつつあるように感じました。カフェやパブで食事やアルコールを楽しむ人の姿も多く見られました。
ウクライナに入る前は「物資が不足しているんじゃないか」と思っていましたが、キーウにある市場やスーパーには食料品がそろっていました。空になっている棚も見当たりませんでした。
キーウには日常が戻っているの?
物流の停滞による影響は出ていました。
市場の人たちによると、物流が滞って、2倍近く値上がりしている野菜などもあるとのことでした。
また、燃料不足も深刻でした。ウクライナの製油施設が攻撃を受けた影響などで、多くのガソリンスタンドが休業となっていました。
そして、営業しているスタンドには、長蛇の列ができていました。「1回の給油につき20リットルまで」などと、制限を設けている所がほとんどで、ドライバーの中には「燃料を満タンにするため、丸1日かけている」と話す人もいました。
キーウで危険を感じることはないの?
私が取材している間、キーウをはじめとして各地で夜間の外出禁止令が出されていました。また、毎日のように防空警報が出されてサイレンが鳴っていました。
キーウ市内では、警報が1日に2、3回出されていて、その際は、町じゅうにサイレンの音が響き渡りました。深夜や未明にサイレンが聞こえることもあり、不安な気持ちになりました。
街の人たちからも「サイレンが鳴るたび、不安に襲われる」という声が聞かれました。
ウクライナで取材を続けていた6月5日には、ロシア軍の爆撃機がキーウ市内に5発の巡航ミサイルを発射し、このうち4発が鉄道車両の修理工場に着弾して、作業員1人がけがをしました。

また、私が帰国したあとではありますが、6月26日にはキーウ中心部に近い地区で、集合住宅などが4発のミサイルの攻撃を受けて、男性1人が死亡しています。
一見キーウでは日常が戻りつつありましたが、キーウの市民の中には「ミサイルでいつ攻撃されるかわからない」「再びロシア軍が首都に迫ってくるのではないか」と話す人もいて、依然としてロシアによる軍事侵攻下にあることを実感しました。
キーウに残った人の暮らしは?
ウクライナでは、防衛態勢を強化するため18歳から60歳の男性の出国が制限されています。
このため、女性や子どもは国外に避難していますが、多くの男性は国内にとどまっています。

私は、ウクライナに残る、アブラホフ・タラスさんという56歳の男性を取材しました。妻と2人の娘は国外に避難していて、アブラホフさんは、キーウ近郊の自宅にひとりで暮らしていました。
アブラホフさんは、バラエティー番組や映画の撮影に使うスタジオを経営していますが、テレビは軍事侵攻のニュース一色になり、スタジオは使われることがなくなったといいます。
収入が減り、従業員の雇用を維持することも難しくなっているということでした。
また、苦労していると話していたのが、毎日の食事作りなのだそうです。これまでは妻が作ってくれていたので、慣れない自炊生活が続いているということでした。
大切な家族との日常が突然奪われ、共に残った愛犬だけが話し相手だと話すアブラホフさん。心境について次のように語っていました。

「この戦争によって、私たちは当たり前だったものの大切さを学ぶことになりました。普通に暮らしていると、それがどれだけ幸せなのか分かりません。失って初めて、いかに大切なのかが分かるのです」
ウクライナの子どもたちはどうしているの?
キーウの街を取材していると、公園などで子どもたちの姿が見られるようになっていました。

子連れの人に話を聞くと、避難先からキーウに戻って来たと話す人もいました。
ただ、国外に避難している女性や子どもたちは今も数多くいて、戦闘が長期化する中で、現在夏休みで休校となっている学校をどう再開させるのかなどが課題となっています。
また、幼稚園などは、子どもたちが避難していて子どもの数が少なくなっているため、いくつかの幼稚園を統合して運営する動きもあるということでした。
支援の動きはどうなっているの?
各国から支援が行われています。キーウ近郊のボロジャンカでは、6月1日にサッカーグラウンドの敷地内に仮設住宅が完成しました。
この仮設住宅は、隣国ポーランドの支援で設置されたもので、350人が入居できるということでした。同様の仮設住宅は、ほかの地域でも建設が進められていました。
また、仮設住宅では、トルコの支援を受けて食事の提供などが行われていました。
ウクライナの人たちはロシアをどう思っているの?
話を聞いた人たちの中には、ロシア軍に対する強い処罰感情を持っている人が多い印象でした。
ロシアは軍事施設を攻撃したなどと主張していますが、一般住宅も多く破壊され、多数の市民が命を落としているからです。
ウクライナでは現在、民間施設や市民への攻撃といった「戦争犯罪」を立証するための捜査と、それを公開の法廷で裁く裁判が同時に進められています。
ロシア軍の攻撃は広い範囲で行われていて、すべてを立証するには長い時間がかかるとみられています。
ウクライナの人たちの多くは、ロシア軍の戦争犯罪の実態を明らかにした上で、裁かれることを期待していました。
取材をして心に残っていることは?
日常が突然奪われるという、理不尽な現実です。

キーウ中心部は、一見平穏を取り戻したかのようでしたが、車で30分ほど移動すると、風景は一変します。
イルピン、ブチャ、ボロジャンカなど、ロシア軍による激しい攻撃にさらされた地域では、町は破壊され、住宅などには、銃弾の跡が生々しく残っていました。
住宅の近くでは、ジャガイモが散乱していたり、破壊された子どもの遊具が残されたりしていました。

道ばたには破壊されたロシア軍の戦車も残っていて、草むらには「地雷」と赤字で書かれた看板もありました。
地雷は至る所に埋まっていて、撤去作業が進められていますが、ウクライナの非常事態庁は、国内のすべての地雷を除去するのに、少なくとも10年はかかるという見通しを明らかにしています。
ウクライナの日常は突然奪われただけでなく、今後も元どおりになるのには、非常に長い時間がかかるという現実に、理不尽さを感じました。









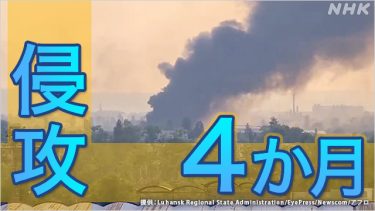




 国際ニュース
国際ニュース
