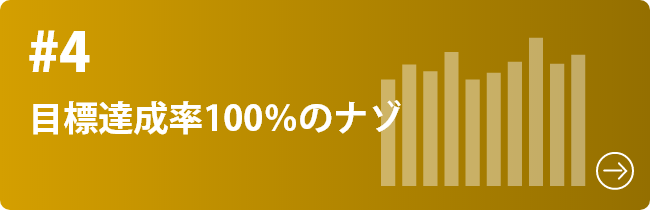![]() “コロナ予算”スペシャル記事
“コロナ予算”スペシャル記事
「トラクター」や「サル捕獲用の檻」がコロナ予算!? 検証・地方自治体
観光のための“巨大なイカ”のモニュメント。トラクターや公用車の購入。
いまコロナ予算としての優先順位に疑問符がつくお金の使い道が、特に地方自治体で相次いでいます。
国が未曾有のコロナ危機の中で地方自治体に臨時交付金として割り当てたお金は総額4兆5千億円。
感染拡大防止とポストコロナを見据えた経済対策の2つの柱で、地方自治体が地域の実情に合わせて細やかな対策を行うことになっていました。
しかし、取材してみると「予算を使い切るために、新たな事業を考えるのは難しかった」という驚きの声が。いったい何が起きているのでしょうか。
(NHKスペシャル「検証 コロナ予算 77兆円・取材班」/中川直樹ディレクター)
人口8千人の町にコロナ予算“5億円”
総額77兆円にのぼるコロナ予算。取材班が行ったレビューシートの解析で、最も大きなウェイトを占めていたのが4兆5千億円にのぼる「地方創生臨時交付金」です。
感染対策や経済対策として全国全ての自治体に割り当てられました。その1つ、人口8000人の、三重県御浜町。
交付金の額は5億1千万円、自治体の財政規模は51億円で、その10%にあたります。町にとっては“巨額”なこの交付金、いったい何に使ったのでしょうか?
交付金360万円で購入したのが、町営グラウンドの整備用トラクター。
一見、新型コロナとの関連性が乏しく感じます。町に取材することにしました。
企画課の鈴木嘉将主幹は「ポストコロナを見据えた経済対策だ」と言います。
このグラウンドではコロナ前、頻繁に野球大会が開催されていましたが、整備に使っていたのは芝刈り機。
時間がかかる上、平らにならすことができなかったと言います。
専用のトラクターで行き届いた整備ができれば今後利用者の増加も見込むことができ、コロナ後に町の経済の活性化につながると考えました。
このほかにも、町では交付金370万を使って農産物直売所に「シャッター」を取り付ける工事を行いました。
これまで“店舗外”だったスペースがシャッターを付けることで“店舗内”となり、売り場のスペースが広がりました。
ポストコロナを見すえ、観光拠点としての魅力アップにつながると考えました。

前代未聞“巨額のコロナ予算” 苦悩する地方自治体
一見、緊急性やコロナとの関連性に乏しいように見えるトラクターやシャッター。
なぜそうしたモノに予算が使われているのでしょうか。
勿論、町は、国が求める新型コロナの感染拡大防止に優先的に予算を割いています。
医療用マスクの購入や、町内の事業者への支援金などに使いました。
しかし、昨年度、町内の感染者の数はわずか2人でした。
こうした基本的な対策に予算を使うといっても限りがありました。
そこで町が力を入れたのが、国の指針にも示されていたもう一つの「ポストコロナ対策」でした。
しかし、人口8千万人の町にとって、国から交付される予算はかなりの規模の額です。
各課から交付金を活用できる事業案を募集していたものの、予算を埋めるだけの新たな事業は出てきませんでした。
事業計画の策定・実行をおこなう人員が不足していたという現実もありました。
そうした中で町がたどりついたのが、将来的に検討していた事業の前倒し。
トラクターの購入やシャッターの建設だったのです。
鈴木主幹は「交付金を使い切る観点で、だが無駄使いはしないように事業を考えた」と言います。
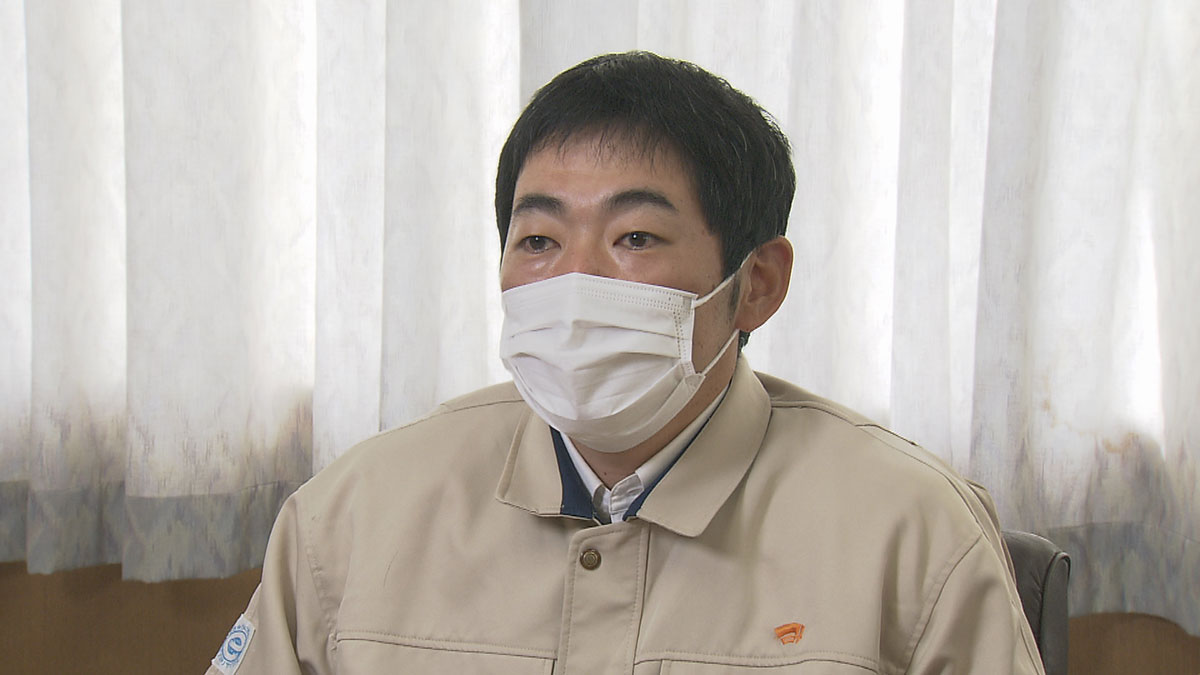
目の前の“危機”に届かないコロナ予算
町民の中にはコロナ予算の使い道に疑問を感じている人もいます。
郷土料理の製造販売を営む石本文夫さん、あや子さん夫婦です。
石本さん夫婦が手がけるのは「さんまのなれ寿司」。
新型コロナの影響で町を訪れる人が減り、売上が4割落ち込んだ月もあったと言います。
赤字を補うため新たに寿司の詰め合わせの販売を始めましたが、午前2時半に起床し家族総出で対応しても収支はギリギリだといいます。
石本さんは「町には〝コロナ後〟のこと先ではなく、まず目の前の窮状を見てほしい」といいます。

4兆5千億円の臨時交付金の額を市町村別に見てみると、大都市でかつコロナの感染者も多かった自治体が上位に並びます。
しかし財政規模に占める交付額の割合で見てみると、大都市は2%程度なのに対し、人口1万人に満たず、感染者も少ない自治体が、財政規模の10%以上の交付金になっていました。果たして効果的な政策だったのか。
今後検証が求められます。
記事一覧