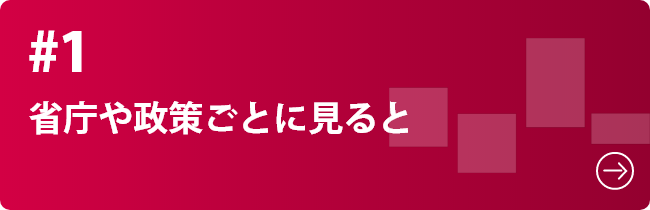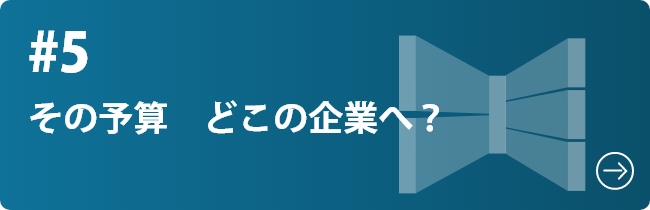![]() “コロナ予算”スペシャル記事
“コロナ予算”スペシャル記事
中小企業・巨額支援26兆円のゆくえ
コロナ予算77兆円の中で、最もお金を費やした政策分野は何だと思いますか?
答えは「中小企業支援」。
総額26兆円に上ります。
日本の99%を占める中小企業。
相次ぐ緊急事態宣言や休業要請、新型コロナによって、飲食業や観光業などは影響を受け続けてきました。
経営者たちから漏れ聞こえてくるのは切実な声と厳しい現実です。
一方で、中小企業に対する巨額な支援については、専門家の間で「今回はやむを得ない」という意見と、「“ゾンビ企業”を温存することになる」と意見とで大きく分かれています。
はたしてどのような支援が適切なのでしょうか。
(NHKスペシャル「検証 コロナ予算 77兆円・取材班」/阪野一真ディレクター)
“徹底的に支える”26兆円の効果は

新型コロナの発生以降、国は、中小企業に向け“徹底的に支える施策”を講じ続けてきました。
事業の数や予算規模はどのくらいなのか。
私たちは行政事業レビューシートに書かれている「主要経費」に注目。
その中で「中小企業対策」に分類されていたのは、持続化給付金や無利子無担保の融資など52事業で、予算規模はおよそ26兆円にのぼっていました。
この巨額支援の効果はどうだったのか?
2020年の倒産件数は7800件あまりと2000年以降で2番目に低い水準となりました。
中小企業政策に詳しい宮川大介准教授は、政策の効果はあったと評価します。

一橋大学 宮川准教授
「融資によって無借金の会社がドンと減り、それなりに借り入れも増えていて、手元に現金も残していることを考えると、金融政策のところはある意味機能はしたと思う。
問題は、じゃあそれが良かったのか、悪かったのかということですが、なかなか今の状態から当時のことを後知恵で言うのは適切ではない。
当時の段階においては何が起きるか分からなかったので、そのタイミングにおいては資金をたくさん借り入れて、急場をしのぐということが恐らく合理的だったため、政策はおそらく間違ってなかったのだろうと思う」

一方で、巨額支援の結果、もともと経営が厳しくなっていたいわゆる“ゾンビ企業”をも生き残らせてしまったのではないか、と指摘する専門家もいます。
財政審の委員を務める、佐藤主光教授です。
一橋大学 佐藤教授
「なかなか成長やこの先行きも見通せない企業がそのままズルズルと事業を続け、まさに借金を重ねていくという状況になりかねないのかなというふうには思う。
この辺りもう少し、中小企業政策全体の政策体系を変えていかないといけない局面にきているのではないか。
少なくとも経済政策と社会政策は分けたほうがいいと私は思っている。
これからなかなか伸びない企業もあるわけで、でも雇用は守らないといけない、でもそれは社会政策でするべき。
成長の見込みのある企業へのケアについては経済政策としてやるべきことなのだと思う。
どうも中小企業政策は、入り口は経済政策の顔をしているわりには、出口はみんなまんべんなく保護してあげるような社会政策になってしまっていると感じる」
ポストコロナ 支援の対象は“意欲示す企業”のみ
そうした状況の中、国は、ポストコロナを見すえ、中小企業支援のあり方を大きく転換しました。
ことし3月に始まった「中小企業等事業再構築促進事業」です。
第3次補正予算で採択された事業です。
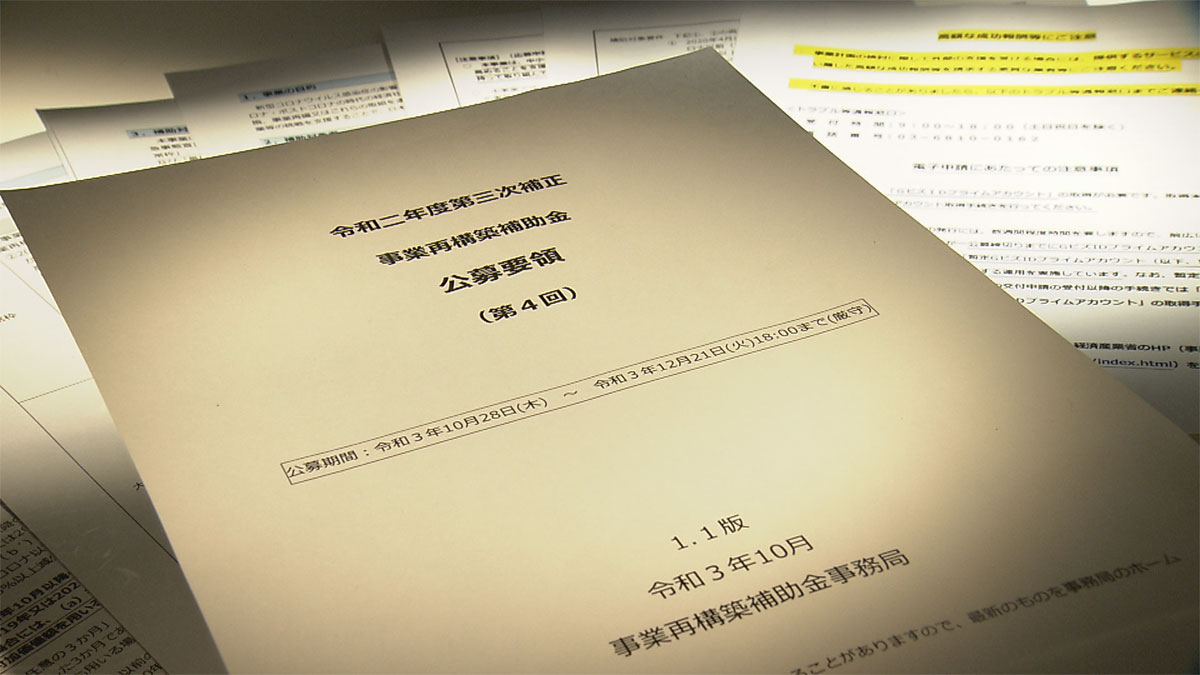
これまでの「すべて企業」を対象にしていた支援ですが、「一歩前に進もうとする一部の企業」だけを後押しする形に“線引き”されることになりました。
予算規模はおよそ1.1兆円。
新事業や業態転換など再構築の意欲を示す一部の企業に、最大1億円の補助が支払われます。
事業再構築補助金は、これまで3回の応募があり2万者(註:中小企業庁の表記による)を超える企業が採択されました。
採択率は、およそ4割。
不採択になった当事者からは、何が「再構築」に該当するのか、線引きの仕方があいまいなのではないかといった声が国に寄せられています。
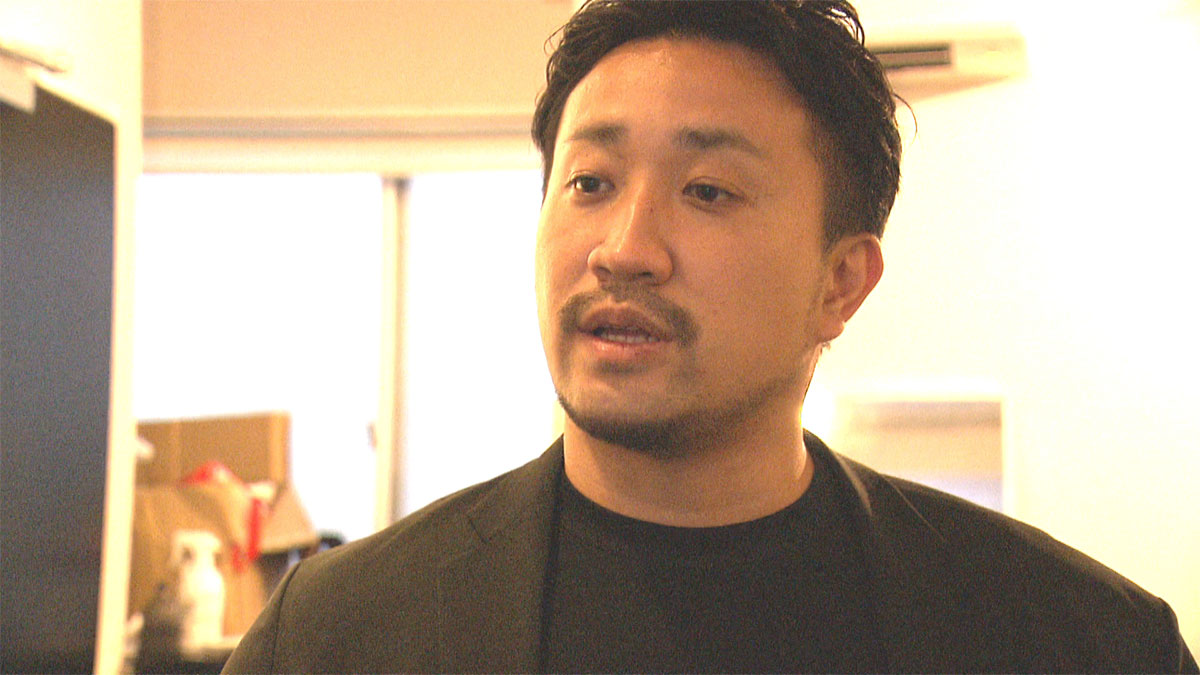
都内でパーソナルジムを運営する氏家清志さんです。
コロナの拡大によってジムの退会などが相次ぎ収入は半分ほどになってしまいました。
氏家さん
「月に150万円~200万円ほどいっていた売り上げが、休業によって1回0円になった。
その後は退会など影響もあり、いまは半分から100万円ほどになっている」
氏家さんは、事業再構築補助金を活用して、ジムの会員のみが利用できるバーの運営、さらにデリバリーの経営にもチャレンジしようと考え補助金を申請しました。
しかし、結果は不採択に。

補助金を申請した人は、制度上不採択の理由を開示してもらうことができるため、氏家さんは確認することにしました。
理由として示されていたものの1つに、氏家さんは驚いたと言います。
「大胆な業態転換であるが、既存事業の顧客をそのままターゲットとするため多大なリスクはない」
氏家さん
「“多大なリスクはありますよ”と思う。
設備投資をするだけでも多大なリスクなのに、既存顧客をそのままターゲットにするからリスクはないというのはおかしいなと思う。
本当に、リスクしかないと思う」
氏家さんはなんとか現状を打開しようと、軽貨物のドライバーを雇用する仕事を新たに始めました。
自己資金を投じて、新たな収入の柱をなんとか確保しようとしています。
「ワーケーション」に「グランピング」 新たなトレンドは
一方、事業再構築補助金の対象となった企業は、どういった点を「再構築の意欲」として評価されたのでしょうか?
千葉で44年続く、旅館・滝見苑です。
社長の富澤真実さんは、長引くコロナの中で新たな収入の柱をつかもうと、新事業へのチャレンジを決断しました。

計画は、30年以上前に建設され、いまは全く使われていないバーベキュー場を解体し、そこに新たにテレワークなど仕事として活用できるスペースを作るというものです。
富澤さんはこれを機にワーケーション事業に参入しようと考えたのです。
補助金の額はおよそ1200万円。
古い建物の取り壊しや設備投資に充てたいと考えています。
千葉県有数の観光地「粟又の滝」を眺めながら仕事が出来る、というのを売りに新たなニーズをつかみたいと考えています。

富澤さん
「旅館は観光のお客さまがメインですが、ビジネスとしても使ってもらいたい。
そうすることで、お客さまの層や受け入れる幅が広がることを期待しています」
私たちは、事業再構築補助金に採択された企業の新たな事業内容を解析することにしました。
飲食業関連だと「テイクアウト」。
宿泊業関連では、「ワーケーション」「テレワーク」や「グランピング(テントやキャンプ道具などを用意しなくても気軽に楽しむことができ、ところによってホテル並みの快適なサービスも受けられる新しいキャンプスタイル)」に集中していました。
特にワーケーションやテレワーク、グランピングにチャレンジしようとする企業の数は、830者に上りました。
国はこの補助金に応募するにあたって、事業者には達成すべき成果目標を課しています。
「事業終了後3~5年で、付加価値額の年率平均3%以上増加を達成すること」
(※付加価値額=営業利益+人件費+減価償却費)
営業利益だけでなく、雇用を増やし、設備投資を行うなど、総合的に成長する企業を育てようとしているのです。
目標達成や今後の効果検証について、中小企業庁に見解を聞きました。
中小企業庁 技術・経営革新課
「成果目標の達成状況については、各企業からの「報告書」を通じて進捗状況を把握し分析する予定です。
現時点では、好事例を公表することや、共同で計画を策定した認定経営革新等支援機関が事業実施についてもサポートするよう呼びかけることなどを通じ、成果の最大化を図っていきたいと考えています。
企業の“付加価値”は上がるのか
補助金の対象となった企業には不安もあります。
国が求める成果目標を短期間で達成できるのか。
千葉の旅館・滝見苑では、新たに作るワーケーション用のスペースを5000円で貸し出す計画です。
「付加価値額」は、事業始める前のおよそ6700万円から、5年後にはおよそ2億4千万円になると試算しており、目標は達成可能と見込んでいます。
ただ、ポストコロナにおいて、どこまでワーケーションが根づくのか、先が見通せない部分があるのも確かです。
富澤さん
「コロナが落ち着いたときに、やっぱり会社で仕事をしたほうが、効率いいのか、元の日常に戻ったら前のように戻ってしまうのではないか、不安はある。
期待してやっていかないと頑張っていけないので、不安はあるが、期待のほうが大きい。
今よりは絶対良くなるということを期待している」
この事業で掲げた目標を、本当に企業は達成できるのか。
効果が見えるのは、長くても5年かかります。
ポストコロナを生き抜こうとする中小企業が、今後どうなっていくのか。
この事業に投じたお金がきちんと効果を生み、“生きたお金”となるのか、今後も検証していきたいと思います。
記事一覧