
目指せ!時事問題マスター
1からわかる!「同一労働同一賃金」(3)知っておこう「キャリア権」
2020年04月09日
(聞き手:伊藤七海 鈴木マクシミリアン貴大 )
働き方改革の一環で4月から大企業で始まった「同一労働同一賃金」。文字通りだと、同じ労働には同じ賃金を支払うということ?当たり前のような気がするけど、どういうことなの?何が変わるの?私たちにも関係あるの?ギモンを1から聞きました。
 「何でも屋」では戦えない!? 「自分のキャリア」って?
「何でも屋」では戦えない!? 「自分のキャリア」って?
ここからもうひとつ上の本質論にいくけど、同一労働同一賃金というとすぐ「なぜ同一賃金じゃないんだ!」という話になるよね。

竹田
解説委員
でも本当に考えてほしいのは「なぜ同一労働ではないのか」。

「なぜ日本において同一労働は成り立たないのか」ということなんだよね。


竹田忠解説委員は経済、雇用、社会保障が専門。経済部記者時代には通産省(当時)や大手商社を担当。日本だけでなく、世界10か国以上の雇用現場を取材した経験も。

学生
伊藤
なぜ同一労働ではないか…。
仕事が決まっていない日本の正社員。会社の意向による配置転換に応じて、はい総務です、はい営業です、はい企画です…

こういう風に会社の都合に合わせることが求められる「何でも屋」で、これからもうまくいくのか?という状況が出てきた。


学生
鈴木
やっていけないということですか…。
AIやIT技術の進化で、われわれの仕事のうち定型的な業務は、どんどん自動化されたり、置き換えられたりするかもしれない。

そうすると、1を10にするという大量生産や効率化の延長とは違う、0から1をつくる、新しい柔軟な発想や個性が必要になってくる。

そういう中で本当に必要になってくるのは「キャリア」。みんながもっと「自分のキャリアを大事にする」こと。


キャリア…ですか。
今に、健康な人は70歳まで働く時代がやってくる。ひとつの会社で定年退職まで勤めあげるイメージを持っているかもしれないけど、70歳まで働くとなると、途中で転職するのが普通になるかもしれない。

たとえば40歳とか50歳で転職しようとした時に、「何でも屋」でどこまで通用するだろうか。いい条件で転職できるかな?

「何でもできます」ということは裏を返せば「とりたてて得意なものはない」ということかもしれない。そうすると買いたたかれるよね?


そのためにも専門性というか得意分野を何か…。
そう。若い人たちにはね、これから会社に入った時のために、ぜひ「キャリア権」ということばを覚えておいてほしい。


キャリア権ですか…。
そう、キャリア権。「キャリア・オーナーシップ」とも言われます。キャリアの所有者は自分であるということ。

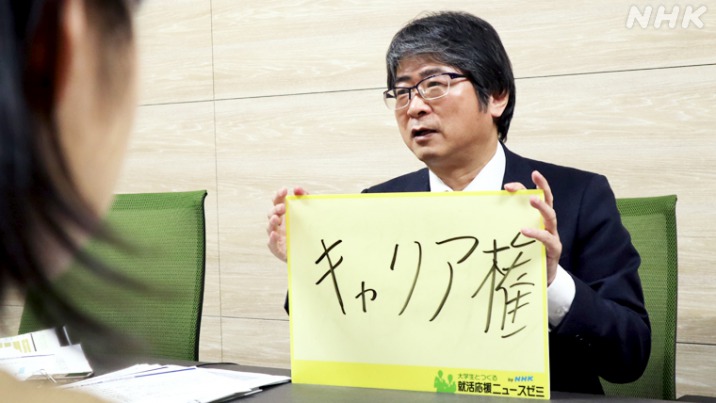
自分のキャリアは、自分で育てる。労働者にはその権利があって、会社もそれを支援すべきだという考え方。

まだ権利として確立されたものではないけど、もう20年以上前に法政大学の諏訪康雄名誉教授が提唱した日本発の法概念なんです。

「何でも屋」でうまくいく時代はそれでよかったかもしれないけど、これからは「プロ」が必要。「プロ」になるためには自分で自分の砦となるキャリアをもっと主張すべきなんだと。


それって、非正規の人はどうなるんですか?
このキャリア権という考え方は、非正規の人にとっても重要なんです。

非正規の人が、自分はこの仕事に向いているからもうちょっと上のレベルでやりたい、だから非正規にも人材教育をしてくれと言ったら、会社はちゃんとそれに見合った研修を受けさせるべきだという考え方だよね。

キャリア権を正規も非正規もちゃんと持てるようになれば、みんながワンランク上を目指して頑張れる。それって会社にとって絶対プラスだよね。



キャリア権を実現するためには具体的にはどんなことが必要になるんですか?
日本型雇用システムと欧米型の雇用システムをそれぞれひと言で言うとね、日本はメンバーシップ型の雇用だと言われる。

「この人をこの会社のメンバーに入れました」、つまり会社のメンバーであることが最大の目的なんだよね。メンバーであり続けることに価値がある。

一方、欧米はジョブ型雇用だと言われる。最初からポスト、ジョブが決まっていて、その仕事をするためにそこにいる。

だからたとえば業務の見直しで、会社がその仕事から撤退したりやめたりしたら、その人は解雇されても仕方がないということになる。


そうか、そういうことになるんですね。
そういう契約だからね。でもまあそうは言っても、急に辞めさせられたらやっぱり困るよね。

日本の場合は、こういう時でも簡単に解雇することは許されない。会社は他の仕事をあてがわないといけないんだよ。メンバーシップだから。

メンバーシップ型は雇用が安定するので、ローンを組んで家を買ったり、結婚して子どもを持ったり…労働者にとって人生設計が立てやすいというメリットもあります。

でも経団連は、日本でもこれからはジョブ型雇用を増やすべきだと主張しているんです。

今、企業がのどから手が出るほど欲しい人材ってどんな人だと思う?


のどから手が出るほど欲しい人材ですか…?何だろう?
IT人材ですよ。こういう貴重な人材は、せっかく高い給料で雇っているんだから、配置転換などせずに、専門的な仕事にずっと専念してもらわないと。



まさにジョブ型ですね。ジョブ型で就活でもスペックがある人が優先されるようになったら、私たち学生はつらいなあと…。
そうだよね。今はそう感じると思うけど、そのうちみんなが自分のキャリアやキャリア権をもっと意識するようになったらどうだろうか?

この仕事はこのスペック、この資格を持っていないとダメですと採用基準が示されたら、そのために一生懸命勉強するんじゃないかな。


確かにそうですね。

経団連はね、今、日本型雇用システムの見直しを明確に打ち出していて、新卒一括採用ではなく中途採用を増やしましょうということも言っている。

中途採用で正社員を雇おうと、企業側も少しずつ採用制度を見直し始めているんです。これが実現すればいわゆるブラック企業って少なくなると思いますよ。


なぜですか?
なぜブラック企業がなくならないのか。それは会社を辞めて他にいこうとしても転職が簡単じゃないからなんだよね。

次は正社員になれないかもしれない、だったらもう少し我慢しようとブラックでも耐えてしまうんです。

たとえ会社を辞めても、また他の会社で正社員になれる、それが当たり前になったらブラック企業で働く人はいなくなるでしょう。


日本の学生は、キャリアって会社が与えてくれるものだと思っているでしょう。まずそこから変えないと。それぞれが、それぞれのキャリアを、それぞれの責任で模索して作っていくんです。

でもね、ずっとメンバーシップ型でやってきた日本企業が、ある日突然「来年からジョブ型に変えます」と言っても教育もついてこないし、人事も対応できない。

だからメンバーシップ型かジョブ型か二者択一ではなくて、最初はメンバーシップなんだけど勤続10年、15年…管理職になるまでの間にはちゃんとジョブ型を自分で志向できるように…。そして自分のキャリアを築けるように…。

そういう「ハイブリッド型」でやっていくのがいいんじゃないかという意見もあります。メンバーシップでやってきた日本型雇用の良さも、なくすべきではないという考え方もあるのでね。


なるほど。
そうなっていくためにも若い人たちにはキャリア権についてきちんと知っておいてほしいと思います。

10年後15年後、必ず大きな差になると思いますよ。キャリア権という考え方、問題意識を持って仕事をした人と、上司に言われたとおりにやって「いい点数を稼いでおきました」という人とでは。



社会に出たことがないからわからないんですけど、そんなに意識を高く持ってやっていけるのかなと…。

今まで中学校だったら高校入学、高校だったら大学入学という風に必ずゴールがあったじゃないですか。でも社会に出たらそういう明確なゴールはなくなるわけですよね。その先のステージはそれぞれなので。
会社に入ったら、社会に出たら、理不尽なことはいくらでもあるんです。

ブラック企業だって特別な存在とは限らない。実はブラック的なことは身近にいくらでもある。自分の身は自分で守るしかない。

何を自分のキャリアの柱とするか見極める力がないと、自分で自分を不利な立場に追い込むだけですよ。


どんどん求められることが高度になっているなと感じます。学生たちにとって厳しい時代になっていくのかなと…。
厳しいと言えば確かに厳しいんだけど、滅私奉公ではない、自分で自分の人生を切り開くということがより認められやすい社会、という風にも言い換えられるよね。


まさに僕たちがそれを求められている世代だということなんですね。
そうそう。でも、きょうはよく理解してくれたんじゃない?鋭い質問もたくさんしてくれたし。


就職して社会に出る前にこのお話が聞けてよかったです。ありがとうございました。













