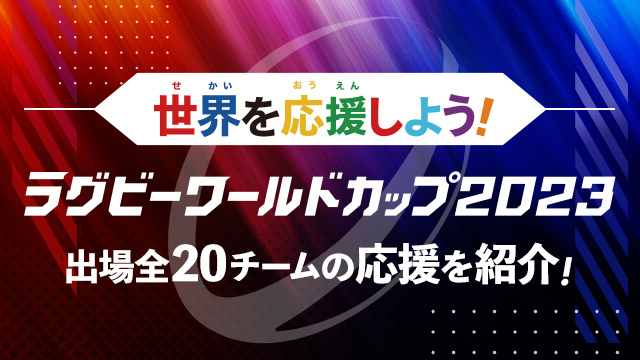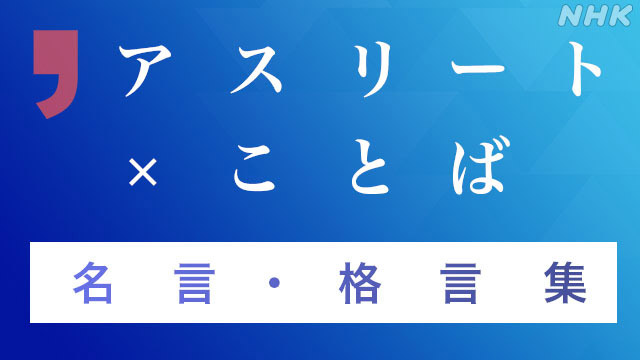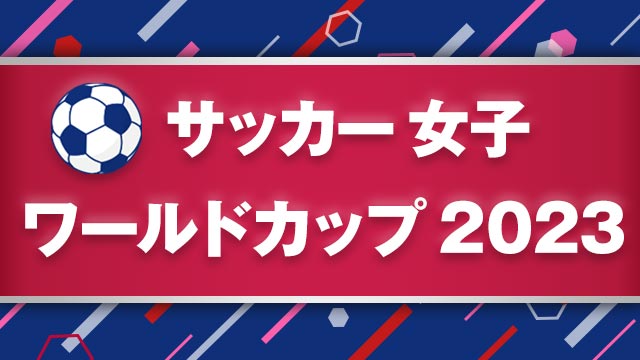エベレストの「デスゾーン」へ
ワールドカップの戦いを、標高8000メートル以上の高地「デスゾーン」に見立てて臨んだ日本。酸素濃度が低い状態では、1つの小さなミスが命取りになる。ラグビーを極限での登山に置き換え、強豪との戦いをイメージしてきた。

キャプテンの姫野和樹選手は、決勝トーナメントをかけた大一番のアルゼンチン戦を「死闘」と表現し、“笑わない男”稲垣啓太選手は「相手を殺すか、自分が死ぬかの2択だ」と覚悟を口にした。
しかし、強豪の壁は高かった。タックルミスから簡単なトライをアルゼンチンに許し、ラインアウトからの展開やハイボール処理、密集でのボール争奪戦も劣勢となった。

ラグビーの原点であるフィジカルでの勝負に敗れ、勝負どころで点を与えない試合運びでも相手が一枚うわてだった。
ジェイミー・ジョセフヘッドコーチは「選手たちはこの4年間で最高のプレーをしたと思う」と話したように、日本は力を出し切って敗れた。試合後の姫野選手のことばが印象的だった。

姫野和樹選手
「アルゼンチンが僕たちを上回ったというシンプルな話だと思います。今回、エベレストの頂上に桜を咲かすことはできませんでしたが、自分たちのレガシー、文化、目標、夢というものは、次に必ず受け継がれていくものだと思います」
今大会の敗戦の意味
今回の敗戦は、ここ数年の日本ラグビーにおいてターニングポイントとなった。成績のうえでは右肩上がりが続いていた躍進が、一度ストップしたからだ。
2015年のイングランド大会、強豪の南アフリカから歴史的勝利をあげるなど、1つの大会で3勝の大躍進を見せた日本。

2019年の日本大会は、アイルランドやスコットランドを破り、史上初のベスト8進出を果たした。

さらにことし、日本はワールドラグビーから「ハイパフォーマンスユニオン」に認定された。実力と伝統を兼ね備えた世界最上位層のカテゴリー「ティア1」を刷新した新たな枠組みに、11チーム目として加わった。
今回のワールドカップでは、その地位に見あった成績を残せるかが注目されたが、日本は1次リーグを突破できなかった。
これが日本ラグビーの現在地。まだ、名実ともにトップ層とは言えない現実を突きつけられた。

リーチ マイケル選手
「世界の壁はすごく大きいと感じました。十分戦えましたが、自分たちのほうが弱かったというのは事実です。今回の大会では強豪相手に負けてしまいましたが、たくさんの選手が世界の壁とぶつかって、この経験をどうつなげていくかだと思います」
新型コロナの影響を受けた代表強化
日本が前回以上の成績を挙げられなかった原因は何か。その1つに、新型コロナウイルスの影響で代表活動がストップしたことが挙げられる。
前回大会でベスト8に入った日本は、勢いそのままに若手の発掘など代表強化に力を入れたかった。しかし、厳しい渡航制限で十分な活動ができなかった。ワールドカップまでのテストマッチの数を前回と今回で比較すると、その差は歴然だ。
日本代表のテストマッチ数
日本大会まで 31
フランス大会まで17
ヨーロッパのチームは、日本が活動できなかった時期にも試合を行うなど、強化の面で差が出ていた。

藤井雄一郎ナショナルチームディレクター
「コロナの影響で全く活動できなかったときに、ヨーロッパ勢は試合をやっていたんですよね。ニュージーランドもちょっと早く始めていました。そういう意味ではイーブンなコンディションであったかというと、そうではなかったと思います。もちろん、その中で工夫してやってきましたが、影響は全くなかったかと言えば、そんなことはないと思います」
また、世界最高峰のリーグ、スーパーラグビーに5シーズン参戦していた日本のチーム「サンウルブズ」も2020年に解散となり、世界トップレベルの経験を積める環境は大きく減っていった。

ラグビーでは世界トップ層との対戦でしか得られないものがある。フィジカルの強さや、試合の中でのギリギリの判断がその代表例だ。
日本は、新型コロナの影響などでその部分を磨く時間が十分に得られなかった。
2027年大会に向けて 強化の方針は
今後、選手たちが国際舞台で十分な経験を積んでいくにはどうすればいいか。選手の強化を支える日本ラグビー協会はすでに動き出している。
来年6月にイングランド代表と、10月にはニュージーランド代表との対戦が決まっているほか、ニュージーランドやオーストラリア、それにイタリアのラグビー協会と相互の連携を深める覚書を結んだ。今後、定期的な対戦が行われる予定だ。

さらに、来年からは日本、アメリカ、カナダ、サモア、フィジー、トンガの6チームによる「パシフィックネーションズカップ」が開催されるほか、2026年には世界のトップ12のチームが参加する新しい国際大会が創設され、そこに日本が参加できる可能性も高い。
日本協会は、こうしたレベルの高い試合を数多く組んでいくとともに、トップチームの下のカテゴリーが戦う機会も確保して、日本全体の底上げを図っていく方針だ。

土田雅人会長
「2024年以降のスケジュールをしっかり組んでいけば、間違いなく強化を図ることができると思っている」
次期ヘッドコーチに求める一体化した強化
現在、水面下で交渉が進められている次期ヘッドコーチの人選においても、日本ラグビー全体を強化していくという方針はぶれていない。

日本協会は、ヘッドコーチの選考ポイントについて「日本をワールドカップで優勝に導いてくれる人物」という点に加えて、各年代を幅広く見て強化するという点も重視している。
土田雅人会長
「高校、大学も含めて全部見てもらいたい。一気通貫でやってくれる人を選考したい」
岩渕健輔専務理事
「選手層をいかに厚くしていけるかがポイントだ。代表チームの強化は代表チームだけで進めるのではなく、より一体化していく必要がある」
代表強化の柱となるリーグワン

直接的な代表チームの強化はもちろんのこと、日本協会が強化の柱として期待しているのが、3シーズン目を迎える国内リーグ「リーグワン」だ。国内リーグのレベルが代表チームの強化に直結することは、世界の多くの国で証明されている。
そのリーグワンに今、世界から熱い視線が注がれている。海外の有名選手たちがこぞってプレーするからだ。

このうち、ワールドカップ決勝に進出したニュージーランドからはチームの中心メンバー、アーロン・スミス選手(SH)やボーデン・バレット選手(FB/SO)、それにリッチー・モウンガ選手(SO)などが来日する。南アフリカからは、ゴールキックをチャージして大会を沸かせたチェズリン・コルビ選手(WTB)がやってくる。

世界のトップ選手たちが来ることで、リーグワンのレベルが上がることはもちろん、在籍チームの選手たちが一緒に練習することで得られるものは大きい。
海外選手からなぜ人気?
ここで少し脱線するが、そもそもなぜリーグワンは、海外の選手から人気があるのか?
リーグワンの東海林一専務理事は、生活環境のよさ、金銭面の好待遇、さらには企業・地域と一体になったチーム作りが評価されているのではないかと語る。
リーグワンの関係者によれば、年俸で億単位の額を用意して有名選手を受け入れ、チームの強化と広告塔としての役割を期待するケースもあるという。

リーグワンのレギュラーシーズンは、ディビジョン1で16試合。ラグビーという競技の特性上、プロ野球のように年間140試合以上をこなすことはできない。チケットやグッズの販売、それにスポンサーからの協賛金などには限界がある。
海外からビッグネームを呼び寄せるには、こうした収入だけで賄うことはできず、母体となる企業の支援に頼る部分は大きくなっている。
一方で、こうした母体企業と一体となって運営するスタイルは、世界から見れば「新しい形」に見えるようだ。

リーグワン 東海林一専務理事
「今、リーグワンの姿というのは、チームにプロと社員が共存しています。それから協賛という形ではありますが、母体企業というのが存在して、母体企業からさまざまなサポートを得ています。さまざまな要素が混ざり合っている状態。実はこれこそが、一番ラグビーとしては適しているんじゃないかという考え方があります」
世界のプロリーグで財政難に苦しむチームが相次ぐ中、企業をバックに潤沢な資金を用意できるリーグワンのチームは魅力的に映るようだ。
海外の指導者の中には、世界のラグビーの名だたるリーグの中で、リーグワンの価値は3本の指に入るという人もいる。

クロスボーダーマッチとアーリーエントリー
こうした中、リーグワンでは代表強化につながるさまざまな取り組みが進められている。その1つが、今シーズンから予定されている「海外クラブとのクロスボーダーマッチ」だ。
リーグワンのチームが、海外の強豪クラブと試合をする機会が作られる。日本のトップ選手に、レベルの高いプレー機会を提供するという目的で、実施に向けた調整が進んでいる。
また、昨シーズンからスタートした「アーリーエントリー制度」も若手の育成に一役買っている。大学生が卒業前にリーグワンの試合に出場することができるこの仕組み、若手選手がレベルの高いプレーを経験できるという点で貴重な場となっている。実際に昨シーズンも多くの若手がこの制度でデビューを果たした。

東海林専務理事は、代表強化におけるリーグワンの重要性を強く認識している。
「非常に大きな責任を感じています。この責任感や強いアスピレーション(=熱意)は全チームで共有しています。リーグワンは日本代表のためにあるというよりは、リーグとして魅力のある試合を展開して、ファンに楽しんでいただくのが一番のミッションです。ただ、全チームがそういうことを達成する中で、代表強化が非常に重要であるという共通認識を持っています。チーム、リーグ、協会が一枚岩になることが大切です」
行く末決めるリーグワンでの戦い
今シーズンのリーグワン開幕は12月9日。日本の選手たちにとって、貴重な力試しの場となる。
エベレストの頂上=ワールドカップの優勝を目指すのならば、世界のトップ選手としのぎを削る中で、実力をつけていかなければならない。
4年後、さらにはその先に向けて、行く末を決めるシーズンがまもなく始まる。