退職金の税金が変わる?
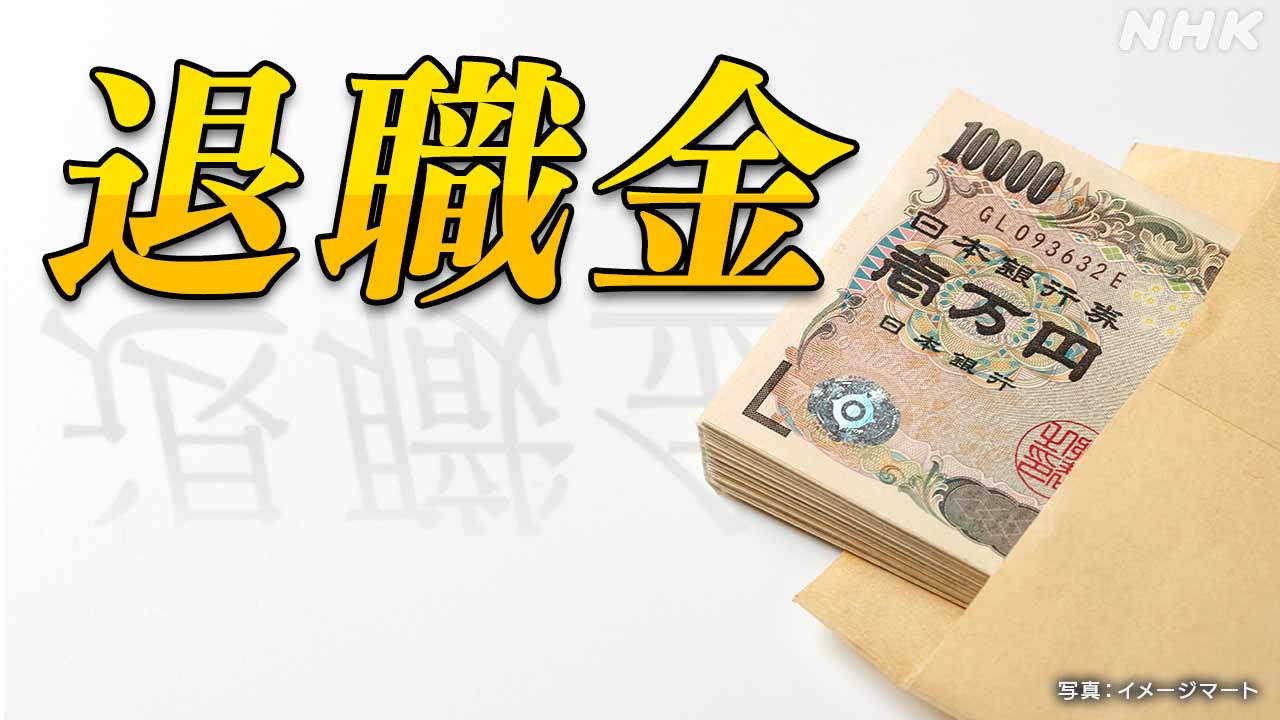
政府はことしの「骨太の方針」で、退職金にかかる所得税の見直しを盛り込みました。政府のねらいは?そもそも退職金にかかる税金の仕組みはどうなっているの?財務省の取材を担当する横山太一記者、教えて!

退職金への課税見直しが打ち出されたのはなぜ?
労働市場改革の一環です。
ことしの「骨太の方針」や、「新しい資本主義」の実行計画では、構造的な賃上げの実現に向けて成長産業への労働移動を円滑化させる必要があるとして、労働市場改革を推進する方針が盛り込まれました。
ところが、退職金にかかる税金は同じ企業で長く働けば働くほど、税負担が軽くなる仕組みになっています。
それが、転職への意欲を阻害しているという指摘が出ているんです。


長く働くと、どれくらい税負担が軽くなるの?
退職金を「年金」として分割で受け取るケースと、「一時金」として一括で受け取るケースでは税負担は違います。
一時金として受け取る場合、勤続年数がポイントとなります。
課税対象となる退職金の額を計算する際に、勤続年数が20年までは、1年あたり40万円が受け取る退職金から控除=差し引かれます。
それが、勤続年数が20年を超えた分については、控除額は1年あたり70万円に引き上げられます。
例えば、勤続年数が30年だと、仮に2000万円の退職金を受け取ったとしても、そのうち、1500万円が課税対象から控除されます。
これが、仮に勤続20年だったら控除額は800万円にとどまります。



どうして、そんな仕組みになっているの?
背景にあるのが日本の雇用形態です。
戦後の日本は、終身雇用を前提とした働き方が広がり、多くの企業や官公庁では、長く働けば働くほど、退職金の支給額が増える仕組みが定着しました。
こうした実態を踏まえて、退職金で一時的に収入が増えても、税負担が急激には増えない仕組みとなっているんです。


見直しに向けてどんな議論になりそう?
実は、税の有識者などでつくる「政府税制調査会」でも退職金への課税は長年、テーマとなってきました。
ただ、政府税制調査会の中里実会長は今月の会見で「多方面に目を配る必要があり、そう簡単に結論が出るとは思えない」として、丁寧な議論が必要だという認識を示しています。

勤続年数による差を解消するため、20年を超える分の控除額を引き下げた場合、退職金を住宅ローンの返済や老後の生活資金にあてようとしている人に対する影響は、小さくありません。
「新しい資本主義」の実行計画でも、「制度変更に伴う影響に留意しつつ税制の見直しを行う」とされています。
多くの働く人の手取り収入に関わる話だけに、慎重な議論が求められます。

# 注目のタグ
- # 新型コロナ (51件)
- # 暮らし・子育て (34件)
- # 銀行・金融 (34件)
- # 環境・脱炭素 (33件)
- # 自動車 (28件)
- # AI・IT・ネット (27件)
- # 財政・経済政策 (24件)
- # 働き方改革 (21件)
- # 給与・雇用 (21件)
- # 日銀 (19件)
- # 企業の合従連衡・業界再編 (18件)
- # 消費税率引き上げ (17件)
- # エネルギー (17件)
- # 農業・農産品 (15件)
- # 原油価格 (14件)
- # 人手不足 (14件)
- # 物価高騰 (13件)
- # 外食 (13件)
- # 旅行・インバウンド (12件)
- # 株式市場・株価 (12件)
- # 景気 (12件)
- # 経済連携・貿易 (12件)
- # ウクライナ侵攻 (11件)
- # 携帯料金 (10件)
- # コンビニ (10件)
- # お酒 (10件)
- # 携帯電話 (9件)
- # 鉄道 (9件)
- # キャッシュレス決済 (9件)
- # 為替 (9件)

