これまで障害や病気、けがなどのために、投票に行けなかったという人もいらっしゃるのではないでしょうか。
私たちが選挙で投票して代表を選ぶことは、憲法で決められた権利です。
みんなの1票を大切にするために、投票についての基本をまとめました。
投票はいつ、どこで?
選挙で投票できる期間は、選挙の種類によって違います。
例えば県の知事選挙なら、告示日(選挙をすることが公表された日)の翌日からの17日間が、投票できる期間です。(期間が長くなることもあります)
※選挙の種類によって、投票できる期間は違ってきます。
また、ことしのいろいろな選挙の予定はこのページをご覧ください。
投票できる期間の最後の日は「投票日」と言って、決まった投票所で投票します。
その場所は、世帯ごとに送られてくる「入場整理券」に書かれています。
投票時間はほとんどの場所で午前7時から午後8時までです。時間が短くなることもあるので、入場整理券をご確認ください。

整理券の例です
期日前投票って?
投票日の前に投票することを「期日前投票」といいます。
告示日の翌日から投票日の前の日までは、お住まいの地域の役所のほかに、ショッピングセンターなどで投票できるところもあります。
ある程度、期間に余裕があるため、体調にあわせて投票する日を選ぶとよいかもしれません。
また、投票所がバリアフリー化していないなどの理由で、別の投票所へ行きたいという希望もあるかと思います。投票日は決まったところでしか投票することができませんが、「期日前投票」では、役所などバリアフリー化が進んでいる場所を選んで投票することもできます。
一部の自治体では、投票日の当日、その自治体に住む人であれば利用できる「共通投票所」を設けているケースもあります。
どこで投票できるかは、お住まいの自治体のホームページなどをごらんください。
※「お住まいの市区町村の名前」と、「選挙 投票所」などで検索する、またはお住まいの自治体の役所の代表電話番号から問い合わせるなどの方法があります。
どうやって投票する?
投票所に着いてから1票を投じるまでの流れをまとめました。

まずは受け付けで「入場整理券」と引き換えに投票用紙が渡されます。
実は入場整理券がなくても投票はできますが、本人かどうかを確かめるのに時間がかかる場合があります。
続いて投票用紙を書く台に進みます。

台の上で投票用紙に、票を入れたい候補者の名前を書いて投票します。
複数の選挙が一緒に行われる場合もあります。例えば県知事選挙と県議会議員の補欠選挙が行われることもあります。
その場合は、それぞれの選挙ごとに候補者の名前を書いて投票します。
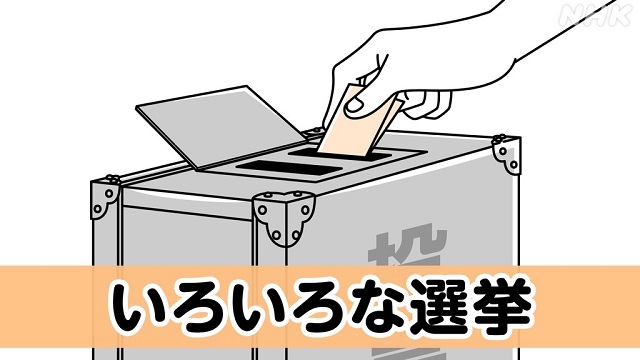
選挙の種類によって投票期間は違います
- 都道府県の場合、知事選挙は、告示日の翌日から17日間。
議会の議員選挙は告示日の翌日から9日間。 - 政令指定都市の場合、市長選挙は告示日の翌日から14日間。
議会の議員選挙は告示日の翌日から9日間。 - そのほかの市の市長選挙や市議会議員選挙は、告示日の翌日から7日間。
- 東京23区の区長や区議会議員選挙は、告示日の翌日から7日間。
- 町や村の町長や村長選挙、議会の議員選挙は、告示日の翌日から5日間。
どの選挙も、投票の基本的な流れは同じです。

「無投票」で決まることもある
投票が行われずに当選することもあります。
定員と同じ人数か、もしくは少ない人数しか立候補する人がいなかった場合、投票は行われません。そのまま当選する人が決まります。
知事選挙や市長選挙なども、立候補する人が1人しかいなかった場合は、無投票で当選が決まります。
サポートを利用しましょう
投票所に行ったり、投票用紙に書いたりするのがむずかしい人たちが投票できるようにするための、いろいろな仕組みがあります。
このサイトで詳しく説明していますので、ぜひ参考にしてください。