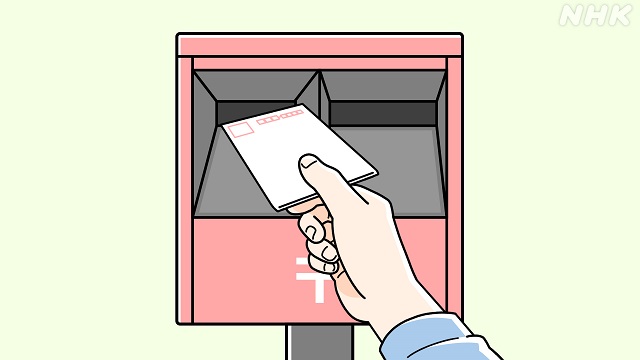
自宅にいながら投票ができる郵便投票については、「体に重い障害がある人のほかにも、郵便投票の対象を広げてほしい」と訴える声は少なくありません。
2000年に、精神的な障害があって投票所に行くのが難しい男性が起こした裁判があります。
男性は精神発達の遅れと「不安神経症」のためにひきこもりの傾向があり、外出が難しかったといいます。
外に出て他人の姿を見ると体がかたまり、動くのが難しくなるなどの症状が表れるため、投票所に出向いて投票することがきわめて難しい状態でした。
しかし郵便投票が認められるのは「体に重い障害がある人」など一部に限られているため、男性は「精神障害がある人は対象になっていないのはおかしい」と主張。選挙権を保障した憲法に違反するとして、国に損害賠償を求めました。

最高裁判所の判決(2006年7月13日)
1審・2審ともに男性の訴えは退けられましたが、2006年の最高裁判決。
国に賠償を求める訴え自体は退けたものの、今後の投票制度のあり方について次のように指摘しました。
「選挙権は民主主義を支える権利なので、精神的な障害がある人が投票しやすい制度を検討すべきだ」
国会に対応するよう促しました。
しかし今もなお郵便投票ができる人は限られており、最近でも「障害の等級(レベル)に限らず、郵便投票を認めてほしい」といった訴えが起こされています。
郵便投票の制度はもともとは障害のある人からの求めを受けて、1950年に法律が改正されて認められたものです。
しかしその翌年(1951年)の選挙で、障害のある人になりすまして郵便投票を悪用した違反が相次ぎ、なかには当選が無効になったケースもありました。
これを受けて郵便投票の制度は一時的に廃止されたものの、制度を望む声が高まったため1974年に再びスタートしたといういきさつがあります。
また新型コロナウイルスの感染が広がり、2021年からは自宅や施設にいる患者の人たちにも、一定の条件のもと郵便での投票が認められています(特例郵便投票)。
「選挙を通じてもっと社会に関わりたい」
「参政権の行使は、生きることの意義につながる、きわめて大事なこと」
障害のある人たちが訴えてきたことばです。
投票のあり方について、みんなが関心をもって考えていくことが、みんなが暮らしやすい社会につながる一歩になるかもしれません。