- トップ
- コラム ママの感じる孤独の正体は①
コラム ママの感じる孤独の正体は①

こんにちは、このサイトを担当している記者の大窪奈緒子と岡田真理紗です。
先日、ラジオ第一で放送している「Nらじ」で、野村正育キャスター、黒崎瞳キャスターと、産後ケアについて解説させて頂きました。

ラジオで話していて思ったのが、ラジオって、キャスターとリスナーの方との距離が近くていいなあと。
実は、頂いたご意見で、このようなものもありました。
ひとりじゃ絶対ムリさん
無理と承知の上での提案です。
一日中ママ向け放送のラジオ局を新たに開設してください!
「ママ☆深夜便」が大好きです。とっても安らぐ雰囲気と先輩達からの有用なメッセージが満載。これがいつもあれば、求める情報、思いもよらなかった知識を得られますし
「つらいのは私だけじゃない」と救われます。
「ママ☆深夜便」というのは、NHK「ラジオ深夜便」の特集番組で、赤ちゃんと眠れぬ夜を過ごすママやパパのために、午後11時5分から朝5時まで放送している番組。これまでに3回放送されています。
ママ向けラジオ放送局をすぐにご用意することはちょっと難しいのですが、ひとりぼっちの夜にそっとお届けする、「ラジオのようなサイト」になっていきたいなあと感じました。
そこで、頂いたご意見について、同じサイトを担当している大窪と岡田で、ラジオのように読ませて頂きながら、話した内容をコラムにする試みをしてみました。今回のテーマは「孤独」です。

岡田
では、頂いた投稿、ご紹介させて頂きます。一人目はこちらの方です。
ここすけさん(40代・香川県)
第一子の妊娠中に実母が病気になった。残業続きの夫。いい母親を演じる日々が始まった。実母が寝たきりになってしまったため、産後をどこでどう過ごしていいのか不安なままどうにか乗り切るが、産後=実家でゆっくり過ごす、過ごさなければいけないとか言われる世間の言葉が痛かった。その後他界してしまったが、自分のゆっくり帰る場所がなく辛かった。育児がしんどいというママ友もケロッと帰省していく。笑顔で送り出すけれども、頼れない、こんな育児から逃げ場がない環境が辛かった。余裕がなさすぎてあの頃の辛い思い出、寂しい気持ちしか思い出せない。今思えばもっといろいろな助けを求めてもっとらくに育児をしておけば良かったと思う。世間の情報に合っていない自分を責めず、自分は自分と楽しめば良かったと思います。
岡田
産後、お母様のご病気で、「実家に行く」ことが自分にはできなかった、世間の「当たり前」とのずれがあることが、「自分だけ頼る場所がない」という、いっそうの孤独感に繋がってしまったという体験。
私たちも、産後は実家で過ごすのが当たり前みたいなメッセージを、知らず知らずのうちに発信してしまっているのかなと思って。気をつけなければと思いました。
大窪
お母様のご病気と、その後、亡くなられたこと。頼れない、頼る場所が私にはないっていうこと。一緒に辛さを共有しながら育児していたママ友さんが実家に帰省していく姿を見ること・・・どれもすごく切なかっただろうなぁと。
岡田
「育児から逃げ場がない環境が辛かった」たしかに、実家に頼れる人の場合は、いざとなったら逃げ場があるっていう安心感があるような気がします。夫が残業続きで、しかもご実家のお母様が病気で、すごく孤独感を感じてらっしゃったと思います。
大窪
私の場合、母とは、ありのままを電話で話して、LINEで写真を送って、メッセージを送って、「大変ね」って言ってくれる、共感してくれる存在。
岡田
確かに、私も頻繁に実家には帰れないけど、よく子どもの動画や写真を母にLINEで送っています。
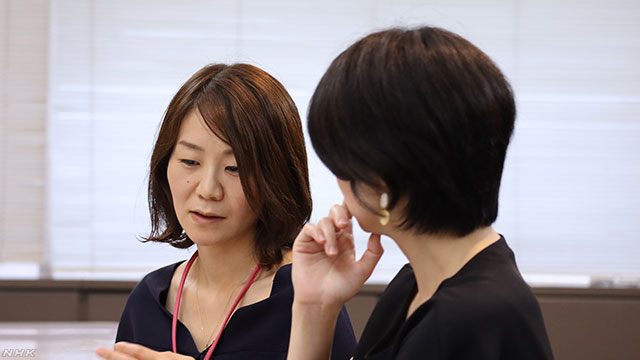
大窪
実は私も母が乳がんで闘病中なのですが、母が病気になってから、体力的に頼れないというだけじゃなくて、精神的に愚痴ったり共有できたり、同じように動画とかを見て笑ったり困ったり、育児相談に乗ってくれたりという母の存在のありがたさを再認識したんですね。ここすけさんは、きっと何重もの喪失感があったんだろうなと思って。切なくなってしまいました。
岡田
この方はお子さんの年齢は書かれていませんが、「今思えばこうしておけばよかった」と書いていらっしゃるから、もしかしたらお子さんはある程度大きいのかもしれません。
ここに書いてくださった通りで、「“世間ではこれがスタンダードだろう”というものからもしずれていても、それで自分を責めたりしないでもっと肩の力を抜いてやっていけばよかった」って。私もそうできたらいいなと思います。
今、育児で大変な時期の真っただ中にいる方は、肩の力を抜くことはなかなか難しいとは思いつつも、いろんなところに頼っていけるといいなと。
大窪
さっき岡田記者も言っていたけど、私たち取材する側も、「産後はこうするものだ」とか、決めつけるような表現になっていないかっていうのは気をつけていかないといけないなと思いました。
岡田
サポートにも、「いろんな形があるよ」ってむしろ紹介していきたいですよね。
では、次の方なんですけど「ハタママ」さん。
ハタママさん(30代・東京都)
旦那の転勤で東京に引っ越してきました。元々、独りは気にならないタイプだったのですが、知らない土地に来ていたのと、子育ては実はストレスだったんでしょうね。ある日、心のスイッチがきれました。テレビを消すように、色も音も視界からなくなった感じで、夫とも子供とも付き合えなくなりました。しんどい気持ちやなんでやらなきゃいけないの?とか、なにかするたびに浮かびました。たまたま、近所にあった親子カフェに入って、おむつをかえているときも、店員さんやお客さんとは話したくなかったです。オムツを持って帰ろうとしたら、「お預かりしますよ」と声をかけられました。たったこれだけのことなのに、涙が止まらなくて大声で泣いてしまいました。初めて会うお母さんにも話しかけられ、自分が辛いことを話して、こんなことは人生で初めてでした。私がすんでいる杉並区は子育てには熱心と聞いてます。でも、それでも、私のように家に独りでいるお母さんには支援は届いてなかったです。
岡田
ご意見頂く方、旦那さんの転勤で引っ越したというパターンの方がすごく多いですよね。
旦那さんの転勤についていくために仕事をやめたという方も多い。

これまでつちかってきた、職場や地元の人間関係がリセットされてしまって、かつ育児という大変なことを独りでする、というのは本当にストレスがたまることだと思います。
LINEとか今はありますけど、やっぱり会って話したいですよね。
大窪
うん、話したい。私もそうですが、転勤族だと、転勤するたびに、せっかくできた顔見知り、ママ友までいかなくても、連絡先は知らないけど、ちょっとスーパーで会って話すとか挨拶するとか、少しだけどこれまではあった人間関係も全部リセットされて、またその土地で一からってなりますよね。友人もいないし、知らない土地でゼロからのスタートで、って本当に大変ですよね。
岡田
この方が書いてくださったエピソードで、「親子カフェに入って、おむつを替えているときも店員さんやお客さんとは話したくなかった」ここは気持ちがわかるなと思って。すでにコミュニティーが出来上がっちゃっているところって、入りにくいですよね。
そのあと、「おむつお預かりしますよ」って言われただけで、すごく泣いちゃったっていうのもわかるなと思って。張り詰めているときにふと優しくされるとすごく泣いてしまったりします、私も。
大窪
私、これを読んで思ったのが、ほんの少しの声かけとかが、一生の宝物というか、ずっと覚えていられるものになるなって。

私の場合、横断歩道で子ども3人を連れて渡っていて、赤信号になりそうなのに、みんな言うことを聞かなくて動かなくなっちゃって、ベビーカーもひっくり返って。
あぁもうどうしようっていう時に、もう子育てを終えたであろう60代前半くらいのご夫婦が、すっとベビーカーを持ってくださって。子どもたちも一緒に誘導しながら横断歩道を一緒に渡ってくれたことがあって、「この時期って大変よね」みたいに言ってくれて、そのまま去っていかれて。
連絡先を交換したとか、全然そういうのじゃないけど、本当にその時にかけられた一言、助けてもらった一言がもう一生の宝物というか。
ことばって、一言で地獄にも落とされるし、一言で一生にもう忘れられないくらい嬉しいエピソードにもなるので。「たったこれだけのことなのに涙が止まらなくて」って書いてくださっているんですけど、「これだけ」の、その一言っていうのが、優しい一言が、もっと世の中にあふれたらいいなぁって思います。
岡田
そうですよね。自分がしてもらったら、今度は自分が誰かに対して優しい言葉をかけようっていう気持ちにもなりますしね。
今回は以上です。
2人とも共感する部分が多すぎて、思いのほか長くなってしまいました。
この続きは次の機会に紹介させてください。
もしよろしければ、引き続きコラムでご意見を紹介させていただきたいと思います。
どうぞ引き続き投稿フォームからお寄せ下さい。
お待ちしております。

