審査対象の11人が
関わった主な裁判裁判の一覧へ
2020年2月25日判決“被爆による病気で経過観察”
原爆症と認めるか

どんな
裁判か
- 広島や長崎で被爆し、病気になって経過観察とされた人たちを原爆症と認めるか
- 経過観察について、どのような場合に原爆症と認められるか初めて判断示す
- 5人の裁判官全員一致で被爆者の訴え退ける
被爆の影響で白内障などになり経過観察とされた被爆者らが国に原爆症の認定を求めた3件の裁判では、広島高裁と名古屋高裁が一部の被爆者を原爆症と認めた一方、福岡高裁は認めませんでした。
国が原爆症と認定して手当を支給するには、「現在、医療が必要な状態にある」という条件を満たす必要があり、経過観察とされた人がその条件にあてはまるかをめぐって裁判所の判断が分かれていました。
この3件の裁判について最高裁第3小法廷は「経過観察は単に治療時期の見極めのために行われているものも含まれ、経過観察が行われているだけでは医療が必要な状態とはいえない。原爆症と認定するには、経過観察じたいが病気の治療に不可欠で積極的な治療の一環だといえる特別の事情が必要だ」という初めての判断を示しました。そして、「病気の再発や悪化の程度と、結果の重大性など、医学的にみて経過観察が必要な事情を総合考慮して個別に判断すべきだ」と指摘し、3件の裁判についてはいずれも、「特別な事情があるとは言えない」とし、原爆症と認めない判決が確定しました。

原爆症認定の歴史
戦後、被爆者が必要な医療を求めた運動の高まりを受けて、1957年に「原爆医療法」が施行され、被爆者健康手帳の交付や原爆症の認定が始まりました。さらに、
1968年には「原爆特別措置法」が施行され、医療手当が支給されるようになりました。
被爆50年の節目となる1995年には、これら2つの法律が一本化され、「被爆者援護法」が施行されました。被爆者援護法は国の責任で被爆者に対して総合的な対策を実施するのが目的です。
こうした中、国に原爆症の申請をしても「放射線起因性がない」、つまり「原爆の放射線が原因とは言えない」として、認められないケースについて、原爆症の認定を求める裁判が相次ぎました。当初は多くの裁判で放射線起因性があるかないかが争点となっていました。
2000年に最高裁で長崎の被爆者の女性の訴えが認められたほか、2003年以降、全国で原爆症の認定を求める集団訴訟が起こされ、国に原爆症と認められなかった被爆者の多くが裁判によって原爆症と認められました。
司法が放射線起因性について、幅広く認める判断を示したのを受けて、国は放射線起因性を審査する基準を見直してきました。
一方で、今回の3件の裁判では、認定のもう1つの条件である「要医療性」、つまり、「現在、医療が必要な状態にあること」という条件の解釈が争点となりました。厚生労働省が示している審査の基準では、「要医療性」については「個別に判断する」という表現にとどめていて、最高裁がどういった場合に要医療性があると判断するのかが焦点となっていました。
審査対象の裁判官たちの判断は
-
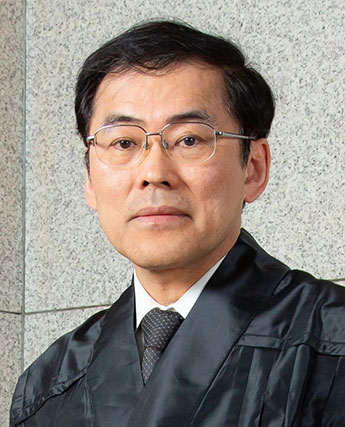
裁判長宇賀 克也
プロフィール
結論と同じ 補足意見あり
慢性甲状腺炎の経過観察であれば、症状の状況の変化などにより「特別な事情がある」と認められる可能性がある。
-

林 道晴
プロフィール
結論と同じ
関連する裁判・記事クリックで詳細記事へ

