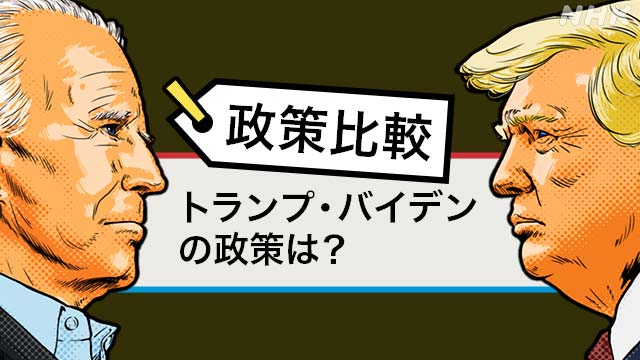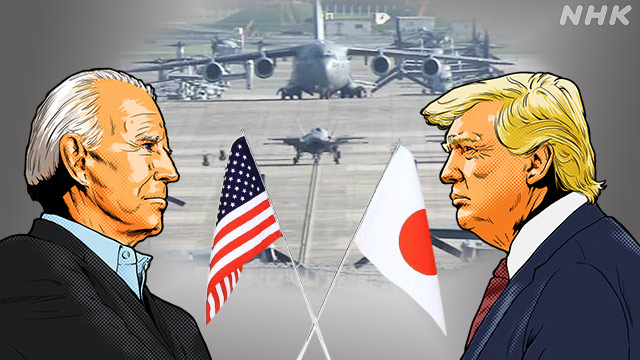共通点
アメリカ第一主義を掲げ、国際協調よりも自国の利益を優先させる共和党のトランプ大統領。
これに対し、同盟国との関係や多国間の枠組みを重視し、国際社会でのアメリカの指導力を新たな形で取り戻すと主張する民主党のバイデン前副大統領。
国際社会への関与、同盟国との関係、両者の路線は一見、異なっているようにも見える。
だが、実はいくつか共通点がある。
その1つがアメリカ史上、最も長い戦争とも言われるアフガニスタンでの軍事作戦への対応だ。
トランプ政権は終結を目指して、アフガニスタンの反政府武装勢力、タリバンとの和平交渉を進め、アメリカ軍部隊の撤退を進めた。
そしてバイデン氏もまた、およそ20年にわたる戦争を終わらせると訴える。バイデン氏が副大統領として支えたオバマ前大統領は終結を公約に掲げたが、その出口戦略に苦しみ、道半ばで任期を終えていた。それをみずからの手で実現するというのだ。
バイデン氏のもと先日、打ち出された民主党の政策綱領と、トランプ政権のこの3年間の外交政策。そのどちらにも根底にある静かな流れがあるように見える。
200年前のクインシー・アダムズ国務長官の志向を源流とする「非介入主義」である。
クインシー研究所

去年12月、首都ワシントンに新たなシンクタンクが設立された。
「クインシー研究所」。
クインシー・アダムズ国務長官の名前に由来するこの研究所が掲げるのが「外交を中心とし軍事的な関与を抑制する新たな外交政策の基盤の構築」だ。その紹介文の一行目には「アメリカが海外に行くのは破壊すべき怪物を求めるためではない」というクインシー・アダムズ国務長官のことばが記されている。
この研究所の設立は、ワシントンの専門家の高い注目を集めた。その理由が出資者だ。
アメリカを代表する投資家ジョージ・ソロス氏と大富豪チャールズ・コーク氏。この組み合わせを専門家たちは驚きを持って受け止めた。というのも、2人の政治信条は正反対といえるものだからだ。
ソロス氏は投資家の中でも民主党に多額の献金を寄せ、富裕層への増税にもみずから進んで賛意を表明するリベラル派の代表格。一方のコーク氏は減税など「小さな政府」を掲げる共和党の大口献金者として、保守勢力に多大な影響力を及ぼしてきた。
政治信条では「水と油」ともいえる2人がクインシー研究所の設立に共に賛同した理由。それがアメリカによる軍事的な関与を抑える「非介入主義」だ。
クインシー研究所の代表を務めるアンドルー・ベイスビッチ氏は設立にあたっての演説で「私たちはアメリカの外交政策を変えることを目指している。ワシントンの外交政策はあまりにも軍事力に頼りすぎてきた」と述べた。
そして、こう続けた。
「党派や政治信条に関係なく、われわれと同じ目標を持つ人たちと一緒に取り組んでいきたい」
ばく大な戦費と多くの犠牲者を出してきた戦争。その負の歴史を見つめ直し、他国に軍事介入しない「非介入主義」を実現すべきだと訴えたのだ。
左右の結束

「非介入主義」を具現化しようという動きはすでに始まっている。
去年6月。アメリカとイランの緊張関係の高まりを受けて、アメリカ議会である法案が提出された。イランへの軍事攻撃に連邦予算を使うことを禁じる国防権限法の修正案だ。
起案したのは民主党でも左派で知られるロー・カンナ議員、そしてトランプ大統領に近い共和党のマット・ゲイツ議員だ。両者はトランプ大統領の移民政策や人種をめぐる問題では全く相いれないが、この法案では完全に一致した。
カンナ議員は「イランとの戦争への反対が党派を超えたものであることの証拠だ」と強調。
ゲーツ議員も「終わりのない戦争はアメリカをより弱くし、強くはしない。イランが核兵器を入手したり、国際平和を脅かしたりするのを防ぐ必要があるが、議会は軍事行動を監視する権利がある」と応じた。
後遺症
党派を超える「非介入主義」の流れ。その根底にあるのが、長きにわたるアフガニスタンでの軍事作戦の後遺症ともいえる「戦争疲れ」だ。

右派の退役軍人の団体、「アメリカを懸念する退役軍人の会(コンサーンド・ベテランズ・フォー・アメリカ)」の上級顧問を務めるダン・カルドウェル氏は「これはアメリカで根本的な変化が生まれていることの表れだ」と話す。
2001年の同時多発テロを機に20年近く続く軍事作戦での犠牲、そして人々の暮らしへの影響。退役軍人の自殺者は今も膨大な人数に上る。
カルドウェル氏はこの流れはトランプ大統領が作り出したのではなく、その以前からアメリカ社会の底にあったと指摘する。
カルドウェル氏 「トランプ大統領はすでに生まれていた流れをうまく利用しているにすぎない。アメリカ国民は、戦争への継続的な関与が自分たちの安全につながっていないことに気付き始めたのだ」
この団体では去年、左派系の退役軍人の団体「ボート・ベッツ」と初めて共同でアメリカ議会でアフガニスタンからの軍の完全撤退を求めるロビー活動を展開した。ここでもまた政治信条の違いを乗り越えてこれ以上の軍事介入に反対する動きが起きていた。
アメリカ社会を覆う戦争疲れ、そして「非介入主義」の潮流。
11月の大統領選挙でトランプ大統領が再選されれば、この流れはさらに加速するだろう。
そしてバイデン氏が政権を奪還したとしても、またアフガニスタンからの撤退、他国への軍事的な関与を抑制する動きは大きくは変わらないのではないか。
その意味でアメリカの外交安全保障政策は今、まさに大きな転換期に入っているのかもしれない。