感染者数減少なぜ?“宣言”解除は?
2021年9月24日

新型コロナウイルスの新規感染者数を1週間平均で比較すると、緊急事態宣言が出ている地域を含めほぼすべての都道府県で減少が続き、東京都は緊急事態宣言が出される前の7月初めとほぼ同じ水準となっています。
感染者数の傾向と、専門家の分析をまとめました。
全国 46都道府県で減少 “宣言”19都道府県すべてで減少

NHKは各地の自治体で発表された感染者数を元に、1週間平均での新規感染者数の傾向について前の週と比較してまとめました。
全国では、
▽8月26日までの1週間では前の週と比べて1.13倍と9週連続で増加していましたが、
▽9月2日に0.84倍とおよそ2か月ぶりに減少に転じ、その後、
▽9月9日は0.64倍、
▽9月16日は0.55倍、
▽9月23日まででは0.50倍と、4週連続で減少しています。
1日当たりの新規感染者数はおよそ3424人で、先週のほぼ半数となり、およそ2か月ぶりに5000人を下回りました。
46の都道府県で減少し、緊急事態宣言が出されている19の都道府県すべてで減少が続いています。
東京都 緊急事態宣言発出前とほぼ同じ水準

東京都は8月中旬まで9週連続で増加していましたが、
▽9月2日は前の週の0.72倍、
▽9月9日は0.59倍、
▽9月16は0.55倍、
▽9月23日まででは0.54倍と5週連続で減少しました。
1日当たりの新規感染者数はおよそ547人と、先週より460人余り減り、緊急事態宣言が出される前の7月初めとほぼ同じ水準となっています。
直近1週間の人口10万人当たりの感染者数は27.53人と、先週の半数ほどになっています。
専門家「一人一人のリスク下げる行動とワクチン効果重なる」
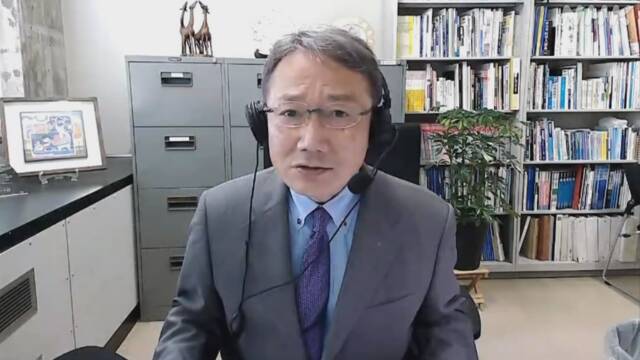
新型コロナウイルス対策にあたる政府の分科会のメンバーで、東邦大学の舘田一博教授は、感染者数が減少していることについて「これまで5回の感染の波を経験する中で、一人一人がどういう状況、環境で感染しやすいのか正しく判断できつつあり、リスクを下げる行動を取れるようになった効果も出ているのではないか。対策への努力やワクチンの効果が重なる中で感染者数の減少につながってきている。この傾向を続け、どこまでベースラインを下げられるかが大事だ」と話しています。
“宣言”解除の判断「期限までにどれだけ医療ひっ迫が取れるか」

一方、医療のひっ迫状況については「入院患者は東京でしばらくぶりに2000人を切ったが、それでも1900人以上が入院している。医療のひっ迫は軽減してきているが、まだ今の段階では注意して見ていかなければいけない状況だ。9月30日の緊急事態宣言の期限までにどれだけひっ迫が取れるかが解除の判断の上で重要になってくる」と指摘しました。
基本的な対策はしばらくとり続ける意識で行動を

今後については「緊急事態宣言が解除される地域が出ることが今のところ考えられるが、市中にはウイルスが潜んでいると考えておかないといけない。一気に緩んでしまい、1週間、2週間後にリバウンドして、感染の波を作ってしまうことをこれまで経験してきたので、基本的な対策はしばらくの間とり続ける意識で行動することが重要だ。どうしたらリバウンドを抑えて生活を戻していけるか、一つ一つ段階的に確認しながらゆっくり進めることが大事になる」と話しています。
「ブレイクスルー感染」ワクチンで重症化や死亡リスク下がる

「ブレイクスルー感染」については、「ブレイクスルー感染を起こすとは言え、ワクチンの効果が無くなっているわけではなく、重症化や死亡のリスクは確実に下がっていて、これがいちばん大事なポイントだ」と話し、特段の理由がなければなるべく接種をするのが望ましいとしました。
ワクチンだけに頼るのは高リスク 感染対策維持を

そのうえで、新型コロナ対策をワクチンだけに頼るのはリスクが高いとして、「アメリカやイギリスなどワクチン接種が先行していた国では接種率が一定の水準に達して感染対策がおろそかになってしまい、大きなクラスターが発生したと報告されている。そういった事例を見てもワクチンだけに頼るのではなく打った人も打っていない人もしばらくの間は感染対策、リスクを下げる行動を維持していくということが大事になる。ワクチンを打ったからといって何も対策をせずに動き回り、油断して食事やお酒を飲むということがないように一人ひとりが注意していかなければいけない」と指摘しました。