





















原爆で被爆した人たちの悩みや苦しみの声がつづられた「相談カルテ」。その数は今も増え続けています。カルテが保管されているのは東京都内にある被爆者の相談所です。広島や長崎で被爆し、その後上京した人などを支援するために設けられました。終戦から72年がたった今も、相談所を訪れる人は後を絶ちません。

東京・文京区にある被爆者の相談所では、東京都からの委託を受けて、被爆者健康手帳の交付や原爆症の認定といった手続きの支援などにあたっています。

戦後72年となるいまも電話やメール、訪問などによる相談が相次ぎ、その数は1日平均30件以上だということです。

相談所は被爆者の団体によって昭和37年に開設されました。現在は医療や介護の事務の知識を持つ5人がスタッフを務めています。これまでの相談やアドバイスの内容を記録した“相談カルテ”は、およそ5000人分にのぼります。

相談員の1人、村田未知子さんは35年にわたって被爆者たちの支援を続けてきました。
村田未知子さん:
「被爆者は心と体と両方傷つけられている。よく『体の中に原爆抱えてる』という言い方をしますけど、いつ出てくるか分からないという恐怖があって『ついに原爆が出てきたか』とおっしゃる方もいます」

カルテからは相談に訪れた原爆の被害者の苦しみが浮かび上がってきます。被爆者への偏見が、家族の仲を裂いたケースのカルテには、「長男の嫁は一緒にいると自分たちまで被爆したと見られるからと言って一家をあげて遠くに行っている」と記されていました。

「娘より電話あり。『父は自殺しました』とのこと」と書かれたカルテ。被爆の後遺症に悩んで自殺を選んだ相談者もいます。

広島の原爆で両親と妹を亡くした男性のカルテには、その後の壮絶な人生が記録されていました。妹は、半身にやけどによるケロイドができ、白血病も発症。アメリカのABCC・原爆傷害調査委員会に研究のために引き渡され、まもなく亡くなりました。「どうせ死ぬのだからいいだろう」と言って妹を連れて行ったという主治医をこの男性はナイフで刺し、少年院に送られました。

上京後に体調を崩した男性は生活保護を受け、70代後半になったいまも社会から孤立したまま、ひとりアパートでの生活を続けているといいます。
村田さんは「いまだに心を開ける人がいないんじゃないでしょうか。私と話しているときもいつも壁があります。自分を守らないといけないという思いをずっと持って生きてこられた方だと思います」と話しています。

相談者の中には被爆者であると明かせず、長年葛藤を抱き続けてきたという人もいます。原爆症認定の申請のために初めて相談所を訪れた中村彰吾さんは3歳の時に長崎で被爆し、姉2人を亡くしました。その後、大学進学のために上京しましたが、偏見を恐れ、被爆したことを周囲に明かさず、当初は妻にも言えずにいたといいます。ようやく妻に伝えたのは、結婚後しばらくして妊娠したときだったということです。14年前に前立腺がんの手術を受ましたが、このときもあえて原爆症の認定を避けました。しかし75歳と高齢になり健康に不安を覚えたことや知人の被爆者から強く勧められたこともあって、認定を申請することにしました。

被爆者としての悩みを誰かに打ち明けたいとも考えるようになりました。その悩みのひとつが同居を続ける一人娘のことです。自分が被爆者であることが娘の人生にも影を落としたのではないかと心配してきました。娘はこれまで何度かあった縁談をみずから断ってきたといいます。中村さんは娘が被爆2世であることを気にしているのではないかと思いつつも、確かめることができずにいます。
中村彰吾さん:
「聞けないですね。そうだって言われたときに何て答えていいのか。彼女には責任ないですからね。そこまで原爆は人の心まで傷つけるのかと今も思います」
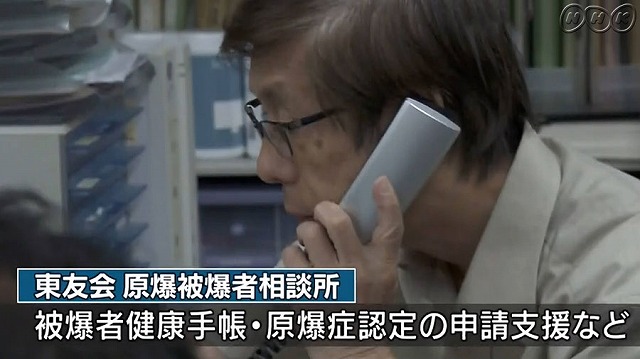
今も終わらない原爆の被害者の苦しみ。相談所はその声に耳を傾け続けます。
村田未知子さん:
「70年以上も人に不安を残すような被害はないと思うんですよね。私たち相談員はそういう被爆者の話を聞ける立場にいますから、責任と使命があると思います」
相談員の村田さんは今、相談カルテに残された被爆者の人生を講演などで紹介する活動を始めています。活動を通じて原爆がもたらした果てしない苦しみを次の世代に伝えていくつもりです。
この記事のニュース動画はこちらをご覧ください
