





















私たち大学生には遠いできごとに感じてしまう80年前の戦争を、当時の人たちの日記や手記から追体験していこうという、そんな番組を見る機会があった。
「追体験」ってどんな手法?
制作者は一体どんな思いで制作しているのだろう?

わたしたちが視聴した「NHKスペシャル」は、8月12日に放送された「新・ドキュメント太平洋戦争1943 国家総力戦の真実 前編」
5年がかりのプロジェクトで、太平洋戦争の時代を1年ごとに“追体験”するという番組だ。
手がかりとなるのは当時を生きた人々の日記や手記で、「エゴドキュメント」といわれ、今、研究者の間で注目されている。
先の大戦を巡っては、政府や軍の意思決定のプロセスなどについては、さまざまな史料から研究が進んできたが、銃後の市民や戦場に駆り出された兵士たちの「本音」や、彼ら彼女らが感じていた時代の「空気」といった部分は専門家の間でも検証が進んでこなかった。
戦争体験者の多くが鬼籍に入るなかで、エゴドキュメントを活用することで、たとえば現代におけるSNS上の発信を分析するかのように、個の視点から3年8か月に及んだ太平洋戦争を“追体験”することが目的だ。
番組の取材班は2年前に立ち上がり、全国各地から個人の日記や手記を収集。これまでに集めたエゴドキュメントは1190人分にのぼる。兵士や、軍や国の指導者、戦場には行かなかった一般市民や子供のものもあるという。
3年目となる今回の番組で描かれたのは1943年。
当時の日記から、徴兵されていない一般市民も「徴用」というかたちで軍需工場に動員されるなど、生産力の多くが戦争に振り向けられていく様子が浮かび上がった。

人々は食糧の確保に苦労しあくせくしながらも、そこにはまだ日常生活があったが、しだいに戦況の悪化が市民にも伝わってくる。
真珠湾攻撃を成功させ国民に人気のあった聯合艦隊司令長官 山本五十六が戦死。北太平洋のアッツ島で部隊のほぼ全員にあたる約2600人が戦死した。
死が身近になっていくなかで、「あとに続け」という国の宣伝に呼応する形で、市民は戦争協力を強め、14歳の若者までもが軍へと志願することになる。

私は世界史が好きだ。でもかつての戦争については、実際に体験したわけでもなく、戦争の時代を実際に生き抜いた方は減っている。それは教科書や本を見て知った「歴史上の出来事」でしかない。一体何が起こっていたのか?知りたいと思っていた。
今回の番組は「エゴドキュメント」と呼ばれる、当時を生きた人々の「日記」など、公開される前提でない、極めて個人的な文章から、戦争の時代を追体験することを試みていて、とても興味深かった。
この日見た「前編」で描かれていたのは1943年の前半、ブーゲンビルでの山本五十六連合艦隊司令長官の死と、アッツ島守備隊の玉砕までだ。この頃までは日本とアメリカの消耗戦がつづいており、エゴドキュメントからは、少しずつ生活が厳しくなり苦悩したり憂慮したりする気持ちが伺えるものの、多くの人々は「戦争」という究極の非日常の中で仕事や家事、子育てといった日常生活を必死に送っていたという「当たり前の光景」が目に浮かんできた。
番組のサブタイトルは「国家総力戦の真実」。日記では、物資供給の停滞などによる工場の生産力の限界に不満を綴りながらも、山本長官の死やアッツ島の玉砕にはショックを受け、より一層の奮励努力を誓ってしまう。この一連の変化に末恐ろしいものを感じた。
記録映像にはない、個人の日記に綴られる日常をどう描き、「追体験」させるのか。表現手法においては、現在も使われている工場や田園風景、趣のある民家などでイメージ映像をつくり、その上にエゴドキュメントの画像を映すなど、制作陣の苦心、工夫がちりばめられていた。
特にブーゲンビルで飛行場の設営に従事した軍属の方の日々を追体験する場面では、戦争体験者が残した絵を巧みなカメラワークで撮影し、そこに効果音やナレーションを付け加えることで豊かに表現していた。チープな再現ドラマにするのではなく、視聴者の想像力を掻き立てるような作りにひきこまれた。
ウクライナの人々が戦争下でも街に出て買い物する様子が報じられるように、戦争が始まったという大きな一点のみで人々の日常が一変するわけではない。気付かないうちに少しずつ、少しずつ、苦境に向かい、変化に気付いたときには誰もが引き返せないところにたどり着いている。そのことを今回の番組で学んだ。
日記に表出されるような個人の内面、いわば誰にも語られることのない歴史こそ、私を含めた戦争を知らない世代は知るべきだと強く思う。
十人十色で、学校の授業や歴史書で教えられることのない「本当の歴史」を伝える中で、当時の人々が戦争や国家をどう思っていたのか知ることこそが、現代において価値があると思った。

8月、メディアでは毎年戦争に関連する特集番組が放送される。私は「終戦から78年の月日が経っている今日、歴史的事実についての情報はある程度出尽くしてしまっているのではないか」と感じていた。「戦争を伝えること」は、これからどのようにアップデートされていくのだろうか。そのようなことを考えながら今回の番組を見た。
今回、大きな軸に据えられた日記。「戦争の伝え方」として手紙や遺族による証言は今もなお貴重で大切なものだが、その時代を生きたひとりひとりの視点として、「日記」にも強い力があることを感じた。
伝えることを本来の目的としていないが、その時の書き手の世情の受け取り方や心情が如実に伝わってくる。ある日、母が幼い娘に配給のキャラメルを渡すと、一緒にいた友人らにも分けてしまいあっという間になくなってしまう。母の視界を想起させる映像と併せて読み上げられた世界は、2023年でも起こり得る日常だった。
日記を通して様々な人の日常や心情が淡々と提示されていく中、「一体この番組はどこに向かって進んでいくのだろうか」と感じる瞬間もあった。しかし最後まで視聴することで、淡々と描かれた「日常の積み重ね」の意味を理解した。
そして同時に少し怖くなってしまった。
市井の人々が「深刻な状況に置かれている今だからこそ私または私たちも頑張らないといけない、戦い抜くしかない」という心理状態へ陥るまでの移ろいが自然と腑に落ちたからだ。
ぼんやりとした不安はありながらも生活は続いていたという中で、アッツ島守備隊の玉砕や心の拠り所のひとつとも言えた山本五十六の死などが伝えられる。現状を受け止めきれず、各々が不安や戸惑いを抱えながらも、いよいよ真剣にならなければならないということだけが共通して内心に芽生えたのだろう。
子育てをする母、作家、徴用で働く人など社会における多様な立場の視点から俯瞰的に1943年を見つめてきたことで、その年を生きた銃後の人々全体の空気が浮かび上がってきた。
どうしたら根本的に解決されるのか分からないけれど、事態は深刻で、とにかく自分にできることをしなければ。そんな行き場のない焦りのようなものが、2023年を生きる私へ届いた。
長い年月がたち、情報が出尽くしたように見えても毎年繰り返される戦争の特集番組。しかし「なぜ戦争は起き、どのような戦いが繰り広げられ、何が問題だったのか」といった情報はやはり必要不可欠で、「繰り返してはならない」と世代を超えて警鐘を鳴らし続けなければならない。
当時、社会におけるひとりひとりがどのようなことを感じ、思索していたのか。特定の立場や人物に焦点を当て、その視点を増やしていくことで、私たちは戦争への理解を深めていけるのではないだろうかと感じた。
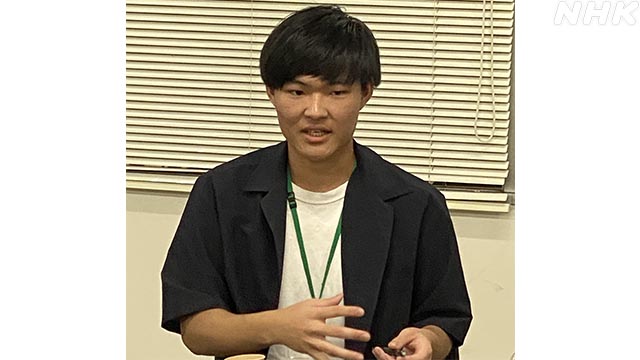
私は高校1年のときに熱中症で祖父を亡くした。祖父には適切な情報が伝わっていなかったのだろうか?以来私は「命を守る報道」に関心を持ち、毎日のようにネットやテレビのニュースをくまなく見る毎日を送ってきた。
そんな中、ロシアによるウクライナ侵攻に衝撃を受けた。戦争を身近に感じ、自分事として考えなければと思うようになったのだが、私は自分が生まれた国で起きた戦争について、教科書以外で触れることが少なかった。今生活できているのは、70年以上前の戦争を生き抜いてきた人がいるからだ。だからその人たちがどんな気持ちで当時を生きたのか、知りたいと思った。
映像でも、写真でもない「日記」。当時の戦況の中で、何か後世に残したいという思いがあったのだろうか?私もSNSで日常の出来事を残そうとしているが、それと似たような感覚だったのだろうか?その真意を理解することはできなかったが、戦時下の人々が残した日記は、当時の人々の感情やその感情に至った経緯を「能動的に」考えるきっかけを私に与えてくれた。
番組を通じて私が感じたのは「戦争はすぐに深刻に感じるものではない」ということだった。じわじわと軍から国民へと派生していく怖さ。アッツ島の玉砕の後に行われた当時の合同慰霊祭で、それまで人ごとだと思っていたことが、いきなり現実味を帯び、やがては自分もその戦没者のひとりになるかもしれない恐怖と向き合うことになる、その心の変遷を知ることになった。
また番組を見た後のディスカッションで印象に残ったのは、制作者の取材に対する姿勢についてだった。戦争を体験した人々の中には、その悲惨さが故に、取材に応じる人々ばかりではないのではと私は考えていた。
私はディレクターの2人に率直に聞いてみた。2人の答えに共通していたことは、「なぜこの取材をしたのか、なぜこの取材をしなければならないか」という取材する意義、つまり、その取材によって「誰が」「何を得ることができるのか」を自身の中で明確にし、相手に伝えることが大事だということだった。情報をしっかりと伝えなければいけないという制作者としての使命感を感じた。
私は後世に、「戦争の痛みは、最初は感じられないかもしれない、じわじわと広がっていくのだ」という怖さを伝えていきたいと思った。他人事だと思っていたことが、いきなり現実になり、やがては自分も戦争で命を落とす一人になるかもしれない。そうした怖さがあるから、戦争を行ってはならない、ということをこれから生まれてくる人々には伝えていきたい。

私はバラエティやお笑いが好きだ。趣味といってもいい。だから正直いえば、NHKスペシャルの番組内容は重い気持ちになるので避けてしまいがちであった。だがロシアによるウクライナ侵攻もあり"戦争"に向き合う必要性を感じ、避けられないと感じるようになった。
NHKスペシャルを視聴し、どう戦争に向き合っていくべきかを避けずに見つめる、考えることができる貴重な機会だと思い、今回参加を決めた。
作家や主婦、村長など様々な銃後の人々が綴った日記からは、それぞれの戦時下の暮らし、1943年のリアルな「心の景色」が伝わってきた。
アッツ島玉砕前後の日記を比較すると、銃後の人々の"戦争"への意識が、他人ごとから自分ごとへと変化し、戦争へ疑問や不安を持たずに「戦い抜くしかない」と向き合う国民の様がひしひしと伝わってきた。
今まで目にする機会が少なかった銃後の人々の日記、エゴドキュメントを垣間見るということは、太平洋戦争の時代に自分が生きていたら、おそらく同様の立場だっただろう人々の生活を知るということであり、私の中の戦争に対するイメージはより具体的になった。
銃後の人々がささやかな日常を記録していた日記が、どんどん大きくなる戦争という存在によって、戦争への思いや覚悟を綴った日記に変わっていく様子を見て、戦争が"人間"にもたらす影響の大きさを改めて実感した。
今まで以上に「戦争を考えること」を避けてはいけないという思いが強くなった。
今後戦争の時代を生きた世代がいなくなってしまい、戦争を経験したことがない世代が伝えていく立場になっていく中、日記が主役のドキュメンタリーは、新たな伝え方を確立する試みで、大きな一歩だと感じた。
今回の番組を通して知った当事者のことばや記録から、悲惨さや失ったものの大きさを痛感し、このようなことが二度と起きてはいけないと強く思う。
私は戦争を経験した世代ではないけれど、「戦争は恐ろしかった」と過去のものとして終わらせるのではなく、戦争の状況を後世に伝えようとしてなのか、日記に残した方々や、先祖の残した思いをずっと伝えてきた方々の思いを背負って、戦争はもう二度と繰り返されてはいけないということを次の世代に伝えていきたい。

8月12日の試聴会の様子
