





















ロシアによるウクライナ侵攻をきっかけに、77年前のシベリア抑留体験を詩につづり始めた人がいます。
過酷な体験を後世に伝えていこうと、95歳にして初めて詩作に取り組む男性。しかし、どうしても踏み込めない、表現できないものがありました。
ロシアによるウクライナへの軍事侵攻開始から3か月余りがたった6月6日。
栃木県の地元新聞社の紙面に1編の詩が掲載されました。
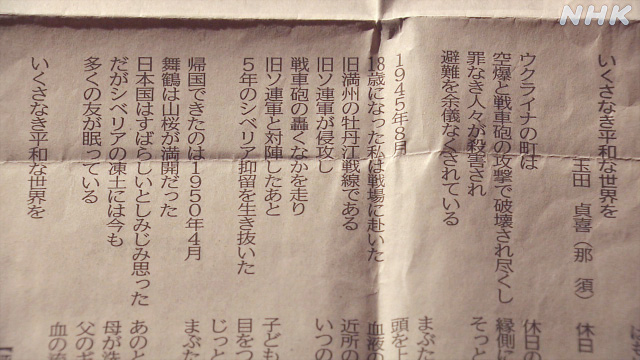
下野新聞 2022年6月6日付
いくさなき平和な世界を
玉田 貞喜
ウクライナの町は
空爆と戦車砲の攻撃で破壊され尽くし
罪なき人々が殺害され
避難を余儀なくされている
1945年8月
18歳になった私は戦場に赴いた
旧満州の牡丹江戦線である
旧ソ連軍が侵攻し
戦車砲の轟くなかを走り
旧ソ連軍と対陣したあと
5年のシベリア抑留を生き抜いた
帰国できたのは1950年4月
舞鶴は山桜が満開だった
日本国はすばらしいとしみじみ思った
だがシベリアの凍土には今も
多くの友が眠っている
いくさなき平和な世界を
この詩を投稿した栃木県那須町に住む玉田貞喜さん(95)です。

玉田貞喜さん
昭和17年、広大な大地で牧場を経営する夢を抱き、14歳で「満蒙開拓青少年義勇軍」の一員として旧満州へ渡りましたが、戦況の悪化で開拓の夢はかないませんでした。
終戦間際の昭和20年8月には、旧ソビエト軍との戦闘の最前線となった「牡丹江の戦い」を経験。多くの仲間を失ったといいます。
玉田貞喜さん
「目の前に爆弾が落ちて、近くにいた25人が即死しました。飛び交う戦車砲と燃える建物で、牡丹江の街全体が熱くなっていました。ウクライナのがれきの街が、かつての牡丹江の街と重なるんです」
終戦直後は旧ソビエト軍によって連行され、強制収容所での生活を余儀なくされました。5年間にも渡るシベリア抑留の始まりです。
抑留中はわずかな食糧しか与えられず、貨物の運搬や原生林の伐採など、過酷な強制労働に従事しました。

旧満州にいたころの玉田さん
玉田さん
「ダワイダワイ(急げ急げ)と言って労働をさせられました。飢えと寒さと重労働とで、とても言葉にできません。同郷の仲間5人のうち、自分しか生きて帰れなかった」
他の抑留者から密告され、戦犯収容所に収容されたこともあったといいます。
玉田さんが終戦の前の年に2か月間、旧日本軍の軍人から教育を受けていたことが密告されたのです。
玉田さん
「密告することでもらえるわずか350グラムのパンが欲しくて、彼は密告をしたんです。それほど収容所の生活は過酷だった」
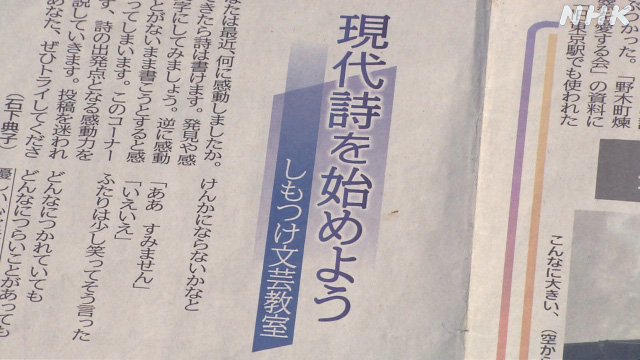
詩の投稿を呼びかける新聞のコラム
ロシアによるウクライナ侵攻で、みずからの体験が呼び起こされたという玉田さん。ことし4月、新聞の文芸欄に掲載された「現代詩を始めよう」というコラムを読み、戦争体験を詩にしてみたいと感じました。
こうして、玉田さんが初めて作った詩が「いくさなき平和な世界を」でした。反戦の思いを込めた詩は、投稿後、すぐに新聞に掲載されました。

石下典子さん
コラムで詩の投稿を呼びかけた、詩人の石下典子さんです。
地元紙の文芸欄の選者を務める石下さんは、投稿された数多くの詩の中で、玉田さんからの投稿に強くひきつけられたといいます。
石下典子さん
「95歳で初めて詩を書いたという衝撃。玉田さんの経験を思いつくかぎり詩にしてもらい後世に残してほしい。戦争体験者の生の声を聞ける最後の世代として、そうお願いするのが選者の責任だと思いました」
石下さんはすぐに、玉田さんに宛てて「詩を書き続けてほしい」と手紙を出しました。
数日後、玉田さんからの返信には、詩に込める強い思いが記されていました。
「95歳の初心者のため詩作をためらっております。でも詩を書きたいのです」
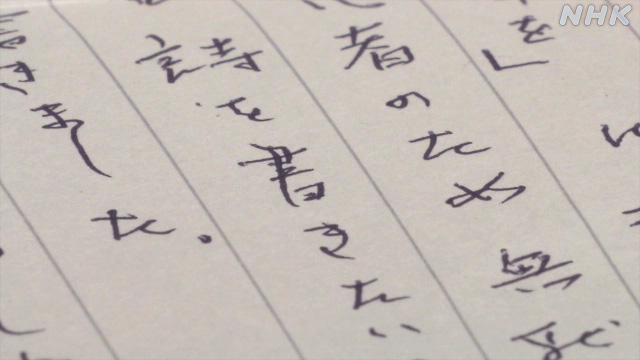
玉田さんからの手紙
石下さんとの文通が始まって2か月で玉田さんは30余りの詩を完成させました。その1つが「シベリア抑留」です。
終戦直後、旧ソビエト兵から「日本に帰国できる」と聞かされながら、シベリアの凍土まで連行された時の様子を描いています。
シベリア抑留
玉田 貞喜
東京ダモイのかけ声により
旧満州から歩行すること一週間
沿海州の大草原に辿り着いた
前夜はハロリー村で
牛の放牧場に固まって野宿した
上衣には薄い霜が降りていた
生の大豆が支給されたが
火も水もなかった
抑留されたのに住む家はなく
大草原に工夫して寝よという
4キロ離れた湿地帯に柳が密生していた
刃物もなく手折った枝を草で束ね
アーチ型のねぐらが完成した
5人が座って入る大きさであった
土の上に乾草を敷き潜って寝た
屋根に草をかけても
雨の時はずぶ濡れになった
ロシアの大鎌で草を刈った
朝、粟のスープと昼のパンは一緒に食べた
昼は空腹に耐え
草原に寝転んで空を見上げていた
祖国日本の方角に
雁の群れが飛んでいく
18歳のシベリア抑留であつた
※ダモイ…帰国、帰還
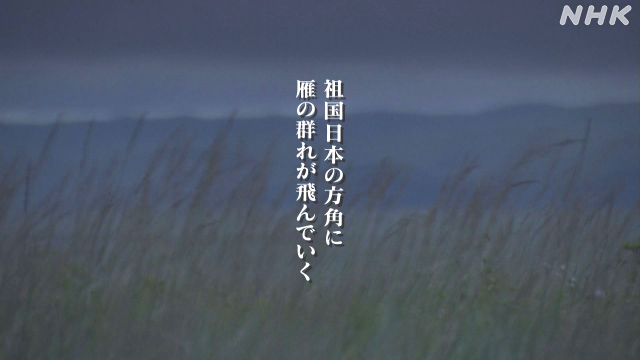
最初の詩の投稿から4か月がたった8月。
選者の石下さんは、ある大切な提案をするために、初めて玉田さんのもとを訪ねました。
戦争体験をより深く伝えていくうえで、玉田さんの詩に足りない要素があるというのです。
この日、石下さんが伝えようとしたのは「戦争の事実を書きつづるだけでは、人の感情を動かすことは難しい」というメッセージでした。

石下さん
「事実を書き連ねるだけではなく、その時の感情の高ぶり、悔しい思い、そうした人間味が少しでも出されると詩の完成度が上がり、戦争の悲惨さが伝わるんです。だから苦しい作業になると思うけれども、当時の胸のうちまで詩に書いてほしい」
思いや感情を詩に込めてほしいという石下さん。
これに対して玉田さんは、深い悩みを打ち明けるように、こう答えました。
玉田さん
「そこがどうしても踏み込めないんです。核心まで書こうとすると、それを書いたらまずいと思い筆が止まってしまうんです」
当時のつらい胸のうちや感情まで詩にさらけ出すことは難しいという玉田さん。後日改めてその理由を尋ねると、次のような言葉が返ってきました。

玉田貞喜さん
玉田さん
「当時のことは正直に言うと思い出したくはない。胸のうちまで書くのは難しい。表現できない。それほど抑留生活は悲惨だった」
8月下旬、私(筆者)は、玉田さんが詩作に取り組む様子を記者リポートにまとめ、栃木県域のニュース番組「とちぎ630」で放送しました。
すると、放送の約1週間後、地元紙の読者欄に、リポートを見た視聴者の方からの反響が掲載されたのです。
シベリア抑留を体験した父を持つ、栃木県内に住む60代女性からの投書でした。
(投書の引用)
「玉田さんが伝えようとしているのは戦争の過酷さだと感じることができます。共に赴いた仲間が飢えと極寒で亡くなる様は、亡き父から聞いた話と重なりました。しかし父からそれ以外は語られませんでした。玉田さんの詩は受け継がれるために必要であります。記憶を書き続けてほしいと願っています」
この投書を目にした玉田さん。
これからも後世のために詩を書き続ける決意を強くしました。

玉田貞喜さん
玉田貞喜さん
「自分の詩を求めてくれている人がいると思うと、詩を書き続け、自分の経験を書き継いでいこうと改めて思いました。自分の息子や孫には、決して戦争を経験してほしくないですから」
