空飛ぶクルマ いつ乗れる?

プロペラで垂直に離着陸。ビルの屋上から乗ってそのまま自宅に帰る…。
そんなSFに登場するような「空飛ぶクルマ」の開発が急ピッチで進んでいます。8月下旬、人を乗せたテストフライトが国内で初めて行われました。2025年の大阪万博では、来場者を運ぶという構想もあります。私たちが乗ることができるようになるのも、そう遠くはないかもしれません。試験機のテストフライトを取材してきた大江麻衣子記者、教えて!

空飛ぶクルマって、ヘリコプターや小型の飛行機とどう違うの?
 大江記者
大江記者
まだ明確な定義はないんですが、国がつくった実現に向けた行程表では、『電動のプロペラを使ってドローンのように垂直に離着陸でき、パイロットなしで遠隔から操縦できる乗り物』とあります。各社が開発している実験機を見てみると、たくさんのプロペラが付いたドローンのような形状をしています。
垂直に離着陸できることを想定しているので、飛行機のように滑走路はいりません。開発を手がける会社のイメージ映像では、仕事が終わった人がビルの屋上にある空飛ぶクルマに乗り込み、渋滞する道路の上を移動して自宅に戻るといった様子が描かれています。
またヘリコプターに比べて設計がシンプルで、乗用車よりも部品の数が少なくすむとされています。実現すれば「空の移動革命」になるとも言われているんですよ。

夢みたい!実現するのは10年後?20年後?
 大江記者
大江記者
いえいえ。目標をみると、それほど遠い未来のことではなさそうです。日本では官民の協議会が2023年ごろの実用化を目指しています。それまで、あと3年です。
2025年に予定される大阪万博で来場者を運ぶという構想もあるんです。
8月下旬に愛知県豊田市で人を乗せた初めてのテストフライトが行われ、実際に見てきました。実験を行ったのはスタートアップ企業の「SkyDrive」。

トヨタ自動車や国産初のジェット旅客機MSJを手がける三菱航空機の出身者などが参加している会社です。
公開された空飛ぶクルマは、全長4メートル、高さ2メートルと、まさに自動車と同じようなサイズですが、1人乗りで前後左右に上下に重ねられた合計8枚のプロペラが備わっています。
時速4キロのゆっくりとしたスピードで、地上2メートルの高さを維持しながら旋回。4分後に離陸した場所に戻りました。ゆったりとした動きですが、空中で機体が安定していたのが印象的でした。
乗っていた人に聞くと、「低空での安定性は高く、乗用車で一般道を走っているような乗り心地だ。
以前よりも静かになって、少し音がする程度のスポーツカーに乗ったような感じだ」と話していました。開発のステップが一歩進んだといえます。

ほかにどんなところが開発しているの?
 大江記者
大江記者
国内では重工大手の「川崎重工業」が機体、「NEC」が運航システムの開発を進めているし、航空会社の「ANAホールディングス」「日本航空」も空飛ぶクルマの運航サービスを検討しているんです。
海外でもアメリカのライドシェア大手の「ウーバー」が“空のタクシー”という構想を打ち出していますし、ドイツのベンチャー企業は去年秋にシンガポールで試験飛行を行って成功しています。

ドローンを開発しているベンチャー企業「イーハン」も人を乗せた飛行実験を行っていて、開発競争ははやくも激しくなっているんですよ。

多くの会社が力を入れているのはわかったけれど、実用化の目標までおよそ3年。本当にそんなに早く実現するのでしょうか?
 大江記者
大江記者
乗り越えるべき課題は少なくありません。
まずは、なんといっても安全性です。例えばSkyDriveでは、8つあるプロペラのうち1枚が故障しても飛行を続けられるよう設計しているそうです。ただ、人を乗せて移動する以上“万が一”も許されません。少なくとも航空機並みの高い安全性が求められると思います。1回の充電で航続できる距離を伸ばす必要もあります。
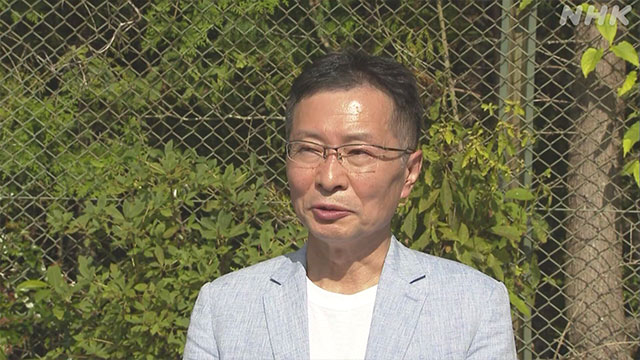
SkyDriveで最高技術責任者を務める岸信夫さんも「開発はまだ3分の1くらいのところだ。技術的なめどはついてきたが、今後は、具体的な飛行用途にあわせた新たな試験機を開発し、前例のない審査にクリアするハードルが残っている」と話していました。
新しい乗り物だけに、機体の審査基準、騒音の基準、離着陸場の整備、飛行する空域の調整など、制度面の整備も多岐にわたります。
日本企業には空飛ぶクルマに応用が可能な技術力があります。実現すれば、新しいサービスや産業が生まれることも期待されるだけに、官も民もスピードアップをはかってほしいと思います。
# 注目のタグ
- # 新型コロナ (51件)
- # 暮らし・子育て (34件)
- # 銀行・金融 (34件)
- # 環境・脱炭素 (33件)
- # 自動車 (28件)
- # AI・IT・ネット (27件)
- # 財政・経済政策 (24件)
- # 働き方改革 (21件)
- # 給与・雇用 (21件)
- # 日銀 (19件)
- # 企業の合従連衡・業界再編 (18件)
- # 消費税率引き上げ (17件)
- # エネルギー (17件)
- # 農業・農産品 (15件)
- # 原油価格 (14件)
- # 人手不足 (14件)
- # 物価高騰 (13件)
- # 外食 (13件)
- # 旅行・インバウンド (12件)
- # 株式市場・株価 (12件)
- # 景気 (12件)
- # 経済連携・貿易 (12件)
- # ウクライナ侵攻 (11件)
- # 携帯料金 (10件)
- # コンビニ (10件)
- # お酒 (10件)
- # 携帯電話 (9件)
- # 鉄道 (9件)
- # キャッシュレス決済 (9件)
- # 為替 (9件)

