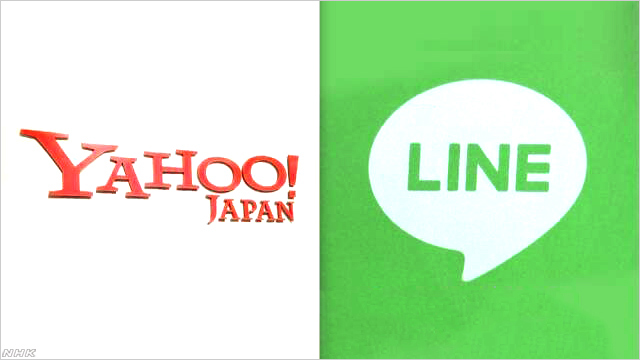「CSF」って、なに?

いまブタの間で感染が広がっている病気「豚コレラ」。国が、その呼び方を「CSF」に変更しました。感染が相次ぎ、国も対策に乗り出したことなどで、一般にも病気の存在が知られるようになったばかりですが、なぜいま、呼び方を変えたのか?農林水産業の取材を担当している岡谷宏基記者が解説します。

それにしても「CSF」って、なんとも呼びにくい感じもします。
 岡谷記者
岡谷記者
ほとんどの人が初めて聞くと思います。これは豚コレラを指す英語の「Classical Swine Fever」の頭文字をとったものなんです。直訳すれば、「古典的なブタの熱病」となります。
ブタがこの病気にかかると、高熱や食欲不振が見られ、多くのケースで死んでしまいます。去年9月に、国内では26年ぶりに岐阜県で感染が確認され、その後埼玉県など関東地方にも広がっています。

どうして、わざわざ呼び方を変える必要があるんですか?
 岡谷記者
岡谷記者
この病気は、1800年代にアメリカで初めて発生が確認されたときに、当時流行していたヒトのコレラに症状が似ているとして、「Hog Cholera」と命名され、日本でも豚コレラと呼ばれるようになりました。しかし、実際にはヒトがかかるコレラと豚コレラは全く別の病気です。そのため、現在ではアメリカを含めて、国際的に「CSF=Classical Swine Fever」が使われているのです。

今回、日本国内でも国際的な呼び方にそろえることになった訳ですが、最大の理由は豚肉への風評被害を防ぐためです。この病気はあくまでブタの病気で、感染したブタやワクチンを接種したブタの肉を人が食べたとしてもうつりません。しかし、豚コレラという呼び方だと、人間の病気であるコレラを連想してしまい、消費者の不安を招き風評被害につながるとの指摘が、生産地の自治体などからあがっていました。
家畜の病気の呼び方を変えたケースは、これまでにもあります。牛では、牛海綿状脳症いわゆる狂牛病が「BSE」という呼び方に変わって、定着しました。

豚コレラと名前が似ている「アフリカ豚コレラ」という病気もありますよね。これも、呼び方が変わるんですか?
 岡谷記者
岡谷記者
アフリカ豚コレラは、「ASF」という呼び方になりました。「African Swine Fever」の頭文字です。ASFはCSFと似た名前ですが、全く別の病気で、より感染力が強く、致死率も高いのが特徴です。現状では、ワクチンも治療法も見つかっていません。このため、去年8月に感染が確認された中国では、これまでに約1億頭が殺処分されたとみられ、豚肉の価格が大幅に値上がりするなどの影響が出ています。
このほか、ベトナムやモンゴル、フィリピンなどにも感染が広がり、9月には韓国でも確認されました。このままでは日本に入ってくるのも時間の問題だとも言われています。

病気の呼び方は変わりましたが、その脅威は変わりません。感染防止に向け、より一層の対策が求められています。
# 注目のタグ
- # 新型コロナ (51件)
- # 暮らし・子育て (34件)
- # 銀行・金融 (34件)
- # 環境・脱炭素 (33件)
- # 自動車 (28件)
- # AI・IT・ネット (27件)
- # 財政・経済政策 (24件)
- # 働き方改革 (21件)
- # 給与・雇用 (21件)
- # 日銀 (19件)
- # 企業の合従連衡・業界再編 (18件)
- # 消費税率引き上げ (17件)
- # エネルギー (17件)
- # 農業・農産品 (15件)
- # 原油価格 (14件)
- # 人手不足 (14件)
- # 物価高騰 (13件)
- # 外食 (13件)
- # 旅行・インバウンド (12件)
- # 株式市場・株価 (12件)
- # 景気 (12件)
- # 経済連携・貿易 (12件)
- # ウクライナ侵攻 (11件)
- # 携帯料金 (10件)
- # コンビニ (10件)
- # お酒 (10件)
- # 携帯電話 (9件)
- # 鉄道 (9件)
- # キャッシュレス決済 (9件)
- # 為替 (9件)