金融緩和策の一部修正ってどういうこと?

日銀は、31日まで開いた金融政策決定会合で、今の大規模な金融緩和策を一部修正することを決めました。長引く緩和の副作用を和らげ、政策の持続性を強化するため、長期金利の一定の上昇を容認するなどの新たな措置を取ることになりました。

日銀の金融緩和ってずいぶん長く続いていますよね。今、一部を修正するってどういうことですか?

黒田総裁は、日本経済を長年苦しめたデフレという病を退治するため、みずからが異次元と呼ぶ規模で5年前から金融緩和を続けてきた。言ってみれば、極めて強いカンフル剤を処方してきたわけ。
実際、景気は回復を続けているけど、肝心の物価は、日銀が掲げた2%の物価目標に届いていない。それどころか、今回、物価の状況を詳しく点検してみると、これまで想定した以上に物価の伸びは鈍いことがわかったの。病を完全に治すには、まだまだカンフル剤を打ち続けないといけないということね。
一方で、強力なカンフル剤を5年以上も処方してきたのでこのところ地方の銀行などの収益力が低下するといった「副作用」も懸念されるようになってきた。だからこそ、副作用にも配慮して政策を長く続けられるようにするため、きょう、一部を修正したのね。
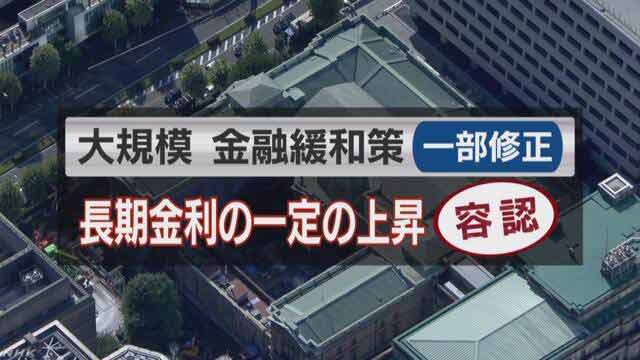

金融緩和の方向性を修正したわけじゃなく、緩和を長く続けるために政策を修正したということなんだ。

日銀はそう説明している。
今回発表された修正点はいくつかあるけど、最大のポイントは、長期金利の一定の上昇を容認するということ。
日銀は、誰でも低い金利でお金を借りられるようにして世の中のお金の動きを活発にしようと長期金利を0%程度に抑え込んできた。
ただ、長い間、低く抑え込んだため、長期金利の指標になる国債の取り引き自体が細ってしまった。銀行などが企業に融資する際の金利も下がりきってしまい、融資で稼ぐことが難しくなっている。
そこで今回、長期金利が動く幅をこれまでの2倍程度に広げて国債の取り引きを活発にさせ、金利が一定程度上昇することも容認することにしたの。
副作用を抑える効果がどこまであるかはまだ見極めが必要だけど、これまで緩和の強化一辺倒だった日銀が副作用に配慮する姿勢を見せたことは大きな変化と言えるわ。

今回の決定で本来の目的の、デフレという病の克服は実現できそうなのかな。

道のりは険しいと言わざるを得ないわね。
日銀は、これまで物価目標の実現時期の見通しを何度も先延ばししてきている。物価が伸び悩んでいる原因はいろいろと指摘されているけど、大きな背景として、十分に賃金が伸びないため、消費者が財布のひもを緩めない。

だから企業も、原材料の価格が上昇したとしても販売価格をなかなか引き上げられないといった構造があって、この状況がいつ変わってくるか、はっきりは分からない。
目標実現のためにカンフル剤を打ち続けていると、今後、景気が悪化した際に経済を下支えする政策の余力が乏しいといった指摘もある。
日銀には、今後も緩和の効果と副作用の両方に十分に目配りし、必要な対応を取っていくことが求められるわね。
# 注目のタグ
- # 新型コロナ (51件)
- # 暮らし・子育て (34件)
- # 銀行・金融 (34件)
- # 環境・脱炭素 (33件)
- # 自動車 (28件)
- # AI・IT・ネット (27件)
- # 財政・経済政策 (24件)
- # 働き方改革 (21件)
- # 給与・雇用 (21件)
- # 日銀 (19件)
- # 企業の合従連衡・業界再編 (18件)
- # 消費税率引き上げ (17件)
- # エネルギー (17件)
- # 農業・農産品 (15件)
- # 原油価格 (14件)
- # 人手不足 (14件)
- # 物価高騰 (13件)
- # 外食 (13件)
- # 旅行・インバウンド (12件)
- # 株式市場・株価 (12件)
- # 景気 (12件)
- # 経済連携・貿易 (12件)
- # ウクライナ侵攻 (11件)
- # 携帯料金 (10件)
- # コンビニ (10件)
- # お酒 (10件)
- # 携帯電話 (9件)
- # 鉄道 (9件)
- # キャッシュレス決済 (9件)
- # 為替 (9件)

