2023年1月11日
新型コロナウイルスの感染拡大で、1月9日までの6日間に全国で確認された高齢者施設のクラスターなどは722件、その前の年末年始の週では861件と第7波のピーク前後の水準が続いています。
厚生労働省は毎週、報道などをもとに自治体がクラスターと認定した事例や2人以上が感染した事例をまとめていて、1月11日は年末年始の週の分も含めて発表しました。
それによりますと、1月9日までの6日間に、全国で確認された「高齢者福祉施設」でのクラスターなどは合わせて722件でした。
過去最多となった2022年12月25日までの週の954件より200件余り減りましたが、年末年始を挟んだ1月3日までの週は861件と第7波のピークだった8月の850件を上回っていて、面会制限など厳しい対策が行われている介護の現場で、依然としてひっ迫した感染状況が続いています。
クラスター3回目の施設では

感染対策の徹底が続く中でのクラスター発生に高齢者施設の担当者も苦悩しています。
千葉県市川市にある特別養護老人ホームでは、2022年11月から12月にかけて利用者と職員あわせて23人が感染するクラスターが発生しました。
この施設でのクラスターはコロナ禍が始まって3回目です。
感染拡大による病床のひっ迫を背景に、今はコロナに感染しても入院できずに、施設で療養を続ける高齢者が数多くいます。
そうした人たちを支えるため、保健所などの指導のもと、施設がまず行ったのはエリアごとに分ける“ゾーニング”です。
感染が広がったフロアへの立ち入りを一部の職員に限定した上、通用口から各階まではほかのフロアの職員どうしが接触しないよう、細かく導線を設けました。
また、感染防止のため食堂を閉鎖し、防護服を着た職員がそれぞれの部屋に食事を届け、食事を介助する方法に変更。
その分、膨大な手間と時間がかかるようになったためやむをえず、毎日の入浴をとりやめて体をふくだけにしたほか、週1度のシーツ交換は汚れがひどく無いかぎりは中止にせざるをえませんでした。
また、予約制で行っていた利用者と家族との面会も、付き添える職員がいないため、クラスターが発生している間は休止する措置をとっているということです。
また、施設では併設するデイサービスの休止は、利用者や家族への影響が大きいとして当初はデイサービスの事業を継続しました。
ところが、施設で感染者が出た2週間後には、感染経路はわからないもののデイサービスでも感染が確認され、休止せざるを得なくなったということです。
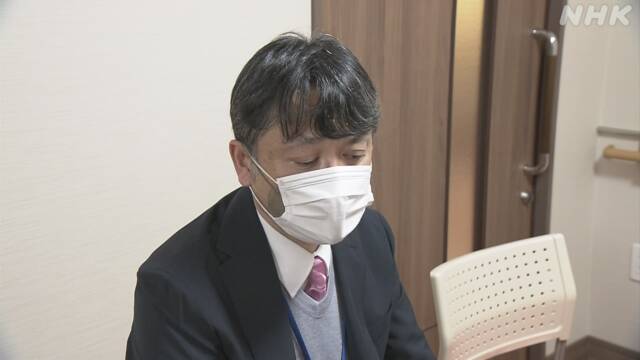
特別養護老人ホーム「親愛の丘市川」の千野哲孝施設長は、「デイサービスが止まると、家族が仕事に行けずに困るため何とか事業を続けようと頑張ったが、結果的に止めてしまいやるせない気持ちです。事業を続けていくために、一時的に何のサービスを残して中止するかの選択はすごく大変で心苦しく、今後どうしていくべきか、具体的な方法を考えていきたい」と話していました。
BCP研修に介護施設の応募殺到

クラスターが起きた場合でも、介護サービスをできるだけ止めないために施設内での感染症の流行を想定したBCP=業務継続計画の策定が、来年の春からすべての介護施設で義務づけられました。
現在は「努力義務」となっていて、早いところではすでに計画を作る施設がある一方、「どうすればいいかわからない」という施設も多く、国の調査では全体の4分の3の施設で策定できていないということです。
そこで、厚生労働省は12月からコロナ感染症のBCP策定について介護施設向けのオンライン研修を開いています。
この日の研修では、感染者が発生した場合、
▽誰が何をするか、担当者の連絡先などとともに役割を明記しておくこと、▽行政の支援が始まるまで最低5日間は自力で業務を続けられるよう、必要な物資を決めて備えること、
▽業務の優先順位を整理することなどを確認しました。
また、グループワークではさまざまな介護事業者が現状を話し合い、「クラスターの経験がないので、BCPはどこから手を付けていいのかわからない」とか「ほかの事業所の事例を学んだうえで、きちんと策定したい」などと、悩みや意見を出し合っていました。
オンライン研修は、12月は応募が殺到して予約枠が埋まったため、厚生労働省は1月以降も追加で開催するなどして施設のBCP策定を支援したいとしています。
特別養護老人ホーム施設長「BCPはあくまで計画」

一方、2022年の春に暫定的にBCPを作った千葉県松戸市の特別養護老人ホームでは、7月と11月にそれぞれクラスターが起きましたが、事前に作った計画がほとんど役に立たなかった場面があったと指摘しています。
2022年7月には、高齢者の共同部屋が連なる1階のエリアで感染が拡大。
合わせて11人が感染したまま施設にとどまることになり、施設では、ゾーニングのために廊下の天井からビニールシートをつり下げて分断し、「感染ゾーン」と「清潔ゾーン」を分けることにしました。
2つのゾーンの間には、「中間ゾーン」を設け、職員がこの中で防護服を脱着し、高齢者の往来も防ぐことで「清潔ゾーン」に感染拡大させないようにしたということです。
しかし、11月のクラスターの時は、2階の個室エリアで感染する人が相次ぎ、「感染ゾーン」を部屋ごとに設けることになりました。
すると、個室はそれぞれ壁やドアで区切られているため、新たにビニールシートなどで隔離する必要はないものの、「中間ゾーン」が設けられず、部屋に出入りする際や、廊下で着替える際には、通りかかる利用者に感染させるおそれがないかなど、常に気を配る必要があったということです。
事前のBCPでは、こうした細かい対応までは定めておらず、実際にクラスターが起きてから対応を決めたことが多かったとしています。
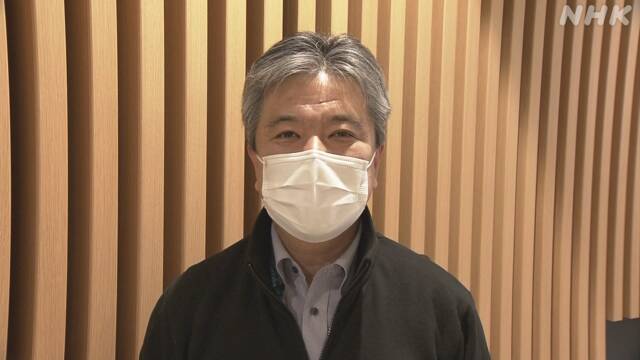
特別養護老人ホーム「アウル大金平」の飯野聡施設長は、「クラスターは、いつどこで起きるかわからず、一気に感染拡大する場合やそうでない場合もあり、その都度対応の仕方が変わるため難しい。BCPはあくまでも計画で、それを実行して評価して、やり直して、新しい計画を常に作っていく必要がある。決して止まることが許されない業種だと思うので、常に継続していける方法を模索しながら、何とか対応していきたい」と話していました。
専門家「施設の事情に合わせたBCPを」

介護の現場に詳しい東洋大学の早坂聡久准教授は、「介護施設では抵抗力があまりない高齢者が多い一方で、食事や入浴などの介助は人との接触が前提にならざるをえない。オミクロン株は感染力が強い一方で重症化しにくいことから、施設には無症状の感染者も多くいるとみられ、そうした状況が重なって感染が広がっていると思われる」と分析しています。
そのうえで、「クラスターを経験し、厳しい対応をとっている施設でもクラスターが起きていることから、ウイルスは持ち込まれたら広がることが前提で、感染を最小限にとどめるための仕組みや、重症化した際に迅速に対応するための体制の整備が必要だ」と話していました。
また、クラスター時の業務継続については、「BCPはあくまでも大枠としての考え方を示すもので、作ったからといって事業継続がなされるものではない。施設ごとに、対応は変わってくるため、施設の事情に合わせたBCPを作ることが大事だ」としています。
そのうえで、「ゾーニングや職員の配置、シフトなど細かく想定した準備が重要で、行政側もBCPを作らせて終わりではなく、有事の時ほど積極的に関わって応援職員を募ったり、病院との連絡調整にあたったりと、事業継続に向けて一緒に行動するスタンスや体制をとってほしい」と話していました。