2022年4月14日

成人年齢の引き下げによって懸念されているのが若者の消費トラブルです。
未成年が親などの同意を得ずに結んだ契約は、原則、あとから取り消すことができます。
ところが18歳と19歳のみなさんは、4月1日から成人となったため、これまでと違って年齢を理由に契約を取り消すことはできなくなりました。
消費者被害やトラブルの相談は、これまでも成人となる20歳を境に増える傾向にあり、契約者が20代前半だったケースは2020年度までの5年間で20万件余り(国民生活センターまとめ)。
さらに今後は18歳や19歳に被害が拡大するおそれがあるのです。
そこで、そもそもなぜ若者は消費トラブルに巻き込まれやすいのか。
そしてだまされないためにどうすればよいのか。
心理学の観点から、立正大学の西田公昭教授に話を聞きました。
なぜ若者は被害にあいやすいの?
 西田教授
西田教授第一に「経験不足」だからです。
お金を使って何かを買ったり、契約したりすることの経験が不足しています。悪徳業者からうまい話を持ちかけられた時、経験がないので、「そうなのかな」と受け入れてしまう。
経験がある人なら「こんな話がうまくいくはずない」と思うようなことでも、「うまい話だ」と思い込みやすいんです。結果的にどうなるのか、悪い予測もしにくい。
さらに、冒険心や好奇心が強いのも若者の特徴です。つい「やってみようか」と、軽い気持ちでチャレンジしてしまう。こうして、被害にあってしまうんです。
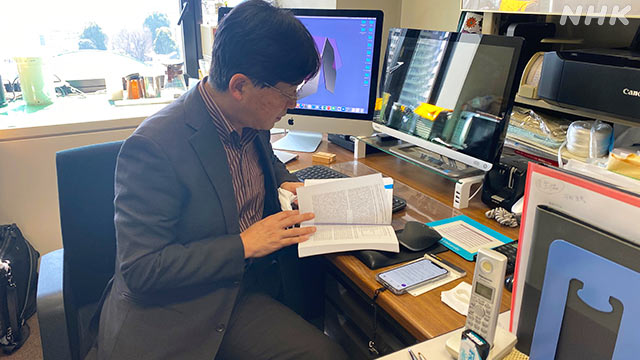
 西田教授
西田教授 要するに、若者はだます方からすると“だましやすい”、“ちょろい”のです。
だます方も、全世代をまんべんなくだますのでなく、効率のよいところを狙います。
若者向けのシナリオを作ってだまそうとする、だます仕掛けが多いわけですから、必然的にだまされる人も増えてしまうんです。
SNSをきっかけにしたトラブルも増えているといいます。
なぜ、若者は巻き込まれやすいのでしょうか?
 西田教授
西田教授若い人ほど、SNSは、小さいころからの身近な情報ツールになっています。
SNSで情報を入手することで世の中を知り、あとから現実社会を知る。
ですので、SNSの世界観が本当なのかうそなのか、区別がつきにくいんです。
さらに、人間は自分の都合のよいものを信じてしまう“バイアス”、“ゆがみ”があります。
人間の認知の仕組みというのは、SNSがあろうとなかろうと同じで、自分の知りたい情報を能動的に集める習性があり、それに反する情報は無視してしまいがちです。
だまされない人はどんな人?性格は関係ある?
 西田教授
西田教授性格が影響することは確かです。
ただ、消費者被害の現場を見ると、そうした個人差よりも、相手と交渉しているときに働く、心理的な圧力の影響というのが非常に大きいんです。
要するに、誰もが被害にあう可能性があるということです。
買い物をしたり、契約する際に、交渉を重ね、断るという経験を積んだりすることで、強くなれるわけですが、若者は圧倒的に経験不足なので、その場の状況に流されてしまいがちで、よりだまされやすいと言えるでしょう。
だますテクニックはあるの?
 西田教授
西田教授人間の思考には2つのモードがあります。
「直感的に判断する」モードと、「熟慮して判断する」モードです。
実は、日常生活で私たちは、深く考えずに直感で判断しています。早い時間で判断できますが、誤りをおかしやすいとされています。
一方で、例えば受験のときは体調を整えてベストコンディションで臨もうとするように、大事な意思決定をするときは、「熟慮モード」に切り替わります。自分の力を全て出し切ろうとしている人をだまそうとしても、難しいですよね。
熟慮モードでない相手は、だましやすい。
だから悪徳業者の人たちは、「今だけですよ」とか「30分以内に決めて下さい」などと時間を限定してみたり、長時間拘束したり、ときに甘い期待も与えたりして「直感的に判断」するモードに引っ張っていこうとします。
ここまで読んでも「私はだまされない」と思っているあなたへ
 西田教授
西田教授「私はだまされない」、「私はだまされたことがない」と思っている方もいるかもしれません。
でも、人を全く信じない人っているでしょうか。私たちは人を信じているからこそ、物を売ったり、買ったりすることができます。世の中は互いを信じ合い、信頼することで成り立っているわけです。小さいころから人を信じることは素晴らしいことだと教えられてきましたよね?そして、幸いにして今、日本の社会は、圧倒的に多くの人たちがうそをつかず、信頼し合っているからこそ成り立っています。
でも、そこにうそが紛れ込んでいた場合、本当に見抜けるでしょうか。
みなさん、よくよく考えると一度や二度、「あれ、ちょっと違ったな」と思うような買い物をした経験はありませんか。もしかしたら気づいていないだけで、だまされたことのない人間なんていないんです。
人を傷つけないために、相手のためによいことだと思って、うそをつくこともあります。うそはある意味、社会の潤滑油です。
そうした中で、悪いうそだけ見抜けるのかというと、そんな都合のよい論理はありません。だからこそ、だます方が優位に立っているんです。
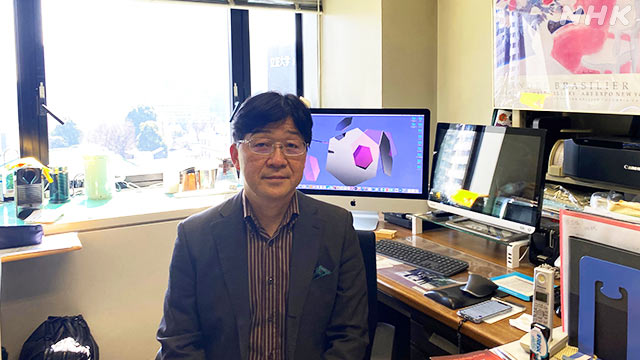
だまされない方法はあるのか
 西田教授
西田教授残念ながら決定打はありません。
だます方が優位な立場にある以上、わたしたち消費者は強くならないといけないのです。
消費者保護に関する法律をより整備すべきだとも思いますし、自分の身を守るためにどうすればいいのか、どんな手口があるのか事前に学習しておく。アンテナを高くして、うまい話があったときに「これはまずい」と、ドキッとする感覚を身につけないといけません。ですから、消費者教育というのは非常に重要です。
ただ、今の状態では、若者への消費者教育は不十分と言わざるを得ず、悪徳業者からするとつけ込みやすいままだと思います。
“狙われている”若者たちへ
 西田教授
西田教授極めて残念ながら、世の中には思っているよりも多くの人があなたたちをカモにしようとしています。みなさんは、自分たちが経験不足であることを認識しておくべきです。
経験のないところで勝負をする、判断をすることは危険です。自分を過信せずに、家族、友人、専門的な知識を持った人、公的機関など、必ず命綱を持つよう心がけてください。

ラジオセンター
瀬古 久美子
2005年入局
3歳の娘がお買い物ごっこの支払いでカードしか使わず、早めの消費者教育を検討中。