英語で「倫理的」を意味する「エシカル」。最近は、環境や社会問題に配慮した商品を選ぶ「エシカル消費」ということばなども知られるようになっています。
「エシカル就活」とは…
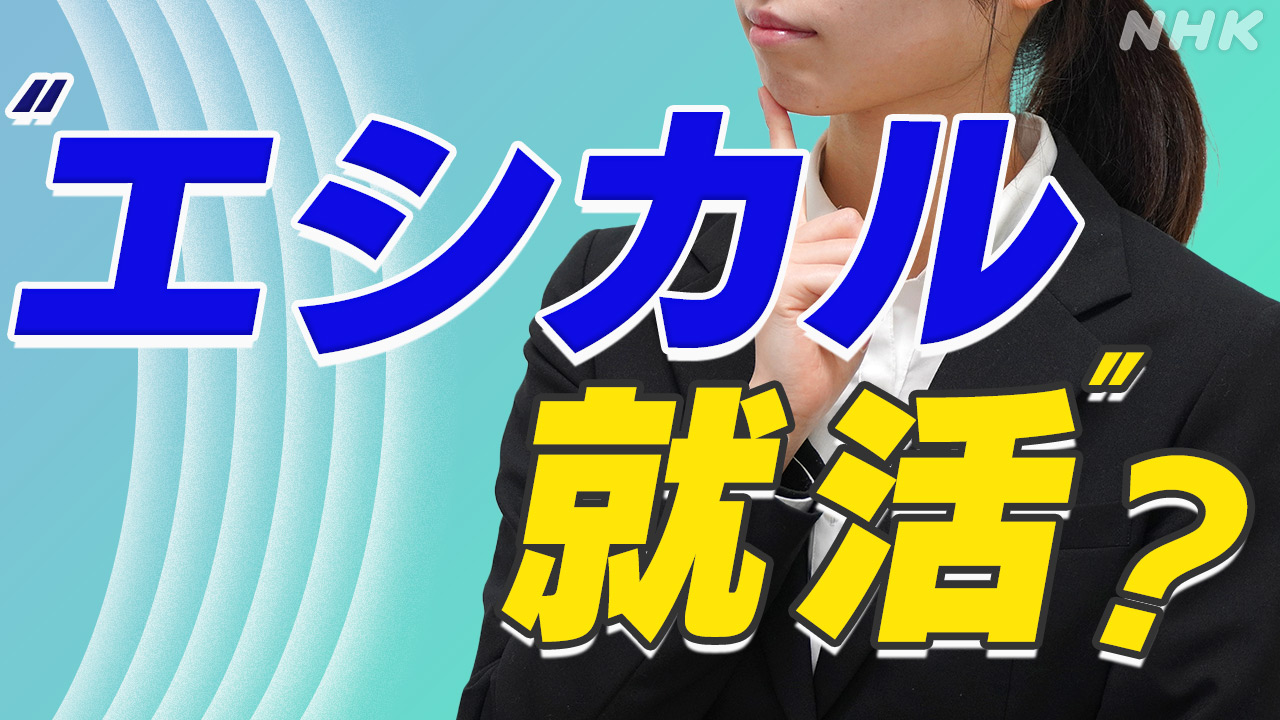
企業選びの新たな軸に?「エシカル就活」聞いたことありますか
グループの従業員10万人超のメーカーの内々定を断り、ベンチャー企業に入社することを決めた大学生。決め手は「脱炭素に取り組む社員の熱量」でした。
いま、地球環境や社会貢献への関心の高まりなどを背景に、若者の就職活動は多様化が進んでいます。
「エシカル就活」、聞いたことありますか?
「エシカル」=「倫理的」な就活とは?
企業の規模や知名度ではなく、環境問題や社会問題への取り組み、自分と企業の価値観がどれだけ合致するかなどを重視した企業選びのスタイルを指す造語
就職情報会社によりますと、就職を目指す学生などの間で、数年前から徐々に広がっているということです。
「エシカル就活」をした学生は?
東京都内に住む大学4年生で広島県出身の内田慶悟さん(22)は、高校2年生の時、西日本豪雨の土砂災害の被害を目の当たりにしたことがきっかけで、地球温暖化をはじめとした環境問題に関心を持つようになりました。

企業の脱炭素への取り組みを軸に据えて就職活動に取り組み、グループの従業員が10万人を超える大手電気機器メーカーからも内々定を得ましたが、すでに断りを入れ、都内のエネルギー関連のベンチャー企業に入社することを決めました。

選択の決め手になったのは「脱炭素に取り組む社員の熱量」だったといい、内田さんは「温暖化によって地球規模の課題が起きる中、やりがいのある仕事だと思いました。どの企業もSDGsを掲げてはいますが、本気度は違うと思います。会社の意向と自分自身の意向がマッチしているかどうかはとても大事にしていました」と話していました。
内定を出した東京・中央区のベンチャー企業で採用を担当している遠藤昌紀マネージャーは「脱炭素や地球人類のこれからに対して価値のあること、貢献できることを、働く軸にしたいと考える学生が選考を受けてくれるのは、とてもありがたいです。オープンに情報を伝え、本人の熱量を会社の事業につなげてもらうことが、大事だと考えています」と話しています。
「エシカル就活」専用の就活サイトも
東京・渋谷の就職情報会社では3年前に「エシカル就活」の学生向けに企業を紹介する専用サイトを立ち上げました。
サイトでは登録されている130余りの企業の中から「気候変動」や「貧困問題」といった社会の課題、「ジェンダー」や「持続可能性」などのキーワードで検索ができ、企業の取り組みなどを紹介しています。

ほかの大手の就職サイトとは異なり、あえて給与や福利厚生といった情報は掲載していないということですが、利用する学生は、ことし4月時点でおよそ1万5000人と、開設後の3年間で20倍以上に増えているということです。
この会社には、面談での就職相談を希望する学生も訪れていて、2026年春の就職に向けて企業を調べている都内の大学3年生は「自分が好きなことや、やりたいことができなければ、どれだけお金をもらっても、働いていてきつくなると思います。楽しいな、好きだなと思えて自分が輝ける会社から内定をもらいたいです」と話していました。

この就職情報会社によりますと、学生の「売手市場」と言われ、内定を辞退するケースも少なくない中、このサイトを利用して就職活動を行い、内定を取った学生が、最終的に入社する割合はおよそ8割にのぼっていて、効率的な人材の確保につながるとして登録する企業も増えているということです。

就職情報会社の勝見仁泰社長は「就活は企業側が学生を取る時代から、企業が選ばれる時代になっている。会社に入っていただきたい従業員たちが心地よく働くための紹介だと思っている」と話していました。
「エシカル就活」広がるか?
就職情報会社の「学情」が2025年春に卒業予定の大学生など550人余りを対象に去年、インターネットで行った調査では「仕事選びで社会課題の解決に貢献できるかを意識するか」という質問に対し、「意識する」、または「どちらかと言えば意識する」と答えた人の割合が合わせて72%にのぼっていて、社会課題への貢献が若者の企業選びの重要な要素になっていることがうかがえるとしています。

就職活動に詳しい採用コンサルタントの谷出正直さんは「今の学生たちは育った時代背景の中で『SDGs』ということばを見聞きし、東日本大震災以降、ボランティア活動も身近になっている。大手企業の希望退職の募集や倒産のニュースも目にして、今ある企業がずっと続くわけではないと考えるようになっているので、企業の側も自分たちの活動の理念などをしっかり伝えていかなくては人材を集めにくくなっている」と話しています。
大学生とつくる就活応援ニュースゼミ
