
「自由で開かれたインド太平洋」の実現に向け、協力を進めている日米豪印4か国の枠組み、クアッド。東京で5月に開かれた首脳会合の共同声明には、太平洋島しょ国との経済協力を、さらに強化することが盛り込まれました。
すると同じ日、中国外務省は、王毅外相がソロモン諸島など太平洋の島しょ国8か国を10日間かけて訪問することを発表しました。
アメリカと中国が競い合うように関与を深める、南太平洋地域。
なにが起きているのか。
この地域の戦略的要衝とされるソロモン諸島を取材しました。
(アジア総局 松尾恵輔・ワシントン支局 渡辺公介)
中国外相 異例の10日間訪問

中国の王毅外相が、異例ともいわれる10日間をかけた太平洋の島しょ国歴訪で、5月26日に最初に訪問したのが、ソロモン諸島でした。
ソロモン諸島では「歴史的な訪問だ」として歓迎を受け、ソガバレ首相やマネレ外相と、経済や保健分野などで協力を拡大する方針を確認しました。
中国と安全保障協定締結 内容は?
中国とソロモン諸島はことし4月、安全保障協定を締結したと発表しました。しかし、協定の具体的な内容については、公式には明らかにされていません。
「中国がソロモン諸島に軍事基地をつくるのか」という周辺国の懸念に対し、ソガバレ首相は「そのつもりはない」と否定。
中国の王毅外相は、会見で「ソロモン諸島の社会の安定を維持するための支援を行うものだ」とした上で、「第三者を標的にしたものではなく、軍事基地を建設する意図はない」と発言しています。
実はこの協定をめぐっては、締結の発表に先だって、草案だとされる文書の画像がSNSに投稿されていました。NHKが取材したところ、投稿したのは地元の有力者であることがわかりました。オーストラリアのメディアは、この文書が本物だと報じています。

書面の端がななめになっていて、あわてて撮影されたようにも見えます。
文書に記載されていた主な内容はー。
〇 ソロモン諸島は、社会秩序の維持や人々の生命、財産の保護のため、中国に軍や警察の派遣を要請できる。
〇 中国はソロモン諸島の同意を得て船舶を寄港させて補給でき、中国の人員やプロジェクトを保護するために関連する権限を行使することができる。
〇 協力に関する情報は、書面をもって互いの同意が得られなければ、第三者に公開することはできない。
ソガバレ首相は議会で、文書の流出があったことを認め、内容を否定しませんでした。
協力は他の太平洋の国々とも
中国の王毅外相は、5月30日にはフィジーで、太平洋の島しょ国の外相らとの会議に臨み、気候変動や防災などの分野で支援を進めていく方針を示しました。中国は、この会議で、安全保障や貿易などの分野で、島しょ国との協力を進める新たな構想の合意を目指していると伝えられていましたが、引き続き、議論が必要だとして、合意は見送られました。中国としては、合意を諦めたわけではなく、引き続き、各国との個別の協議を積み重ねていくものとみられます。
なぜ中国と接近?
ソロモン諸島はおよそ1000の島からなる島国で、主な産業は農業や漁業。豊かな自然に真っ青な海、まさに、絵に描いたような「南の島国」です。

1978年にイギリスから独立し、その後は近隣のオーストラリアやニュージーランドから、多額の経済支援や、治安維持のための警察の派遣を受けるなど、強いつながりを保ってきました。
首都ホニアラがあるガダルカナル島は、南太平洋の戦略的要衝とされ、太平洋戦争の激戦地となったことでも知られます。
外交政策の転換は、2019年。長年友好関係を維持してきた台湾と断交し、中国と国交を結びました。
ソロモン諸島は、なぜ中国に接近するのでしょうか。
答えの一端は、首都に設けられた高さ5メートルほどはある、門の向こうにありました。

門には「中国援助 China Aid」と中国語と英語で書かれています。
高い塀に囲まれていますが、高所から撮影してみると、大型機械やトラックなどが稼働し建設作業が進められている様子が確認できました。

ここでは、中国の支援により、陸上競技場やプールを備える複合スポーツ施設が建設されていて、2023年に国を挙げて開く国際的な大会で使用される予定です。
4月下旬、施設の一部が引き渡される式典が開かれ、ソガバレ首相と現地の中国大使がそろって挨拶しました。

ソロモン諸島 ソガバレ首相
「(台湾と断交し、中国と国交を結んだ)3年前に、歴史の正しい側に立つ決断をした。これが両国の関係の最初の成果だ」
中国 李明大使
「われわれは今後もソロモン諸島の発展を支援し続ける。 中国は施設だけではなく、友情も手渡す」
さらに、治安機関どうしも関係を深めています。
ソロモン諸島では、去年11月、中国との関係を深めるソガバレ首相の退陣を求めるデモが行われ、一部が暴徒化。中国系の住民たちが経営する商店が襲撃されました。
こうした事態を受け、中国はソロモン諸島の警察に、盾などの装備を供与したほか、中国の警察官が定期的に暴動の鎮圧訓練を行っています。
私たちは、ソロモン諸島警察に訓練の実態が知りたいとインタビューを申し込みましたが、警察側は「取材に応じる必要性を感じていない」などとして拒否。
今回、ソロモン諸島での取材に協力してくれた、現地で25年以上ジャーナリストとして働く、オファニ・エレマエさんは「安保協定の締結以降、政府や関係機関は口を閉ざすようになった」と話し、中国との関係の実態がつかみにくくなったと指摘しています。


警戒感を強めるアメリカ
中国とソロモン諸島の接近に、アメリカは警戒感をあらわにしています。
アメリカは、中国とソロモン諸島の安保協定の締結発表からわずか3日後、アジア政策を統括する2人の政府高官をソロモン諸島に派遣。中国軍の部隊の常駐化に向けた措置がとられた場合、しかるべき対応をとると警告しました。
一方で、1993年に閉鎖した大使館の再開を早めることや、公衆衛生の問題に対応するための病院船の派遣、それに海洋状況や船舶の航行情報などを把握するためのプログラムの開始といった協力を約束しました。いわば「アメとムチ」で、ソロモン諸島に中国軍の拠点をつくらせるのを防ぎたいという思惑がうかがえます。
アメリカ議会下院でアジア・太平洋などを統括する小委員会のトップ、ベラ委員長は次のように話しています。

アメリカ議会下院 ベラ小委員会委員長
中国政府やソガバレ首相が「軍の基地をつくるつもりはない」と公言しても、中国がこれまで行ったことを見れば、今後の展開は明らかだ。
アフリカ東部のジブチでは、中国は「軍事基地ではなく、輸送拠点を設置するだけだ」と言っていたが、いまやそれは軍事基地となっている。南シナ海でも同じようなことが起きている。中国政府の言っていることは信用できない。
オーストラリアと連携した抑止に影響も
また、アメリカは去年、海洋進出を強める中国への抑止力を高めようと、ソロモン諸島に近い、同盟国オーストラリアへの原子力潜水艦の配備支援を打ち出しました。
南太平洋の安全保障政策に詳しいオーストラリア戦略政策研究所のピーター・ジェニングス氏は、この計画にも影響を及ぼすと指摘しています。

オーストラリア戦略政策研究所 ピーター・ジェニングス氏
オーストラリア政府が原子力潜水艦の基地を新たにつくろうと計画しているのは、オーストラリア東部の沿岸の3つの都市だ。
もし、中国がソロモン諸島に自由にアクセスできるようになれば、海上に哨戒機などを展開し、情報収集をできるようになり、オーストラリアに新たな脅威を突きつけることになる。さらに、中国軍が、アメリカのインド太平洋軍が司令部を置くハワイとオーストラリアの間のソロモン諸島に駐留することで両国の連携を制限することが可能になるかもしれない。

住民の考えは?
島の住民は影響力を増す中国についてどう思っているのでしょうか。
街でカメラを回して話を聞くと、中国からの援助については、「ソロモン諸島は発展途上国なので、受けられる支援はすべて受けるべきだ」「感謝している」と評価する声も聞かれたものの、協定については「安全保障に関しては他国に任せず、自国で行うべきだ。望ましくない」とする声があがりました。
一方、住民の考えを知る手がかりとなる興味深い調査があります。シンガポールに本社のある民間の調査会社「APMIパートナーズ」が協定締結の後に、ソロモン諸島の住民を対象に行った調査です。
問い:中国からの資金援助を受けるべきか
答え「はい」 ・・・23%
「いいえ」・・・77%
問い:中国との安全保障協定は、ソロモン諸島の利益になると思うか
答え「はい」 ・・・19%
「いいえ」・・・81%
※協定締結後の5月に約1500人に実施
結果について、一緒に取材した現地のジャーナリストのエレマエさんは「中国の援助開始から時間が経つにつれ、『援助を受け入れるべきだ』と感じている人も増えてはいる」とした上で、安全保障の協定については、「優先度は高くないのに、情報も明らかにせず急速に締結を進めたことに反発があるのではないか」と話していました。
南太平洋の国々とどう向き合うか
戦略上の要衝である、南太平洋の島々で急速に影響力を拡大する中国に対抗するため、オーストラリアやアメリカなどは、この地域への関与を強めようとしています。
ではこれらの国、そして日本は、どのようにこの地域に向き合うべきなのでしょうか。オーストラリア戦略政策研究所のアナスタシア・カペタス氏は次のように話しています。

オーストラリア戦略政策研究所 アナスタシア・カペタス氏
中国との『入札合戦』に参加しても仕方がない。ソロモン諸島を含め南太平洋の人たちにとってみれば、アメリカと中国の政治的な競争はどうでもいい。
むしろ地球温暖化による海面上昇にどう対応するかのほうが、よほど国の存亡に関わる問題だ。各国が気候変動対策など南太平洋の国々が直面している問題についてどのように支援するか、真剣に考えることが重要だ。
敵はどこにもいないのに・・・
「私たちは主に漁をして暮らしている平和な国であり、敵はどこにもいないのに・・・」
取材の中で聞いた、ソロモン諸島の住民の言葉です。
安全保障をめぐる他の国の思惑に、突如巻き込まれたように感じて、戸惑いを覚えているようでした。
アメリカや中国のせめぎ合いがエスカレートすることで、ソロモン諸島を含む南太平洋地域が不安定にならないよう、動向を注視する必要があります。
そして、一部の政治指導者だけではなく、多くの住民から受け入れられる支援や、関わり方を実現していくことが、この地域とのつながりを深めるためには重要だと感じました。






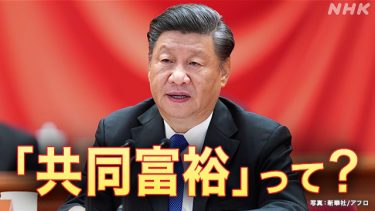

 国際ニュース
国際ニュース
