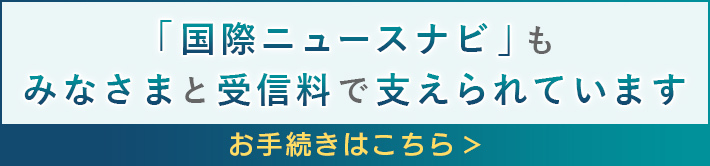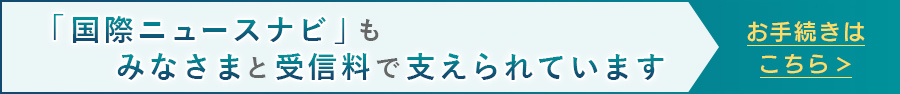「ロシア軍は侵攻当初の損失を補い軍事力を立て直した。ことしは、ウクライナとロシアの戦力差が最大になる」
ウクライナ軍とロシア軍の戦闘を分析し続けるポーランドの軍事アナリストは、こう語ります。
今月、東部の拠点アウディーイウカから撤退を余儀なくされたウクライナ軍。
最新の分析で、ロシア軍が物量でウクライナ軍に勝り、さらに戦闘を優位に進めかねない状況が見えてきました。
(ベルリン支局長 田中顕一)
取材に応じた軍事アナリストとは
ウクライナの隣国ポーランドの軍事アナリスト、コンラッド・ムジカ氏。戦況の分析や今後の展開の予測などの情報をニュースレターとして顧客に提供しています。

分析の手法は、ウクライナ・ロシア双方の発表のほか、兵士のSNSへの投稿などオープン・ソース情報を活用。さらに、みずから戦闘の前線近くまで何度も訪れ、ウクライナ軍の部隊の指揮官や兵士などから直接得た情報も組み合わせて、戦況の分析を続けています。

イギリスの大学で安全保障や軍事を学んだムジカ氏。軍事情報を分析する国際的な企業で働いたあと、独立して軍事コンサルティング会社を立ち上げました。ウクライナの戦況の分析で知られるアメリカの著名なアナリストなどとも交流があり、前線での調査は常に合同で行っているということです。
前線の最新状況は
ムジカ氏がいま、注目しているのが双方の兵力差の状況です。その典型として挙げたウクライナ東部の部隊の配置図です。東部ハルキウ州の要衝、クピヤンシクに近い前線で、ロシアとウクライナの双方の軍がどのように部隊を配置しているのかを示しています。

左側の青色がウクライナ軍、右側の赤色がロシア軍です。ロシア軍の部隊の方が多く展開している状況が一目瞭然となっています。ウクライナ軍と対峙するロシア軍の部隊のさらに後方に、さらに規模の大きな部隊が控えているのがわかります。
ムジカ氏は、ロシアが2022年9月に始めた予備役の動員によって、兵力が補充され、兵力という点でウクライナに優位に立とうとしていると指摘します。
ムジカ氏の分析では激しい戦闘が続く東部ドネツク州でも、2023年10月はじめの時点で、双方の部隊数はおおむね同じでしたが、ロシア軍は増え続けているといいます。

部隊数の増加のペースにはロシアとウクライナで大きな開きがあります。ウクライナ軍はロシア軍よりもひとつの部隊の規模が大きいため、単純な比較は難しいという意見もあるということですが、ムジカ氏は、戦闘によって双方の部隊に損害が出ていることを考慮に入れると、動員によって大規模に兵力を増やしているロシアが優位に立っていると分析しています。
さらに、ウクライナ軍が発表しているロシア軍の攻撃回数も、2023年9月までは減少傾向だったのが、それ以降は攻増加傾向にあります。ムジカ氏は、ロシア軍がウクライナ軍との戦闘で受けた損失を動員によって埋め、軍事力を立て直しているとみています。

軍事アナリスト コンラッド・ムジカ氏
「2年前、ロシア軍はこの戦争が数週間で終わると考え、準備不足の状態で開始し、すぐに兵力が十分ではないことが明らかになった。そして、動員を行い、経済を戦時体制に移行させた。ロシアは、侵攻当初の損失を補い、軍事力を立て直したと思う。動員を始めてから1年以上かかったがこれからさらに増強される」
「ことし戦力差は最大に」
なぜ、両軍にこれだけの違いが出てきたのでしょうか。
ムジカ氏は、ウクライナ軍は「兵力」と「弾薬」の確保の点で課題があるとみています。

① 兵力について
「ウクライナでは『動員』を行った場合の政治的なコストが大きすぎて、指導部がその選択肢を排除している。その代わりに『影の動員』とも言えるような、街頭や会社での勧誘を進めているが、ウクライナ軍が100万人の兵力を保有・維持し、損失を埋め、新たな部隊を編成しようと思うなら、このようなやり方では不十分だ。動員に前向きだったザルジニー氏は解任され、後任のシルスキー総司令官はそうではない。私は必要だと思うが、状況は変わらないだろう」

② 弾薬について
「2023年11月に私がバフムト周辺を訪れて現場で話を聞いたところ、『この夏は1日に250発の砲撃が許可されていたが、いまでは40発まで減らされた』と話していた。ウクライナ軍は能力を使い果たし、反撃を行うことが出来なくなっている。欧米製の兵器は品質がすぐれていて、現場で評価も高い。問題は量だ。それが欧米側に十分にない。今回の戦争はその強度があまりにも激しく、支える側の欧米にはその準備が出来ていなかった」
ムジカ氏は、ロシア軍は部隊を統合して戦闘を進める能力が低いほか、ウクライナ軍がドローンの増産によって砲弾不足を補うなど、多くの不確実性があると前置きをしながらも、2024年の戦況の見通しについて、次のように語ります。
「ことしは、おそらくロシアとウクライナの戦力の差が、侵攻が始まって以来最も大きくなり、極めて重要な年になるだろう。ウクライナにとって最上のシナリオとして期待できるのは戦線をこう着状態に持ち込むことだ。一方で、最悪のシナリオは、ロシア軍にドネツク州で前線を突破され、さらにその先まで進まれることだ」
ドネツク州の全域制圧へ攻勢強めるか
ムジカ氏が最新の分析で懸念を深めているのが、さきほどの部隊の配置図でもみたハルキウ州のクピヤンシク方面の戦況です。

クピヤンシクには、大規模な鉄道の拠点があり、制圧すれば部隊の展開が容易になります。さらに、クピヤンシクから南に向けて軍を動かせば、プーチン政権が一方的に併合を宣言したものの、全域を掌握できていないドネツク州へと到達することができると指摘。

ムジカ氏は、ロシア軍は今春、前線の後方に展開させる部隊を投入して圧力を強め、クピヤンシクを経由してドネツク州全域の制圧を目指していると予測しています。
守勢に回るウクライナ、どう動く?
一方のウクライナ軍はロシアを押し返し、攻勢に出ることができるのか。ムジカ氏は次のように語ります。
「大規模な動員と戦車や装甲車などの軍用車両の調達ができなければ、ウクライナ側が本当に大規模な反転攻勢を行うのは、向こう2年、あるいはそれ以上は難しいのではないか。ことし、ウクライナ軍が行うことは、『アクティブ・ディフェンス』(積極的防御)、前線のうち限られた場所での限定的な反撃、そして、成果のアピールという点で重要なロシア国内やクリミア半島へのドローンを活用した長距離攻撃の組み合わせだと思う」
反転攻勢の失敗に“バフムトの消耗”
2023年6月に大規模な反転攻勢に乗り出していたウクライナ軍。しかし、東部や南部の前線でもロシアの厚い防衛線を突破できず、逆に徐々に押し込まれる状況になっていきました。12月にはゼレンスキー大統領も、望んだ結果が得られなかったことを認めました。

ムジカ氏はこの反転攻勢の“失敗”の要因のひとつとして、長い間、両軍が続けてきた東部ドネツク州のバフムトの激戦の影響があったと分析しています。
バフムトでは以前から、掌握を目指すロシア軍と防衛するウクライナ軍の間で激しい戦闘が続いていましたが、ムジカ氏は、実はロシア側は、バフムトで戦う一方で、ウクライナ側の反転攻勢を予期して、南部では強固な防衛線の構築を進めていたと指摘し、ウクライナ側がバフムトにこだわったのは戦略としてミスだったとの見方を示しました。

「反転攻勢がうまくいかなかった原因は、成果に対する期待があまりにも高く設定されてしまったことや、ウクライナ軍が部隊を分けて進軍させたことなどがあるが、『バフムトの戦い』も影響したと思う。ウクライナがバフムトの戦いに集中している間、ロシア軍は、『スロビキン・ライン※1』(強固な防衛網)を邪魔されることなく構築することができた。ウクライナ側は、当時、防衛線の構築を完全ではないにしても遅らせるぐらいの能力があったにも関わらずだ」
-
「スロビキン・ライン」=ロシア軍がウクライナ側の反転攻勢を見越して、スロビキン副司令官(当時)のもと構築したウクライナ南部の主要な防衛線。アメリカの経済誌「フォーブス」は、世界でもほぼ類を見ないほど強固な防衛線だと指摘している。

ロシアは“安全保障上の脅威”と認識を
軍事侵攻が長期化するなか、ウクライナを支える欧米側の軍事支援の継続が問題となっています。

たとえば、EU=ヨーロッパ連合は100万発の砲弾などを、来月末(3月)までにウクライナに供与する当初の目標を達成できないことが明らかになりました。
ムジカ氏は、ヨーロッパ各国は、みずからの安全保障のためにも兵器の増産など防衛産業の整備に本腰を入れるべきだと、強く訴えます。
「欧米側はやらなければいけないことはしているが、スピードが遅すぎる。兵器の生産能力の復活は、数か月、数年がかりの事業だ。そして、私が欧米側が抱える問題だと思うのは、安全保障の脅威への対応よりも経済に重点が置かれてきたことだ。(軍事侵攻が始まる前)ヨーロッパには、『われわれはロシアと良好な関係を築いている。ロシアから天然ガスを買っている。ロシアは侵攻より実利を取るだろう』という考え方があったが、そうならなかった」
「ロシアは依然として、近隣国を自分たちの影響下におきたいと考えている。そして、何度も軍事力を行使してその衝動を実現しようとしてきた。欧米各国は、ロシアは安全保障上の脅威であり、その問題は解消されないことを認識すべきだ。ウクライナ侵攻後のロシアは、たとえば、さらにバルト三国などへ圧力を強めようとするかもしれない。NATOと直接衝突の可能性は低いと思うが、ロシアとの間で戦争も含めた善後策を講じておくべきだ」
“ロシアを甘く見るな”

「ウクライナ側からの目線で何が起きているかを見がちだが、ロシア側の視点での分析が少ない」
戦況の客観的な分析に努めているムジカ氏は、こう指摘します。ロシアは今回の軍事侵攻を準備不足で始めた上、統合作戦を遂行する能力にも課題があると厳しく評価する一方で、戦争の長期化に適応するための取り組みも見てとれるとしています。
例えば、アメリカが供与した高機動ロケット砲システム=ハイマースも、当初はウクライナ側に大きな成果をもたらしましたが、ロシア側も適応し命中率が落ちているといいます。

さらに戦時的な経済体制を取り、ドローンの生産力も急激に増えていることも指摘。品質に問題があったとしても実戦に投入し、現場で得られた情報を元に改良を進めているとして、ロシアは欧米側より戦場の変化に対応するスピードが早いと懸念を示します。
長期戦を進めるために兵力を増強し、戦時下の体制で侵攻を続けるロシア。兵力確保の問題と、欧米の“支援疲れ”に直面するウクライナ。
ことし戦況は、正念場を迎えることになりそうです。
(2024年2月22日「BS国際報道」などで放送)
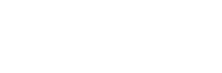













 国際ニュース
国際ニュース