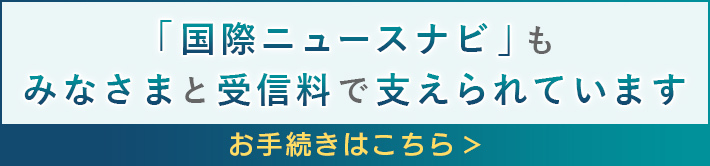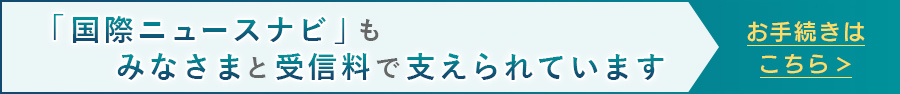「これから世界戦争が起きるのが必然だとは思わないが、その可能性はあると言わざるをえない」
ロシアによるウクライナ侵攻から1年となる中、そう警鐘を鳴らすのは京都大学大学院の中西寛教授です。
なぜウクライナでの戦争が世界に拡大するのか。これから世界はどこに向かっていくのか。国際政治学が専門で、安全保障の歴史に詳しい中西教授に話を聞きました。
(聞き手:井上二郎アナウンサー / 国際部記者 岡野杏有子)
※以下、中西教授の話
侵攻1年 ウクライナ情勢どう見る?
ロシアもウクライナも戦争を続ける意志と能力を失っておらず、「戦争が長期化する」というシナリオが今後も続くだろうというのが一番可能性が高いと思います。
2022年の早い段階では、仲介による停戦ということもある程度言われていましたが、ロシアの戦い方が非常に非人道的であるという印象が強くなって西側諸国はより強くウクライナの勝利にコミットメントするようになりました。

一方、ロシアは9月にウクライナの東部4州を国内法的に併合し、ロシアの国内法では占領した地域あるいは今戦闘しているドネツクなどはロシアの領土であるという位置づけになってしまったので、なおさら妥協が困難になってしまいました。
ウクライナは市民生活に対しても攻撃を受けて多大な被害を受けていますが、ゼレンスキー政権の下でロシアに奪われた領土を取り戻すということで結束しています。

ロシアは、プーチン政権の内部である種の動揺や論争というようなものが見られないわけではないですが、政権を揺るがすような事態にはなっていません。また、ロシア軍は大きな被害を受けているものの、今のところ戦争を続ける能力に大きな支障が出るほどの損害は受けていないように見えます。
プーチン政権の動揺 崩壊の可能性はないか?
今のところそこまでの兆候は見えないというのが結論になると思います。
ロシアの中で保守派からは戦い方が手ぬるいという批判がありますし、リベラル派には戦争に対する潜在的な批判があったり徴兵を恐れて国外へ脱出したりする人もいます。

全般的にロシアが経済制裁に苦しんでいることは間違いなく、ロシア市民の生活水準は低下してきました。
今後もそういう可能性が高いと思いますが、それがプーチン政権の打倒という方向になる可能性は今のところない、とりわけプーチン政権に代わる、受け皿となるような政治勢力がロシアにはないので、今のところプーチン政権は基本的には安定しているという状況だと思います。
プーチン政権を支持してきた中高年層からすると「現在の生活水準の低下は、西側がロシアを圧迫しているから起きている」というプーチン政権のプロパガンダ的メッセージを受け入れる素地が、やはりあるのだと思います。
現状は厳しいものの、プーチン政権を支えていこうという意識はそれなりにあり、大規模なデモがプーチン政権を揺るがすというような可能性は今のところあまり考えられないと思います。
有名なナワリヌイ氏のように反プーチンの政治勢力がいないわけではないですが、過去20年あまりのプーチン体制のもとでそうした勢力はほぼ無力化されていると言えます。

国外には反プーチンのロシア人勢力がそれなりにありますが、国内社会とは切れてしまっているので国内の状況に大きな影響力を及ぼせる存在ではないと思います。
プーチン政権崩壊すると国際的にも混乱するか?
最大の問題はプーチン政権が倒れた場合、それに代わる受け皿、安定した政治を営めるような政治勢力がないということです。
そうなるとプーチン政権が倒れたあと、分裂した政治勢力の間で権力闘争が生まれるでしょう。ロシアは世界最大の領土を持っており、その中に数千発の核兵器や原子力発電所、その他の非常に重要なものもありますので、国際社会としても放置することはできない。

各国が何らかの形でロシアの安定化のために影響力を及ぼそうとするでしょうが、西側と、長い国境を接している中国ではロシアのあり方についても考え方が大きく違うでしょう。
そうした各国のロシアに対する干渉というのは改めて国際的な対立を乱す可能性も高いと思います。
核兵器使用のリスクはあるか?
今のところロシアが核兵器を使用する兆候はないと思います。
2022年のある時期には、ロシアがウクライナの反攻を受けて厳しい状況になったという認識のもとで、ロシアがヨーロッパに対して牙を向けて、戦術核兵器も使うという可能性は一定程度はあったと思います。
しかしロシアとしてもやはりその道はプーチン政権にとって自滅の道であることは間違いないので、それは控え、ロシア国内で動員を増やしウクライナでの戦いを続けるという選択をとりました。

今のところそれが続いていますので、現時点でロシアが戦術核を使うという可能性は比較的低いと思います。
ただ、今後ウクライナでの戦況がロシアにとって非常に不利になり、プーチン政権の存亡にかかわるような事態になってきたときに、プーチン氏がどう考えるかはそのときになってみないと分からないのも実際のところだと思います。
ウクライナが徐々にロシアに対して攻勢をかけて奪還していくというのが今後、一番ありそうなシナリオで、西側なり国際社会にとって望ましい方向ではあります。
しかし、それがどんどん進んでいくと当然ながらプーチン政権としては追い詰められていくことになるので、追い詰められたプーチン政権が何をするか分からなくなってくる、よりリスクが高くなってくるということも率直に言って、あると思います。

ウクライナ侵攻前後で世界は変わったのか?
ウクライナ戦争ですべてが変わったわけではなく、2010年代を通じて徐々に国際社会は分裂の方向に進んでいたと言うことができると思います。
ロシアだけでなく中国も西側の秩序に対してある種の距離を取って自前の秩序を作ろうという傾向を示し始めていました。
また、トランプ政権に典型的に見られるように、西側でも従来のグローバリゼーションのやり方には問題があったと考え、ある種の保護主義や関係の制限に動きだしています。

それを加速したのが新型コロナによる国際的な動きの停止で、それによってグローバリゼーションの動きはいったん大きく停止しました。
そして、今回の戦争によって貿易や経済関係が政治的な目的のために使われるということを世界は改めて認識せざるをえなくなったのです。
ロシアはこれまでもエネルギーを他国にプレッシャーを与えるために使ってきましたが、今回は西側もロシアに圧力をかけるために従来の仕組みを乗り越えて、金融や貿易でも積極的に制裁をかけていくという方針を示しました。
経済関係を政治的手段のために使うという先例になりましたので、今後そうした傾向は簡単には元に戻らないと思います。
なぜ世界は分裂の方向に進んでしまったのか?
ある種の驕り、楽観主義というのが西側にあったと私は思います。
それは非常に大きな問題で、現代の世界が本当によく考えないといけない、反省しないといけないことです。
西側は冷戦に勝利したということで、自由民主主義の政治体制や市場経済がもはや唯一の正解になってしまい、それに従わない国や社会はどんどん力を失っていくだけで、気にする必要もないと考えるようになってしまいました。
ただ、そうした認識が現実とずれているということは、北朝鮮という国とずっと向き合っている我々はわかっています。
核開発やミサイル開発、そういうことを何とか止めようとアメリカもやってきましたが、結局今に至るまでできていない。

北朝鮮のような非常に経済的にも小さく人口も少ない国に対してすら、圧力で体制を変えて市場経済を採用させるということはできなかったわけです。
そんなに簡単に世界が自由主義という1つの価値観で塗りかえられるわけではなかったのだと思いますが、そのことについてとりわけ西側が直視してこなかった結果なのです。
ウクライナ侵攻 日本にはどう影響?
「戦争は過去のものではなく、未来のものでもありうる」と考えざるをえなくなったというのが今回の戦争の基本的な影響だと思います。
ロシアは日本とも海を隔てて国境を接しているわけで、現在の戦争が東アジアに波及してこないとも限りません。
また、北朝鮮のミサイルは常に日本に対してある種のプレッシャーを与えていますし、中国と台湾、そしてアメリカを巡る緊張もかなり高まっています。今のところそれがおさまっていく可能性というのはあまり見えませんので、日本としても安全保障という問題を真剣に考えざるをえないというのは間違いないことだと思います。
戦後日本は二度と戦争をしない、戦争への反省、平和主義こそがアイデンティティーだという認識が強かったと思います。
しかし2010年代に入って国際環境がしだいに厳しくなってくる、いわゆる大国間の競争というのが本格化していくにつれて、日本という国も、そうした国際、大国間競争から無縁ではいられないという感覚が強くなってきて、そうした状況に対応しないといけないという意識が徐々に強まっていたところだと思います。

今日ではその方向にさらに踏み込んでNATO諸国、アメリカの同盟国であるヨーロッパやカナダのような国と足並みをそろえるということに、基本的に日本人はもう躊躇しなくなってきています。
そういう意味で、日本人が自分で思ってる以上に、日本人のアイデンティティーに対する認識はいま、変わりつつあるような気がします。
G7議長国 日本はどうすべき?
ロシアによるウクライナ侵攻が始まって以来、日本は西側と歩調を合わせてロシアに制裁を行い、ロシアの侵略を非難して国際的にもそうした方向で結束を高めようと努力をしてきました。それ自体は国際的にも高く評価されているものだと思います。
また、日本が安保防衛政策を大きく転換して防衛力を強化するという方針に転じたこともとりわけ西側の中では歓迎されていることだと思います。
私自身、これはしかるべき政策だったと思いますが、軍事力だけでは国際秩序はできません。
現在の国際秩序を守るにしても軍事力は不可欠の要素ではあるけれども、それだけでは十分ではないのです。ですから、外交や経済やそうした面と軍事力をどういうふうに組み合わせていくかというのが、日本とりわけG7の議長国の日本として問われるところだろうと思います。
例えば、米中の対立でも論理的に考えると米中の間で妥協点はもうなくなってしまっています。

中国は「1つの中国だ」と言っていて、その中国は民主主義の国ではない。それに対してアメリカは台湾の民主主義は絶対守らないといけないと言っています。もう妥協点はないはずなんですが、その妥協がないところでどう妥協を作り出すかというのが発想力だと思います。
それは簡単なことではないですが、やはりそういうところで知恵を出すかどうかというのが日本の安全保障であったり、我々自身の生存、生活に関わってきますので、そこを頑張らないといけないと思います。
ウクライナ侵攻から学ぶべきことは?
やはり、現在の世界が大きな変化の時期にあるということだと思います。
変化の時期というのはやはり危険性をはらんでいて、我々の視野が狭いと、今回の戦争のような暴力、あるいは流血の事態が起きてしまうということだと思います。

起きてしまったことに対してはできるだけその犠牲を少なくして収束させていく必要がありますし、起きそうな所ではできるだけそれが現実にならないように配慮していく必要があると思います。
少なくとも、人類が滅亡する選択を誰も望んでいないことは確かなので、その選択を回避しながらよりよい世界をつくっていくにはどうすればいいかということを、改めて根本から考え直すべき時期にきているということが、今回の戦争が我々に教えている最も重要なことではないかと私は思います。
我々が忘れてはいけないのは1930年代の末、1936年にスペインで内戦が始まり、それに対してファシズム国家や西側がそれぞれ介入して内戦が3年ほど続きました。
1937年には日本と中国の間で本格的な軍事戦争が始まりました。
そういうことの積み重ねのあとに1939年9月にヨーロッパで第2次世界大戦が始まり、1941年12月には日本がアメリカなどを攻撃して太平洋戦争が始まって最終的に第2次世界大戦という戦争になっていきました。

現在、ロシアとウクライナの間で起きていることがそうした世界戦争に向かう1つのステップであるという可能性も現段階では否定できないと思います。
これから世界戦争が起きるのが必然だとは思わないですが、正直、その可能性はあると言わざるをえません。
ですから我々は、その点について非常に自覚的であるべきで、いかにそれを回避しながら、よりよい秩序に変えていくかということを考えないといけない。
それが現代の我々が負っている課題であり、過去の教訓もそういう観点から学んでいくべきだと思います。

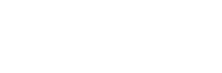


















 国際ニュース
国際ニュース