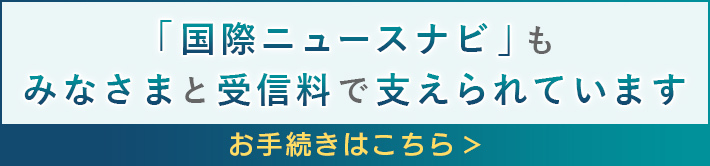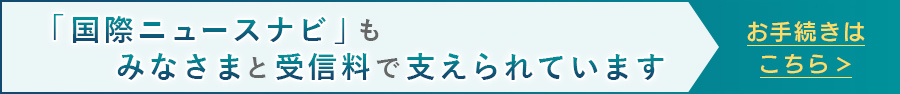「真つ青な 空がミサイル 落としけり」
14歳で俳句に魅了されたウクライナ人女性が詠んだ俳句です。
「ペンは私にとって平和のための武器」と語る彼女。
長引く戦禍の日常を、きょうも俳句に詠み続けています。
(国際部記者 海老塚恵)
ある日 空から

この俳句を詠んだのはウラジスラワ・シモノワさん(24)。

軍事侵攻が始まって4か月後の2022年6月。
戦禍の日々となった故郷ハルキウで、大好きな青い空を見上げた時の思いを詠みました。
ウラジスラワさん
「空の色が移り変わる様子や、雲の形が動物や人の顔のように形作るのを眺めるのが大好きです。
ところがある日、この青く美しい空が、危険をもたらすものになったことに気づいたのです。ほどなくしてミサイル攻撃が始まりました」

俳句との出会いは
ウラジスラワさんが俳句に出会ったのは10年ほど前、14歳の時でした。

心臓の病を患い、冬の寒い時期に孤独な入院生活を送っていたとき、たまたま病院の本棚で見つけた本。
江戸時代の俳人、松尾芭蕉や与謝蕪村の俳句がつづられていました。
ウラジスラワさん
「俳句の3行の詩は希望の光を発していて、とても簡潔で素敵でした。短い詩がこんな深さを持てることに感動しました。まるで、芭蕉自身が語りかけてくれているように感じたんです」
何か俳句のテーマに出来ないかと病室を見回したウラジスラワさん。
その晩、初めての俳句を詠みました。

外はだんだんと暗くなる時間。
風の音を聞きながら1人病室に横たわる心細さをまぎらわすように、指を折って俳句の音節を数えながら詠んだといいます。
海外でも親しまれる「HAIKU」
日本独自のものというイメージがある俳句ですが、実は海外でも「HAIKU」として親しまれています。
愛好家は70か国以上200万人あまりにのぼると言われています。
俳句で重要な5-7-5のリズムは、HAIKUでは音節の区切りで表現されます。
例えば、ウラジスラワさんが詠んだ句。日本語では

一方、ウラジスラワさんが詠んだ元の句。
音節ごとにほぼ5-7-5に分かれます。

日本では季語を含むことがルールとされていますが、世界では国や地域によって、必ずしも「季語」を含まなくても季節を感じさせる言葉があればいいともされています。
また、5-7-5でなくても、近い形で韻を踏んでいればよいとする人もいるそうです。
「この経験を世界に伝えなくては」
俳句にすっかり魅了され、以来ペンを取り自然を歩いては句を詠むようになったウラジスラワさん。
花や木、風、空の美しさや感動を5ー7ー5のリズムに落とし込んできました。
しかし、2022年2月に始まったロシアによる軍事侵攻。
ウラジスラワさんの生活は一変します。

明け方、急なミサイルの攻撃音で起こされ、両親と愛犬とともに地下のシェルターに逃げ込みました。
その日から地下で息を潜める生活が始まったのです。

俳句の内容も軍事侵攻下での生活や思いを詠むようになりました。
こちらは侵攻から3か月後に読んだ句。

故郷のハルキウで、攻撃を受けて地下シェルターに逃げ込んだウラジスラワさん。
混乱しショックを受けた大勢の人でひしめく地下シェルター。
そんなとき、突然、子どもたちが飛ばした紙飛行機に目を奪われたといいます。
どんな時も楽しみを見つける子どもたちのけなげさ。
そして地下シェルターの真上の空には戦闘機が飛んでいる対比の衝撃も込めました。
ウラジスラワさん
「私にとって俳句は日記のようなものです。生活の場が地下シェルターに移ったとき、その感情や経験を、どうにかして残さなければならないと思いました。
いつか、私が経験したことを世界の人に伝えなくてはいけないと思ったのです」
遠く離れた日本の俳人が
先の見えない生活が続く中で、ウラジスラワさんはある夢を抱くようになります。
世界の人たちに戦禍の日常を詠んだ自分の俳句を知ってもらいたい。自分の思いを込めた俳句集を作りたいと考えるようになったのです。
その思いが届いたのが、遠く離れた日本でした。
俳人の黛まどかさん。2022年3月、新聞記事でウラジスラワさんの存在を知りました。
その思いに共感し、ウラジスラワさんに1通のメールを送りました。

黛さん
「ウラジスラワさんの俳句は戦争が突然やって来た日常をうたっています。それがものすごく衝撃的なんです。戦時下での庶民の息づかいが本当にリアルに伝わってくるような俳句で」
始まった俳句集作り
軍事侵攻から半年近くが経った2022年8月。
黛さんは、ともに俳句を詠んできた俳人と、通訳、ウクライナ出身の人たちを集めたチームを結成。俳句集作りに臨みました。
はじめに、ウラジスラワさんから寄せられた元の俳句を日本語に直訳。
そこから、句が詠まれたときの情景や心情を想像しながら、いくつか日本語の句の案を考え、最終的な句として整えていきます。
黛さんは、日本語の句を絞り込むため、何度もオンラインで会議を開きました。

特に議論を重ねたのは、ウラジスラワさんがバラの花束について詠んだ句です。戦時下にも咲き誇るバラの花束に心打たれた時の思いが込められています。
元の句を直訳すると、
「バラの茂みをカットします/自分を慰めるために/花束を持っていきます」
会議ではことばのリズムやニュアンスを丁寧に検討しながら、日本語の句にまとめあげました。
「薔薇摘んで 地下シェルターに 帰りけり」
俳句が詠まれた時期、まだウラジスラワさんは故郷ハルキウの地下シェルターで生活していたことに注目。
傷ついた心をバラに慰められる切なさと、戦時下にも咲くバラの美しさの対比が際立つように言葉を選びました。
しかし、通訳を担当したメンバーから、元の句のニュアンスでは、バラを摘みに行く様子ではなく、すでに切り取られた花のイメージだという指摘を受けました。
そこで黛さんは、ウラジスラワさんに俳句を詠んだ状況をさらに詳しく説明してもらいました。
ウラジスラワさん
「バラがミサイルによる攻撃で傷ついたので、持ち主が摘み取ったんだと思ったんです。満開のバラを切り取るなんておかしいですから。
私もふだんは咲いている花を切り取るのは好きではないのですが、このときは、わずかに咲き残った花が新鮮なうちに、持ち帰ることに決めました」

話を聞いた黛さん。
これまでの案から大きく変えて、情景に忠実に、日本語の句にすることにしました。


黛さん
「ウラジスラワさんの俳句はとても繊細。日常のすごく小さな機微を、自然を通してすくい取っているんです。その中で、日常にほんの少しの美、あるいは光、春を見いだすということをしています。
彼女の俳句には、日に向かう『向日性』があるのが特徴だと思います。どんな極限状態にあっても人生を楽しむことができるし、美しいものは美しいと思うことができる。
その権利があるんだということをこの小さな一冊の句集を通して、多くの人に呼びかけたいと思います」
俳句集の完成

およそ1年にわたる作業のすえ、2023年8月、ウラジスラワさんの俳句集が完成。
発表を前に、東京都内で会見も開かれました。
ウクライナからオンラインで参加したウラジスラワさんに、黛さんはパソコン越しに完成した本を見せました。

ウラジスラワさん
「このような機会が本当に巡ってくるなんて想像もしませんでした。
日本の読者の皆さんに、私の俳句を通して、戦争の中の日常や、俳句の表現でこそ読み取れるような微細な変化など、日々のニュースで見られないようなものを読み取っていただければうれしいです」
黛さん
「この俳句集には、戦禍で力強く生き抜くウラジスラワさんへの応援と祈りを込めました。
どうか早く軍事侵攻が終わって、ウラジスラワさんに、この俳句集を直接手渡したいです」
最新の俳句は・・・
軍事侵攻から2年が経った先月(2月)、ウラジスラワさんから私(記者)に新しい俳句が届きました。

つくったばかり、と送ってくれた俳句。5-7-5にはできていませんが、通訳さんの力も借りて、私なりに訳してみました。
「春一番の花! 心配しながらながめる 天気予報」
まだ寒さ厳しいウクライナで、今年初めての花の開花を見つけて喜ぶウラジスラワさんの興奮。
それに、この時期にしては早い春一番の花が弱ってしまわないか心配で天気予報をながめてしまう優しさが込められていました。

この春、ウラジスラワさんの2冊目の句集が日本で出版される予定です。
実はこれまで、ウラジスラワさんの句は、生まれ育った故郷ハルキウの母語、ロシア語で詠まれてきました。ただ軍事侵攻が進むにつれ、ウクライナの言葉で俳句を詠みたいとウラジスラワさんは思うようになっていました。
ウクライナの人々に攻撃を続けるロシアの言葉を使うことが苦しくなったためです。
今回新たに出版される句集ではウクライナ語に詠み直したおよそ300句が収められています。
いつか日本にウクライナ語で詠んだ俳句を届けたい、というウラジスラワさんの夢が叶おうとしています。

取材を通じて
私(記者)がウラジスラワさんの俳句の活動を知り、初めてメールをしたのは2023年1月でした。
それから1年以上が経ちました。やりとりしたメールやメッセージは300通以上にのぼります。
その中でウラジスラワさんはこの2年間の体験を丁寧につづってくれました。
多くの人でひしめく地下シェルターに逃げ込み、睡眠や食料も満足にとれなかったこと。ロシア国境近くの故郷は昼夜を問わず攻撃が続いたこと。

電気が頻繁に切れ外の世界から孤立したこと。
家の前にミサイルが落ち、故郷を追われたこと。
彼女からの返信が途切れると、彼女の身に何かあったのではないかと、不安が募りました。
それでも、どんな状況にあっても、ウラジスラワさんの、俳句を通じてウクライナの人々の思いや状況を伝えたいという姿勢は揺らぎませんでした。
ウラジスラワさん
「ウクライナの人々は毎日、大きな犠牲を払っています。いつ戦争が終わるのか誰にも分かりません。
でも、どうあろうとウクライナの人々はできるだけ価値のある生き方を続けようとしています。人々は結婚して、働いて、次の世代を残していきます。
自分の家に帰り、仕事に就き、通常のように平穏な暮らしを送ることができるようになる、それが私の夢です。
その時が来るまで、私は戦争に対する平和のための武器のように、自分のペンを握って戦争に立ち向かいます。私はウクライナという遠い国の俳人です」
ウクライナと日本。
遠く離れていても、送ってくれる俳句を通して、またメッセージやメール、動画を通して、ウラジスラワさんが込めた優しい思いを近くに感じてきました。
でも、今度はリモートではなく直接会って、ウラジスラワさんから俳句を教えてもらいたい。その日が1日も早く来ることを願っています。

(2023年9月5日おはよう日本などで放送)
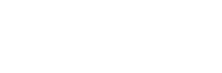













 国際ニュース
国際ニュース