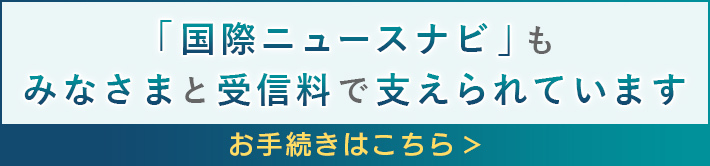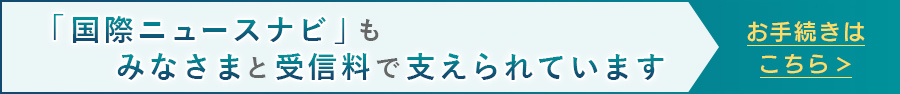「ことしを耐え抜くことは、戦争に耐え抜くことを意味する。重要かつ決定的な時期だ」
ゼレンスキー大統領は年が明けた2024年1月5日、動画の演説でこう国民に呼びかけた。
まもなく2年を迎えるロシアによるウクライナへの軍事侵攻。
欧米各国からの軍事支援の先細りが懸念される上に、戦闘の終結も見通せない。
しかし、将来必ず必要となるウクライナの復旧・復興に向けて動き出している日本人たちがいるのをご存じだろうか。
(ヨーロッパ総局記者 渡辺信)
晩秋のキーウに到着 日本代表団
それはすでに動き出していた。
2023年、晩秋のウクライナ。首都キーウの駅にポーランドからの特別列車が警笛を鳴らしながら入ってきた。早朝、まだあたりは薄暗い。

ホームで出迎えたのは、松田邦紀・駐ウクライナ大使をはじめとする日本の外交官たち。
列車に乗っていたのは、外務省と経済産業省の副大臣、それに日本企業10社の関係者たちで構成された「経済ミッション」の一行だ。到着の直前、まるで演出かと思うくらいの絶妙なタイミングで、キーウを象徴する曲「愛さずにはいられない、私のキーウ!」がホームに流れた。
ウクライナ首相が歓待、かかる期待
その後、一行は、午前のうちにウクライナのシュミハリ首相と会談。今月(2月)19日に東京で行われる予定の「日ウクライナ経済復興推進会議」に出席するキーパーソンでもある。

今後の復旧と復興において、ウクライナ側の日本にかける期待の大きさは、その発言からも感じられた。

シュミハリ首相
「ロシアによる侵略が続く中での、日本政府や企業の皆さんの支援は大変ありがたい。今回の訪問が、復興に向けた具体的な成功につながると確信している」
一行は、スビリデンコ第1副首相兼経済相らとも会談。両政府は、ロシアの軍事侵攻で破壊された橋などのインフラ整備に連携して取り組んでいくことを確認した。
「最後の地雷撤去まで」交わした約束
実はすでに復旧、復興に向けた日本側による支援が始まっているー
その1つがロシア軍が埋設した地雷の撤去だ。
ウクライナ内務省によると、地雷などの爆発物が残る土地の面積は、ウクライナの国土の30%にあたる17万4000平方キロメートルに上るという。キーウの日本大使館によると、ウクライナ側は、この数字を去年の初め頃から政府の統一見解として使っている。その内訳は11万9000平方キロメートルがロシアに占領された地域、1万9000平方キロメートルがロシア軍が一時的に展開していたロシアやベラルーシとの国境地帯、3万6000平方キロメートルがロシアに占領されたが、その後の戦いで奪い返した土地だという。ウクライナ側は、ロシアから奪還した地域を中心に、地雷除去を開始しているということだ。
今回の経済ミッションの訪問に合わせて、キーウでは、日本の地雷探知機などの引き渡し式も行われた。

式典が行われた場所はキーウ中心部にある世界遺産、聖ソフィア大聖堂の前の広場。
日本側を代表して、辻外務副大臣が「地雷や不発弾の処理は、住民の安心や安全の確保に不可欠であるだけでなく、生活や農業、そして、産業の再建にも必要だ」と挨拶した。
ウクライナ側も歓迎し、ある約束を挙げて日本側の支援に期待を示した。

スビリデンコ第1副首相兼経済相
「ウクライナ政府としては、今後10年間で地雷や不発弾で汚された土地を、すべてきれいにするという野心的な目標を持っている」
「日本の松田大使は、最後の地雷が撤去されるまでウクライナを支援すると約束してくれている。日本の友人が約束を守ってくれることで、われわれは現在の戦いを勝ち抜くことができると確信している」

JICA=国際協力機構を通じて、ウクライナ非常事態庁に供与される「ALIS」と呼ばれる地雷探知機50台、地雷除去の隊員たちが作業現場に向かう際などに使用するトヨタ自動車の車両40台がお披露目された。

大聖堂の前の広場に、ずらりと並ぶ車両。式典で、この場所を使ったことについて、日本側の関係者は「ウクライナ側は、日本への最大限の敬意を表すため、この場所を選んでくれた」と説明した。
地雷の撤去作業員の姿も
会場には、地雷の除去作業に従事する非常事態庁の隊員たちも整列して参加していた。私(筆者)は、その中に1人、以前の取材で知り合ったイワン・シェペリエフさんを見つけた。

彼と最初に出会ったのは昨夏。キーウ近郊のブチャにある訓練場での取材の際だった。当時、彼は、対戦車地雷を発見する訓練を行っていた。

そして、インタビューに「ウクライナは、世界で最も多くの地雷が埋められた国のひとつであり、日本の皆さんからの支援は非常に重要だ」と話してくれていた。
日本製の探知機を使い、日本という国の文化にも関心を持つようになったというシェペリエフさん。命の危険を伴う仕事ではあるが、祖国の土地を少しずつ元どおりにしていくことにやりがいを感じるという。
改めてインタビューすると「日本製の地雷探知機だと、効率よく正確な作業が可能になる」と語ってくれた。
この日のキーウは晩秋とはいえ気温は氷点下。空は澄み渡っていたが、肌を突き刺すような冷たい風が吹いていた。

シェペリエフさんたち隊員は、式典の最中、ずっと整列したままだった。そんな中、すべての行事が終わると、彼らに歩み寄り「寒い中、ありがとう」と声をかける松田大使の姿があった。
「経済ミッション」一行は?役割と商機は?
さて、話を日本側の「経済ミッション」一行に戻そう。
今回、参加した日本企業は10社だった。どんな企業か参加し、そして、どのような役割を担おうとしているのか。
実は私(筆者)は、当初、この企業側への取材は困難ではないかという感触を得ていた。なぜなら、参加する日本企業の多くは、ロシアでもビジネスを展開しているためだ。ウクライナの復旧や復興に関わるとなると、ロシア側から嫌がらせを受けることを懸念し、社名の公表を控えたいというところもあると聞かされていたのだ。
しかし、それは杞憂に終わった。同行していた政府関係者の尽力もあって、複数の企業が、しっかり取材に応じてくれたのだ。
まず、大手機械メーカー「IHI」。理事の松野憲司さんによると、侵攻で被害を受けた橋や道路などのインフラ整備を中心にウクライナに協力したいという。

松野さんは「短期的には黒海に抜ける物流が大事だ。破壊された橋りょうや道路があると思うが、私たちとしては、ヨーロッパの多くの国が採用している基準で設計された仮設の橋りょうなども持っているので、それらを活用できるのではないか。中長期的には、隣国ルーマニアへと抜ける道路建設の需要も出てくるだろう」と指摘した。
そして「われわれ日本企業は、戦後の復興や震災などの苦難を乗り越えて活躍してきたという自負がある」と言って、胸を張った。
IHI 松野理事
「ニーズを正確につかまないと適切な支援はできない。スピードも重要だ。こうした機会をとらえて、ウクライナ政府の要人などと直接、話ができる関係を作りたい」
次は「アライドカーボンソリューションズ」。この会社は、ウクライナ特産のひまわりのタネなどから取れる油を原料にして、界面活性剤の生産を目指しているという。シャンプーや洗剤などに使われる界面活性剤。会社ではさらなる用途の拡大を目指して、ウクライナ産の原料を使った天然由来の界面活性剤の製造を増やすことを計画している。

話を聞いた代表取締役の山縣洋介さんは「私たちの商品の主な販売先はヨーロッパ市場だ。その意味でも、市場に近いウクライナで生産できるメリットは大きい」と強調した。そして、ウクライナとの協力のあり方について「生産方法も共有できるし、一緒に合弁企業を立ち上げることもできる」と述べた。
アライドカーボンソリューションズ 山縣代表取締役
「現在、世界の界面活性剤の原料のトレンドは、石油由来から天然の油由来へと大きくシフトしているので、農業が盛んなウクライナとの協力には意義がある。軍事侵攻が続く間は技術者を派遣できないが、戦後になれば本格的に仕事ができる。ウクライナ産の植物油を購入するのは、現状でも可能だ」
そして、風力発電などの分野でウクライナ側との連携を目指す「駒井ハルテック」。

常務取締役の駒井えみさんは「私たちは、300キロワットの発電力がある風力発電機を作っている。ウクライナ国内の工場など、独立した電源を必要とするような場所での自家消費用に採用してもらえないか調査している」と意欲を示した。
駒井ハルテック 駒井常務取締役
「ウクライナの人たちから『雇用と産業が生まれれば、外国に出て行く必要はなくなる』と聞いた。私たちも、ものづくり企業なので、彼らの考えに感銘を受けた。何か少しでも役に立ちたい」
このほかにも、隣国モルドバとの間を結ぶ鉄道インフラの整備に向けた調査を開始する企業や、農業が盛んなウクライナでトラクターなどの農業機械の販売を模索している企業もあった。
ウクライナ側とのマッチングも
キーウにあるホテルを会場に、日本とウクライナの企業関係者どうしの会合も行われた。
両国の企業のマッチングは非公開だったが、同行する外務省や経済産業省の関係者によると、日本の企業の感想の中には「ウクライナ側のニーズは玉石混交だった」というものもあったが、全体としては、大きな手応えがあったという。

日本企業のブースには、ウクライナ企業関係者が列を作ることもあり、彼らの復旧や復興に対する熱意が感じられたということだった。

一行は、わずか1日ではあったが、キーウ訪問を終え、夜、ふたたび夜行の特別列車に乗り込み、帰路についた。
死活的に重要な消火剤も
今回の経済ミッションの訪問にあわせて「地雷探知機」などとともにウクライナ側に引き渡された支援がもう1つあった。(通関手続きが遅れたため式典には間に合わず)
それは、石けんの成分で作った「泡消火剤」だ。
日本側によると、ロシアによるミサイルや無人機の攻撃があった現場では、火災が発生することが多いことから、消火剤はまさに死活的に重要な支援だという。
「泡消火剤」は、北九州市にあるメーカー「シャボン玉石けん」が、北九州市消防局や北九州市立大学と共同で開発したものだ。消火用の水に混ぜて使う。ウクライナには1缶20リットル入りのものが150缶供与された。輸送費も含めて、すべて企業が負担したという。

担当の日本大使館員は「通常の消火剤よりも少ない量の水で火を消すことができる。しかも、主な原料が化学物質ではなく、石けんの成分なので、環境にもやさしいという特徴がある。日本の企業は、そこまで配慮している」と説明した。
「日本ならではのきめ細やかな支援を」
欧米各国のように、殺傷能力のある武器や弾薬の供与といった軍事支援は行わないという方針のもと、こうした日本ならではの支援がある。
今回、ウクライナ側に供与された地雷探知機「ALIS」を開発した東北大学の佐藤源之名誉教授の話を聞いた時にも、そんなことを感じた。
佐藤名誉教授は、カンボジアなどでの地雷除去にも携わってきた経験がある。

佐藤名誉教授が開発した地雷探知機は、金属探知の機能だけでなく、地中の様子がわかるレーダーが組み込まれているのが特徴だ。レーダーで地中の物体の形状を捕らえられるので、確実な作業ができるという。さらに家電製品のようにも見える外観は、あえて軍の装備品でないことがわかるようなデザインにしたためで、「国連のシンボルカラーでもある水色を選んだ」と説明してくれた。

さらに佐藤名誉教授は「雨が多いカンボジアなどでは、地雷が深い地中に潜ってしまう傾向があるが、ウクライナでは、まだ地表付近に埋まっていることが多いと思う。作業を行うのは早ければ早いほどいい。特に、市街地では、がれきにさまざまな金属片も混じっているので、地中の物体の形状がわかる、このALISが役立つだろう」と指摘した。
ただ、その高性能がゆえ、去年7月にウクライナ非常事態庁の隊員たちに使い方を教える研修が行われた際、「複雑すぎて使いにくい」といった不満も相次いだ。

ただ、そんな時、佐藤名誉教授は、JICAの人たちや通訳も交えて知恵を絞り、彼らが納得いくまで丁寧に根気強く説明したという。
佐藤名誉教授は「機材を供与するだけでなく、ウクライナの人たちがマスターするまで、彼らの意見を聞きながら丁寧に訓練を積み重ねてきた。ぜひ役立ててほしい」と語った。
取材後記
2023年12月6日、G7=主要7か国の首脳会合がオンラインで開かれ、ウクライナのゼレンスキー大統領も参加した。去年1年間、G7の議長国を務めてきた日本にとって、締めくくりの会合でもあった。
岸田総理大臣は、中東情勢が緊迫する中でも、G7の対応は変わらないと指摘。日本としてもウクライナの復旧・復興などに、総額45億ドル規模の追加支援を行っていく意向を表明した。
ある外交筋は「日本が追加支援を表明した背景には、欧米で『支援疲れ』が見える中、ウクライナへの連帯を強く表明し、ロシアの侵略を1日でも早く止め、公正で永続的な平和を実現することへの日本の関与を、世界に幅広く発信する狙いがあった」と指摘した。
ウクライナの反転攻勢が困難を極めているという見方も根強い中、日本の支援は、ウクライナの人々を、どこまで救えるのだろうか。
その成否の鍵を握るのは、外交官や支援機関の人たちはもちろん、実際に支援を担う日本企業の技術力と担当者の熱意、そして、研究者たちの情熱ではないかという思いを強くした。

(2023年11月21日 おはよう日本などで放送)
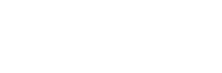









 国際ニュース
国際ニュース