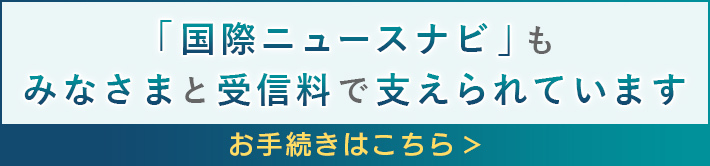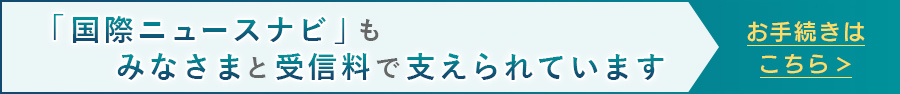「台商」という言葉、聞いたことがありますか?
台湾企業の関係者や企業家のことを指す中国語です。
中国でビジネスを展開する「台商」、その数は推計でおよそ20万人、家族なども含めると関係者は100万人とも言われています。
台湾総統選挙の結果次第では、自らの仕事にも直接影響が出かねない人たちです。
「台商」は中国とどう向き合い、今回の選挙に何を望むのか。
中国大陸と台湾を行き来する「台商」たちに胸の内を聞きました。
浮かび上がってきたのは、変わりゆくビジネスの姿、そして「民主」への思いでした。
(中国総局記者 松田智樹)
中国で工場を立ち上げ世界へ輸出 “台商”の成功モデル
「これがヨーロッパなどで人気の寝袋ですよ」

私が中国南部の広州で話を聞いたのは、アウトドア用品メーカーを経営する劉宝鳳さんです。国内最大規模の展示会のブースにはオレンジや青、緑などカラフルな寝袋がずらりと並んでいて、劉さんは、世界中から訪れたバイヤーに商品の特徴を説明していました。
「台商」の多くのビジネスモデルは、中国で立ち上げた工場から製品を海外へ輸出するパターンで、劉さんもその典型です。
1997年に中国・上海に進出して2000年から工場を稼働。世界的に有名なアウトドアブランドの寝袋などを受託生産し、ヨーロッパやアジア、中東などの国々に輸出してきました。

進出以来、「台商」の劉さんは本社のある台北をベースとしながらも台湾と中国の間を数か月に1度行き来してきました。上海では布などの材料の調達が容易で労働者を雇用しやすい環境が整っていたと言います。
激変する中国ビジネス 「賃金高騰も言葉は同じで便利」
ただ、中国の経済発展にともない、ビジネス環境は激変しました。労働者の賃金が高騰し、さらには、工場での勤務を敬遠する若者も多くなりました。劉さんたちの工場でもかつては250人いた従業員は80人に減っています。
実際、「台商」の中でも、ベトナムやカンボジアなどに製造拠点を移転する動きも出ているということです。劉さんの会社も、ヨーロッパの取引先からよりコストを抑えるため、人件費の安いインドへの進出を誘われたと言います。
しかし、劉さんは、言葉がほとんど同じでコミュニケーションがとりやすいことなどから、現時点では、中国から離れる考えはありません。

劉さん
「中国は明らかに豊かになり、状況は本当に変わりました。それでも、上海工場の生産ラインではインドやベトナムと違って中国人のスタッフと簡単に意思疎通ができるので通訳はいりません。中国の人々は知識が豊かになり、競争力もどんどん上がっています。製造業についていえば、中国はまだ優位性があると私は思います」
“中国との安定した関係を” 選挙に期待
今後も中国大陸でビジネスを継続したい劉さん。与野党から3人が立候補している今回の台湾総統選挙では、最大野党・国民党の侯友宜氏を支持する考えです。

侯氏は中国の圧力に対抗する姿勢を示す与党・民進党政権を批判し、中国との関係を前の国民党政権のときのような安定した状態に戻すとしているからだと言います。具体的な政策として、侯氏は、かつて若者らが強く反発した中国とのサービス分野の貿易自由化協定の協議再開や中国人観光客の受け入れといった政策も掲げています。
台湾総統選挙に在外投票はなし 「台湾へ戻って投票する」
日本のように在外投票や期日前投票の制度がない台湾。投票するには投票日までに台湾に帰る必要があります。
劉さんのスマートフォンには投票日を前に、友人からSNSを通じて国民党の集会の盛り上がりや候補者の主張など、さまざまな情報が送られてくるといいます。

国民党が政権を奪還できるよう、必ず投票に行くつもりです。
劉さん
「台湾海峡の両岸の関係がよくなればビジネスがより便利になり、心配が不要になります。みんなが平和に共存し、よりよい未来を創造できるようになるのです」
中国政府も注視する台湾の選挙 政権交代に期待
台湾統一に強い意欲を示す中国の習近平指導部。
中国政府も台湾の総統選挙の行方を注視しています。
投票まであと1か月余りとなった去年12月7日、中国各地に散らばる150余りの台湾の企業団体の代表が会議のため北京に集められました。

そこで演説したのは中国政府で台湾政策を担当する国務院台湾事務弁公室のトップ、宋涛主任でした。
宋主任
「われわれは習近平総書記の台湾工作に関する重要指示を全面的に貫徹し、台商と台湾企業を助けてきた。広範な台湾の同胞と台商が両岸関係を平和と発展の正しい軌道に戻し、壮大な中華民族の経済に貢献することを望む」
「正しい軌道に戻す」という発言からは、現状への不満、つまり、民進党への非難や政権交代への期待が感じられます。台湾や香港のメディアは、国民党支持者が多い「台商」に台湾へ帰って投票するよう働きかけるのが会議のポイントだったという関係者の話を伝えています。
中国を避ける「台商」も アメリカへの投資は9倍
ただ、中国側の思いとは裏腹に、台湾側の統計データは、中国にとって厳しい現実を示しています。

台湾の内閣にあたる行政院によりますと、中国にビジネスのために90日以上滞在していた台湾の人たちの数は2022年には推計で17万人余り。過去10年間で最も多かった2013年の43万人から減り続け、新型コロナウイルスの感染が拡大した2021年以降、その数は4割ほどに減少しています。「ゼロコロナ」政策の影響が大きいものの、以前よりも「台商」の中国での存在感は低下傾向にあるようです。
台湾から中国への投資額も減っています。

台湾経済部によりますと、中国への投資額は2010年のおよそ146億ドルをピークに減少し続け、最新のデータとなる2023年1月から11月までに29億ドル余りと、わずか2割にとどまりました。
一方、アメリカ向けの投資額は2023年1月から11月までにおよそ96億ドルと、前の年の同じ時期と比べて9倍に急増したほか、ヨーロッパ向けの投資額も2023年1月から11月までに53億ドル余りと前年同期比で7倍に上り、いずれも中国の29億ドル余りを上回っています。
こうした背景には、新型コロナの影響に加えて、民進党政権が過度な中国依存からの脱却を進めていること、そして、台湾の半導体受託生産メーカーが欧米や日本に工場を新設していることなどがあるとみられます。

国民党にこだわらず 「戦争避ける知恵があれば誰でも」
台湾をとりまくビジネス環境に変化が見られる中、台湾の総統選挙に対する考え方そのものが変わりつつあると話す「台商」もいます。
中国南部の広東省を拠点にして、食品メーカーを経営する郭弋黎さんです。

1998年からイギリスやフランスなど、ヨーロッパを中心にこんにゃくで作った麺やみずから開発した調味料などを輸出してきました。

郭さん
「両親、親戚、友人がみな台湾にいるので、当然台湾のことが気になります。ただ、今は『台商』がかつてのように、家族ぐるみや会社ぐるみで選挙活動を行っていた時代とは違います。国民党の支持者もいますが、民進党だって今は『台商』をサポートしてくれていますよ」
かつて「台商」は国民党を通じて中国政府にビジネスへの支援や優遇策を求めました。しかし、民進党政権の2期8年で、「台商」は民進党にも頼るようになったと言います。

郭さんは国民党を支持してきましたが、中国経済の先行きが見通せない今、政治よりも仕事が重要で、総統選挙の投票日までに台湾に帰る余裕はないかもしれないと苦しい胸の内を明かしてくれました。
郭さん
「私が投票に行く確率は50パーセントです。『台商』にとって製品を作り、ビジネスをより大きくすることが大事なので、私としては自分の仕事をしっかりやるだけです。候補者は戦争を避ける知恵を持たなければなりません。誰もがよりよい生活を送れるようにできる人が最も重要で、平和を維持できれば誰でも支持します」
取材後記 「台商」が語った民主主義の大切さ
国民党に1票を投じると明言した劉さんと、国民党にこだわらず戦争を避けられる人なら誰でも支持すると話す郭さん。「台商」は国民党の岩盤支持層とも言われてきましたが、新型コロナや政治情勢の変化など、さまざまな要因が複雑に絡み合い地殻変動が起きているのかもしれないと感じました。
そんな立場こそ違う2人ですが、共通していたことがあります。それは「台湾には多様な意見がある。誰が当選しても結果に従う。それが民主主義だから」と話してくれたことです。1996年に初めての直接選挙が行われてから、今回で8回目となる総統選挙。民主主義が台湾社会にしっかりと根づいていることを実感しました。 一方、中国では習近平国家主席への権力集中が進み、「共産党一党支配」から「習主席の個人支配」に変わったという指摘すら出ています。習主席は繰り返し台湾統一に強い意欲を示していますが、民主主義や自由といった価値観を尊重する台湾の人々がそれを受け入れるのはますます難しくなっていくのではないかと思います。
(1月12日 ニュース7で放送)
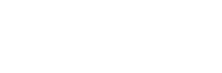


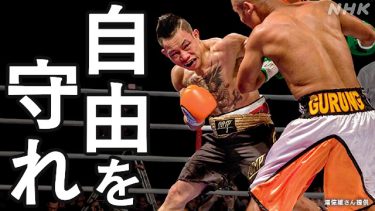










 国際ニュース
国際ニュース